 |
| 【貴重なレコード集「名曲鑑賞レコード」】 |
私の音楽体験の原風景は、幼年時代に聴いたレコードの数々である。そのうち、百科事典『原色学習図解百科』(1968年学研)の第9巻[楽しい音楽と鑑賞]には、クラシック・レコード集「名曲鑑賞レコード」(EP盤全6枚、全30曲)が付属していて、特に聴くことが多かった。レコード・プレーヤーという機械装置に盤を乗せ、針をおくという新鮮な遊戯と、プレーヤーのスピーカーに耳を傾け音楽を聴くという行為は、私にとって最も充足な心の安定と快楽を意味していた。
ともかく、「名曲鑑賞レコード」から私は、音楽的な様々なことを感じ取り、学んだ。今でも第9巻[楽しい音楽と鑑賞]の本は、常に手の届くところにある。それを開けば、ひとときの郷愁を超越してさらなる音楽の深みの泉を呼び覚ましてくれる。幼年時代のこれらとの出会いがなかったならば、私はその後の人生でまったく音楽というものに関わっていなかったであろうとさえ思う。
故に、当ブログでもたびたび第9巻[楽しい音楽と鑑賞]の話題が登場する(ブログのカテゴリー・ラベル[原色学習図解百科]を参照していただきたい)。2年前に「名曲鑑賞レコード」でショパンの「マズルカ」を聴いた時、盤の劣化が著しいことに気づいた。当時から既に盤の傷は多く、40年あまり経った今、すっかり聴くに堪えない音になってしまったことは無理もないことである。
そこで、(これも2年前になるが)ネット・オークションを利用して、このレコード集が出品されていないか検索したところ、幸運なことに一品だけ、まったく同じ「名曲鑑賞レコード」(状態良)を発見することができた。そうして特に難しい入札の駆け引きもなく、すんなりそれを入手することができ、今ではそちらの状態の良い方の盤で聴くことができている。
*
――先々月、村上春樹著『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(文藝春秋)を読んでいて、あるフランツ・リストの曲を思い出した。幼年時代に「名曲鑑賞レコード」で聴いていた、リストの「ラ・カンパネラ」である。
私はカナダ出身のピアニスト、グレン・グールドが好きで、以前よりグールド関連の本をいくつか読んでいた。そうしたことで、村上春樹氏のその小説に出てくるピアニスト、ラザール・ベルマンの名前だけは知っていた。あの小説を読んで思いがけず、私の空想は飛躍した。私が幼年時代に聴いていたあの「ラ・カンパネラ」が、もしかしたらラザール・ベルマンの演奏だったのではないかと。
だが、それはあまりにも飛躍した空想であった。リストがパガニーニのヴァイオリン曲「鐘のロンド」を編曲してピアノ曲に作り立てた「ラ・カンパネラ」(「パガニーニによる大練習曲集第3番」嬰ト短調8分の6拍子)の冒頭は、Allegretto(アレグレット)で低音部がファのオクターブ・ユニゾン(スタカート)、高音部がレのオクターブ・ユニゾン(スタカート)で続き、フェルマータ――という4小節から始まる。それは“カンパネラ”=鐘に相応しいとても落ち着いた始まり方だ。実は「名曲鑑賞レコード」の「ラ・カンパネラ」の演奏者はラザール・ベルマンではなく、日本人の賀集裕子さんだった。
賀集さんの「ラ・カンパネラ」は、リストが仕掛けた難解な方程式を、実に人間的な視点で解きほぐした貴重な演奏作品である、と私は思っている。
リストが少年期にハンガリーで過ごした際の、素朴な民族音楽の《記憶》をリズムとして組み込み、それを下地にして演奏の難しい装飾音を無数に鏤めた「ラ・カンパネラ」。彼は自己の感情の激しい揺れ動きを高速の装飾音で具象化し、それ自体が生命体であるかのような錯覚を起こさせ、聴衆を惹きつける才智があった。こうした特殊な情趣を、賀集さんは率直に表現しつつも、彼の情熱的な力、その昂揚の変化の過程までも見事に表現していた。言わば、賀集さんの「ラ・カンパネラ」には、そうした人間の仄暗い哀調が感じられた。
第9巻[楽しい音楽と鑑賞]の「ラ・カンパネラ」の解説で触れられていたのは、素朴なハンガリーの民族音楽について、つまりはマジャール族というアジアの人種と、その地で生活していたジプシーの2つの音楽のことであり、このハンガリーの民族音楽の基礎となっている“チャルダス”の形式の解説がわずかに続く。賀集さんの「ラ・カンパネラ」からそうした《いにしえ》の民族音楽的情趣をリズムとして感じ取ることは容易であって、現にリストはこの曲をそうした情趣に彩られることを希求したに違いない。
*
 |
| 【ユンディ・リ『ラ・カンパネラ~リスト・リサイタル』】 |
ところで今、こうした感覚的な体験を、私は別の演奏者との比較で際立たせてみたくなった。
最も簡単なのはネット動画を通じて、例えば辻井伸行さんの演奏映像などを視聴すればいいのだが、参考にはなっても音質の面で繊細な部分を聴き取るのは難しい。したがって手元にある、中国・重慶出身のピアニスト、ユンディ・リ(Yundi Li)のグラモフォン盤で、2002年ベルリンでデジタル・レコーディングされた「ラ・カンパネラ」と比較してみることにした。結果、この比較は意外なほどロマンチックで面白い試みとなった。
技巧派のピアニスト達が楽譜を通じて得られる、リストの“超絶技巧”的な側面を競い合う様は、私には肌が合わない。そうした問題以前に、ピアノという打鍵楽器を取り巻く《空間》(=空気感の処理)が、昔と今とではまるで違うことに驚かされる。そしてこのことは、録られたソースのテイクを巧みに編集する技術革新の差よりも、もっと直接感覚に訴えてくるものではないかとさえ思う。
ピアニストと録音に関わるスタッフの、ピアノとはいったいなんぞや、という価値観の摺り合わせが、録音される《空間》に大きな影響を与えるのだが、賀集さんの演奏とユンディ・リの演奏とでは、それぞれ個人の身体的あるいは五感的感覚の違いによって、ピアノの音が伝わる《空間》そのものがまったく別物であるかのような印象を受けた。《空間》の存在感が違うということは、その《空間》における時間のゆらぎも違うのではないか。
ユンディ・リの録音は2002年のデジタル・レコーディングである。つまりデジタル・レコーディングの潮流としては、第二第三の進歩的な時代の録音物である。
進歩的であるが故に、賀集さんの「ラ・カンパネラ」が録られた時代よりも、録る技術の蓄積がいったんリセットされ、進歩した新たな技術が熟成されていない面がある。具体的に言えることは、それまで長く続いたデジタル・テープ式のレコーディングの経験則がいよいよ通用しなくなり、新たなデジタル・レコーディングの技術の練達を模索し始めた頃に相応する。
したがって、ユンディ・リのピアノの演奏を録るという現場での作業は、常に未知なる新しいものへの挑戦という形にならざるを得ない。いずれにしてもピアノの響きは明色となり、滲みの少ない分離の良いサウンドとなることは当然だ。まるで白く澄んだような《空間》を意識した、いわゆるオフ・マイクによる録音のねらいは、この時のユンディ・リの「ラ・カンパネラ」のように軽やかで若々しく、婚礼の祝福の場で響く鐘音と紙吹雪を思わせる明るいエレガントな音を作り出すためである。ユンディ・リの「ラ・カンパネラ」はそうした《空間》と自身の五感的感覚とがうまく調合され、結実した作品となっている。言い換えれば、ユンディ・リの「ラ・カンパネラ」のリズムは、彼自身の身体から呼応した「本能のリズム」なのだ。
翻って賀集さんの演奏は、それとは性質が違う。己の身体によるリズムを抑制し、あくまでリストの身体の《記憶》から得たリズム――すなわちハンガリーの民族音楽的なリズム――を再生しようとしたのではなかったか。
そうなると私は、かつての幼少時代に、失われていく民族音楽の痕跡を、賀集さんの「ラ・カンパネラ」から聴き取っていた、ことになる。フランツ・リストの曲が、単なる“超絶技巧”のモンスターではないことを、賀集さんは実践的に示していたのだ。
果たして、私が聴き続けていた「名曲鑑賞レコード」の中の賀集裕子演奏「ラ・カンパネラ」が、いま、誰でも聴ける状態にあるのかどうか、調べてみなければならない。リストがシューマンの妻クララに捧げたと言われるこの曲の真意なる旋律とは、リズムとは、いかなるものであったのか。私の飛躍した空想の矛先はそこに尽きる。
自我の発芽となるような自由で現代的な感性の演奏も悪くないが、どこか仄暗さを感じさせる《いにしえ》の旅とおぼしき音楽の発見は、長くゾクゾクするような気分にさせられるから、これはこれでいい。
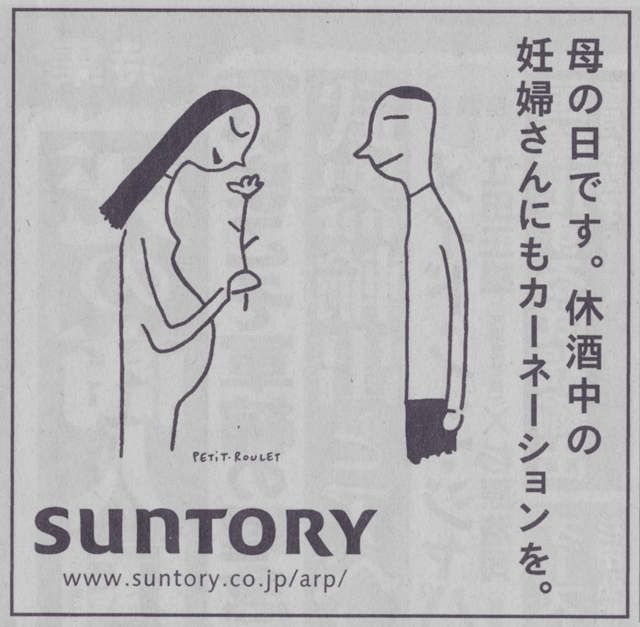
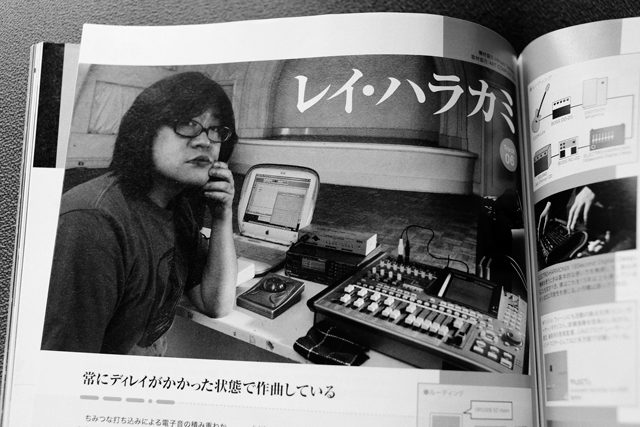
コメント
はじめまして!
賀集裕子さんのラ・カンパネラを是非!聴いてみたいです。
メッセージありがとうございます!
賀集さんの「ラ・カンパネラ」は本当に素晴らしいですね。
調べてみても、今聴ける賀集さんの「ラ・カンパネラ」の音源は見つからないですねえ。CD『束の間の幻影』はプロコフィエフとかフォーレの作品集ですし…。
私がブログで紹介した、例の百科辞典のレコードをヤフオクなどで探し求めるしか方法はないかも知れません。幸い、現時点では、ヤフオクで検索したところ、貴重なレコードセットが出品されていますので、この機会に入手なされると良いかも知れません。
以下、Amazonでの賀集さんのプロフィールを列記しておきます。
《1935年1月1日生まれ。5歳よりピアノを始め、天野愛子、パウル・シュルツ、井口基成、井口愛子に師事。1944年から約1年間音羽ゆりかご会に在籍し、童謡歌手として活躍。退団後はNHKのラジオ放送にピアノ独奏でたびたび出演。1951年、第20回日本音楽コンクール第1位入賞。桐朋女子高等学校音楽科入学後、1953年1月に日比谷公会堂において第1回ピアノ・リサイタルを開催。5月、パリに留学しイーヴ・ナットに師事。パリ国立音楽院ピアノ科及びソルフェージュ科卒業。1956年、エリザベート王妃国際音楽コンクール第10位入賞。帰国後はリサイタルを始め、N響定期公演や東京交響楽団、日フィル、東フィルなど数多くのオーケストラとの共演や労音コンサートなどで幅広く活躍。
その後、国立音楽大学客員教授として後進の指導に専念していたが、1998年に30年ぶりにリサイタルを行い高評を博した》