 |
| 【古河市・古河公方公園内の富士見塚あたり】 |
私が子供の頃の遊び場だった古河公方公園(古河総合公園)を先日訪れた。茨城県古河市にある古河公方公園は、初代古河公方(くぼう)の足利成氏から数えて五代目となる足利義氏の墓所がある公園で、その園内の一角が「史跡 古河公方足利義氏墓所」(徳源院跡)となっている。子供にとってそこは墓所でもなんでもない、大きな木々に囲まれて日差しを遮る屋外の休憩所的存在であって、足利義氏が一体何者なのかさえ知らなかった。私がこの夏、この公園を訪れた理由を正直に言うなれば、とどのつまり「イナゴの佃煮」が食べたかったのである。「イナゴの佃煮」? さて、何の話か――。無論、そこには「イナゴの佃煮」なんてものはない。だが、昔はあった。確かに売っていたのだ。これは、そんなような詰まらぬ話である。
梅雨空でさっぱり映えない、灰色の炎天下の午後。およそ十数年ぶりに茨城県・古河公方公園を訪れた。14年前にこの公園は、ユネスコとギリシャ主催のメリナ・メルクーリ国際賞を受賞している。メリナ・メルクーリ国際賞は、世界遺産として文化景観の優れた人工庭園や公園などに与えられる賞である。古河公方公園は毎年春先に桃まつり(ハナモモの桃林)が催され、全国から多くの観光客が訪れる。
季節によってはそうして人、人、人で溢れて賑やかになるであろうこの公園に、私は久しく、足を運んでいなかった。子供の頃、あまりにもよくここへ訪れていたせいもある。だから、その頃の公園の様子と今の公園の様子とでは、雲泥の差があり、すっかり美しく変わり映えしてしまったことにまず、驚きを覚えた。確か20年ほど前、初めて買った銀塩の一眼レフカメラを試し撮りしたく、ここに訪れて、冬の時期の殺風景な桃林を何枚も写真に収めたことがあったが、その頃からどうも、園内が少しずつ拡張され、あちらこちら整備され、私の“存じ得ない”緑と森の空間に変貌を遂げたらしく、いまこの公園を俯瞰して見返せば、やはり異国の人に感動を与えるメリナ・メルクーリの賞に相応しいのではないか、と思われるのである。
§
 |
| 【古河公方公園・蓮池の風景】 |
公園の中央には、御所沼の水辺が優雅に佇み、植物や小さな生物が豊かに生息する。耳を澄ますと、風で遠くの木々の擦れる音が聴こえ、虫たちの鳴き音も聴こえてくる。きわめて長閑である。水辺に取り囲まれた森の色彩が、とても目に優しく飽きが来ない。ここでの環境というのは、訪れる人にとっても、また自然の生き物達にとっても、時間の流れがとてもゆるりとした、ある種超然とした《憩いの場所》なのに違いない。
桃林の周辺の蓮池は、昔とはだいぶ様変わりしていたので最も驚いた。といっても子供の頃は、ハスという植物に何ら興味が湧かなかった。しかしながら、この蓮池のオオガハスはすくすくと育って大変立派である。子供の身長を優に超えてしまう大きさだ。昔は、こんな立派なハスはなかったのではないか。
そう、昔はきわめて殺風景だったのである。あの頃はただ漠然と、学校の写生会でここに訪れ、あまりにも殺風景でどこをどう描いていいのか分からなかったから、描き始めるのにえらく時間がかかったのだ。今のようにオオガハスがこんなに大きく咲いていたならば、こぞってこれを描いたであろう。どれほど絵の具の水を薄めれば、このような美しい花の色になるか。誰しも絵を描くことが楽しくなったかも知れない。夏はオオガハスが一面繁茂し、サルスベリやノウゼンカズラ、キキョウなどが盛んとなり、秋にはススキやコスモスの花が咲き乱れるのだろう。春には当然、桜や桃の花で人々を魅了する。
 |
| 【ハスの花の美しさは幽玄を思わせる】 |
この公園の「富士見塚」のところで、かつて我々は、木製のアスレチック遊具で遊んだり、そのあたりに腰掛けて談笑したり、時には忍者ごっこなどをしたりして遊んだ。あの頃は単なる盛り土にしか見えなかったこの「富士見塚」は、今はとても美しい景観となって写真映えする。富士見塚という名称よりも、こんもりとした山の形から「緑の丘」という表現が愛称として相応しい。ここは、今でも子供らがはしゃいでめいめいの遊戯に夢中になる一帯である。最も子供らの声が飛び交う場所でもある。そうしたこの場所の片隅に、かつて、みすぼらしい小さな売店があった。
§
昔、そこにあった売店の戸口には、ビニル袋に入れられた「イナゴの佃煮」が、無造作に吊り下げられていた。――その頃イナゴなどは、秋になると、どこの田圃でも刈り上げられた稲の束に、それこそ無数にへばりついていたものである。今ではすっかり見かけなくなってしまった――。私はある日、その売店の戸口に吊り下げられていたビニル袋の中身の、得体の知れない食べ物を発見して、思わずぞっとした。そして奇妙な面持ちでずっと眺めていたことがあった。
それは子供らにとっても、奇怪で得体の知れない食べ物であったに違いない。袋の中は、まったくもって原形のバッタの形をとどめている。どれもこれもふっくらとした体躯のイナゴ数十匹が詰まっていた。見た目、とてつもなくグロテスクである。赤みを帯びて小麦色に煮詰められた佃煮のイナゴは、あまり美味しそうには見えなかった。けれども、どういうわけか私の好奇心は、なかなかその欲求を抑えることができなかった。
私の欲求。そのグロテスクな「イナゴの佃煮」を食べてみたいということ――。公園に来るたびに眺めては、欲求不満になった。
ところがその欲求不満は、ある日解消された。間もない頃、思い切ってそれを買ってみたのだ。300円だったか400円だったか、子供にしては少々高い金額であったけれども、好奇心の度合いからすれば、それ相応の対価であると思われた(こうした好奇心は、その頃テレビで流行っていた“川口浩探検隊”の影響かも知れぬ)。
 |
| 【古河の佃煮の老舗・ぬた屋の「わかさぎ佃煮」】 |
早速、家に帰って買ってきた「イナゴの佃煮」を食べてみると、案外不味いものではなかった。佃煮らしい香ばしくて甘味のあるもっちりとした感触。
だが、さすがにバッタの形は、それなりに大きめで、口の中で乱雑に彷徨い続ける。これがえらく難儀であった。なかなか喉に通せないのだ。何より、イナゴの脚が口の中のあちこちに引っ掛かるのである。引っ掛かった脚を、ちょっとばかり口の外にペロリと出して鏡で見たら、かなりグロテスクで自分が怖くなった。
 |
| 【ぬた屋の「わかさぎ佃煮」】 |
イナゴは、噛み砕くのに時間がかかる。特に大振りのイナゴは難がある、という少年期の発見。食べ応えがある一方で、俺は正真正銘バッタなんだぜぇ、というバッタの強い自己主張に辟易としてくる。ああ、同じ佃煮でも、あの柔らかいアサリの佃煮だったら、まろやかに口の中で味が溶けてそのまま喉に通せるのに。こいつらはまったくな存在だぜ、人間のことなんかちっとも考えていないじゃないか。人間が食べるという自由な夢想に、食べる浪漫ということに、少しも配慮がないんだ、こいつらは。誰がイナゴを、佃煮にした!いったいどこの誰が!刺さるんだよ!脚がぁぁ!
――「イナゴの佃煮」は、そういう人情を包容する優しい趣というかphaseが、まるで欠けているということに気づかされるのであって、決して不味いものではないけれども、原野の如く《野生種》なのである。素っ気なく非哲学的ですらある。その愛情に欠けた「イナゴの佃煮」をもう一度食べてみたいと思ったところ、残念ながら今回はそれに、ありつけなかった――。
§
つまり、公園を去った後、私は、地元の佃煮の老舗、「ぬた屋」に行ってみたのである。以前この店で販売していたはずの「イナゴの佃煮」はあるか、とおかみさんに訊いたら、ない、と言われた。国産のイナゴが捕れない、というのが理由らしい。少々残念でありつつ、ほっとした。
店内に並んでいた佃煮に目移りした挙げ句、一つ選んで買ってみたのが、「わかさぎの佃煮」である。これは美味い。実に美味い。哲学的である。淡水魚のワカサギは「公魚」とも書く。佃煮の王様なのではないかと思った。
「公魚」と書いて思い出したのは、古河公方のことだ。が、もうよそう。公方様のことについては、もう少し本を読んでから勉強しよう。今はあの、美しい公園の風景に、思いを馳せていたい。
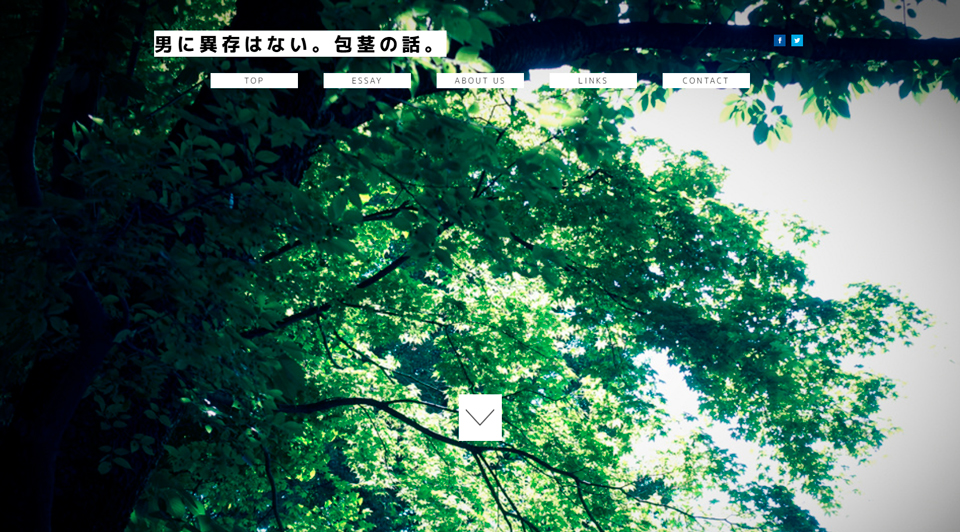
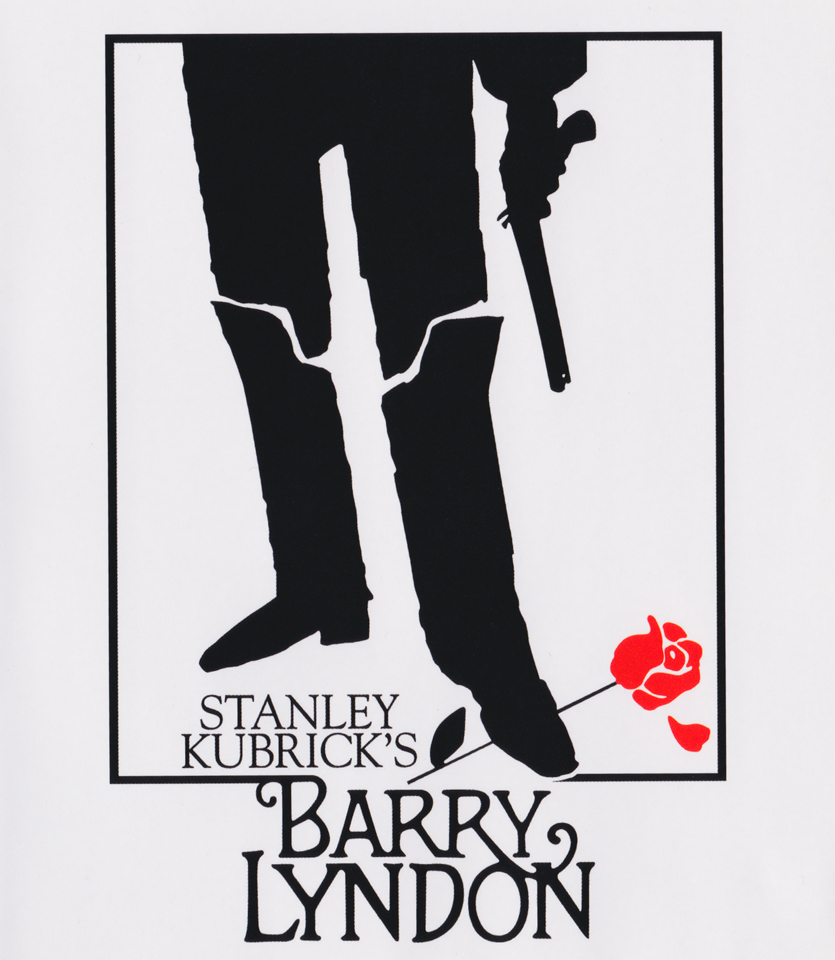
コメント