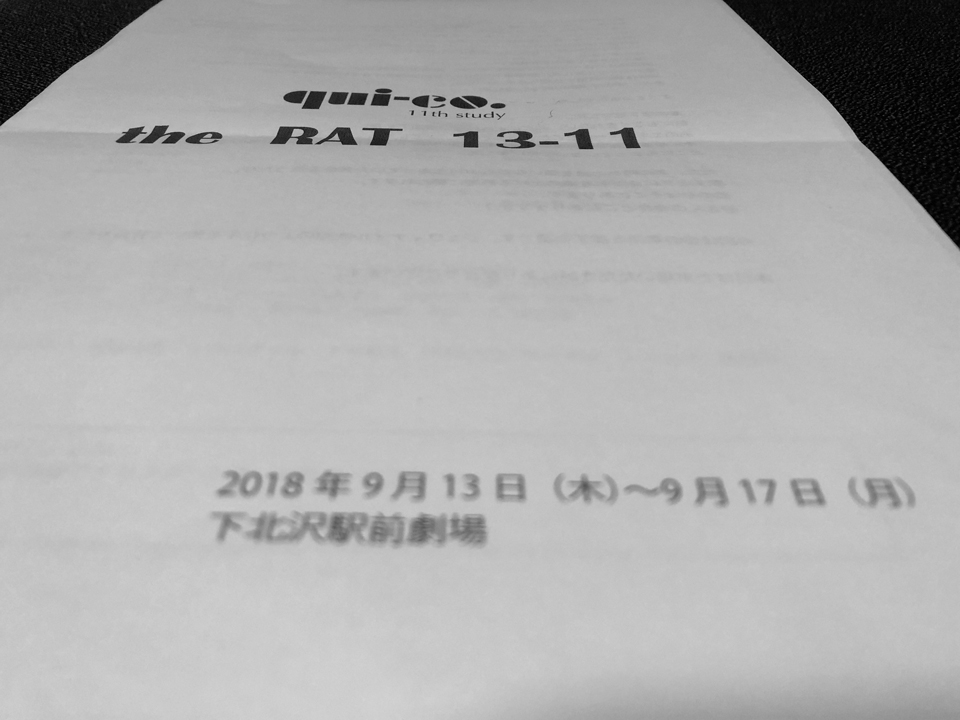 |
| 【キコ/qui-co.公演『the rat 13-11』】 |
工業高校の3年生だった1990年の9月26日。
それは学校の帰り――。友達に連れられて、雨の降る中、下北沢のスズナリの、どうにもならないほど狭いスペースにて、ぎゅうぎゅう詰めの観客の群れに肩や腕を揉まれながら座布団に尻を付けて“胡坐”(あぐら)状態で、演劇を観た。善人会議(現・扉座)の公演『まほうつかいのでし』。
それは魔法使いの弟子が、いっぱしの魔法使いになるために、人間を利用し、洪水をおこさせようとする話。でもこの選んだ人間が、アパート暮らしのぐうたら青年で、魔法使いの弟子の活発な行動癖に興味なく引きこもってしまっている。ところがこのぐうたら青年のイマジネーションの産物が、思いもよらぬ事態へと発展する――。
 |
| 【下北沢の駅前。駅舎工事の最中】 |
“胡坐”で演劇を観たのはたぶん、あれ一度きりだった。高校時代に駆け込んだスズナリの、そのアウトオブバウンズな記憶のレイヤーを重ね合わせつつ、先週の9月16日、世田谷区・下北沢駅前劇場にて、キコ/qui-co.(主宰・小栗剛)の演劇公演『the rat 13-11』を観たのだった。
こうして私が下北沢で演劇を観るのにやって来たのは、本当に久しぶりのことであった。井の頭線の下北沢駅は駅舎工事の最中で、その分、周囲の風景はやや雑然として不均衡であった。しかし、行き交う若者達の表情は明るい。きっとこの空気は、この街の永年変わらぬエネルギッシュな射影なのだろう。ヴィレッジ・ヴァンガードでお気に入りのアイテムを見つけた。が、開場時間がまもなくであることに気づき、店を出る。近いうちにまたここに来ることをここで約束される――。
§
キコ/qui-co.の『the rat 13-11』を観た。2本立て公演であり、私が観たのは片方の「the rat 11」。
――あれから1週間。私がすぐにこの舞台の感想を書くことができなかったのは、個人的に1年以上にわたる、ある「愛の錯誤」の問題を片付けようとしていたからだ。第三者をまじえて、この問題は解決の糸口が見出されたかにも見える。しかし、まだ終わったわけではなかった。愛の問題に終わりはないのだ。尊いはずの愛は、人を幸せにもし、傷つき、不幸にもする。まだ私の心は、落ち着きを取り戻してはいない。
それでもなんとか、あの舞台で起きたことに向き合いたい。向き合うことで、何らかの傷痕を縫合したいと願う。今だから、その第一歩を踏み出そうとしている。この今の、とても形になっていない汚泥のような文章を、どうかお許し願いたい。
「the rat 11」も愛の話である。恋という禍が始まり、その愛する人への告解の儀式=《kiss》によって、万物のすべてが一瞬にして光となり暗黒となり終わってしまう=この世が崩壊する、そんな恐ろしい話である。
実は開演前、観客席の片隅に腰をおろした後、その暗がりのあいだ、パンフの中の小栗さんの挨拶文を読んでしまった。思いがけず、読んでしまったのがいけなかった――。
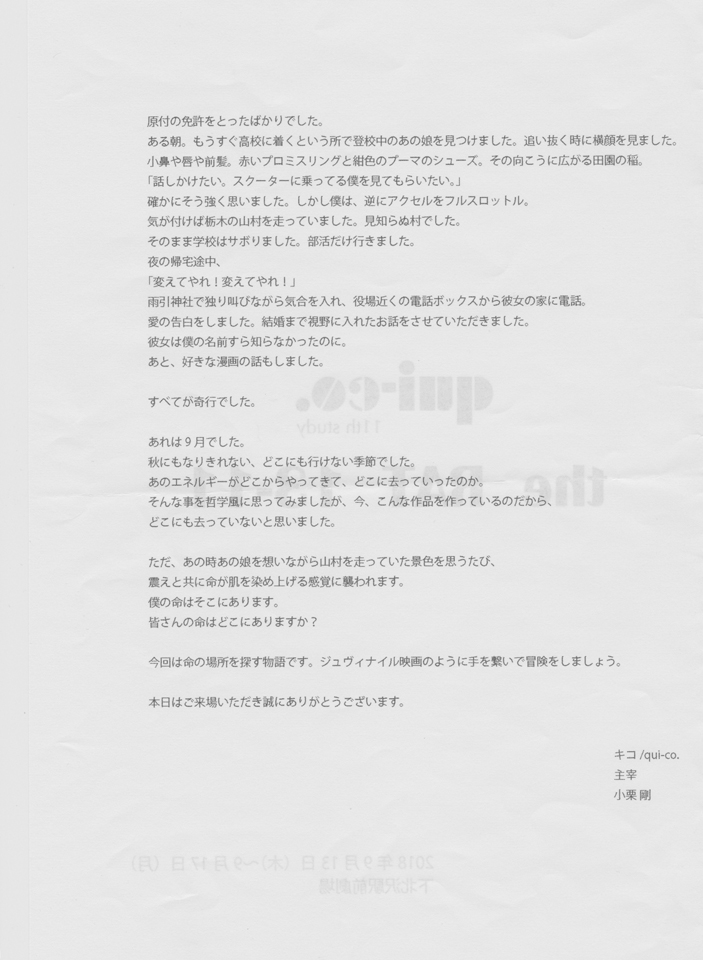 |
| 【公演パンフの主宰・小栗剛さんの挨拶文】 |
それは、高校時代のある回想である。小栗さんも、自身の高校時代の出来事と今回の演劇のテーマをリブートし、イニシャライズしていた。そうして濾過して抽出し、見えてくるのは、命であると。登校中に出会った“あの娘”の話。学校をサボり、その帰りの夜、神社で叫んだ後、役場の近くの電話ボックスからまだ知り合ってもいない“あの娘”に電話したという“奇行”――。
猛烈な恋のざわめきに共鳴して、高校生だった小栗さんは、自身の心と行動とを半端なく合致させていくという、まるで燻って消滅しかけていた焔が、一気に大きく燃え上がるような命の輝きの発見。ある種尋常でない、見境のない反動に、その命の輝きのカオスに、私は演劇を観る寸前にすっかり打ちのめされてしまったのだった。
ぼうっとし、舞台の遠くをただただ見つめるという数十分。何かそこで一つの演劇を観終わってしまったかのような、集中力の途切れた状態。これから始まる本当の舞台を、私はどう観続ければいいのかと、少々真剣に、不安でおののいたのだけれど、「the rat 11」は、あるニュータウンの高層マンションでうごめく人々の謎めいた葛藤を描いていた。
《目を瞑れば海の音が聞こえる。
高層マンションにドライヴィングシアター。住宅地に無理矢理地下鉄を通したニュータウンの街並み。
郊外の工業地帯は真夜中も白い煙を吐き、ニュータウンを貫く幹線道路には赤いテールランプが蛇行する。
彼女は橋に佇んでいた。
綺麗なニュータウンの中で街の外へと繋がるこの橋だけが朽ちている。土曜日の夕暮れには一人訪れ、手すりの錆に触れてみる。その指を口元に近づけると鉄の匂いがした。そうすると彼女は妙に安心し、その時だけは欲情する事ができた。
その日、部屋に戻ると一匹のハツカネズミを見つけた。そして彼女は、気付いてしまった。ある不自然に。ここに住み始めて11年。
この街の住人誰ひとりとして、一歩たりともこの街から出ていない。
それは自分が愛する彼氏もそう。それどころか、自分自身も、そう。
11年間も街の外に出ていないことに「気付かずにいた」。
9月の夕暮れ。彼女は錆の橋を目指す。橋の向こうを目指す。11年間佇むだけで渡る事をしなかったあの橋。
スニーカーを履いてマンションを出る。振り返る。もう戻らないかもしれない住居。そう思うと感傷的になった。
だからその時初めてマンションの名前が目に入った。
その名は「トロイメライ」。
意味は、夢見心地》
(キコ/qui-co.ホームページ、「ラット11」ストーリーボードより引用)
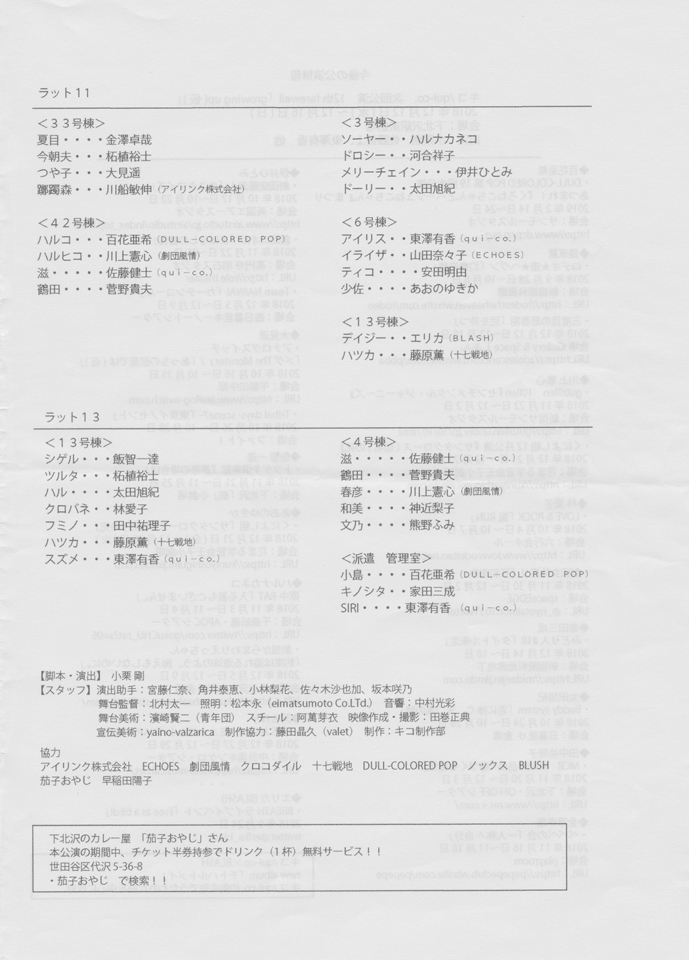 |
| 【パンフ。キャストとスタッフ】 |
そこに住む者達は、いにしえのイコンである古いネットワーク・システムのケータイ端末であるとか、ショウワというとても古い時代の世俗風習を面白がって興味を抱いていた。そうした過去のアンティーク・ムーヴに触れる好奇心というのは、一種の対称化されたサブ・カルチャーに対する萌えであって、未来・現在・過去を行き来する新奇な感覚は、常に人々を興奮させ悩ませる。
人間と人間だけが触れ合っていた時代は過去のこと。人と人、人とAI(人工知能を持ったアンドロイドと言っていい)、AIとAIのコミュニケーションがそこにはあって、さらに付け加えれば、ハツカネズミ。想像を働かせると、見た目、人もAIもハツカネズミも区別のつかない世界なのだろう。もはや――と枕詞にするべき、秩序の安寧も平和も破棄された、ただただ不安だけが残るひとりぼっちなフィールドの、未来のどこかの、ニュータウンの話である。
 |
| 【本多劇場グループの公演掲示板。駅前劇場にキコ/qui-co.のフライヤー】 |
ここでやがて訪れる「静かなる狂気」と言うべきものは、人々がごくありふれた幸せを手にするための平然とした街の佇まいがすべてを裏切って、singularityの先に絶望が待ち構えていた、というとてつもない終焉が、たった小さな心のもたらした《kiss》によって引き起こされるという悲劇である。
《kiss》は、本来、人を幸せにするもの。幸せと幸せを分かち合うもの。愛の告解(懺悔)ではなく清浄な告白であるべきもの。愛しい人への小さな《kiss》は、いかなる時空であっても永遠であるべき尊いものなのに、それがそうではないと知った時。
キコの演劇の、壮絶な愛と命の物語と、私自身が抱えている「愛の錯誤」とが偶然にもsynchronicityの先々へと結ばれていき、私はしどろもどろとなる。飛び越えられない。これ以上の言葉が見つからない。――いや、音楽だ。あの歌の片鱗が、耳の奥にまだ残っている。これは絶望ではない、救いの歌なのだ。
小栗さんは今も、心の中で見知らぬ山村を走り続けているのだろう。何かを追いかけ、何かに出逢うために。その風景を、私は確かに、憶えている。あのあたりの山間は、どこまでもどこまでも暗く、沈んでいるということを。既視感でないはっきりとした残影。私が生まれて育ったニュータウン=団地は、そこからそれほど遠い場所ではなかった。何かが音を立てて共鳴している演劇を、私は観たのだった。


コメント