 |
| 【私がかつて住んでいた団地集合住宅(2018年撮影)】 |
レコードの溝を走る針のパチパチと、歪んだ小型スピーカーのじゃれついた音が懐かしく感じられる。団地集合住宅の5階。六畳間に据え置かれたナショナル家具調カラーテレビの上の、古びたレコード・プレーヤー。幼かった私は、手が届くか届かないかの微妙の高さに心が折れそうになりながらも、音が出る不思議な機械の操作というのは、2歳か3歳の好奇心を掻き立てるのに充分であった。音、あるいは音楽とは、その頃の私にとって《恐ろしい闇》であり、その魔窟をくぐり抜ける孤独な儀式なのであった。次はどんなレコードをかけようか。どんな冒険が待ち受けているのか――。洋菓子の箱の中の積み重なったレコード盤を引っかき回して、一枚のシングルレコードを取り出す。そうして背伸びをしながら針を落とす所作は、大人の仕業を模倣した禁忌的背徳の快感であった。何よりそれが、私という自我の強烈な出発点だったのだから(当ブログ「団地―冬空の経験」参照)。
§
灰色の空であった。それでいて気分は陽気であった。ポール・チェンバースのベース、ソニー・クラークのピアノ、ドナルド・バードのトランペット、そしてジャッキー・マクリーンのアルト・サックスが奏でる50年代のブルーノートのいくつかの曲が、何故か頭の中でぐるぐると反復しながら、私はその懐かしいアパート団地へと向かった。まだ先月末のことである。
そこは“アオバダイ”という住宅地が裏手にひしめく、踏切のある線路沿いの盆地に落とし込まれた、7つの棟のアパート団地。いまではすっかり古びてしまった一角。昔その周辺は沼だったという話を聞いたことがあったけれど、幼少時代、私は確かに其所の、住人であった。
アパート団地の入口の小道には、かつて一軒のあばら家があった。ひそひそと小声で話すまでもなく露骨に、「オバケヤシキ!」と皆で呼んでいた。廃れた家屋のぼろぼろに破れた襖から、家具やこたつがそのまま放置された居間を覗くことができ、夜、その誰もいないはずの居間の、赤い小型テレビがぽつりと点灯して、コマーシャルの映像をちらりと見た――という人がいて驚いた。たぶん地縛霊となった家主が、笑いながらテレビを見ているんだろう、というのだった。私はその大人同士の話をうっかり聞いて背筋が凍り付き、一人では絶対にあそこには近づかぬと決心した。
そんな怪しい話を心に秘め、その日の午後、アパート団地の入口の小道の坂を下り、5階建てのいくつかの棟の中央に差し掛かった。当然ながらあの“オバケヤシキ”は影も形もなく、その周辺はまったくありふれた住宅と住宅の糊代と化していた。42年ぶりにその場所に立った感覚が、あまりにも味気ない、どうってことのない感覚だったので、私はすっかり拍子抜けしてしまった。
いや、あまりにも感覚が、ここで言うのは平衡感覚が、違いすぎたのである。幼少だったあの頃は、団地を見上げるどころかあらゆる設置物や小屋のたぐいすらも高々と見上げていたし、広々とした空間を汗を切らし歩き回ったはずだ。いまそこに佇立してみると、むしろ狭苦しい、鬱陶しい、ひっそりと声もなく静まりかえった趣に、どうもヘンテコな、そこに住んでいた確証を喪失してしまったかのような、不可思議ならざる意識に駆られたのである。
シンボルタワー的存在だった“のっぽの貯水塔”は水簿らしく摩滅し、人々の活気はなく、うごめいているのは風。かつて沼地を吹き抜けていたはずの風だけが、私の頬をかすめて記憶を微かに呼び起こしたのだけれど、もしかするとそれは風などではなくて、あの“オバケヤシキ”の家主の、〈おいぼうず、久しぶりだな〉というご丁寧な霊気の挨拶だったのかも知れないのだ。
§
朝起きるとまず、「ママとあそぼう!ピンポンパン」が始まる。ピンポンパンの大きな樹木の中に積まれたオモチャを目撃した後は、ガチャピンとムックの「ひらけ!ポンキッキ」である。ガチャピンより大人しいムックが好きだった。ペギー葉山が好きだった。その後は、「ロンパールーム」である。番組の中の子どもたちが皆、ナマイキだ…という印象があった。
昼頃になると母親に連れられて、近所の商店で食べ物やら日用品などを買い、雨があがった地べたの水溜まりにぴちゃぴちゃと靴で歩くのがたまらなく愉快であった。そうして昼下がりの午後は、昼寝をしたり、書棚に据え置かれた百科事典などを開いて眺めたりして、夕刻はまたテレビのアニメを見たりする。時折、周辺の団地の住人が奇声を上げているのを聞いてベランダに出ると、なんてことはないそれは奇声でもなんでもなく、テレビを見て笑っている声であったりとか、本当に事件だったのは、同じ棟の住人が「うちの壁にシロアリが発生して…」としどろもどろになって訪れたので、足早にその人の室に駆け込むと、壁一面にうごめくシロアリ達が忙しそうに行進していて驚いた。テレビのベトナム戦争の兵隊さんや日本赤軍の過激派のゲリラ事件と連動して私にとってはそのアリ達も、同じうごめく輩のように思えてならなかった。
夜、寝る前の所作としては、気持ちの高まりを抑えきれない。ハリー・ベラフォンテの真っ黒なレーベルのシングルレコードを取り出し、プレーヤーにかける。A面の「バナナ・ボート」(“Day-O”)が聴きたかったのに、うっかりB面を表にしてしまって音が流れてきたのは、優しいギターの音色で始まるカリプソの「さらばジャマイカ」(“Jamaica Farewell”)。
また明日も平凡な一日を過ごそう。雨の日も、風の日も。重い鉄製の扉を開け、5階を降りたり昇ったりしていた踊り場の空気は、どこか埃っぽくて喉をついた。何かを待ち望んでいたのでも、何かを夢見ていたのでもない。ただただ平凡な一日が、なんてこともなく楽しかった。それが私の、昭和49年頃の、団地での生活であった。
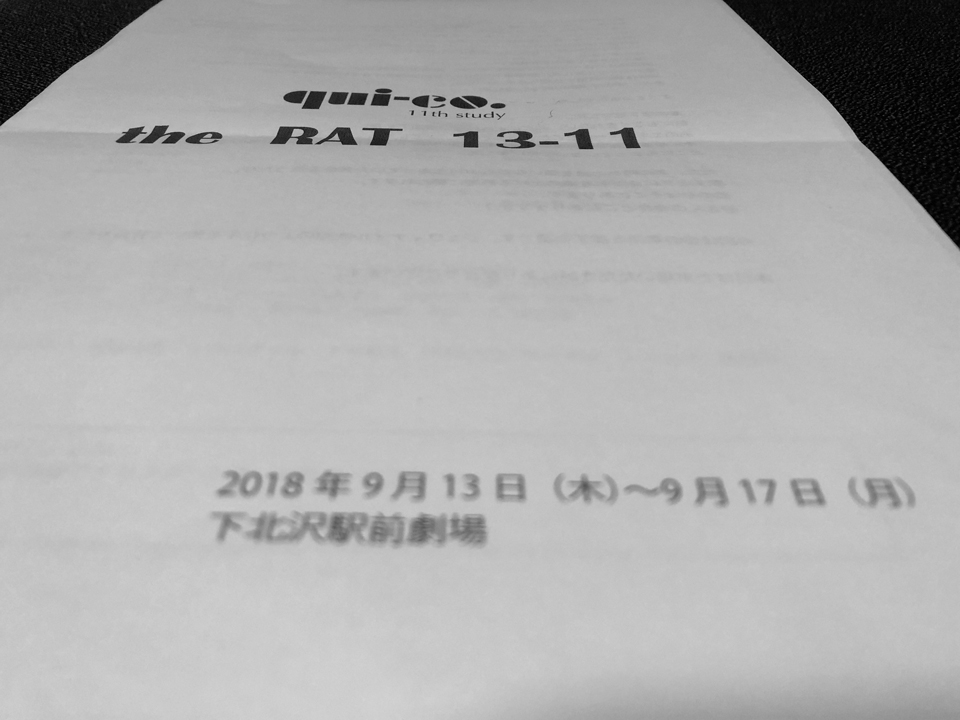

コメント