 |
| 【映画『幸せはパリで』のカトリーヌ・ドヌーヴとジャック・レモン】 |
恋とか愛とかの瑣末で、私自身の内と外で実際に起きていることや起こりつつあることを、露骨にあれやこれやと書くのは控えたい。しかし、とりあえずそのことは脇に置いておくことにして、何より、その恋とか愛とかで露出した《粘膜》の炎症を、さしあたって治癒すべく、意識的に聴き返したバート・バカラックの音楽とその映画について書いておきたい。
私はこの映画を観て、心が大いに和み、平常心を取り戻すことができた。情緒が激しく揺さぶられたのち、やがて心理的には沈静化して、恋とか愛とかの思考を静かに継続することができた。バカラックのおかげである。はて、この男いったい、何を言いたいのかと思うこと勿れ――。ともかくその曲は、バカラックの「The April Fools」であり、ある映画の主題歌でもある。振り返ると私は5年前、こんなことを書いていた。
《春になるとバカラックの音楽が聴きたくなり、キューブリックの映画が観たくなる――。バカラック作曲の主題歌である映画『幸せはパリで』の「The April Fools」。胸が押しつけられるような切ない曲で、20代の頃によく聴いていました。
カトリーヌ・ドヌーヴとジャック・レモン主演『幸せはパリで』(スチュアート・ローゼンバーグ監督)の映画はまだ観たことがない。現在、DVDの販売はないようで、古いVHSでも高値なのでレンタルで借りるぐらいしか手はありません。しかしタイミング良く、NHKさんあたりが放送してくれればいいなと思ってはいますが…》
カトリーヌ・ドヌーヴとジャック・レモン主演『幸せはパリで』(スチュアート・ローゼンバーグ監督)の映画はまだ観たことがない。現在、DVDの販売はないようで、古いVHSでも高値なのでレンタルで借りるぐらいしか手はありません。しかしタイミング良く、NHKさんあたりが放送してくれればいいなと思ってはいますが…》
ホームページ[Dodidn*]の「今月のMessage」のコラムで、2013年の4月にそれを書いたのだった。そうして今年になってこの映画が観たくなり、ネットショップで検索してみたところ、どうやら幸いにも近年DVD化されたようで、簡単にそのDVDを入手することができた。――私は今、この映画を観終わり、余韻に浸っている。エンディングでディオンヌ・ワーウィックが歌う「The April Fools」が、両耳にこびりついている。湿った夜の夏のかがり火となって、私の心はさらによろめいていった――。
§
ジャック・レモン主演の名画の数々を、私はほとんど観た記憶がない。ジャック・レモンの顔をたちまち思い起こそうとすると、ヘンリー・フォンダの顔が浮かんできてしまう。唯一、ジェームズ・ブリッジス監督の映画『チャイナ・シンドローム』(1979年)は別である。あの映画は何度も観た。彼、ジャック・レモンは原発施設のエンジニアというはまり役で、得意なコミカルな演技はかなり抑え気味だった。施設内で起こった事故の危険性を内外に訴えかけるベテラン技師の役柄には、胸を打たれた。
カトリーヌ・ドヌーヴの方は今年、加熱した“#MeToo”運動に対して少々独善的な反ピューリタニズム発言をし、物議を醸した。映画『万引き家族』でパルムドールを受賞した映画監督・是枝裕和氏の2019年公開(予定)映画に出演――といった話題でも国内のメディアを賑わし、いまだ女優としての品格と美貌が健在であることに私は拍手喝采したのだけれど、彼女の代表作であるジャック・ドゥミ監督の『シェルブールの雨傘』(1964年)以外では、レオス・カラックス監督の『ポーラX』(1999年)が印象にある。
カトリーヌ・ドヌーヴの方は今年、加熱した“#MeToo”運動に対して少々独善的な反ピューリタニズム発言をし、物議を醸した。映画『万引き家族』でパルムドールを受賞した映画監督・是枝裕和氏の2019年公開(予定)映画に出演――といった話題でも国内のメディアを賑わし、いまだ女優としての品格と美貌が健在であることに私は拍手喝采したのだけれど、彼女の代表作であるジャック・ドゥミ監督の『シェルブールの雨傘』(1964年)以外では、レオス・カラックス監督の『ポーラX』(1999年)が印象にある。
1969年、スチュアート・ローゼンバーグ監督率いるアメリカ映画に、カトリーヌ・ドヌーヴがフランス映画界から“来賓”として招かれ、なんとあのジャック・レモンと競演――というメルヘンティックな話題だけで充分な『幸せはパリで』(原題“The April Fools”)。キャッチ・コピーは、“ロマンティック・コメディの傑作”。
実際、この映画のストーリーは、しごく単純明快である。複雑な要素が何一つない。夫婦生活に恵まれないサラリーマン(ハワード・ブルーベーカー役のジャック・レモン)がニューヨークの奇天烈サイケ調のパーティで社長夫人(カトリーヌ・ガンサー役のカトリーヌ・ドヌーヴ)と出逢い、その日のうちに恋に落ちる。本当にそれ以外の要素は何もなく、終始、ブルーベーカーはおちゃらけた態度であり、それにくっついて笑い、心がすっかり和むカトリーヌの笑顔。ただそれだけ。
だから不倫で複雑にもつれ合い、双方ゴタゴタズタズタのすったもんだなどのシーンなどなく、からっとしていて爽やか。ミュージカル仕立てにしてもおかしくない。誰のためでもなく明日の自分自身のためだけに、生きよう。すべてを投げ捨て、新しい地で前向きに、快活に生きよう。二人は、新天地――パリに旅立つことを決意し、空疎でなんのときめきもないそれぞれの夫婦関係を断ち、近親者に別れを告げ、パリ行きで滑走路に待機する飛行機へと乗り込む。
だから不倫で複雑にもつれ合い、双方ゴタゴタズタズタのすったもんだなどのシーンなどなく、からっとしていて爽やか。ミュージカル仕立てにしてもおかしくない。誰のためでもなく明日の自分自身のためだけに、生きよう。すべてを投げ捨て、新しい地で前向きに、快活に生きよう。二人は、新天地――パリに旅立つことを決意し、空疎でなんのときめきもないそれぞれの夫婦関係を断ち、近親者に別れを告げ、パリ行きで滑走路に待機する飛行機へと乗り込む。
先に席に着いたのはカトリーヌ。だが、まだブルーベーカーはやって来ず。隣の席は空いたまま。気持ちが落ち着かず、少々哀しみの気分が込み上げてくるカトリーヌ。観ている我々も、ドキドキとしてしまうラスト・シークェンスなのだが、このエンディングの、ささやかな愛のプレゼントが、何を隠そうバカラックの「The April Fools」なのである。
歌っているのはまだ若い頃の、ディオンヌ・ワーウィック。これは個人的な主観に過ぎないのだけれど、ほとんどこの映画、「The April Fools」を流して観客に聴いてもらうためだけの、お膳立て映画なのではないかと思えてしまう。映画の最初の方で二人が“サファリ・クラブ”という、文字通りサファリパークで酒を飲むといったエンタメ形式のクラブで羽目を外すのだが、このシーンを観ていると、この映画…あまりにジャック・レモンが素っ頓狂で大丈夫なのかい? と、不安に思ってしまって、ちょっと行き過ぎた“ロマンティック・コメディ”なのではないかと心配になる。
歌っているのはまだ若い頃の、ディオンヌ・ワーウィック。これは個人的な主観に過ぎないのだけれど、ほとんどこの映画、「The April Fools」を流して観客に聴いてもらうためだけの、お膳立て映画なのではないかと思えてしまう。映画の最初の方で二人が“サファリ・クラブ”という、文字通りサファリパークで酒を飲むといったエンタメ形式のクラブで羽目を外すのだが、このシーンを観ていると、この映画…あまりにジャック・レモンが素っ頓狂で大丈夫なのかい? と、不安に思ってしまって、ちょっと行き過ぎた“ロマンティック・コメディ”なのではないかと心配になる。
それもご愛敬。というかずっとご愛敬のシーンが続いて、それであのラスト・シークェンスなのである。ラスト・シークェンスで「The April Fools」を聴かせるだけの映画。そう言って間違いないのである。
ブルーベーカー夫人のフィリス・ブルーベーカー(演じたのはサリー・ケラーマン)も実を言うと魅力的で、夫人はしょっちゅう持ち家を替えたり内装をいじくったりするのが好きな性癖。ブルーベーカーはこんな身勝手な夫人に愛想を尽かすのだけれど、意外と私は、この夫人の性癖に好感を持っている。もし私が有り余る預金を所有しているならば、もしかするとこの夫人のように、年中家を替えたり内装をいじくって楽しんでしまうかも知れない。
ブルーベーカー夫人のフィリス・ブルーベーカー(演じたのはサリー・ケラーマン)も実を言うと魅力的で、夫人はしょっちゅう持ち家を替えたり内装をいじくったりするのが好きな性癖。ブルーベーカーはこんな身勝手な夫人に愛想を尽かすのだけれど、意外と私は、この夫人の性癖に好感を持っている。もし私が有り余る預金を所有しているならば、もしかするとこの夫人のように、年中家を替えたり内装をいじくって楽しんでしまうかも知れない。
《Are we just April fools
Who can’t see all the danger around us…》
仕事がバリバリでき、昇進したばかりのサラリーマンが突然その仕事を捨て、唐突な出逢いから始まった愛の小さなさざ波に惹かれて、旅立っていくという喜劇。周囲は喜劇としか思えないが、本人達はいたって真面目。自ら感じる愛の不遇を、喜びの愛に変えるには、そんな喜劇を演じるほかはないのだ。邦題の“幸せはパリで”は、実にロマンチックな古めかしき恋愛を想起させてしまうが、原題にある“The April Fools”が示す、男と女の冗談のような瑣事、瓢箪から駒が出たような真の愛、出逢った喜びを分かち合おうといった意味合いが、この映画のテーマの不文律である。
どうやら二人はようやく人生を歩み始めたようで…そっとしておきましょう、といった大人の雰囲気が、ディオンヌの歌う「The April Fools」から感じられ、私は思わず涙ぐんでしまう。現在進行形のエイプリルフールが、様々な春風を巻き起こすに違いないと思った。


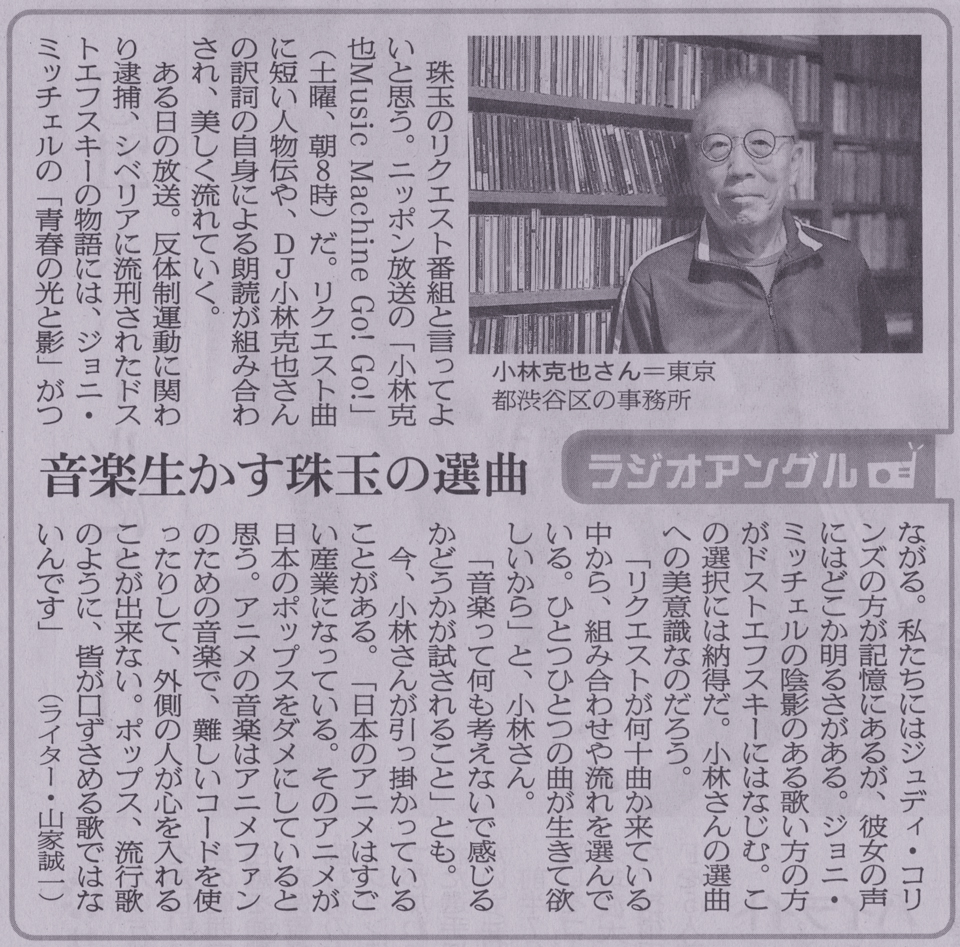
コメント