 |
| 【中国茶「白毫銀針」は白茶の美と味わいの代表格】 |
シリーズとなっている「お茶とサブ・カルチャーのアーティクル」の第10回目。前回は、私淑するmas氏の幻のウェブサイト「中国茶のオルタナティブ」から「茶」の発音の誤読の歴史についてと、中国茶の青茶「白芽奇蘭」(はくがきらん)についての思索であったが、今回登場する中国茶は、「白毫銀針」(はくごうぎんしん)。mas氏がかつてウェブで記した「中国茶のオルタナティブ」の中からコラムをピックアップし、その中国茶についても、深々とした醍醐味を味わってみたいと思う。
§
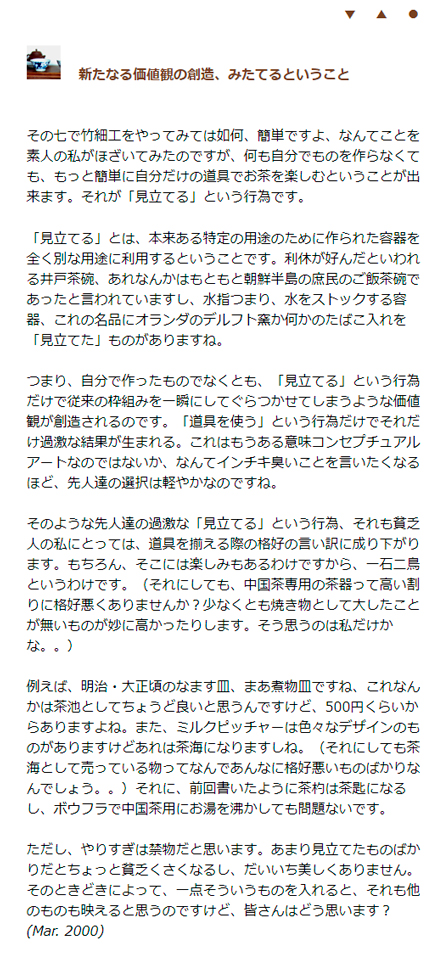 |
| 【mas氏の「中国茶のオルタナティブ」第8番目】 |
mas氏が2000年から2001年にかけて綴っていたウェブサイトのコラム「中国茶のオルタナティブ」の第8番目に、「新たなる価値観の創造、みたてるということ」(2000年3月投稿)というのがあった。茶の湯には、道具を“見立てる”という形式美があるという。以下、mas氏の文章を書き出してみる。
《「見立てる」とは、本来ある特定の用途のために作られた容器を全く別な用途に利用するということです。利休が好んだといわれる井戸茶碗、あれなんかはもともと朝鮮半島の庶民のご飯茶碗であったと言われていますし、水指つまり、水をストックする容器、これの名品にオランダのデルフト窯か何かのたばこ入れを「見立てた」ものがありますね。
つまり、自分で作ったものでなくとも、「見立てる」という行為だけで従来の枠組みを一瞬にしてぐらつかせてしまうような価値観が創造されるのです。「道具を使う」という行為だけでそれだけ過激な結果が生まれる。これはもうある意味コンセプチュアルアートなのではないか、なんてインチキ臭いことを言いたくなるほど、先人達の選択は軽やかなのですね》
(mas氏「中国茶のオルタナティブ」より引用)
《「見立てる」という行為だけで従来の枠組みを一瞬にしてぐらつかせてしまうような価値観が創造される》という文章に、私は、眼が覚めるような心地良い爽快感を味わう。
ここで出てくる「井戸茶碗」とは、高麗茶碗(朝鮮茶碗)の一種のことで、室町時代以後、茶人に珍重された茶碗を指し、侘び茶碗とも称されている。淡い卵色(枇杷色)の釉薬がかかっていて、形や質感は実に豊かで独創的である。
ゆえに、器の雰囲気として井戸茶碗は、現代人にすこぶる好まれる“無印良品”的な素朴然とした色と形の日用品の趣とは、真逆と言っていいだろう。焼き物の“焼き”というのは、常に人間の知力と想像を超えてくるものであるから、その結果としての多面的な構造であるとか質感であるとか、それらを総体的にとらえた美は、「茶の湯の精神」と合致するものなのである。
一方の“無印良品”的素朴さとは、用具としての工芸品の、言わば「生産性効率化への美意識の最適性」を具現したものであり、人間の無垢なる素朴さとは、少し意味合いが異なる。むしろ、人間的素朴さの精神を「人工的な工芸品の素朴さ」に抽象的に置き換えた、まさに「見立てる」という行為に表されることは一般にありがち、であるかも知れないが、画一化された物の羅列、その等価という点でこの発想は実に危ういのである。何故ならば、人間の素朴さとは、その人個人の身体と内面とによって「一滴に結晶化されたもの」なのであって、他者と羅列して等価云々と見るべきものではないのだから。
§
質実剛健をまさに体現したかのような井戸茶碗の現物を、普段、見る機会が個人的にはまったくない――。が、昔、『信長の野望』(1991年にスーファミ版で発売された同シリーズの「武将風雲録」)という歴史シミュレーション・ゲームで、茶碗などの茶器のアイテムを全国の戦国武将からトレードし蒐集して「茶会」を催す――といったゲーム内イベントにはまったことがあった。
それはそれは古風で品のいいBGMが流れつつ、擬似的には、茶碗集めに没頭したことになる。案外そのあたりの頃から、個人的に「茶の湯の精神」に関心があったのかも知れない。何気に思い出してみると、その『信長の野望』では、蒐集した茶器を持参し「茶会」を開くと、文化的教養であるとか忠誠心レベルが上がるといった、ちまちまとしたグロース&エクスペリエンス・システムがあってマニアックであった。なんとなく戦国武将の趣味だとか政治的労苦だとかが理解でき、中世の時代はなかなかたいへんだな、と思ったものである。
ところでもう一つ、mas氏が述べていた「デルフト窯」について調べたところ、それは16世紀頃、オランダのデルフト(Delft)あたりで生産される釉薬のかかった陶器を作り出す工房釜を指していた。そのいわゆる“デルフト陶器”(Delfts blauw)の見た目は、色彩の鮮やかさの点において日本の伊万里焼(有田焼)に酷似し、これまた“無印良品”とは真逆の存在感を醸し出しているものである。デルフトの“たばこ入れ”を茶の湯における水指として流用した――ということを例に取り、その「見立て」は、コンセプチュアル・アート(Conceptual Art)なのではないか、とmas氏は気炎を上げているのである。
 |
| 【産毛に覆われた「白毫銀針」の茶葉】 |
ここで私は一服――。中国茶を淹れることにした。選んだ茶葉は、「白毫銀針」。中国は福建省福鼎市政和県のお茶で、白い産毛(白毫)に覆われた茶葉(銀針)が特徴。白茶に属する。注がれた液体はほとんど透明に近いがやや黄色味を帯び、飲んでみるとこれがまた、実に爽やかで、産毛の生えた茶葉の雑駁としたイメージを覆し、高貴な花の香りで鼻腔が和らぐ。この一瞬は至福に満たされるであろう。したがって、親愛なる友人とのおしゃべりのひとときに最適であり、贈呈品としても好まれるのではないかと思う。
§
自身の生活圏で何かモノを「見立てる」工夫をした形跡はないか、いろいろ探してみたのだけれど、なかなかこれが思いつかないというか見当たらない。昔、英国製の紅茶の入った角張ったアルミ缶を、ピンホールカメラに仕立てた――ということがあったが、あくまでそれは工作のたぐいであって、実質の用途として「見立てる」ことには当てはまらない。「見立てる」という風流な日常の機微が、徐々に失われてきている証であろうか。
中国茶を淹れるための茶具といったものは、むしろそれ自体が日常の機微を思い起こさせる作用点となり得るのかも知れない。ぷっくりとした形の茶壺を眺めているだけでも、何か心がゆったりとしてくるし、茶盤の中から茶荷や茶海、六君子を取り出す所作は、友人をもてなす心構えを整えるのに重要な準備時間となる。そうして湯の具合を丁寧に見届け、差し出す碗から茶の香りが仄かに漂う瞬間から、人と人とが交接する喜びと一期一会のありがたさに感謝する気持ちが湧いてくる。茶の湯の極意とは、決してお高くとまった横柄な物言いではなく、まったく日常的な、それでいて忘れかけてしまいそうな人と人とのあいだの何気ない心の機微――これを心のよろめきと称してもいい――にこそ潜んでいるものなのだ。
春先に摘まれた芽の馥郁とした香りを味わう。ここからは遠い大陸の、その茶畑の、雲霞のごとく広がる青々とした光景を想像してみるべきだ。茶とは、一心不乱に愛おしさを求める心の優雅であることを、思わずにはいられない。次回に続く。

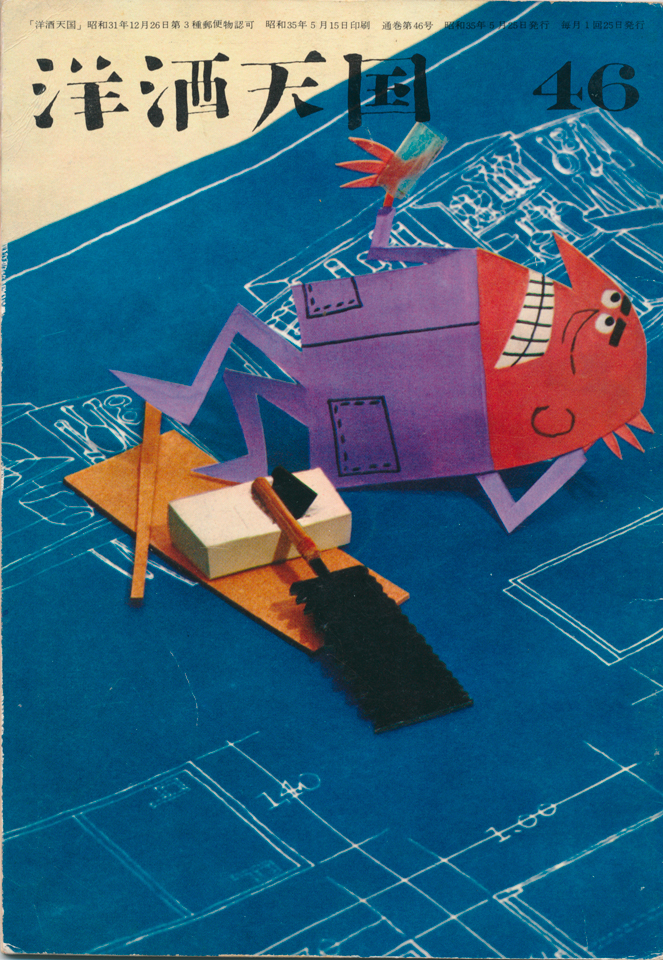
コメント