 |
| 【小学生時代に買った「おむすび探偵団」がひょっこり家の中から発見された】 |
古い歴史を持つマンカラ(mancala)のボードゲームについて見識を拡げようとしていた矢先――。
自宅の雑貨類を整頓している棚の奥から、ボードゲーム「おむすび探偵団」(野村トーイ)が出てきてすこぶる驚いた。「おむすび探偵団」は、小学5年生だったか6年生の頃におもちゃ屋で買い、その頃はよく友達と遊んだものだが、もう何十年も経ってから、〈そう言えばそんなゲームがあったな〉と思い返すたびに、〈あれはいったいどこへしまってあるのだろう〉と、保管場所が分からないでいたのだ。古い物である以上、既に処分してしまったのだと思い込み、実物を確かめることは諦めていたのだけれど、こういう時に発見されるとは思ってもみなかった。
この間、幻の「おむすび探偵団」を、オークションサイトで手に入れようと企てたこともあった。ところがこれが、たいへんレアなアイテムとなっており、ほとんど出回ることはなく、稀に出品されていたとしても、入札価格が高値すぎて手が出せずにいた。今にして思えば、買わずにいてよかったということになる。
風流なおむすびの知的なゲーム
「おむすび探偵団」は、いったいどんなゲームであったか――。
《カンと推理でおむすびの中味を当てるおいしいゲーム》とパッケージに記されているこのボードゲームは、1984年に野村トーイから発売された。1984年というと国内では、自民党の中曽根内閣の頃で、3月には江崎グリコ森永事件の最初の事件が勃発し、夏にはロス五輪が開催された。熊本の「からしれんこん事件」というのもあって、その事件の生々しい報道については、かすかに記憶に残っている。
ちなみに近年、「おむすび探偵団」はAndroidやiOSのアプリで再販され、若い人にもこのゲームの存在が認知されているようなのだが、とどのつまり、元祖は84年のボードゲーム版なのである。
パッケージの素材が、リアリスティックというかユニークなのであった。今でこそ主流ではないが、古式所縁の竹細工を模した、プラ製のおにぎりかご(おむすびかご)。
元は竹細工であるこの入れ物には、確たる名称がないようだ。おにぎり入れ(おむすび入れ)とか、おにぎりケース(おむすびケース)と呼んだりすることもある。いつの時代からか、竹細工のおにぎりかごが再び息を吹き返したように出回るようになり、おにぎりをお弁当として持っていくのに最適な入れ物――とは言え、決して主流派でもなく、そういう竹製の製品は今でも販売され流通している。それが職人による手づくり工芸品ともなると、それなりに高価な商品であったりする。
昭和のあの頃、プラ製が大はやりであった。旧来の竹細工のおにぎりかごは、プラスチック製に取って変わっており、ニチイの「ピクニックケース」として販売されていた。当然これは、本物の竹細工による抗菌効果だとか消臭効果は期待できなかった。その点において、洗って何度も使えるプラ製の「ピクニックケース」に、おにぎりをアルミホイルで包んで入れる――という方式(というか文化)が多数派となった。話が長くなるので、おにぎりを入れるパッケージの話は、これくらいにしておこう。
 |
| 【カンと推理でおむすびの中味を当てるおいしいゲーム「おむすび探偵団」】 |
風流に化けているのであった――。ゲームの中身の話である。
「おむすび探偵団」の遊び方。まず親が7種類のおむすび(うめ、さけ、たらこ、こんぶ、かつおぶし、しお、ふりかけ)の中から、4種だけ選んで、“おむすびかくし”で隠しつつ、それを事前に並べておく。対戦する子は、その“おむすびかくし”に隠された4種のおむすびの中味と位置を推理し、7回目までに当てられなければ、親の勝ち。7回目までに当てられれば子の勝ち――という簡単なルール。しかしながら、これが意外なほど知的で面白いゲームなのである。むろん、子どもでもじゅうぶん楽しめる。
子が4種のおむすびを並べていった時に、親はヒントを与えなければならないのもルール。ヒントを出す方法。もしそのおむすびの中味と位置が合っていたら、親は子に「おしんこカード」を1枚与える。もし、おむすびの位置は違うが中味だけ合っていたら、合っている分だけの枚数の「お茶カード」を子に与える。
子はもらったカードをヒントに、2回目3回目とおむすびを4つずつ並べ、推理していく。7回までに4種の中味と位置を当てなければ負けになるので、子は何も考えず、当てずっぽうだけでおむすびを並べているのでは勝てない。もらった「おしんこカード」と「お茶カード」の枚数いかんで、どのおむすびの中味と位置が当たっているのか、あるいは外れているのかを推理しなければならないのだ。
蛇足になるが、子は親からもらったカードで、4つのおむすびの中味と位置を推理しなければならないのはその通りである。けれども、親の方も、実は子の提示した4つのおむすびの中味と位置を確認しつつ、的確なカードを与えるというルールがあるので、それはそれでやはり、神経を使う知的な作業となる。
親は単に、子のはずれっぷりを見て、〈おまえはバカだな。まだ分からないのか…〉と笑っているだけでは済まない。親の出したカードこそ、そもそも合っていないじゃないか、間違えている――ということもしばしば起こりうる。そういう時は、たいてい立場が逆転し、親が子に罵倒される――。要は、双方とも集中していないとできない、なかなか知的なゲームなのだということだ。
「おむすび探偵団」は、実際に子どもでも大人でも長く楽しめる、頭の体操ゲームなのであった。7種類のおむすびを全部裏返しにして、“神経衰弱ゲーム”を楽しむこともできた。ちなみに近年再販されたアプリ版では、7種類のおむすびの中味は変更され、うめ、焼きたらこ、明太子、こんぶ、ツナマヨ、焼き肉、わさび味、となっていたようである。
 |
| 【おむすびの中味はうめ、さけ、たらこ、こんぶ、かつおぶし、しお、ふりかけの7種類だった】 |
パソコンゲームの「マスターマインド」
風流に化けている――と私がさっき言ったのは、つまりこういうことである。
この「おむすび探偵団」は、もともと、「マスターマインド」(“MASTERMIND”)という1970年代初めに英国で発売されたゲームを元にした、言うなればアレンジ版である。英国人の知的なゲームが、こういう形で日本流にアレンジされ、人気を博したというのは、まさにその時代のカウンター・カルチャーをよく表している。カウンター・カルチャーとは、常に主流とした既成事実や文化を「上書き(rewrite)」していくことに意義がある。
“7種類のおむすび”という和風のアイテムに化けていたものは何か――。それはもともと「マスターマインド」では、色のついた解答用ピンであり、判定用の赤ピンが「おしんこカード」に化け、判定用の白ピンが、「お茶カード」に化けていたわけだ。
子はボードにピンを4つずつ刺し、親はそれを見て判定用のピンを使って当たりはずれを示し、子はさらにそれをヒントに推理しながら、色のついたピンをあらためて刺していく――。これが、オリジナルの「マスターマインド」である。ちなみにこのゲームは、“Hit and Blow”とも呼ばれている。
オリジナルの方のルールは、「おむすび探偵団」とほとんど変わりない。ただし、「マスターマインド」では、色のついた解答用ピンで“神経衰弱ゲーム”は不可能である。この点において「おむすび探偵団」の方が、ボードゲームとして優れていたことになる。ゲームの汎用性は、派生し展開した時に広がっていくものであり、カウンター・カルチャーの強みである。
小学生だった私は、まさかあの(名前だけ知っていた)「マスターマインド」が、「おむすび探偵団」と同じルールのゲームだったとは、全く知らなかったのだ。「マスターマインド」はそれよりも前に、8ビットパソコン・ブームの折に、パソコン・ショップなどでカセットテープ版のソフトウェアとして見かけていたゲーム・タイトルでもあった。しかしながら残念なことに、「マスターマインド」には縁がなく、これを知る機会がなかったために、「おむすび探偵団」は〈全くのオリジナルのゲームである〉と、ずっと思い込んでいたのだった。
証左としては、1982年(昭和57年)刊のすがやみつる著『こんにちはマイコン』(小学館)を示しておく。最後半の「ゲームカセット全リスト」というページに、NEC PC-6001用のゲーム・ソフトウェアとして、「マスターマインド」が掲載されている。定価は2,800円。メーカーは高電社となっている。これとは別に、1982年にアスキー出版から発売されたゲーム集『AX-6 パワード・ナイト』にも、少々斬新なビジュアルの「マスターマインド」が収録されていた。
牡牛と雌牛
実は何を隠そう「マスターマインド」も、“Bulls and Cows”(牡牛と雌牛)という数字当てゲームが原形なのであった。こちらの歴史は多少古いようで、日本の歴史区分で言うと、近代にまで遡るらしい。
“Bulls and Cows”の数字当てゲームは、紙と鉛筆さえあれば、どこでもできる。ルールは「マスターマインド」や「おむすび探偵団」と全く同じである。対戦する片方の人(親)があらかじめ4つの数字を紙に書いて伏せておく。もう片方の人(子)が、4つの数字を紙に書き、相手が伏せておいた4つの数字を推理していく。位置と数字が当たっていればBull、数字だけ当たっていればCow。“B1C2”といったような書き方で紙に記していき、当たるまでの回数で勝敗を決めるなど、勝負の付け方のルールは任意で決めて競う。
こうした数字当てゲームのたぐいは、人工知能の可能性を示唆する意味において、世界的にコンピュータ開発の研究者やプログラマーの中で盛んに愛玩されてきたし、戦後のコンピュータ革命の歴史を綴った文献を読むと、たびたび登場する。その最も高尚なゲームが、チェスであることは言うまでもない。
ところで“Bulls and Cows”の場合、1968年にケンブリッジ大学のメインフレームでプログラミングされたものから着想され、1970年にマサチューセッツ工科大学のJ. M. Grochow氏が、IBMで開発されたPL/Iというプログラミング言語に焼き直しして、“Moo”(※これは牛の鳴き声にちなんでいる)と名づけてプログラムは完成した。こうした人工知能を匂わせる知的なゲームへの探究というのは、その大型コンピュータの性能を測る目的というよりも、研究者達が何気ない発想で作り始めて試す、言わば自分達が遊ぶためのソフトウェアであり、余暇のためのゲームなのであった。彼らはこうした形で頭脳を競い合ったわけである。
知的好奇心の強い西欧人が生み出した、“Bulls and Cows”の歴史的背景をもつ日本の『おむすび探偵団』は、そうした知性を育む一級のゲーム・ブランドの側面をほとんど感じさせずに、ほのぼのとした雰囲気でお茶の間の団らんに一世を風靡した。おむすびの中味を当てる、といった最も日本的な食文化の遊び事にのっとって――。
今も尚、「マスターマインド」のゲームは、“Hit and Blow”という名で多少なりとも抽象化され、その知的ゲームの王道として、グローバルに言語化されている。こうした言語化されたシンプルなゲームにこそ、将来のカウンター・カルチャーの担い手が嗅覚をもって近づきつつ、またそれに刺激を受けて知的好奇心を育むのは自明なのである。
“Hit and Blow”がおむすびでなければ日本人は気づかず、ひらめかない――のであれば、それも已むを得ないだろう。しかし、原形の遊び事=「4つの数字を当てる」といった、紙と鉛筆さえあればどこでも誰でもできる、いっさい「ビジュアルの無いシンプルな状態」において、その面白さの本意に直接触れる感性だけは、鍛えておかなければならないのではないかと私は思うのだ。
無味乾燥なもの――その姿は単調でつまらないものに見えるかもしれないが、そこにこそ、つまり「無から有を生む」知的な作業こそ、ビジネスチャンスとなり得る。先見性とは、そういうものである。先見人を多く育むことが、大事である。

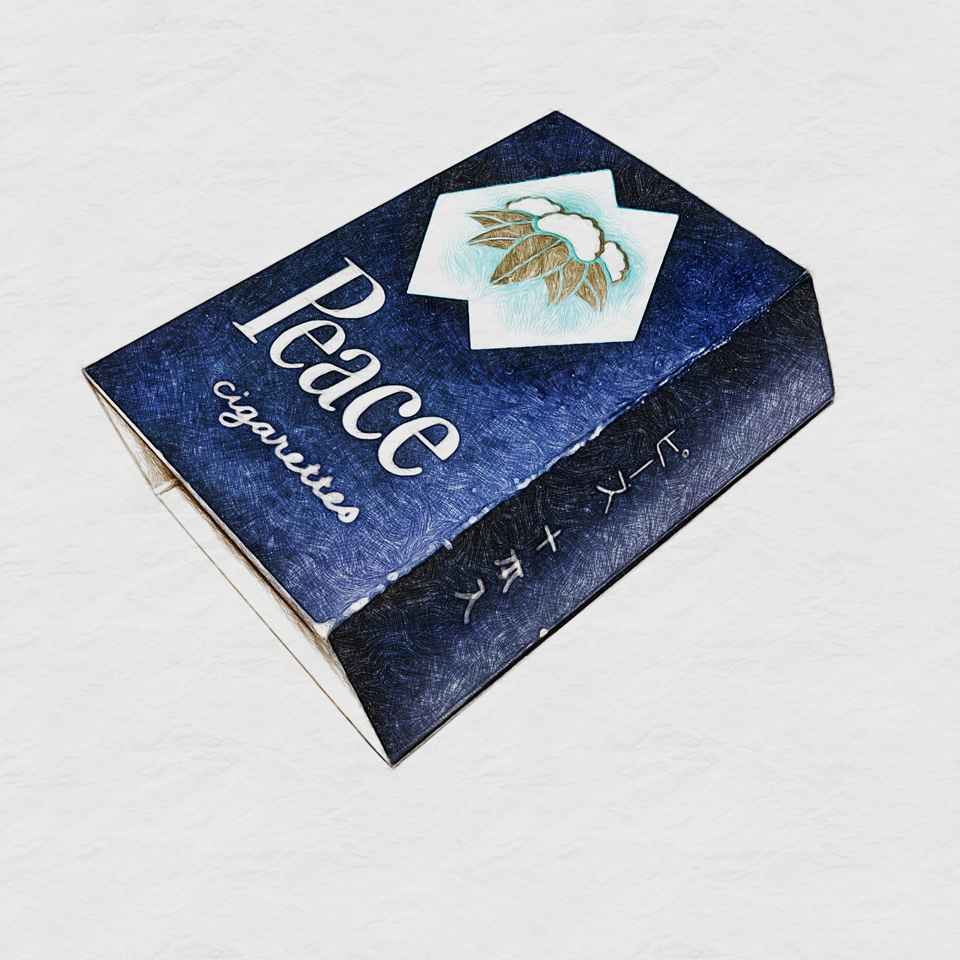
コメント