学校の帰り道、駅の高架線の下で、懐かしい中学校時代の友人と久しぶりに出くわした。
それ以前に何度か彼の姿を目撃していたものの、傍に寄って声を掛け合ったのは、5年ぶりのことであった。もっとも、挨拶程度の会話で、時間にしてほんの数秒たらず。表情はお互い緩んだものの、それ以上の会話はやはり弾まなかった。
彼との付き合いは、同じ小学校と中学校の9年間にわたる。中学1年くらいまでの彼は、小柄で可愛らしいという印象が強く、その可愛らしさは、小声が特徴的だった内面性からにじみ出たものであった。
さすがに思春期に差し掛かると、その印象は少しずつ変化していき、むしろ内面性の変化は大きかった。
小声なのは変わらなかったが、その音声は低くなり、彼自身、周囲に漂う可愛らしいという評判が少しずつ減っていったのを感づいていたはずだ。自分らしさとは何かを、無心になって引き出そうとしていた彼の痛々しさが伝わってくる中学校時代であった。
だが、久しぶりに再会した時の印象は、さらに変化の一途をたどっていた。
もうあの頃の面影はまったくないというのが、その時の私が抱いた率直な気持ちである。何よりその時の彼は、昔と比べてさらに頬が痩けてしまっていた。
内面はどうであろう。あの頃とは変わったのであろうか。
いや、私はそこまで考えるゆとりがなかった。
何せその時の風貌は、頭からつま先まで、70年代に流行したサイケデリックな服装だったのだから。もともと彼は、すぐ流行に飛びつく性癖ではあったが、推測するに、彼の日常生活は、そういう流行にのっとった生活観に支配されているのかもしれない。
私にとって、小学校、中学校、そして高校の学校生活というのは、急流に飲まれつつも、次第に緩やかな下流に向かって流れていった一括りの時代である。少なくとも高校卒業後、しばらく経っても、あの時代の思い出に関しては、それなりの鮮度を保って記憶していた。だが、その後10年という年月が人を丸飲みしてしまうと、学生時代の記憶など、かなりいい加減なものに朽ちるようである。
まるで昨日の出来事のように鮮明であり続けた記憶は、いつの間にか、バケツ一杯の墨汁をぶっかけられたように真っ黒になり、映像としての品質が保てなくなっていた。気が付くと私は、あの学校時代以上の急流を下りながら、膨大な実時間の旅をしたのであった。
旅はまだまだ続くのであり、緩やかな下流など、私の視界には到底差し掛かってきていない。
彼、の話に戻る。
子供の頃、童顔でしかも頭が良く、さっぱりとした性格であった少年は、中学生になって、ちょっぴり世間に対して抗え、その勢いが尽きる直前にバンドを始めた。当時、まだまだ自分の諒恕内にあった彼は、20歳を過ぎて、一つの世界観を築いた。それはあくまでも私の推測である。彼の良識の境目など、私が知るよしもない。が、あの時代、同じ激流を下った私と彼との間に、何らかの共通した観念が生まれたと仮説をたてても、決して荒唐無稽な話にはならないだろう。私は過去を必要とはしないけれども、彼もまた過去を必要としていないのではないか。そうした観念があったからこそ、あの時の挨拶が木訥としたもので終わったのではないのか。
旧友との「再会」を考えるに、この出会うという抽象的な模擬は、憮然と過去の記憶をたどってしまう。二人は何気なく出会い、そして悠久の時間に逆らうことなく従順したまま、その場を去るのである。友人との関係というのは、密接な何かに偏るよりも、激流の中ですれ違うような、一瞬のきらめきにこそ意味があるのではないかと、私は思う。
彼、曰く、
「頑張ってね。じゃ」
人にとって不可欠なのは、平穏ではなく、明らかに事件性である。感情や憶測の集合体ではなく、心情を絡めた厳然たる物理的な事象を求めている。その事象の一つ一つの粒が結合した時、自分の本当の存在価値がみえてくるのではなかろうか。


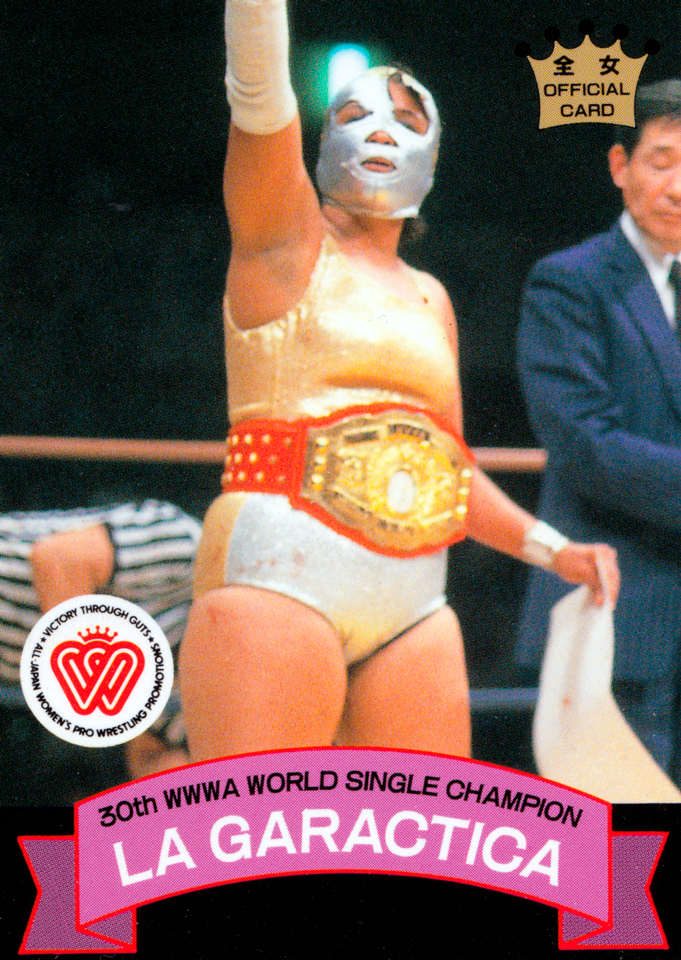
コメント