文化祭シーズンたけなわと言うべきなのだろうか。先日、新聞で茨城県の「県高校総合文化祭」開会式が水戸の県民文化センターでおこなわれたという記事を読んだ。
総合文化祭いわゆる総文祭は、10月から11月にかけて、県内の各高校文化部が水戸市やつくば市、小美玉市などで創作物の展示や発表、音楽や演劇の上演をおこなうというもので、その10月8日の開会式典では、高校生ら100人による構成劇「真綿のような白雲がみえる」が披露されたという。
この構成劇は、高校生が過去にタイムスリップし、旧日本海軍の海軍飛行予科練習生(予科練生)と出会うというストーリー。丸刈り頭に白い予科練の制服姿で凛々しく佇立する二人の若者を中心に、もんぺを穿いた女子らが取り囲むという劇の一場面の写真が掲載されていて、私は胸が熱くなるのを感じた。予科練というのは、かつて茨城県阿見町に海軍航空隊があり、今の中学生くらいの少年達が航空技術の基礎を習得するために入隊した練習生部隊である。総文祭で戦争と平和をテーマにした、このような劇に取り組んだ今の若い人達の、真剣な眼差しと情熱とを、紙面から想像しないわけにはいかなかった。
*
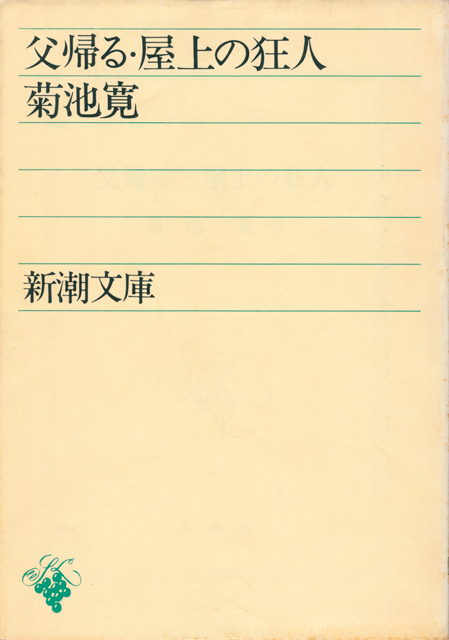 |
| 【菊地寛の『父帰る』を読む】 |
翻って、自分が10代の頃経験した淡い、演劇の想い出について書いてみたい、と思った。言わば照明を当てられた側の、ゾクゾクするような体験、を思い出そうとしたのだけれど、私が真っ先に思い出したのは、実はそういうものではなくて、中学校の演劇部で文化祭のために上演した古典劇、菊池寛の『父帰る』なのであった。
これは、舞台の上の経験というものではない。当時私は中学1年生で、演劇部に入ったばかりの1年生は、役がもらえる状況になかった。したがって私はその舞台に立っていない。仮初めにも“照明係兼大道具係”という裏方があてがわれ、その文化祭での本番では舞台の袖から「芝居を見守る」という、まったく役に立たない体たらくなポジションにあった。
戯曲『父帰る』を古い新潮文庫版で読み直してみた。いや、台本ではなく菊地寛の戯曲を直に読んだのは、これが初めてである。
その情景は《中流階級のつつましやかな家》となっており、時代は《明治40年頃》、場所は《南海道の海岸にある小都会》とある。幾分イメージと違っていた。私の記憶に残っていた演劇部の舞台装置の印象としては、もっと田舎の、貧しい家というふうに、かなり錯誤していた。
登場人物は5人。黒田賢一郎28歳、その弟・新二郎23歳、その妹・おたね20歳、彼ら兄妹の母・おたか51歳、そして彼らの父・宗太郞(父の年齢は記されていない)。
賢一郎を演じたのは演劇部の部長だった。3年生の女子で、女子でありながら男らしい逞しさというか恰幅のある性格は、賢一郎と瓜二つで適役だと思った。その他の弟や妹、母や父の役はみな3年生と2年生の女子で占められ、稽古の初めこそゆるく、和気藹々としていた雰囲気が、やがて文化祭の本番の日が迫ってくると、異常に口数が減り、態度もずいぶん真面目になって、それがいよいよ本番の前日ともなると、果たしてうまくいくのか、これはうまくいかないのではないかという焦りが先行して、甚だ消極的な緊張感が漂っていたと記憶する。
ともかく、1年生だった部員の面々は、何の役にも立たなかった。見ているだけであった。本番前日は、本番と同じ校内の体育館を借り切って、何度も繰り返しゲネプロがおこなわれた。
もしかすると、その日の午後は、演劇部の部員は授業に出なくてもよい、という意向が先生側からあったのかも知れない。かなり長い時間、体育館にこもっていたように思う。ゲネプロは本番通りのリハーサルであり、照明や音響のタイミングのチェックや大道具の移動のリハーサルが入念におこなわれたはずなのだ。
とは言え、菊地寛の『父帰る』をいま読んでみると、これほど短い芝居だったのかと少々絶句した。私が読んだ古い新潮文庫版(昭和44年改版による昭和57年第41刷版)の解説者の永井龍男氏は、この『父帰る』をべた褒めしているのだけれど、一幕物の戯曲としてはやや唐突な展開であり、各人物の描き方が直情的すぎ、台詞による感情の表現があまりにも素直すぎる。言い換えれば、嘘がなさ過ぎる。例えばシニカルな態度で己の内面を欺く、というような複雑な心理的表現のたぐいはほとんどなく、家族会話としての器用な素振りは何ら無い。
ちゃぶ台のある六畳の間。賢一郎と母がおたねの結婚話をしているあたりで、新二郎が帰ってくる。そしてかつて出奔してしまった父の姿を見た人がいる、と話を兄に持ちかける。やがておたねも帰ってくると、家の向こう側にこちらの家をじっと見ている年寄りの人がいる、と告げられ、賢一郎達は不穏な面持ちとなる。そこへ、表の戸を開ける人が現れる。父・宗太郞である――。
あまりにも有名な戯曲であるから、それ以降の展開については割愛する。
おそらく演劇部で扱ったあの時の台本は、『父帰る』の戯曲を顧問がある程度手直ししたものと思われる。が、充分中学生でも理解できうる内容ではあった。――久しぶりに現れた父を、賢一郎は硬直した態度で詰め寄り、半ば追い出してしまう。しかし父が出ていった後、その気持ちのわだかまりを抑え、弟の新二郎に父を呼び返してこい、と叫ぶのはこの戯曲の白眉であり、劇的な場面である。兄に言われて新二郎は飛び出してみたものの、父の姿はどこにも見当たらない。それを兄に告げた時、この時の賢一郎の感情の剥き出されたもの、あるいは身体に衝撃が走った状態こそが、菊地寛が演劇として描こうとした進歩的表現の真髄であろうかと私は考える。
*
私が当時接した演劇部の部長は、男勝りの面があって、多少日常では、損をしていた。単純に口調が怖いところがあって、1年生だった私はいくらか叱られたこともあったのではないか。故に賢一郎役としては相応しい存在感を示し、部長自らも立派な大役を果たした感のある、思い出深い卒業公演だったのだろう、と推測する。
『父帰る』のゲネプロが、夜間にまで及んで、最後の最後までそれに夢中になって付き合った1年生らの気持ちの中には、部長やその他の先輩部員の、日頃垣間見られない熱心な姿勢を間近で見ることができ、ある種の格好良さと爽快さがあったはずだ。
演劇はこうして出来上がっていくものなのかという驚きと、役者が何と向き合い、何と闘っているかを最初に経験したのが、私にとって中学演劇部の『父帰る』なのである。それは台本の型通りの状態から大きく飛び越えていくことになる、貴重な体験であった。


コメント