 |
| 【ウィンダム・ヒル『THE STORY OF NAOMI UEMURA』】 |
ここ数日、連日のように“ひんやり”としたウィンダム・ヒル(Windham Hill)の音楽を聴いている。1986年、カリフォルニアのバークレーにあるスタジオでレコーディングとミキシングがおこなわれたアルバム『THE STORY OF NAOMI UEMURA』。私が中学2年の時に買ったCDである。そのため、ジャケットも経年劣化して色落ちが著しい。ウィンダム・ヒル・レコードのレーベル。エグゼクティヴ・プロデューサーは村井邦彦とウィリアム・アッカーマン。そう、いま聴いているのは、同年の佐藤純彌監督の映画『植村直己物語』(東宝)のサントラなのだ。
§
母校だった小学校の卒業アルバムを、しばらくぶりに眺めてみた。忘れかけていた思い出が、ふっとよみがえる。卒業したのは1985年の春だが、卒業アルバムの一番うしろのページに、その頃世界各国で起こった出来事や事件事故などの略歴があって、小学6年時だった1984年2月13日の日付には、「登山家・植村直己がマッキンリーで消息を絶つ」云々が記されていた。当時のニュースの印象は憶えていない。ただ、卒業アルバムのこの略歴の、植村直己という名前より、“マッキンリー”という山の名前の方に何故か惹かれた。
2年後に映画化された時、卒業アルバムを見返しては、〈彼が消息を絶ったのは、本当についこのあいだのことだったのだ〉と、出来事の生々しさを想った。映画(主演は西田敏行、倍賞千恵子)を観たのは中学2年の時で、植村直己の生き様と音楽の素晴らしさに感動し、すぐさまサントラのCDを買ったのだった。
ウィンダム・ヒルの音楽は、ゆるさのない、てきぱきとした音の羅列(quantize)に魅力を感じる。それがすなわち、このサントラでは、《凝固した氷の塊》のような“ひんやり”とした印象を形成していた。例を挙げれば、ハープ・ギターを弾いているマイケル・ヘッジスの「Because It’s There」におけるかすれた弦の旋律が、冷たいそれをイメージさせ、フィリップ・アーバーグのピアノの連弾が、雪の山の壮大なスケールを思わせる。さらには、植村が「孤独」に悶え苦しみ、その危機に瀕した心理を、ハンマード・ダルシマーで表現したマルコム・ダルグリッシュの、チリチリとしたサウンドが聴ける「The Ice Bear」など、何度聴いても心が昂揚させられる。そして収録曲の中でも、アーバーグのピアノ・ソロによる「Kimiko」は特別である。
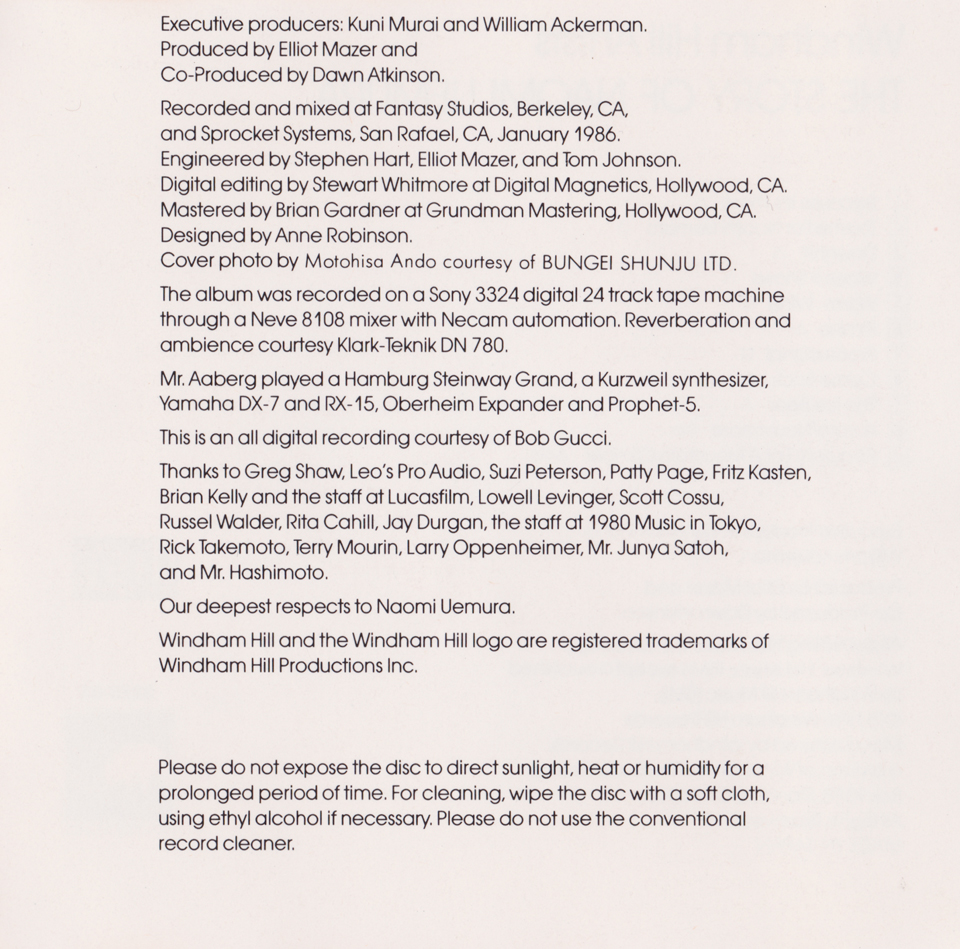 |
| 【アルバムのスタッフ・クレジット】 |
アルバム『THE STORY OF NAOMI UEMURA』は当時、バークレーのFantasy Studiosにて、Neve 8108コンソールでミキシングをおこない、Sony PCM-3324のデジタル・マルチ・トラック・レコーダーで記録したことが、アルバムのクレジットを見て分かる。このことに付け加えると、このコンソールでは、ムービング・フェーダーのNecamオートメーション・システムが用いられ、リバーブ・マシーンはKlark Teknikのデジタル・プロセッサーDN 780が使われたことも記されてあった。
要するにこれらによって構築されたデジタル・サウンドというのは、まさに地平高く伸びた雪山の重厚な世界、そして冷たく凍り付いた氷床と絶壁の、人智を拒む「白」と「青」の心象空間を作り出していると言える。興味深いことに、植村と公子夫人の温和な人柄とはじつに対照的なイメージでありながらも、この“音楽的プロセス”は何故か、二人の情愛を漂わせているのだ。然るに解く鍵は、それぞれの演奏者の、卓絶した《旋律》のひらめきにあるとしか、私は思えないのである。
当時中学生だった私は、このアルバムを何度も聴いているうち、植村直己という人の「孤独さ」について深く考えるようになった。音楽のイメージの浸透がそれを物語っていた。
明治大学山岳部出身で登山の経験を積み、いつしか五大陸の最高峰をすべて登りつめた男。犬ぞりによる北極圏の単独制覇。こういった前人未踏の数々の偉業をなした冒険家という肩書きの栄光の陰に隠れた「孤独」。映画では、そんなふうに彼を印象づけていた。
実際、植村直己という人はそうだったのだろうと思う。何故彼は「孤独」なのか。何故彼は、思い描く山に登るのか。何故彼は、前人未踏の冒険を続けたのか――。ウィンダム・ヒルによるサントラは、映画音楽の劇伴という位置づけを越えて、むしろ明確に、彼と、その伴侶である公子という存在をクローズアップし、リスペクトしている。最期の冬のマッキンリーで遭難してしまうまでの彼の人生の一つ一つが、まるで一つ一つの音に照応されているかのように、私は『THE STORY OF NAOMI UEMURA』を聴くことによって、自らの内省的な、「孤独さ」への信奉を深めていったのだった。そう、やはり私にとっては、“マッキンリー”だったのだ。

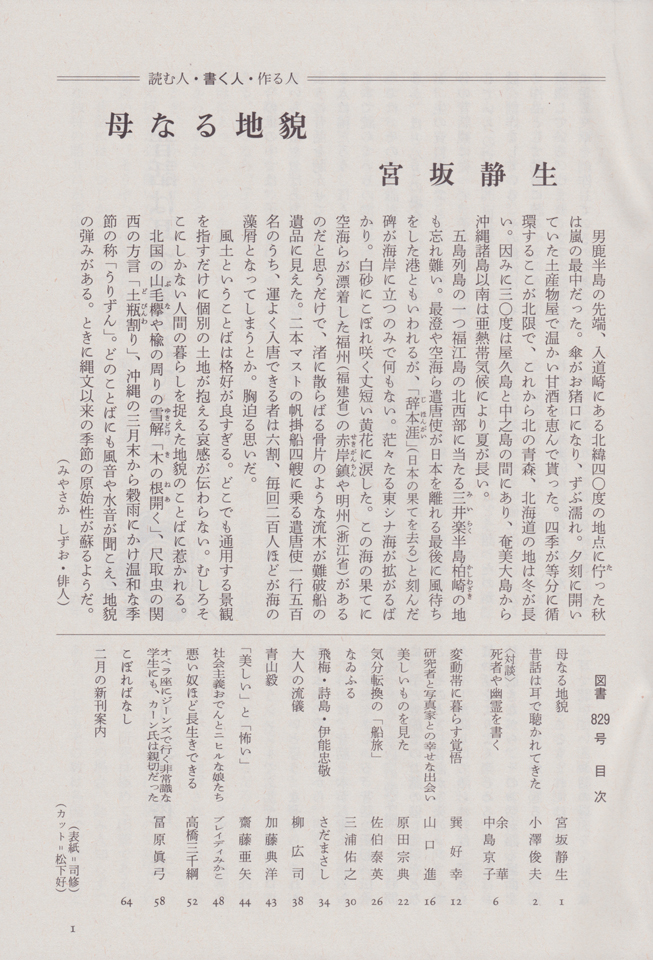
コメント