 |
| 【ドキュメンタリー映画『ミックステープ』】 |
音楽の嗜好がメジャーJ-POP一辺倒、という人にはまったく訳が分からないであろう、ヒップホップ業界の“複雑怪奇”なミュージック・シーンとプロダクトにまつわる話。90年代のサブカルだとか、ブートレグに興味をそそられる人なら、いくつかキーワードを並べるだけでああその話ね…と分かってしまう、という音楽の話。なんと言っても、カセットテープとラジカセの全盛時代を知らなければ、この話はまったく理解できないだろうし、退屈かも知れない。ああ、boredom…boredom…。
2007年、その頃私は24pのデジタル・カムコーダーでデジタル・シネマ(ショートフィルム)の自主制作をやっていた。それまでの5年ばかり、音楽制作にすっかり飽きてしまってそっちはほったらかしにしていたにもかかわらず、あれよあれよと“音楽熱”を見事に再燃復活させてくれたのが、Pro ToolsのDAWの存在とウォルター・ベル(Walter Bell)監督・脚本・編集のドキュメンタリー映画『ミックステープ』(“MIXTAPE”2005年、アメリカ作品)のDVDなのであった。ちなみに、この映画のDVDの販売元であるアップリンクは、その頃とっても(私的に)好きだった、サブカルの宝庫=ポータルである。
§
ところで実際、ウォルター・ベル監督のドキュメンタリー映画『ミックステープ』は、語弊を怖れずに言えば、映画としては見どころがほとんどない、“あまり面白くない”映画である。と、言い切ってしまっていいと思う。いくらヒップホップ界の大御所(チャック・DやDJレッド・アラートら)が次から次へと登場してくると言ったって、ただ彼らがカメラの前に立ち、ヒップホップの成り立ち話や現状をまくし立てるシーンのワンパターンとあらば、観ていて次第に飽きてきてしまう。
で、“あまり面白くない”というのを承知のうえで、彼らのまくし立てるトークやアティチュードを反芻していくと、実は喉越しにミントのキレッキレの爽やかさが感じられるが如く、爽快な気分になれる。音楽業界に興味があるならば――。要するに、『ミックステープ』は、一音楽業界の内紛事情を露わにしたドキュメンタリー映画であり、DVDパッケージ裏面の解説文を借用すれば、《音楽の利権を握る巨大企業はマーケットを操作し、楽曲のリリースを規制することで「ヒップホップ」カルチャーの定義を押し付けている》ことの問題提起なのである。この映画では、肝心のヒップホップ・サウンドそのものは、なんとなくバックグラウンドで流れているだけに過ぎず、彼らの制作現場で機材をいじって見せたり、思いきりパフォーマンス…というシーンは、特にない。あくまで彼らのコメントに次ぐコメントで編集しまくった、とてつもなく地味な、映画だ。
だが、私は当時(2007年)このDVDを観、なんだかだんだんと興奮してきたし、久しぶりに音楽をプロダクトしてみたくなって、それまで軽々に使用していたDAWのPro Toolsを本格的にいじるようになり、いても立ってもいられなくなったのは事実である。そういう意味では摩訶不思議なドキュメンタリー映画と言える。
こめかみがつんつん痛くなるようなやかましいラップでまくし立て、いかにもアンダーグラウンドの臭味がプンプンするショップの店員の登場で思わずにやけてしまった、私。これぞヒップホップ。そういえば古びた映像クリップの中でプロ・ボクサーのモハメド・アリが“元祖ラップ”を披露してくれるが、カニエ・ウエストが喋っている途中からおいおいおい、それおしゃべりじゃなくてラップになっちゃってるじゃん、っていうのを目撃してしまうと、やはりこの人達は天才なのだなと思う。ネオ・サイケ調のカラフルな広告のたぐいやジャケット、レーベルはいかにもそれっぽくて、私はやっぱりほくそ笑んでしまったし、粗くて雑で独特なセンスのCGやデジタル・アートでイメージされたヒップホップの世界観を、彼らのラップまがいの冗長トークだけで見せてしまうウォルター・ベルもまた、天才肌であり、そうしたセンスとセンスのピッチが見事に釣り合った作品が、『ミックステープ』なのであった。
考えてみて欲しい。そもそも音楽なんて、人類の壮大な歴史を遡れば、その始まりはちょっとした遊びや祭事のうちの、“余興”に過ぎなかったはずだ。そう、音楽と歌の伝播及び伝統というのは、即興の、冗談的な“余興”から、始まった。だからあくまでentertainmentである。
ミュージシャンがちょっとした“余興”のつもりで、ビニル(レコード盤)を乗っけたターン・テーブルを適当にぐちゃぐちゃいじってそれに合わせてしゃべくりまくった調子がすごく面白く、なんだかそれが格好良くて、どこかおちゃめで、そこからヒップホップというルーツが始まった、のだと想像する。そのうち今度は、ラジカセを使い、アーティストの音楽テープをあっちこっちダビングしてカットイン/アウトしながらブレイクビーツをつくり、エンドレステープでリピート再生してみせる――。そこに、悪ふざけな(人の悪口とか下品な掛け声とかの)ラップをかまして、別のラジカセでそれらを録ると、とてつもなく創造的で刺激的な芸術作品(=ミックステープ)が生まれる。
こりゃあ面白い、となって、政治ネタや自虐ネタなんかも織り交ぜたりする。仲間内でそうした遊びが流行り、それを得意とするストリート・パフォーマーが少しずつ現れてくる。面白いことやってる連中がいるぞ、というので注目を浴びる。俺にもその面白いの聴かせてくれ、となると、カセットテープをどんどんダビングして配り始める。家内制手工業。
ありゃ、これってもしか、売れるぞ…。様々な形で利権が発生していく。ラッパーという確固たるアーティストが誕生し、人の手垢がいっぱい付いた傷だらけのカセットテープ(ミックステープ)が、驚くほど値がついて売れるようになる。これってサブカルのいい見本だけれど。
ともかくカセットテープはダビングに継ぐダビングで、幾度ものコピーされたテープの音は、相当に悪い。でも、直接会ったこともない伝説のラッパーのプレミア・テープとなると、想像するだけで興奮する。高値を払ってそれを買いたくなる。手渡す方としてはこりゃあますます商売になる、っていうところから一気に火が点く。昔、こぢんまりとした仲間内の“余興”から始まったヒップホップは、こうしていつのまにかアンダーグラウンドにおける、利権争いの壮絶な無法産業と化していった。
§
 |
| 【DVDパッケージ裏面】 |
昔はたぶん、レコード・プレーヤーと買ってきたアーティストのビニル、それから安価なマイクロフォンとラジカセさえつなげばミックステープは出来た。ただし、誰でもできるわけではない。音楽的なセンスが必要。ただ、もともとアーティストの既存のビニルには、当然ながら著作権があるわけで、それをミックスして販売することは違法行為だ。しかし、ターン・テーブルをどういじってブレイクビーツを構成するか、ブレイクビーツにどんなラップを加えるかという部分は、いっさいクリエイティヴな範疇で、ヒップホップ文化の本質の部分ともなっていた。
どうやれば創造的なブレイクビーツになるのか。アーティストはただ、そこに夢中になる。が、別の見方で言うなれば、彼ら創造的なアーティストは金の卵だ。そこに群がる錬金術師の多勢の輩の、利権をひっくるめた競争は苛烈を極め、カッコいいミックステープは評判になるが、ダサいのは見向きもされない。そうしたレッテルを貼られたアーティストは街に捨てられていく(ドラッグとカネと女に溺れて廃人になるアーティストも多い)。いずれにせよ、ただそれだけの世界。だから彼らはバックステージで必死に特訓をする。そしてひたすら自分の作ったミックステープを配りまくる。
そのうち、音源元のアーティストが敢えてDJやラッパーに音源を提供し、ミックステープを作って売るということになってくると、些かややこしくなる。著作権はクリアしているが、ミックステープがコピーされ、ブートレグ化されていく途上で闇の利権に分散され、収まりがつかなくなる。カセットテープの時代が終わった90年代以降、媒体はCDと変わり、それがやがてネット上のデジタル・データのやりとりとなってくると、複製技術はより簡単なものとなり、ブートレグの量産は増加の一途を辿り止まらない。そうして結局、メジャー・レーベルと全米レコード協会(RIAA)が手堅く踏み込んでくるわけだけれど、ともかく『ミックステープ』というドキュメンタリー映画は、そういう内容なのである。だから言ったでしょ、メジャーJ-POP一辺倒の人には、雲をつかむような訳の分からない話だって――。
この話にまあまあ近いことを、自分の中学生時代のエピソードで思い出した。私の友人が、自分の好きな音楽(幾多のジャンルを織り交ぜて)をテーマごとにピックアップ&レイアウトして、定期的にそれをカセットテープにまとめて自前でアルバムを作っていた。音源はラジオからだったり、ビニルからだったり。カセットテープという媒体は趣味の度合いが極端に濃厚で、それが面白い。友人は、定期的にアルバムを作っていたので、ずいぶんマメな奴だなと思った。
そうして自己トリビュート・アルバムのカセットテープはどんどん増えていく。でも、テーマごとにその人の趣向で音楽が並べられているから、自分で聴くにしても、友達に聴いてもらうにしても、確かにリスニング自体のモチベーションに変化が生じて楽しくなってくる。これがカセットテープの不思議な魅力。今でこそそれって、ネット配信ミュージック・サイトのプレイリストのこと。つまり昔は、それをカセットテープに録音してやっていたのだ。
かつて、ミックステープのマスター1本で、それをダビングしまくっては、飯を食っていた人達がいた。究極的にはマスターテープ自体が大金で取引できたという。ホットでエモーショナルな音楽が聴きたい、というリスナーの純朴・純真な気持ちが、ヒップホップというジャンルの裾野を広げてきたサブカル的音楽史。
そういった話が垣間見られるドキュメンタリー映画『ミックステープ』をいま、なんだか10年ぶりに鑑賞してしまったけれど、やはり観てみると、“音楽熱”が沸点に達する己がいたりして、なかなかミックステープの存在はポリティカルな要素が絡んで面白い。
そういえば、昔は隣近所なんかで、高校生くらいの兄ちゃんが部屋でギター鳴らしてたりアカペラのヴォーカルが聴こえてきたりしたのに、最近はすっかりそういうのがなくなって寂しい。音楽は聴くもんじゃない、やるもんですよ。周囲にやかましく思われながらもやってみればいい。音楽やってる連中なんていうのは、やかましくて鬱陶しくて邪魔くさくて厄介者で胡散臭い? そうです。その通りです。でもそういう勢いのある心を、カルチャーを、世の中からなくしちゃいけない。若者だろうが年寄りだろうが関係ない。熱くなろう。そういう部分をもっと、啓発していかなくちゃ――ね。

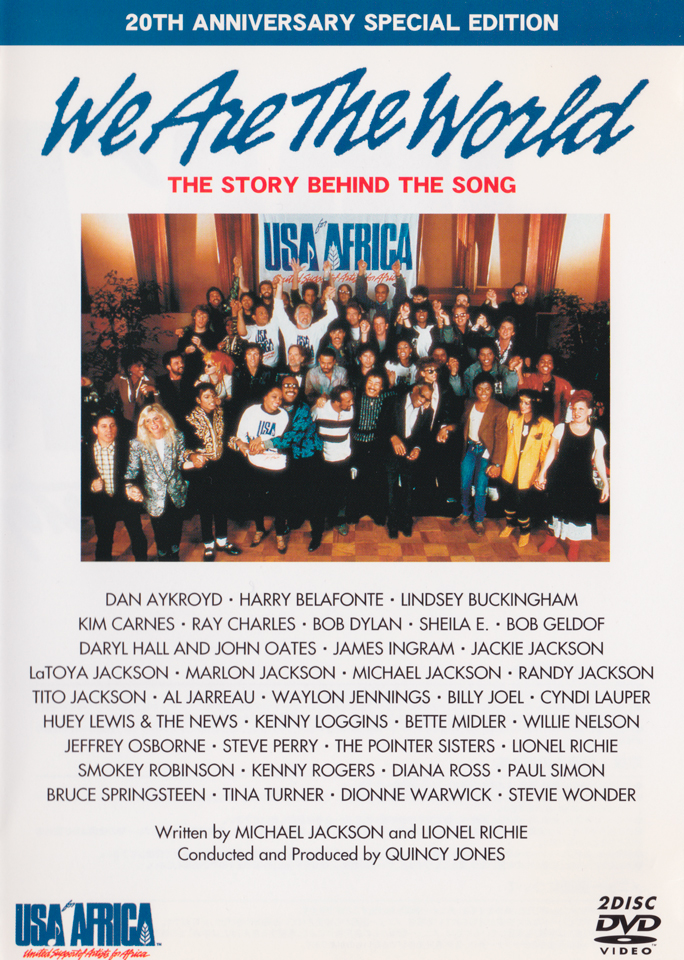
コメント