 |
| 【中国茶の青茶に属する「武夷肉桂」】 |
前回からの続き。言わずもがな、お茶とサブ・カルチャーにまつわる話。
中国茶の「武夷肉桂」(ぶいにっけい)を取り寄せたので飲んでいる。このお茶は、福建省の武夷山が産地で、山肌の岩に生育することから岩茶と言われ、青茶すなわち烏龍茶の一種である。文春新書の『中国茶図鑑』にはこのように書かれている。
《葉は長めの楕円で肉厚。茶葉は黒ずんだ緑でツヤがある。果実あるいは乳の香り》
(文春新書『中国茶図鑑』「武夷肉桂」より引用)
武夷の岩茶は香り高く、「武夷肉桂」は口に含む際に仄かなキンモクセイの香りがすると言われる。このような香りは、日本の煎茶にはない。実際に私も「武夷肉桂」の茶葉に湯を注いでみたのだが、花の香りで一瞬心がよろめき、なんともたまらない幸福感を味わった。高貴な気品が感じられ、味もまたとても青茶らしく奥深い。
前回紹介した中国茶「平水珠茶」は、その乾いた茶葉のエロティックな装いを礼讃したのだけれど、「武夷肉桂」もその姿がエロスを連想させてくれる。肉桂とはシナモンのことで、その香りに似ているというところから名付けられたようだが、この細く丸まった茶葉の縮れ具合を見ていると、まるでそれが女陰の小陰唇のように思えてならないのだ。
女性の慎ましやかな陰門の香りを愉しむ――といった淫らな“あるまじき”心の片隅の欲望は、あながち精神性への蔑み、冒涜、離叛の対象にはならないのではないかとさえ思う(むろん女性に対しても)。老子の古典を読んでいても、イスラムのアブー・ヌワースの『飲酒詩選』を読んでいても、これは私自身の雑感としてとらえられた感覚の傍証に過ぎないけれども、微量のエロスの抱合はかえって物事を(その多くは男と女の関係を)豊かにするものである。そうでなければ中国茶の真髄も軽やかさも理解できないに違いない。
そういったことを踏まえてみても、中国茶は私にとって休息を愉しむための飲み物であり、精神修行の嗜みの一つである。いや、精神修行と言うのはあまりにも仰々しい。言わば、サブ・カルチャーにどっぷりと浸かるための心の準備体操、そのリブートのための精神的沐浴にすぎないのだから。尤も、体内には実際、茶のエッセンスが流れ込むわけだから、身体は純然とその養分で潤う。茶を飲んで心を清廉に、落ち着かせる――。これは酒を飲むのとは違う種類の、生きる歓喜である。歓喜の種は、いくつかあった方が人生をより楽しめる。
§
“日本人として中国茶を楽しむということとは何か?”という副題の、mas氏のウェブサイト「中国茶のオルタナティブ」は、2000年2月から2001年1月までの1年間に更新され、12のエッセイ(アーティクル)がかつてWWWに存在していた。しかし現在、このウェブサイトは消滅しており、以前より私は、そのHTMLファイルアーカイブしておいて、密かにハードディスク内に眠らせていたのである。私のごくわずかな茶に関する教養は、この「中国茶のオルタナティブ」を基礎としていたと言っても過言ではない。
mas氏は写真やカメラをはじめ、ジャズ・フュージョン、ギター、書物、陶器、中国茶、スイーツ作りなどのサブ・カルチャーに卓越していた。当時、愛娘の成長記録もウェブ日記として投稿していたりして、しばしその家族写真のたぐいも、バルナックやM型(M4?)ライカの結実として私の記憶に印画された。そうして彼の趣味の世界に私はすっかり魅了され、趣味人としてのmas氏を私淑するようになったのである。ここで再び6年前の当ブログ「中国茶とスイーツの主人」の中の凡庸なる言葉を用いるけれども、私は、彼の存在をこのように表したのだった。
《いつしか私は、彼は日本人ではなく、中国人あるいは台湾人なのではないか、と考えるようになった。なんとなく、その節々がそれぞれの文脈の中に感じられた。実際のところは分からない。彼のプロフィールは念入りに多くが伏せられており、横浜近辺が居住地なのではないかとこちらが推測するほかはなく、出身地については謎であった。
しかしながら彼の日記の中における、その日常全体の空気が、どこか貴族的、上流階級的な情趣があって、むしろそれは好感の持てるたぐいであったが、日本から少し距離を置いたアジア人、古い言い方をすれば渡来人という位置づけを空想してみると、彼の人物像がよりいっそう輪郭を帯びて際立つのである》
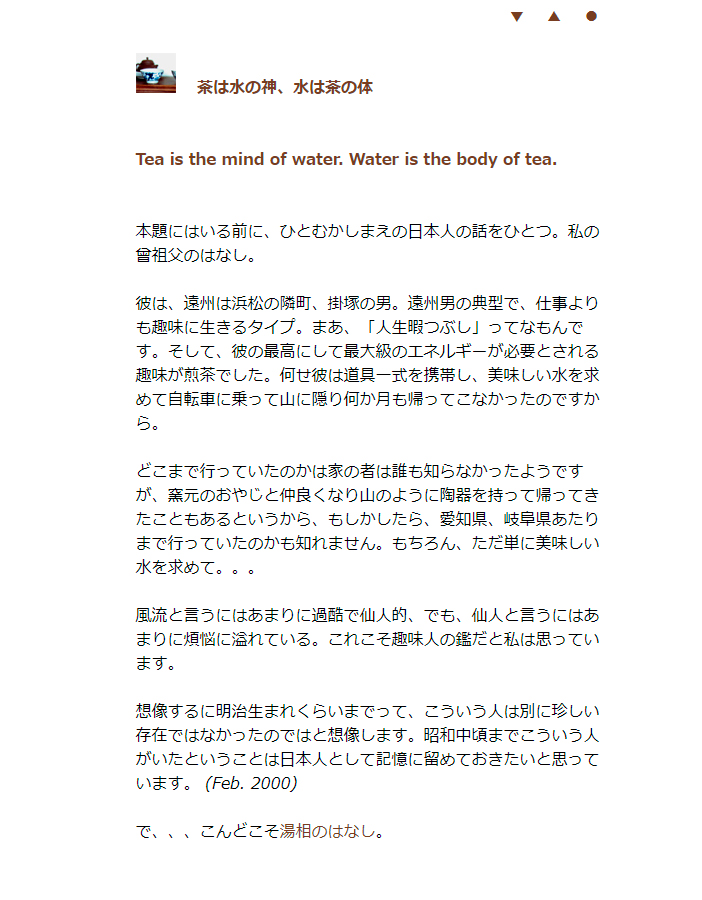 |
| 【私淑するmas氏のウェブサイト「中国茶のオルタナティブ」より】 |
《Tea is mind of water. Water is the body of tea.》
「中国茶のオルタナティブ」のその三は、「茶は水の神、水は茶の体」というタイトル。ここでは実に興味深い、mas氏の曾祖父に関する記述が窺える。
《彼は、遠州は浜松の隣町、掛塚の男。遠州男の典型で、仕事よりも趣味に生きるタイプ。まあ、「人生暇つぶし」ってなもんです。そして、彼の最高にして最大級のエネルギーが必要とされる趣味が煎茶でした。何せ彼は道具一式を携帯し、美味しい水を求めて自転車に乗って山に隠り何か月も帰ってこなかったのですから。
どこまで行っていたのかは家の者は誰も知らなかったようですが、窯元のおやじと仲良くなり山のように陶器を持って帰ってきたこともあるというから、もしかしたら、愛知県、岐阜県あたりまで行っていたのかも知れません。もちろん、ただ単に美味しい水を求めて。。。
風流と言うにはあまりにも過酷で仙人的、でも、仙人と言うにはあまりにも煩悩に溢れている。これこそ趣味人の鑑だと私は思っています。
想像するに明治生まれくらいまでって、こういう人は別に珍しい存在ではなかったのではと想像します。昭和中頃までこういう人がいたということは日本人として記憶に留めておきたいと思っています》
遠州は掛塚――という古き良き時代を想わせる表現が、彼の教養の文語的品性を醸し出していて、私はそこに惹きつけられる。掛塚(かけつか)という町は、遠州灘に注がれる天竜川河口の地域にあって、貴船神社で知られる静岡県磐田市南西部の旧町名である。しかし現在も、あのあたりにはところどころ掛塚の地名が残っている。
おそらくここで平凡社の『世界大百科事典』でも開けば、もしかすると掛塚に関連した詳しい町史・文化史などの伝承が得られるかも知れないが、敢えてそれは遠慮しておく。ともかくmas氏の曾祖父は掛塚出身であり、その彼は朗々とした趣で煎茶のために清水を追い求め、悠々とあてどない旅をした明治男であった、という点をここでは押さえておくことにする。
§
 |
| 【作法ではなく心の安息を、人に寄り添うひとときを…】 |
どうも私は中国茶を嗜むとき、エロティックな装いの茶葉を見つけ出して愉しむ、といった個人的な嗜好を見出してしまって始末がわるい。しかし、茶を飲んでストレスを忘れ、落ち着くという点においては、最も効果的な連想のようでもある。これをもし《風流》と思っていただける方がいるならば、些か気分は萎えずに済むのだけれど、ところでこの《風流》という言葉を聞くと、私はつい九鬼周造の名著『「いき」の構造』を想起してしまう。岩波文庫の『「いき」の構造』の本には、「風流に関する一考察」というのも収録してあって頼もしい。
九鬼周造と岡倉天心の近親的及びその心情において複雑極まりない関係(不埒な縁故と言っていい)を思い浮かべると、《風流》という哲学の、その見事な到達観への、短い人生における道程の裏返しには、過酷で煩悩に満ちた黒い驟雨の壮麗さが秘められている――としか言いようがない。九鬼周造という人を思うと、心情としてまことに不憫であり愛憐の極みであり、かつ愛情という問題を語る上での芸術や思想を飛び越えた鋭い魂の衝動こそが、彼の哲学を推し進めたのではないかと想像される。
「いき」を論じるのも《風流》を論じるのも、不憫というある種の美醜の観念を含有してこそのものであることを、九鬼周造の人生がすべてを物語っている。その点において、岡倉天心もmas氏も、そして彼の曾祖父の明治男も、みな《風流》の人であったことだけは、私は熟知したつもりである。 次回はこちら。


コメント