 |
| 【これが幻の『洋酒天国』第1号】 |
振り返れば当ブログでは、2011年の7月、「開高健と『洋酒天国』」と題し、初めて“ヨーテン”すなわち『洋酒天国』の“冊子を並べた写真”を掲載してそれを紹介している。それ以後より一冊一冊、順不同で“ヨーテン”の中身を書き尽くしてきたつもりである。
あれから8年の歳月が流れてしまった――。西遊記をもじれば、それでも私はまだ天竺に到着していないのである。当初、所有していた冊数は、30冊にも満たなかった。そうしていつの間にか8年ものあいだに、ちょこちょこと古書店を調べては、未所有の号が入手できるとなれば買い足しし、少しずつ蒐集を増やして今日に至る。幸いなことに、あの時代に発行された全冊のうち、現在ほとんど所有することができ、厳密には残り一冊(第58号!)のみ未所有――という状況である。
8年前のブログで『洋酒天国』について初めて書いた時、こんな文章でそれを紹介していた。
《『洋酒天国』は昭和31年(1956年)創刊。サントリーの前身である「壽屋」の宣伝部にいた開高健氏が坂根進氏、柳原良平氏らと協力して編集した、《酒》にまつわる大人向けのPR誌(発行は洋酒天国社)。かつてはトリスバーに置かれていたようです(因みに、当時の頒価20円)。開高健氏独特の情趣で酒とエロスの話題に富む一級のコラム集である…というのが私の持論。さらにグラスを片手に、この萎びた古本に読み耽るのが、本物の大人の嗜みである…と嘯き豪語させていただきます》
§
あれから8年、今回は、その記念すべき創刊号(第1号)を、万を辞して紹介することにする。壽屋PR誌『洋酒天国』(洋酒天国社)第1号は昭和31年4月発行。表紙はイラストレーターの柳原良平。
ところで、『洋酒天国』創刊にまつわる余話としては、編集者であった開高健の、当時の来歴に触れておく必要があるだろう。これに関しては、小玉武著『「洋酒天国」とその時代』(ちくま文庫)が詳しい。
開高健は昭和29年2月、大阪の壽屋(現サントリー)に入社。当時24歳。最初の仕事らしい仕事は、宣伝部の意匠課に配属され、得意先向けの雑誌『発展』(編集長は栗林貞一)の編集であった。あちらこちらの地方の酒屋などへ赴き、それこそ地道に駆けずり回って取材活動をしたようである。この時、同じ意匠課には、のちの“ヨーテン”スタッフともなる柳原良平や坂根進がいた。開高氏はさらに孤軍奮闘し、労働組合の機関誌「スクラム」の編集も任されるようになり、この頃の開高氏は言わば、のちの“芥川賞作家”として花開く以前の、つぼみの状態であり、学生時代からの文筆志向と雑誌編集の才が結び付いた「下積み時代」と称することができよう。
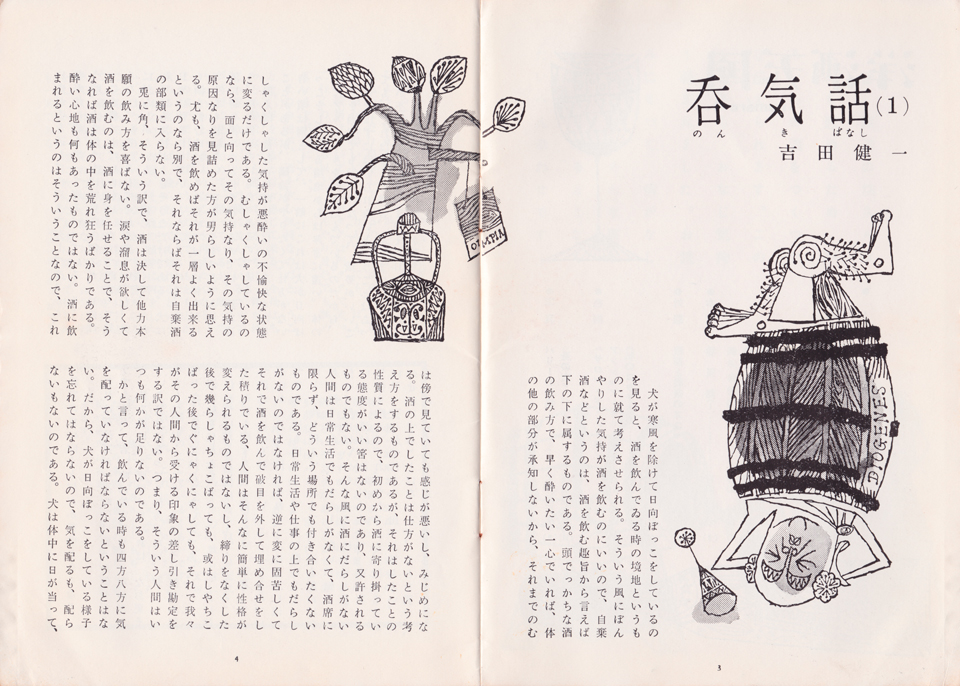 |
| 【吉田健一のエッセイ「呑気話(1)」】 |
さてさて、中身――。創刊号(第1号)のトップを飾るエッセイは、英文学の翻訳家・評論家である吉田健一氏の「呑気話(1)」。吉田氏の文体はとてもスマートで、落ち着きを払った明弁家と言える。一応、あまり関係ないこととして補足しておけば、吉田氏の父親は、あの吉田茂である。吉田氏は明治45年東京生まれで、若い頃に渡欧。ケンブリッジ大学を中退して帰国後、東京・神田駿河台のアテネ・フランセに入学。アテネ・フランセを卒業した頃から、自身の作家活動が活発となった。ちなみに、“ヨーテン”第25号(当ブログ「『洋酒天国』とパリの饒舌」)では、写真家・田沼武能氏の撮影による吉田氏の、その頃の容姿が窺える。
「呑気話(1)」は、吉田氏の硬調の文体技巧が相まって、“酒の飲み方”に関し、理路整然と語られたエッセイとなっている。酒を飲むというのは、犬が日向ぼっこしているかのごとく境地でぼんやりと、といった話から始まり、こういうことも述べている。
《兎に角、そういう訳で、酒は決して他力本願の飲み方を喜ばない。涙や溜息が欲しくて酒を飲むのは、酒に身を任せることで、そうなれば酒は体の中を荒れ狂うばかりである》
(『洋酒天国』第1号、吉田健一著「呑気話(1)」より引用)
まるでラ・ロシュフコー公爵の箴言を思わせる口調(文体)で酒について語っている。つまりは、その酒を飲む主人の態度について、あるいは酩酊における他者との紳士的な関係性であるとか、酒との交渉、良識、道徳観といったことをとくと提言しているのだ。嫌味には聞こえない――。したがって、このエッセイが創刊号のトップを飾っていることの、それ相応の意味合いを過小評価すべきではないのである。
面白いことに“ヨーテン”は、内容の充実を図るべく試行錯誤が繰り返され、回を重ねるごとにエロティシズムのエッセンスが多分に醸造されていく。言うなれば、トリスバーに訪れる独身、または若い所帯主の男性サラリーマンがそのターゲットであったに違いない。
しかし、エロティシズムのエッセンスを加えていった意味合いは、酒に酔えば無礼講という意味では毛頭なく、少々のお色気路線と酩酊によって膨らむ男性陣の幻想譚、可愛らしく少年じみた妄想、あるいは仕事場から解放されたサラリーマンの束の間の享楽のためのお供――といった感じで、やはり、ふんわりとした日向ぼっこの気分なのである。その点まだ、洋酒の女性愛好者に対する配慮という部分ではまったく物足りず、時代的にそれは無理な話だったのではないか。
ただし、間違っても“ヨーテン”は、酒や人を嘲笑う無作法で不愉快な個人主義的快楽とは無縁であった。また考えるに、戦後日本で横行した悪酒とその風俗の蛮行に対する、ある意味においての絶縁宣言とも受け取れ、この点においては、吉田氏の「呑気話(1)」は画期的な散文詩的警句となっていて、洋酒に関心のある新世代サラリーマンへの、その知識人の啓蒙に成り得たのではないかとさえ思うのだ。
§
 |
| 【「パリの小さい酒場」撮影は木村伊兵衛】 |
写真家・木村伊兵衛の写真と文による「パリの小さい酒場」。こういった何気ないフォト・エッセイが、“ヨーテン”の喜怒哀楽の絶妙なスパイスとなっており、個人的には好感が持てる。
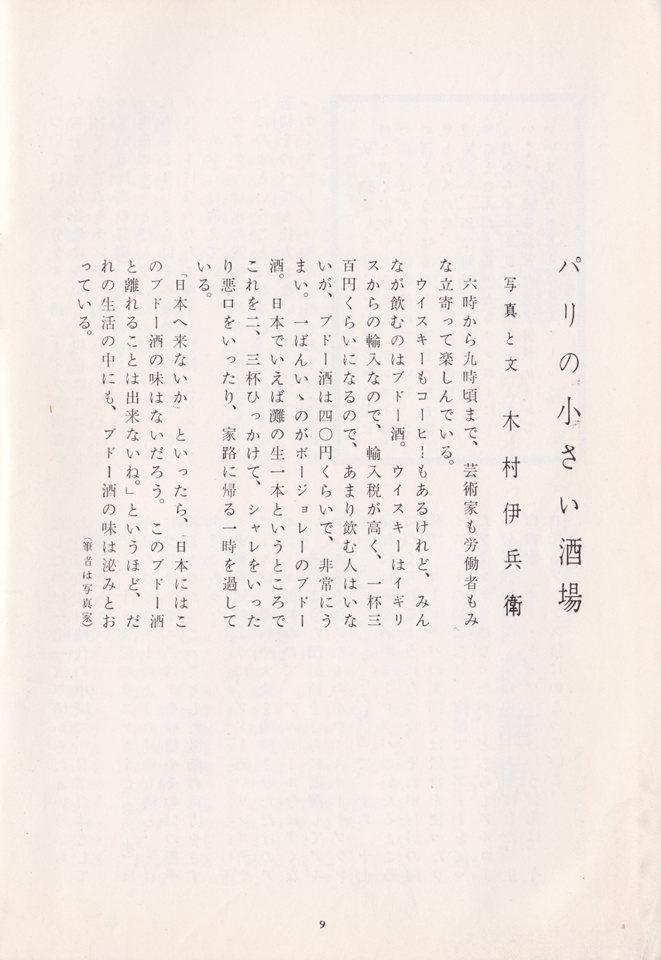 |
| 【こちらが木村伊兵衛氏の文章】 |
どこの外国でも、いかなる街々においても、小さな酒場というのは時代を超越して実存し、人が戯れ、悠々とした夜の静かなる活動の時間が流れている点で、その意味は、文学上の暗喩的存在である。それだけで単純に風情があるというものだ。木村伊兵衛がパリを訪れ、そのパリのある小さな酒場をとらえたこの貴重なカットは、彼が溺愛する名機ライカのレンジファインダーで撮影したものなのだろうか。その可能性は「極めて高い」というより、そうに違いない。カラー・フィルムであるというのが、いかにもパリでの木村伊兵衛らしくて、超然とした紳士的な感じが画面にもよく反映されている。ちなみに、パリの人々の衣食住を活写した木村伊兵衛の古い写真集を眺めれば、より濃厚なパリの気分を味わうことができるであろう。
 |
| 【中谷宇吉郎氏のエッセイ「味を楽しむ」】 |
さて次。
雪の結晶や人工雪の研究で知られる理学博士・中谷宇吉郎のエッセイ「味を楽しむ」もまた、仄かなひとときの“酒の飲み方”指南、あるいは渡米での経験譚となっている。
家族を連れてアメリカでの2年間の暮らし。日本のように、亭主が外で夕食を済ませ、女房が家で待っている、ということがほとんどなく、アメリカの中産階級の人達は、夫婦同伴で食事をするのが当たり前だとか。友人夫婦らを何組か招いて一緒に食事をし、カクテル・パーティを楽しむ、ということらしい。また、アメリカには民族の酒というものがあるわけがなく、いろいろな国の酒を混合したもの、それがすなわち、カクテル(cocktail)であり、アメリカ人はそういう酒の楽しみ方をするということ。
さらにアメリカ人の酒の飲み方について、中谷氏は流暢に綴っている。要約すると、こういうことになる。
アメリカではケンタッキー産のバーバン(bourbonのこと)があり、同じくケンタッキーで造っているジンがある。ジンは無色透明の蒸留酒だ。どの酒に混ぜても邪魔をしない。ジンにいろいろな味を付けたものが、カクテルであると思って差し支えない――と彼は述べる。
一方で、「マンハッタン」という「四薔薇」のウイスキーを基調にしたカクテル(アメリカ産バーボン、ベルモット、ビターズを混合)もある。ちなみに「四薔薇」とは、言うまでもなくあれ。そう、あれです。Four Rosesのバーボンのこと。そういった「マンハッタン」などと称したバーボン基調のカクテルも含め、中産階級のアメリカの家庭では、だいたい安い酒であるジンに味を付けて、カクテル・パーティを楽しむ。カクテル・パーティを毎週末やっても、経済的にひどい負担にはならない、と彼は綴る。
日本では、「酒は酔うために飲むもの」ととらえがちだが、アメリカのカクテル・パーティなどは、「味を楽しむために飲むもの」と中谷氏の見解は明瞭である。バーやキャバレーで酒を飲むといった、日本の都会的な、ある種気取って酒を飲むスタイルとはまったく違い、アメリカではむしろ家庭的なのだ。少なくとも中谷氏がアメリカを訪れた当時、そのうち交際していたアメリカ人は皆そうだった、ということなのだろう。これ以上のことは、私は何も言わない――。
§
 |
| 【“ヨーテン”の名物ページの「私のコクテール」】 |
“ヨーテン”第1号は、昭和31年の4月に好スタートを切った。ビール、ウイスキー、ワイン、カクテルといった洋酒ブーム旋風が吹き荒れていた時代である。果たして“ヨーテン”がその時代をつくった、と言えるかどうかは、私の調べが足りず、よく分からない。が、まだその頃日本では、「酒の味を楽しむ」といった落ち着いた感じではなく、わいわいガヤガヤ、あくまで大勢で飲むこと、会社の上司と付き合いで飲む、あるいは場末の酒場でちびちび日本酒、焼酎を嗜む、といった雰囲気。
あくまで酔うためのもの、酔って嫌なことを忘れるといった趣。洋酒は特に、明るく開放的で、若いサラリーマンにはうってつけの好材料であったに違いない。
今は逆に、酒の味を楽しむ孤独な酒の飲み方が流行る時代だ、と言えよう。尤も、そうした場では、落ち着いた雰囲気が大事になってくる。“ヨーテン”の存在というのは、むしろ現代的なのである。
一人酒の善き友として新たな快楽を与えてくれた昭和30年代、まったく画期的な壽屋の洋酒群が登場し、“ヨーテン”というPR誌がそれを宣伝した。そこに加えられたのは、酒の守護神であるバッカスの一滴、すなわち、密やかなエロティシズムだ。酒の味わい方が、それでがらりと変わった。むしろこれは、文学の楽しみ方に近い。私はそこに、その“ヨーテン”の旨味に、すっかり取り憑かれてしまったのであった。


コメント