 |
| 【ジョージ・ルーカス監督の映画『アメリカン・グラフィティ』】 |
つい先日、ロン・ハワード(Ron Howard)監督の1995年のアメリカ映画『アポロ13』(“Apollo 13”)を観たばかりであった。その精緻な演出――時代考証であったり人物描写であったり、アポロ13号のミッションで起きた諸々のアクシデントに係わる子細なやりとりを、実に丹念に描いていてお見事と思うのだけれど、ついついそのロン監督の面影が、“メルのドライブ・イン”(Mel’s Drive-In)の店内なりネオンなりをバックにした、あるひと組のカップルの若き青年の姿にフラッシュバックしたりすると、もう一度“あの映画”が観たくなる――という衝動に駆られるのだった。
それはつまり、私自身が母校の高校の視聴覚室で『コクーン』(“Cocoon”)の映画を観た時の、〈え? あのスティーヴ青年がこの映画を作ったの?!〉という度肝を抜かれた衝撃は、同じようなフラッシュバックを伴うものであって、ご本人にはたいへん恐縮な話なのだけれど、私の中では今日においても、ロン・ハワード監督は「若き青年のまま」であり、“メルのドライブ・イン”でハンバーガーを食べているスティーヴ青年の印象しかないことは、いかに“あの映画”が強烈であったか、言うなれば、劇薬的なノスタルジーの仕業だとしか、思えないのである。
“あの映画”とは、1973年公開のジョージ・ルーカス(George Lucas)監督のアメリカ映画『アメリカン・グラフィティ』(“American Graffiti”)のことである。ちなみにプロデューサーは、フランシス・フォード・コッポラ。製作費は当時にして78万ドルほどの低予算映画だった。
ルーカスが描いた青春群像劇
むしろ今、日本人の若い人は、USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)の“メルズ・ドライブイン”のそれ――と思い出す人の方が多いかも知れない。いかにもアメリカンな、ベーコンチーズバーガーなどをほおばった後になってから、『アメリカン・グラフィティ』を知ったりするのではないか。
現代においてそういう疑似体験の中で、あの映画の世界を堪能できるとは、まことに羨ましい限りである。ちなみに私が、小学生の時分でこの映画を初めて観、〈これは“アメ車”の映画だ〉――という感想しか思い浮かばなかったのは、ちょっと致し方ないというのか、愚かしいというのか、やはり時代の差は大きい。
『アメリカン・グラフィティ』は、ルーカス自身の学生時代に体験したエピソードを強烈に焼き付けた、いわゆる青春群像劇映画である。そうして映画の全編に、50年代から60年代にかけてのアメリカの輝かしいオールディーズのロックンロールがちりばめられ、DJウルフマン・ジャックのダミ声マシンガントークが、映画の随所に埋め込まれている。
時は1962年。描かれた場所は、カリフォルニア州モデストの片田舎の街。いかにも夏らしい真っ青な空がやがて紅く染まり、“メルのドライブ・イン”に集結した仲良し青年ら4人の、これから始まる最後の一夜のエピソード――。
17歳でめでたく高校を卒業することができたカート(リチャード・ドレイファス/Richard Dreyfuss)とスティーヴ(ロン・ハワード)は、東部の都会の大学に進学するべく、明朝、この街を去ることになる。カートは、どちらかと言えば真面目な性格(日本人の真面目さとは少し毛色が違うが)であり、奨学金がもらえるほど優秀な青年であるけれど、大学進学あるいはこの街を去ることにまだ幾分か躊躇していた。
スティーヴの方は、もっとこざっぱりした性格で、金髪とそばかすが特徴の小柄な青年。カートの妹のローリー(シンディ・ウィリアムズ/Cindy Williams)と恋仲であり、ローリーは真剣に別れがたい気持ちでいる。しかしスティーヴは、どこかあっけらかんとしていて、自分達の関係に対してドライである。あまりにもサバサバしすぎているスティーヴの態度に、ローリーの心は揺れ動く。
同じ仲良し4人のテリー(チャールズ・マーティン・スミス/Charles Martin Smith)は、近眼の16歳。日頃ベスパのスクーターを乗りまわしていて、女の子にはさっぱりモテない。かなりおっちょこちょいである。そんなテリーへのささやかな計らいというべきか、スティーヴは自分の車(58年型シボレー)をクリスマス休暇までのあいだテリーに預ける約束をした。テリーは思いがけない友のプレゼントにいたく感激してしまう。
もう一人、ビッグ・ジョン・ミルナー(ポール・ル・マット/Paul Le Mat)は22歳で年長。体力に自信があり、逞しく、それでいてどこか冷めている。ドラッグ・レースの不動のチャンピオン。女遊びに困ることはないが、この街から逃れられない自己のメンタルの弱さにも気づいている。32年型のカスタム・フォード、デュース・クーペを乗りまわし、あとで中学生の女の子キャロル(マッケンジー・フィリップス/Mackenzie Phillips)と素っ頓狂な出会いが待ち構えている。
彼ら若者達は、この日の夜を、つまりカートとスティーヴがこの街を去る最後の夜を楽しもうと、それぞれの思いを胸に秘めて街をさまよい始める。
スティーヴとローリーはダンス・パーティーを楽しむべく、母校の高校へと向かう。兄上のカートを後ろに乗せて――。カートにとっても、母校の面影を心に刻み込んでおきたいと思っていた。一方、テリーは、女の子と一夏の恋を味わいたいと無我夢中…必死である。“メルのドライブ・イン”のウェイトレスに声をかけまくるが誰も相手にせず。そうして女の子をナンパするべく、借りたシボレーに乗って街に繰り出す。ジョンはいつも通りの行動。街をドライヴし、気に入った女の子を見つけるため、すれ違う同乗者の女の子に声をかけまくるのだった。
 |
| 【コミカルでノスタルジーをそそられつつ、強烈な劇薬を秘めている映画】 |
アメリカナイズされた大衆文化
ナンパしてキュートな女性デビー(キャンディ・クラーク/Candy Clark)を同乗させることに成功したテリーは、“メルのドライブ・イン”でファストフードをテイクアウトしようとする。ダブル・チャビー・チャックとフレンチフライ、それからチェリー・コークを2つ――。
チェリー・コークというのは確か日本でも昔、コカ・コーラが販売したことがあってその味はなんとなく憶えている。が、ダブル・チャビー・チャックとはいったい何か?――もう既に何度もこの映画を観ているけれど、その度にダブル・チャビー・チャックっていったいどんな食べ物なんだろう――と想像を膨らませたまま、よく分からなかった。
どうやら、かつて各地に実在した、ホンモノの“メルのドライブ・イン”で、このダブル・チャビー・チャック(“a double Chubby Chuck”)なる食べ物は、なかったようである。
調べれば――明解であった。このルーカスがこしらえた創造物の食べ物は、実にあっけらかんとして、まことにアメリカ的なのであった。
単に日本人には分かりにくかっただけなのだろう。1960年代に活躍した、ツイスト・ブームの立役者でアメリカン・ロック・シンガーのチャビー・チェッカー(Chubby Checker)をご存じなら、なんてことはない話なのである。彼の名曲“The Twist”は、1960年9月にビルボード誌週間ランキング1位となり、全米のテレビやラジオのメディアで火が点き、一躍ツイスト・ブームが巻き起こった。これ以上の説明は野暮である。
アメリカナイズされた大衆文化というものに対し、私は少年時代(80年代)に比較的敏感だった――と自負するのだけれど、行きつけのレコード・ショップで、洋モノのレコードを買う勇気がなかったのも確かである。そこにビーチ・ボーイズ(The Beach Boys)のLPがあった――。ショップで何度も手に触れるのだけれど、買う勇気がなかった。
映画のエンディングでは、“All Summer Long”が流れるが、このビーチ・ボーイズの1964年の曲が、なにゆえに“1962年夏”の映画に登場するかについては、ここでは言及を避けたい。つまらぬ解説をするよりも、実際に映画を観てもらえばよく分かる。この演出もまた、ルーカスらしい――とは言え日本人にはちょっと分かりにくいけれど――含蓄がある。
《旅立ち》とハピネス
ルーカスがこれまでメディアを通じて、あちらこちらで自作寸評を論じているので、既に映画ファンならお判りかと思われるが、彼にとって《旅立ち》というのが、自身の映画作品に通ずる一貫したテーマとなっていた。
『アメリカン・グラフィティ』を観ていくと尚のこと、それが明白である。
各々の登場人物すなわちカートとスティーヴが高校を卒業し、結果的に都会へ旅立っていく、あるいは大切なものを発見してそれを守るために旅をあきらめる――といった人生の岐路の選択が描かれており、道は必ずしもそこに在るものではなく、またその道のどちらを歩むかも、主体的に自分だけで決断できるものでもなさそうだ――ということを暗にちらつかせ、そのことは人生の中盤以降にようやく気づかされるものでもある――ことを示唆している。
多かれ少なかれ、誰しも自身の中で《旅立ち》を経験し、過去の岐路の選択の記憶として、この映画をノスタルジックな世界に浸る装置として鑑賞することを、私は否定しないし、そうでなければこの映画の旨味は理解し得ない。むろん、ルーカス自身も、『アメリカン・グラフィティ』でそれを具現化したという自負があるだろう。彼にとっては10代の、カリフォルニアのモデストでの生活がその記憶の源水であり、映画の鑑賞者はそのエピソードを疑似体験しながら(ついでにアメリカのオールディーズを耳にしながら)、自身におけるノスタルジックな過去の記憶を重ね合わせて感傷に浸ることになるわけだ。言うまでもなく、それがこの映画の最大公約としての旨味である。
だがそのことは、過去の人生における、《旅立ち》の選択の正誤を評価するためのものではない。むしろ私が見出したのは、この映画に溢れる若者達の、happinessの有り様なのであった。
幸福感を探り当てること、それがノスタルジーの本質であり、アメリカにおけるあの時代の若者のhappinessとは、あのようなものだったということに対する、70年代生まれの日本人である私自身の、強い憧れであってジェラシーであって、さらにその洗練された具象が、カスタマイズされた“アメ車”の数々であり、“メルのドライブ・イン”なのであった。つまり、あの映画で描いた街やモノを含む諸々のエピソードの全ては、「絶対に体験できないこと」の結晶体=幻影なのである。
気づけば、ルーカスの映画の本質は、それが「絶対に体験できないこと」で集約されている。平易な表現で言えば、人生の過去の追体験は不可能だ――ということである。とは言え、『アメリカン・グラフィティ』は人生のうちに何度も見返すべき映画である。映画の最後に流れるビーチ・ボーイズの“All Summer Long”が、その意味を雄弁に語っているではないか。
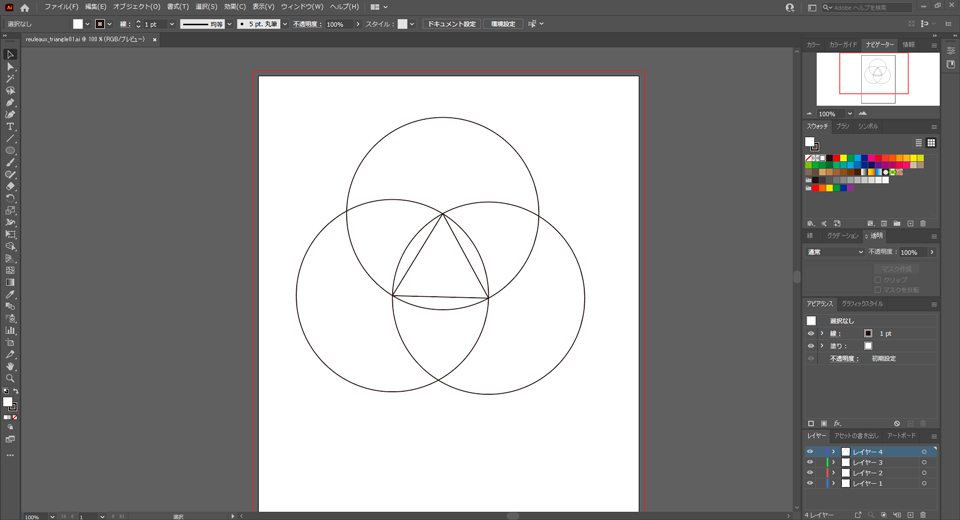

コメント