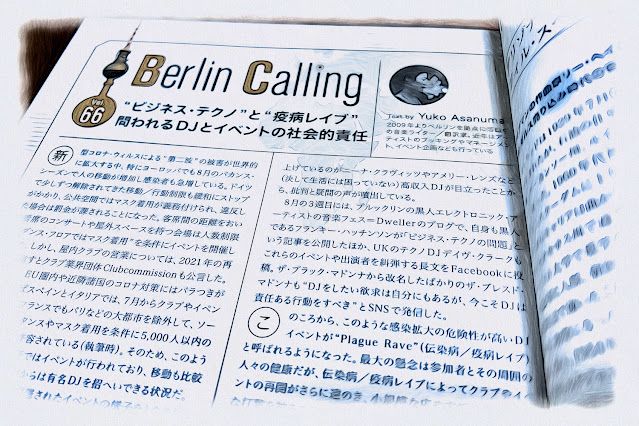 |
| 【『Sound & Recording Magazine』2020年11月号「Berlin Calling」】 |
ここ最近、好んで夜にレヴォン・ヴィンセントの『Levon Vincent』(2015年/Novel Sound)を聴いている。
ウイスキー党の私がうつらうつらしている時に聴く音楽は、クラシックであれジャズであれ、あるいはサンフランシスコの小さなガレージ・スタジオで黙々と重ね録りされたであろうチープなサウンドであれ、いったん耳から脳内にその音の波長がインプットされた時点で、森羅万象の一事象にすぎないのである。知的な作業というよりは、いかに揺りかごの中で気持ち良くいられるかだ。
レヴォンのファースト・アルバムは、喩えていえば、ポータブルなゲーム機で何の気なしに遊ぶ“単純なゲーム”でありながら、どこか際立って毒気があり、薄気味悪さもあり、かつカット野菜にドレッシングをかけ、その歯ごたえと酸味を味わいつつ、過剰な審美性に反応して即座に歯磨きを始めてしまうような、素っ頓狂的な感覚の、デオドラントの装いがある。染み出た彼の本質が、そういう音楽性を創造しているといえなくもなかった。
尤も、これまで私がオルタナティブの音楽を愉しんできた――例えば、『Oh! Penelope』(1995年/MUTSUSHI TSUJI and ZENTARO WATANABE)のサウンドの、イメージとしての“青空の解放感”だとか、ベトナムのニンビンの日当たりのいい屋内で、その間接光を浴びながら外の鳥や虫や風の音を混入させつつ録音された『Ninh Binh Brother’s Homestay』(2020年/玉置周啓&加藤成順)のような――心地良い空気感とは、レヴォンの創る音楽性は、まるで次元の違うハウス系ミュージックであることは、百も承知である。
レヴォンに関していえば、彼の創造物生産の拠点がベルリンであることに、私の音楽的嗜好の特異点を見出しているのは、自分でも少しざわざわとした興奮と驚きをもって、何か奇妙な出会いを経験したかのような新しさを感じるのであった。ちなみに、レヴォンのファースト・アルバムについては、高橋勇人さんのレヴューが詳しい([ele-king.net])。
「Berlin Calling」
ベルリンのクラブシーンを注視し続けている音楽ライターYuko Asanuma氏のコラム――月刊誌『Sound & Recording Magazine』の「Berlin Calling」――は、以前、レヴォンがとんでもない間違いの発想をしてしまったことを伝えてくれた小さなコラムである(当ブログ「オトギのくにのオト―レヴォン・ヴィンセントの音楽的表現」参照)。
そこでは、音楽的多数派であれ少数派であれ、その商業ベースの生産性の背後に見え隠れする、ある種の政治的な思惑や関心事がスポッティングされることがあり、私の関心も熱を帯びてくる。近年においては、Asanuma氏がベルリンにおける初期のコロナ禍(COVID-19のパンデミック)の状況を伝えてくれていたりして、クラブシーンの“危うい特性”を見事にあぶり出しており、とくに活字を舐めまわして読まずにはいられなかった。前回の「コロナ禍の前途を見据えて」では、2020年4月の執筆時のパンデミックの状況を記しておいた。
『Sound & Recording Magazine』2020年11月号の「Berlin Calling」(Vol.66)では、「“ビジネス・テクノ”と“疫病レイブ” 問われるDJとイベントの社会的責任」と題され、COVID-19の第二波(2020年夏)の危機的な状況の中で、クラブシーンでどのような問題があったかについて触れられていた。ここでのAsanuma氏の書いた内容を、以下、箇条書きにしてみる。
- ヨーロッパでは、8月のバカンス・シーズンで人の移動が増加。感染者も急増
- ドイツで移動及び行動制限の緩和にストップがかかる。公共の場でマスク着用義務。違反者に罰金も
- コンサートや屋外スペースなどの会場で、マスク着用を条件にイベント開催
- スペインとイタリアでは、7月からクラブやイベント再開
- フランスでは、大都市は除外するも、ソーシャルディスタンスやマスク着用を条件に、5,000人以内の屋内イベントを容認
Asanuma氏によると、こうした状況下で、SNSでイベントを映した映像が共有され、マスクをせずに密接した観客がパーティーを楽しむ姿が確認されたという。彼らを盛り上げているのは、いわゆる高収入DJのニーナ・クラヴィッツやアメリー・レンズらだったことから、批判と疑問の声が上がったらしい。
 |
| 【「Berlin Calling」でAsanuma氏が伝えていた伝染病/疫病レイブのこと】 |
伝染病/疫病レイブ
ロンドンのオンライン・マガジンAttack Magazineの2020年8月19日付のコラムでは、アメリー・レンズやニーナ・クラヴィッツといった高収入DJのイベントに集まった観客が、マスクをせずに盛り上がっている様子の画像が掲載されており、“Plague Rave”すなわち、「伝染病/疫病レイブ」と称された忌み嫌うべき状況に対する深刻な警告であり批判であり、社会的責任についても言及している。
また、2019年より始まったエレクトロ・ミュージックの黒人アーティストのフェスティバルDwellerのブログでは、ブルックリンでBossa Nova Civic Clubのブッカーであるフランキー・ハッチンソン(Frankie Decaiza Hutchinson)の書いた記事を掲載(2020年8月18日付)。――現在この記事を閲覧することはできなくなってしまっているが、Asanuma氏はこの記事を訳した内容を、自身のnoteに記していて、こちらは閲覧可能である(2020年8月20日「#BlackLivesMatter と人種差別問題の理解を深めるために: 『ビジネス・テクノ』の問題(翻訳)」)。
いみじくも、こうした当時の各国の、コロナ禍におけるクラブシーンが、非常に細々とした情報の中からでも探り当てることができるのは、幸いにして意義深い。
広く音楽は、個人や団体が楽しむもの、楽しめるものという領域の、それを拒む外野にはほとんど恩恵が受けられない、いわば感覚的・快楽主義的な知的芸術なのだから、政治的な背景であったり、COVID-19のパンデミックという壮大なアクシデントが、それ自体に対して著しく影響を及ぼしたことは、歴史的な見地からしても興味深いことである。かのシェイクスピアが、流行下のペスト(黒死病)と社会的対峙を繰り広げながら、自身の創作活動に没頭していたのと同じように、今パンデミックのクラブシーンを垣間見ることは、私にとってもたいへん有意義であり、カウンターカルチャーの極みをちらつかせてくれている。
そんな一方で、逆に、コロナ禍での幾束の瑣末が、次第に忘れ去られ、SNSやメディアにおけるログそのものがしれっと抹消されていたりするのは、まことに残念なことである。非力ながらこうした過去の記述を紐解いていき、有ったことを無いことにしないよう、こうしたカウンターカルチャーを見守っていきたいとも思っている。ともあれ、Asanuma氏の尽力のたまものである。
○関連した私の最近のお気に入りウェブサイト
[OFF THE RECORD PODCAST] https://note.com/offtherecord/
[AVYSS magazine]https://avyss-magazine.com/


コメント