※以下は、拙著旧ホームページのテクスト再録([ウェブ茶房Utaro]2010年8月2日付「スタジオにて」より)。
1992年記「スタジオにて」
2月下旬から3月にかけて、ラジオドラマの仕事で、レコーディングスタジオに入り浸る日が続いた。仕事の締切は刻々と近づいている情況であった。
その日に限って珍しくメンバーの過半数が揃って、午後4時にスタジオ入りする予定であったが、別のグループが午前中から使用しており、まだスタジオは空になっていなかった。そのグループの仕事も難航していたようで、結局私たちのグループが入室できたのは、予定時間を1時間超えた午後5時であった。
中のコントロールルームは彼らの熱気でひどかった。しかも天井に霧が発生していて、その湿度の高さは尋常ではなかった。私たちは急いで仕事の準備に取りかかり、録音のセッティングを施した。ナレーションブースにノイマンのU-87iのマイクを立て、コントロールルームのミキサーの調節を済ませた。私たちのグループに与えられたスタジオ使用の制限時間は、僅か5時間で、そのために作業は簡潔に進行させなければならなかった。
プロデューサー兼ナレーターの大島さんは、ミキシング・ルームにこもって、マイクテストを始めた。
「早く録っちゃいましょうね」
大島さんはミキシング担当の私を急かした。本来、ミキサーとマスターレコーダーの操作は別の担当になるのだが、この日は何故か、その両方を私が担当していた。それがかえって彼女の神経を苛立たせていたようである。
こちらの準備も整い、私は彼女にリハーサルのキューを出した。彼女は必死になってセリフを読んでいる。健気であった。
「どう? これで」
「うーん…。もうちょっと続けて」
彼女は何の異変も知らずに、セリフを読み続けている。一方こちらでは、先ほどからマイクの調子がおかしいのに気づいていた。どうもトリムの入力レベルが不安定なのである。私は、ディレクターの斉藤さんにマイクケーブルの交換を頼んだ。
「何よー。どうしたのよー」
ヒステリックになった大島さんが、ミキシングルームから出てきた。私はその時、事態はだんだんと深刻化し、深みにはまっていくような気がした。
そのうち、斉藤さんがケーブルの交換を済ませたので、もう一度ここでサウンドチェックをした。大島さんの声が妙にうわずっているのがわかった。不安が高まる。だが、結果は何度試してみても同じであった。音は出るものの、どうも不安定で落ち着きがない。大島さんは激しく体を震わせた。
「ねえ、もう本番にしましょ」
「え? でもうーん…。もうちょっと待って」
時間はそれから大幅に経過した。それも実質的な作業とは違う問題で。だがこれを乗り越えなければ作業が進まないのも事実である。そこに超えなければならぬ山があり、一致団結しての全員の力が必要であった。
韓国からの留学生である愚さんは、スタジオの外のロッカーからミキサーのマニュアルを持ち出してきて、あれこれとそれを読み始めた。そしてみんなに説明しだした。
「エト、コノボタンヲオスダロ、スギニコレヲ…」
私は半分耳を傾けていながら、もう半分は聞いていなかった。そのマニュアルに書かれてあることはすべて理解しており、また手順を追ってそれを理解したとしても、目の前の現状は変わらないとわかっていたのである。
「とりあえず、CDでもかけましょうか」
大島さんはさっさとCDプレーヤーをいじり始めた。この何も進行していないこと、時間の浪費、自分たちがコンピュータに振り回されていること、そして締切が迫っていることなどがつらつらと頭の中を駆け巡り、私自身の疲労もピークに達していた。
「ね、じゃ、もう帰ろうか」
同じミキサー担当の伊藤は、きわめて楽観的というか無責任である。早くこの場から去り、帰りたいという心情が見え見えであったが、それが思いがけないユーモアにもきこえた。
私は、彼の愚痴を聞きつつ、ミキサーのフェーダーを最適レベルまで振り上げて、CDからの音を待ち構えた。そのコンマ数秒後、私の耳は炸裂した。
バァーン!
私たちはそれぞれ声を上げて、その幻覚的な世界の中で錯乱した。体験したことのないものすごい音が鳴って、私たちの体を包み込んでしまったのである。
音楽担当の古谷くんは、とっさの条件反射で、マスターフェーダーとモニターヴォリュームを下げた。だがおかしい。音を完全に消したつもりだったのだが、抵抗無限大のゼロ状態であるにもかかわらず、ラージスピーカーからは、数デシベルほどの音が漏れていたのである。
大島さんは、目を鳩のようにパチクリさせながら、CDプレーヤーを止めた。その時、愚さんはコントロールルームの中にいなかった。いつの間にかスタジオを抜け出してしまっていた。
「あー、何が起きたかとおもったー。ビックリー」
しかし、この珍事によってすべてが把握できた。ミキサーはフェーダーを抵抗無限大にしてもマイクからの音を入力する。またライン入力からも同様である。これで私はピンときた。
そう、前のグループが午前から午後にかけてスタジオを占拠していたため、スタジオ内には尋常でないほどの熱気と湿度に侵されていた。何故そうなっていたのか。つまり、前のグループはコントロールルームのエアコンを付けておらず、それが原因で、ミキサー内部のコンピュータが異常を来し、あのような爆音を発生させたに違いない。私は走って電源室に駆け込んだ。
「一体何をするのよ!」
「気でも狂ったのか!」
全員、私が何をするか察し絶叫した。大島さんは特に顔を青ざめ、取り乱した。
「あんた、自分が何をしようとしているのか、わかってるの?」
「ああ、わかってるさ。だがこれしか方法はないんだ」
私は自信と不安の両極をさまよい、決断を一瞬ためらわせたが、やはり残された道はこれしかなかった。大島さんは私の背中に吠えた。
「これはあなただけの問題じゃないわ。全員の将来に関わる問題なのよ! それを承知の上でのことでしょうね」
「ええ。承知してます。僕が責任を取ります」
電源室の中ではエアコンが稼働していて、ひんやりとしていた。
私はコンピュータの電源部に目をやった。ミキサーの錯乱の原因は、過剰な熱気と湿度によるコンピュータの誤動作である。その仮説が正しければ、一度リセットを押し、コンピュータを再起動させることによって、正常な状態に戻すことができる、はずであった。彼らが危惧したのは、それによる他の危機への電気的影響であったが、私はその影響はないだろうとみた。
私は思いきってリセットスイッチを押した。フロッピーディスクが勢いよく動き出した。これは、コンピュータが新たなデータを読み込んでいる証拠である。コントロールルームに戻り、モニターディスプレイを監視すると、そこでもやはり正常な情報を表示していた。
後は、再びCDをかけ、フェーダーのチェックをするだけであった。大島さんはCDの再生ボタンを押した。
全員耳を塞いだ。古谷くんは怖がって、フェーダーをほんの少し上げて手を離してしまった。先ほどの大音量でスピーカーのコーンを傷めただろうと心配したが、ラージスピーカーはホーン型だったために、それは奇跡的に免れたのである。これがもしスモールスピーカーだったなら、高出力でコーンを傷め、その多大な修理費を捻出しなければならなかっただろう。
結局、CDの音は大きく鳴らず、フェーダーは正常に戻っていた。やはり、コンピュータの誤動作だったのである。ここでようやく、みんなほっとした表情を見せた。だが、作業はやっと開始地点に着いただけであった。ここから本当の作業が始まるのである。みんなの顔がもう一度真剣に変わった。
そこからの作業は非常に根気のいるものであったが、何故か辛い気持ちにはならなかった。少なくとも私は、作業を楽しみながらこなすことができた。もし深夜、あるいは明け方まで続いたのなら、それでも続けられたに違いない。私にとって、この場の独特な雰囲気とスタジオそのものの匂い、これらは何よりも優る強壮剤のようなものであった。
「まだまだ続くわね」
大島さんは、数時間の苦闘にもへこたれなかった。女プロデューサーとしての仕事は、肉体的にも精神的にもタフでなければならない。しかし彼女はそれを見事に克服し、鋭い感受性で仕事をこなした。彼女をこの世界に踏み入れさせたものは、一体何であったのか。私には興味ある内面であった。
すべての作業が終わり、それぞれがスタジオを後にした。私と大島さんは最後まで居残り、スタジオの消灯を済ませた。分厚い鉄の扉を閉めると、ズボンのポケットから鍵を取り出し、鍵穴に差し込んだ。大島さんの手元は機敏であった。私は最後に彼女に声をかけた。
「大島さん、部屋のスリッパ、履いたままだよ」
「あら」
彼女は声高に驚いてみせた。そして大笑いして、もう一度鍵を開け、履いていたスリッパを暗いスタジオの中にぶん投げた。まるで私の身体までが、放り投げられたような気がした。
※作中の氏名はすべて仮名
「スタジオにて」【補遺】
「スタジオにて」は1992年、千代田工科芸術専門学校(千代田学園)に在籍中に書かれたものである。当時の本館の数十メートル離れた所に某号館と呼ばれた学園所有の別館の建物があって、その上層階に音響芸術科が使用していた第1レコーディングスタジオ(1スタ)と第2レコーディングスタジオ(2スタ)があった。
ここに当時使用していた機材をリストアップしてみた(両スタジオ混合)。
●コンソール:SSL SL4040E/サウンドクラフト Series8000
●モニタースピーカー:レイオーディオ RM5B/エクスクルーシブ 2401ツイン
●マルチレコーダー:オタリ MTR90
●マスターレコーダー:スチューダー A820/ソニー PCM7030
●ノイズリダクションシステム:ドルビー A-Type/ドルビー SR-Type
●エフェクター:AMS rmx16/レキシコン 480L/EMT 244
●録音テープ:アンペックス 456
●マイクロフォン:ノイマン U87,U47,KM84/AKG C414,C451/ショップス CMC54U,CMC56U/ゼンハイザー MD421/シュアー SM57,SM58/エレクトロボイス RE20,PL20
SSL(ソリッド・ステート・ロジック)のイン・ライン・タイプ・コンソールSL4040Eのモジュールは以下の通りである。ちなみにSL4000Eシリーズの設計はコリン・サンダース。
レコーディングの省力化を図るコンピューター・ミックス(トータル・リコール)によるオートメーション機能及びVCAフェーダーでのサブ・グループ・フェーダー機能が有名。
1.出力アサインメント・セレクター、ミックス・バス
2.ヘッド・アンプ部
3.ダイナミクス・セクション
4.フィルター、EQ部
5.ステレオ・キュー・センド、AUX
6.モニター・インプット、マルチトラック・リモート
7.ソロ/カット、チャンネル・フェーダー。
8.プライマリー・コンピューター、トータル・リコール
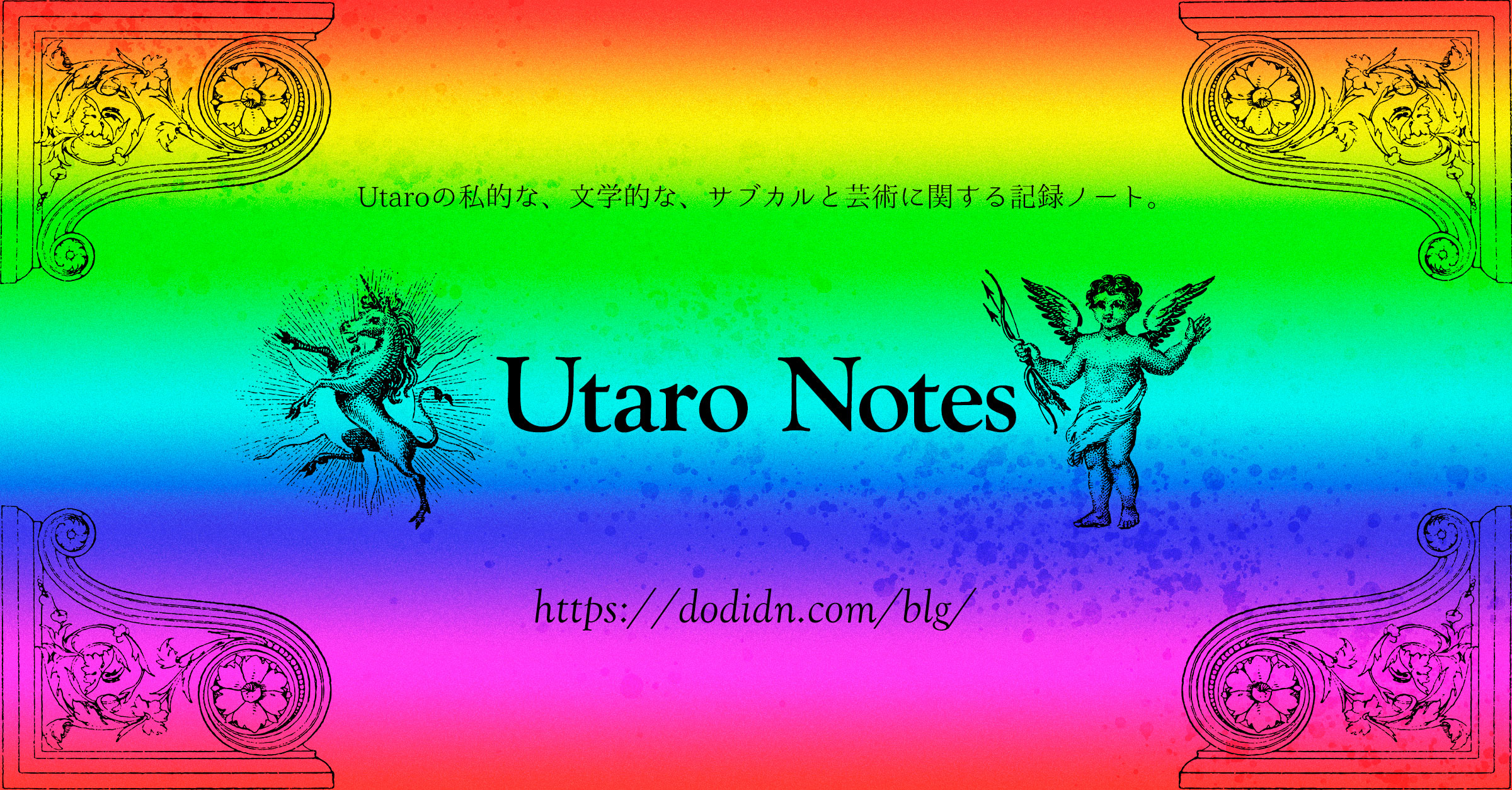


コメント