先週、麗らかな春の日差しに恵まれて、群馬県は館林市に在るつつじが岡公園にて、「つつじまつり」を鑑賞した。風は穏やか、花は見頃。前回は3年前に訪れているが、今年はいっそう鮮やかに様々な品種のツツジが威勢よく咲き誇っていた。
ツツジの魅力は、その多様な色彩で、品種によって同じ紅系でも色の度合いが違う。例年これを見比べるのが楽しみであり、ヤマツツジ、オオヤマツツジ、キリシマツツジなどの紅と朱のバリエーションは見事なものである。そうかと思えば、キシツツジのように、花弁の全体は白色でありながら、ほんのわずかに薄紅の色味がかかっていて、単純な白色ではない美しさの映えにも魅了されたりする。
花の美とは、常に主観である。だから詩歌の題材に好まれる。観る側つまり人間の心の移ろいや時事の感性によってその美的視点が変わる。私も何度か訪れている「つつじまつり」ではあるが、あの朱系のキリシマツツジが最も美しいと思った年もあれば、キシツツジの白色に感興したりもする。
今回訪れて最も感動したのは、ヨドガワツツジである。
原産は朝鮮半島だそうだが、他の写真集や植物図鑑で観るより、このつつじが岡公園のヨドガワツツジの方が遙かに美しい。花弁は紫の濃淡で広がり、ほとんど黒に近い濃紫色とほとんど白に近い薄紫色との構成は誠に自然美の極致、神の仕業としか言いようがない。この花の品格は、この花冠の繊細な造りですべてを物語っており、物理的な美を超越して文学的音楽的詩趣にまで触れたくなるような絶世である。これもまた、人と同じ一期一会の出逢いであろうか。
 |
| 城沼の一帯 |
ところで、公園の北側に広がる「城沼」は、田山花袋の歌でも知られる。
一旦ツツジの群生を背にして、この広く落ち着いた沼の風景を見渡す。向こう側に寺が見える。石材を土台にした白壁が直線に伸びている。沼の水面が鏡となって、その全体が、繁茂する樹木と融和しながら鏡像で浮かび上がっている。
その浮かび上がった寺――禅宗・巨法山善長寺は、江戸期の館林城主・榊原康政の側室お辻の供養塔がある寺で、1605年(慶長10年)、城沼で侍女と共に命を絶ったという伝説がある。館林のツツジの繁栄はこの伝説が発端となっているそうだ。
戦乱の世の、武将の愛妾となったお辻とは、どのような女性だったのだろうか。ここでの私の主観的想像は、あのヨドガワツツジの美しさを生き写した、暁の沼に佇む幽遠なる美の女性である。むしろ、その女があの“紫の花”になったと言ってもいい。
時間はあっという間に過ぎる。
窺い知れない史実伝説に対し私は、ただ盲目的にこの風景を眺め、幾許かの夢想にときめく他はなかった。

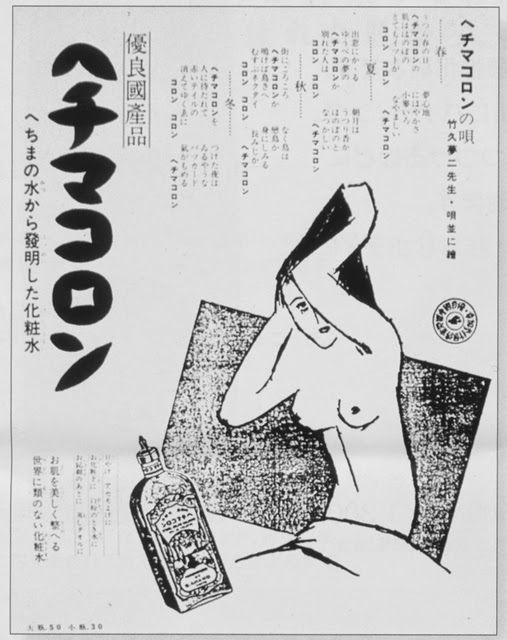
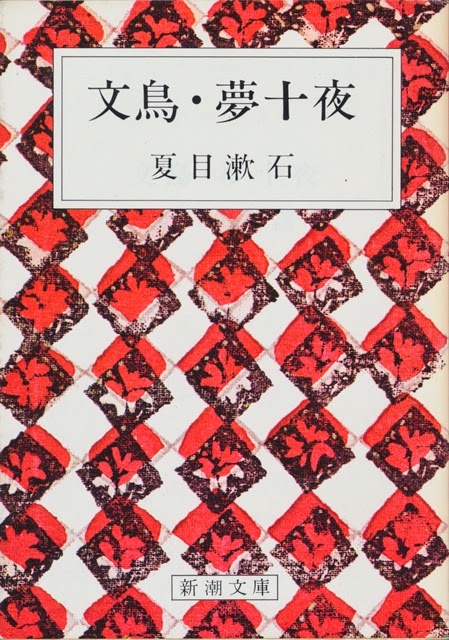
コメント