何気なくチェストの引き出しを引いたら、古い本が出てきた。社会派カメラマン・福島菊次郎の写真集『戦後の若者たち Part II リブとふうてん』(三一書房・1981年初版)である。何故こんな本がここにあるのかと一瞬面食らった。これを買った時のことをすっかり忘れてしまっていたのだ。購入履歴を調べたら、2006年となっていた。10年前に自分が何を思ってこれを入手したのかやはり憶えていないが、いま新鮮な気持ちでこの写真集をくまなく眺めていくと、これが昭和の時代をずっしりと背負った重たい、とてつもない写真集であることが分かってきた。
『戦後の若者たち Part II リブとふうてん』は“リブ”と“ふうてん”に分かれている。二部構成になっていて、第I部は「幻覚の街から」、第II部は「ウーマンリブの蜂起」。どちらも福島氏が1960年代後半から70年代にかけて撮影したものと思われる。ここでは、後者の“リブ”に関する写真に触れてみたい。
まずこの写真集は、幸いにも福島氏自らの解説文がそれぞれのテーマ毎に添えられており、諸処のカットの解題として役立つ。そこから、何故福島氏がこのような写真を撮ることになったかの経緯が透けて見えてくる。この補助によって写真のディテールがよりはっきりとしてくるのだが、第II部「ウーマンリブの蜂起」は、1971年8月、長野県飯山市の山村で開かれた「第一回全国リブ大会」が主な被写体である。
ウーマン・リブ――。
私は1980年代の小学生の頃、午後枠で再放送された日本テレビ系列のテレビドラマ『おれは男だ!』(森田健作、早瀬久美主演)を観て、“ウーマン・リブ”という言葉を初めて知ったように思う。ちなみに『おれは男だ!』は、私が生まれる前の、1971年から72年にかけて放送されたテレビドラマであった。
何やら女子高校生らが集団になって強気に、森田健作演じる主人公(小林弘二)に詰め寄るシーンが多かった、と記憶する。その集団女子の中心人物が早瀬久美演じる吉川操で、いつも二人はけんか腰だった印象がある。
小学生だった私はそういうシーンを見ても、なかなか“ウーマン・リブ”の意味合いが掴めなかったのだが、とにかく女子たちが男たちに負けず、強く生きようとしていたのではないか、ということは感じられた。そこでてっきり“ウーマン・リブ”とは、“Woman Live”の略だと思い込んだのだ。ずいぶん垢抜けたネーミングの運動だなと、私は勝手に信じ込んだのである。
――これは今でもはっきり憶えていることなのだけれど、卒業した中学校では、“…らしく”しなさい、と常に先生たちから言われていた。あくまで個人に対してではなく、生徒全体に生活指導的な内容で、学校の外では特に中学生“らしい”身なりでとか、中学生“らしい”態度で、などと先生たちは口にした。こちらも表面ではそれに納得するのだが、内心、“らしさ”とはなんだろうと、判然としない部分もあった。
むしろ大人たちは自分たちを“らしさ”という人格と顔のない記号に当てはめてとらえたく、そうすることで便宜上教育しやすいと考えているのではないか。個々の人格性のはみ出た面を認めず削り取ってしまえば、指導が楽である。例えば男子生徒の頭髪の丸刈り強制や、女子の長髪の場合の編んで束ねることを強要するといった校則はその最たるもので、個々の個性と人格形成への自由な思考が剥奪され、軍隊式に一律化された生徒らは3年間、大人が捏造した中学生“らしさ”の枠に押し込まれてしまっていた――。
そう振り返ると『おれは男だ!』のドラマは、確かに若者の、生きたドラマであった。あのドラマを一言で片付けてしまえば、テレビ向けにアレンジされた学園青春群像劇に違いない。が、いわゆるスポ根ドラマとは一線を画していたように思う(あのドラマを単に剣道のスポ根ドラマと勘違いしている人が多くいるのではないか)。ドラマの底辺に流れていたのは根性や忍耐云々ではなくて、まさしくウーマン・リブ、すなわち《女性解放》であったし、その先の男女の生き方、拘わり方が命題化された、エポック・メイキングであったのだ。
*
 |
| 【開放的なリブの女性たち】 |
恥ずかしながら私にとっても“Woman Live”が勘違いであったことを、今ようやく気づいた。調べて繙けば、1960年代後半のアメリカの、女性公民権運動に端を発した“Women’s Liberation”の運動が“ウーマン・リブ”の語源であると、講談社の『日録20世紀』[1970 昭和45年]を読んで理解した。
アメリカの女性公民権運動のうねりが最高潮を迎え、ついに1970年8月26日、ニューヨークの五番街で大規模なウーマン・リブのデモがおこなわれた(この日、全米の主要都市でおよそ10万人の女性がデモに参加したという)。活動を指導したベティ・フリーダンや『性の政治学』の著者ケイト・ミレットが活動史の中心的人物であり、日本でもその影響が波及し、1971年の長野県飯山市のリブ大会=リブ合宿へと連鎖していく。日本におけるリブ活動のリーダーであった活動家・田中美津については、やはり福島菊次郎の写真集『戦後の若者たち Part II リブとふうてん』の方が詳しい。
しかしながら、“大正生れの僕”“中年男”と自らを少々侮蔑した福島氏が、《“女の立場”に立って物事を考えたことはほとんどなかった》として、そのリブ合宿に適度ににじり寄ってとらえた写真の数々が、実に生々しかった。第II部「ウーマンリブの蜂起」のことである。
中でも、男子禁制とされた合宿の周縁から、ススキの繁茂する村道の「裸になった女性達」をとらえた開放的風景は、時代や文化のパラダイムを飛び越えた、優雅なる大傑作であると言えよう。私は思った。もしかすると、源氏物語に出てくるような平安貴族の女性たちは、日頃こんなふうに自由闊達な一面があったのではないか。
 |
| 【活発だったウーマン・リブのデモ】 |
リブ合宿以外では、「父権制社会打倒」「なくせ性差別」「中絶禁止法反対」といったスローガンの旗や首に提げられたプラカードが目立つ街頭デモ行進の写真。中には女性がエプロン姿で、そこに「政府は女(の?)子宮に口出しするな!」と書かれてあって思わず唸ってしまった。そんな過激な文句に福島氏も目を留めてシャッターを切ったのではないか。
ところで、先述したアメリカの大規模デモでも、その要求内容の一つとして、「妊娠中絶をおこなう施設の建設」が含まれている。
福島氏はこの写真集の中で、ある種のアンチテーゼを残した。それはリブの女性達に対してではなく、社会全体に対しての痛烈な批判と思われるのだが、ある女性患者の中絶手術写真がそれである。
 |
| 【福島菊次郎が中絶手術の現場をとらえた】 |
妊娠4ヵ月の患者の子宮から取り出された、真っ赤な血と肉の塊。この本の巻頭にそのカラー写真が掲載されていた。見事なくらいに真っ赤な、塊である。妊娠4ヵ月なのだから体長5センチになっているはずの胎児は、子宮の中で粉々に砕かれてその痕跡さえ見いだせなかった、と福島氏は書く。私にもそれは見えない。胎児はどこにも見えない。出産における喜びの現場とは真逆の、暗鬱とした死の始末の現場であることに、福島氏は嘆く。明らかに胎児は殺されたのだと。
《女性解放》を掲げたウーマン・リブの同胞は、こうした現実の直視(というより、《女性解放》を掲げた時から常に傍らにある現実)によって、それが単なる《解放》論では済まされない別の問題への審議を余儀なくされた。無論これは人としての倫理の問題であり、《女性解放》にすり替えてはならない問題である。
福島菊次郎は、戦後日本のこうしたあらゆる社会問題に直面し、それと向き合って、写真を撮り続けた。リブ運動の女性たちを活写したそれらには、生身の人間の憤怒と喜び、そして愛が充満していて、私は自らの身体の昂揚を抑えることができなかった。

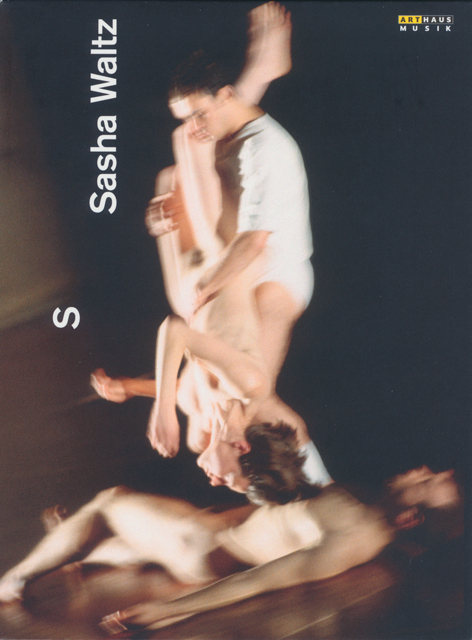

コメント