 |
| 【『洋酒天国』第20号】 |
酒の善き友、壽屋(現サントリー)のPR誌“ヨーテン”。《女房は死んだ、おれは自由だ! これでしこたま飲めるというもの。 今までは一文無しで帰ってくると 奴の喚きが骨身にこたえた》というボードレールの「悪の華―人殺しの酒」の散文詩で始まる『洋酒天国』(洋酒天国社)第20号は昭和32年12月発行。表紙はどうやら、1925年T型フォード車らしい。残念ながらというか申し訳ないことに、その図体の大きいボディの先頭は裏表紙の方になってしまっていて、ここでは見られず。しかしぼんやりと小さく、木箱の上に置かれた瓶はやはり、トリスの白ラベルであり、ヨーテン定番のフェイバリット・アイコンである。
さて、本の中身。まずはヌード・フォト。
――ここで“ヨーテン”に関する面白い話を、思い出した。小玉武著『「洋酒天国」とその時代』(ちくま文庫)の解説を書いた評論家・鹿島茂氏は、昭和37年の中学1年生の時、既に“ヨーテン”の愛読者だったという。
無論、未成年の彼がトリスバーの客だったわけではない。鹿島氏の実家は横浜の金沢区で、酒屋を営んでいた。当時サントリーはビール販売の促進のために、いわゆる営業目的で、どうやら酒屋の主人らに“ヨーテン”を配布していたらしいのだ。販売促進の切り札として、“ヨーテン”のヌード・グラビアが武器になったと、鹿島氏は書いている。つまり鹿島氏本人も、そんなオトナの小冊子の魅惑に惹かれ、愛読者になったというわけだ。
 |
| 【中村正也氏撮影のヌード・フォト】 |
閑話休題。今号のヌード・フォト。2ページを割いた長い黒髪の女性の肢体は中村正也氏の作品。モデルは誰かというのは不明で、どこのページを開いてもその名前は載っていない。モデルが無記名であることを考えると、いつものヨーテン“御用達”日劇ヌード・ダンサーではないと思われる。
それにしても、この肢体のしなやかさはなんとも美しい。絶妙な露光量で黒髪が引き立ち、肌のコントラストが中和され、モノクロームのグラデーションがなめらかに収められている。これぞ中村氏の現像魔術とでも言うべきか。この時代の日本の、モノクローム・フィルムによるヌード・フォトは、そのテクニックにおける一つの芸術的頂点に達した最盛期であったに違いない。
*
香料研究の著書の多い國學院大學の文学博士、山田憲太郎の「ミイラ造りと酒」というエッセイも、読んでみるとなかなか面白い。ここでは匂いや香りの話は出てこない。酒の話である。
紀元前のエジプトのミイラ造りは秘中の秘だとかで、その秘法を唯一伝えるヘロドトスによると、遺体の内臓を取り出した後、腹部をパーム・ワインで洗浄したり、70日間ソーダ水に漬けて遺体をミイラにした後、再びパーム・ワインで洗う、などとあってミイラ造りにおいてパーム・ワインが大活躍する、という話になっている。
山田氏はこのパーム・ワイン(ヤシ酒)に着目した、わけだ。彼はこれを《天国から地獄に通じる酒》と称す。パーム、つまり砂漠の中の樹林に棗椰子(ナツメヤシ)が生えていて、この樹木は建築材になったりパンになったり家畜の飼料になったりする。そういうことでペルシャ人は、360の用途がある「生命の泉」と呼んで、歌にも詠み込んでいるのだという。このパーム・ワインは、ヤシの花から液体を採取し醗酵させたもので、別名“タマル”(最愛の美人の意)と言うらしい。
つまらぬ蛇足になるが、子供の頃、私は上野の科学博物館で、“別館”と称されたほとんど観覧者のいない薄暗い展示室にて、本物のミイラを見たことがある。私は“ベッカン”と聞くと、何か特別な響きが感じられて好きである。
ともかくその“別館”で、一体のミイラを見たのだ。それが女性のミイラだったのか男性のミイラだったのか、全身が包帯でぐるぐる巻きになっていたのかさえ、あまりよく憶えていない。しかしながら、紀元前のエジプトの、その生活文化圏を実際に呼吸して生きていた王侯貴族僧侶の某さんがこのような姿で現代に残り、東京は上野の公園の一角で寝静まっていることに深い感銘を受けた。もちろんそれを見た時、このミイラがパーム・ワインで洗浄されていたなどということは露程も知らず、その秘中の秘の秘法も、世界のあらゆる大小の文明を支えてきた酒の素晴らしさについてさえも存じない、丸裸の“ベッカン”少年であったことは確かである。
*
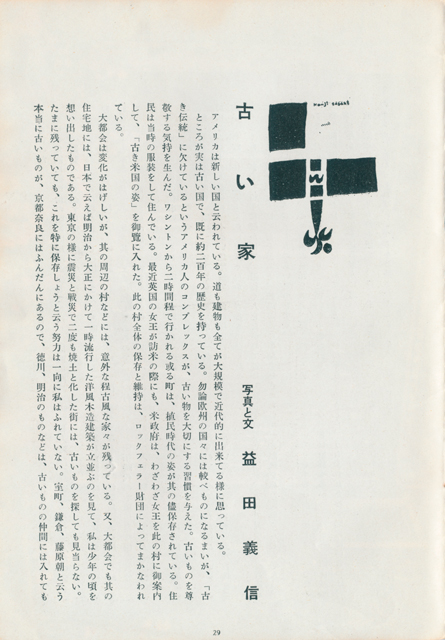 |
| 【益田義信「古い家」】 |
どうも考えていくと第20号は、少しばかり強引な総論ではあるが、古風、というのがテーマであるように思われる。
洋画家・益田義信のエッセイ「古い家」。旅先で出合った古風な家についての、甘美な回想文。そもそも何故、今号の表紙がフォード車なのかということだが、編集部が目を付けたのは益田義信氏の父の、劇作家でもある益田太郎冠者の落語「かんしゃく」(大正期の作)であろう。この噺には当時まだ珍しかった自動車が登場する。フォードが日本で生産を始めたのが1924年。益田太郎冠者の父(益田孝)は三井財閥の創始者であり、男爵である。ちなみに益田太郎冠者も男爵である。
そんな財閥出身の益田義信氏(慶應義塾卒)は、祖父の遺した財産を放蕩三昧した曰く付きらしいが、彼が回想した「古い家」は、近代的なアメリカの都市の片隅に残った、ある古い家を写真に収めたフォト・エッセイである。
 |
| 【益田義信氏が撮影したロス市の古い家】 |
ロス市の一角に残ったその家が、どれほど古い家なのか、私にはよく分からない。紫やピンクの花が乱れ咲く花壇の庭の奥に、その古めかしい建物に囲まれた3つの椅子が、ひっそりと佇んでいる。象牙色の窓枠の内側は網材なのかガラス材なのか判断ができないけれど、それが写真全体の陰の部分となっていて、その黒々とした趣が、やけに恐ろしい。いかにも窓枠の角の向こうで“古きアメリカ”の住人であった地縛霊が、ひょこっと顔を覗かせて潜んでいそうで、怖いのである。
モノクロームのフィルムであればもっと品のある、むしろ花壇の乱れ咲く花の色めきなどいらない、古めかしい建物の直線と黒い陰を生かした静謐な構図が撮れたであろうに、そこが洋画家たる所以の、放蕩家の、色彩の中に埋没した幻を見るかのような1ショットになっていると感じるのは、言い過ぎであろうか。先述した中村氏の写真と好対照であり、「古い家」は酒の話など一切なく、カラー写真に“酔って”しまったvacantの印象が強い。


コメント