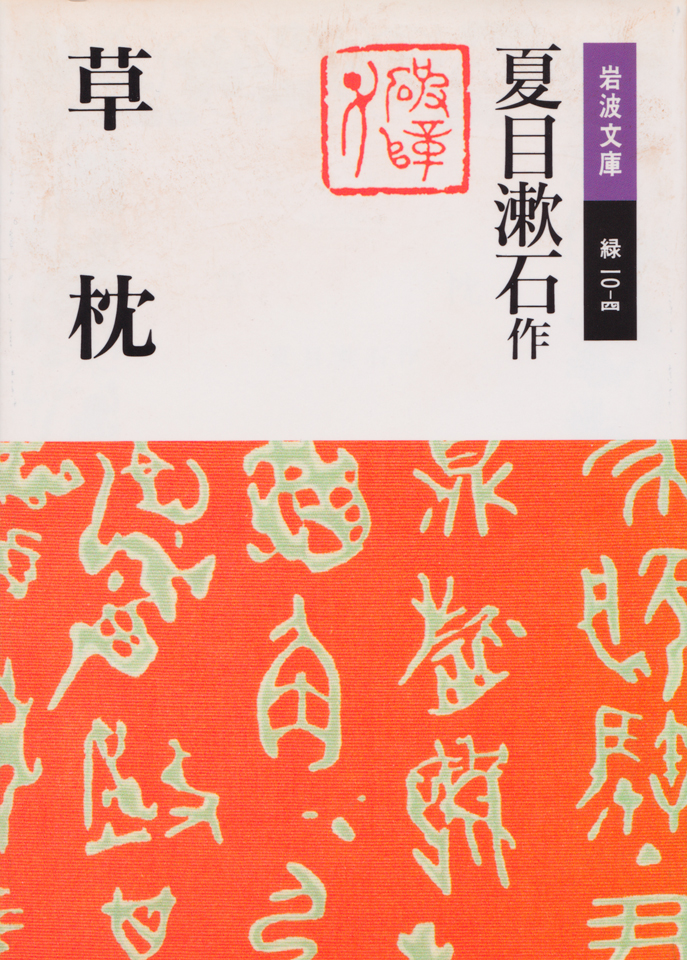 |
| 【何度も読み耽っている漱石の『草枕』】 |
風邪をひいていたから、この前漱石山房記念館を訪れた序で、神楽坂の“物理学校”に寄ることができなかった。悔しい。“物理学校”と言えば、『坊っちゃん』の坊っちゃんである。坊っちゃんは東京物理学校出身で、現在、神楽坂には明治39年建築の校舎が復元され、近代科学資料館となっている。無論、今は“物理学校”とは言わない。東京理科大学である。
先月の26日、朝日新聞の記事で「『草枕』まるで桃源郷」という宮崎駿監督と半藤一利氏の対談の、“草枕”話を読んだ。『草枕』一つで、二人の語らいが熱を帯びたものになったことが想像される。
私も『草枕』が急に読みたくなった。と同時に、羊羹が食いたくなった。――羊羹。紫黒色の、餡を練ったり蒸したりして固めた菓子――。『草枕』を読むと、羊羹が食いたくなる。確か10年ほど前、『草枕』を読んだ際には、まだそれほど実物の羊羹に心を奪われることはなかった(当ブログ「漱石の『草枕』」)。が、それ以降である。この小説を何度も読み返しているうち、すっかり羊羹という菓子の虜になってしまった感がある。
だから私は今、ある老舗和菓子屋の羊羹を調達したのだ。それを頬張りながら『草枕』の字面を愉しんでいる。その老舗は慶応2年創業というから、考えてみれば漱石の生まれた前年ではないか。『草枕』に読み耽り、漱石山房を訪れ、またちまちまと『草枕』を開いたりしている。風邪はなんとかかんとか、おさまってきたようだ。
§
 |
| 【11月26日付朝日新聞朝刊より】 |
『草枕』を何度も読んでいる。人生のうちにこれほど繰り返して読む小説はあろうか。『草枕』の中の些細な文章が、突然何を思ったか光り輝く瞬間というのがある。それを体験するのがすこぶる愉しい。新聞にもあったが、宮崎監督も《何度読んでも、どこから読んでも面白い》と述べて『草枕』を愉しんでいる。飛行機に乗る時も持っていくそうだから、言わば旅のお供の本である。私もそのように感じることがある。
『草枕』は、本(小説)の体裁よりはむしろ、旅に供する“行李”(こうり)に近い。若者からすれば、漱石と言えば『猫』だの『坊っちゃん』を読んだりして、とかく『草枕』は敬遠されているだろう。私も若い頃はこれを読むことはしなかった。けれども、だんだん自分が世の中の垢にまみれてくると、ほかの癇に触れる小説などは読みたくなくなり、なにかとビターなような文章の字面を、頭に詰め込みたくなる(数字がいっぱい出てくるような科学書とか、日経新聞とか)。情に溺れそうな小説より、非人情がいい。『草枕』とか『倫敦塔』とか――。そもそも漱石は、そんなような文章を書くのが得意な作家だ。
今年の夏――。その頃、病で入院していた母のリハビリ生活もだいぶ軽微で快活なものとなり、秋には退院という目処が立った時、なら秋には一人で気晴らしに、松山にでも行こうかと思いついた。買ったばかりの角川文庫の『坊っちゃん』を引っ提げて、宿泊先の予約などもした。だが結局、当日近辺の日程が雑務に追われることが分かってきたので、旅行は取りやめ。手元に残った文庫本の『坊っちゃん』だけは、最後まで読み通した。
ともかくこの秋からずっと、なにやら漱石絡みである。
角川文庫版『坊っちゃん』の解説(「夏目漱石――人と文学」)を書いたのは本多顕彰氏だけれど、その最後のページに、早稲田の漱石山房の外観写真が掲載してあった。この写真がよく目に焼き付いた。ちょうど9月末には、漱石山房が記念館となってオープンすることが分かっていたので、松山には行けなかったが漱石山房には行けるだろうとは思い、開館まもなく訪れる予定を組んではいたものの、これもあえなく中止。父が不慮の病で入院の事態となり、気持ちはこの時、ざっくりと漱石から離れていったのを憶えている。
§
11月。父の葬儀が済んで数週間後。前述の宮崎駿監督と半藤一利氏の対談の記事を読んだ。再び、漱石熱が沸き立った。病院を何度も行き来する半年間の生活の疲労が出たせいか、本格的な風邪をひいて熱も出た。日中、『草枕』を読み返し始めた。どこかうまい羊羹を売っている老舗はないかと、思った。それまでどうにもこうにも度重なる雑務に追われていた日程からようやく解放されて、つい先日、念願の漱石山房へ訪れることができた。序での“物理学校”は諦めたものの、羊羹の老舗も程なく見つかった。美味い羊羹を食いながら『草枕』を読んだ。文中の羊羹の箇所を書き出してみる。
《菓子皿のなかを見ると、立派な羊羹が並んでいる。余は凡ての菓子のうちで尤も羊羹が好だ。別段食いたくはないが、あの肌合が滑らかに、緻密に、しかも半透明に光線を受ける具合は、どう見ても一個の美術品だ。ことに青味を帯びた練上げ方は、玉と蠟石の雑種のようで、甚だ見て心持ちがいい。のみならず青磁の皿に盛られた青い煉羊羹は、青磁のなかから今生れたようにつやつやして、思わず手を出して撫でて見たくなる。西洋の菓子で、これほど快感を与えるものは一つもない》
(角川文庫版・夏目漱石著『草枕』より引用)
昔私は羊羹を見ると、あまりにもあの濃密な、いわゆる朱鷺色を暗黒にまで濃くしたような黒紫色が苦手で、それだけで尋常でない甘味を連想させ、好きでなかった。貰い物の羊羹はとりあえず食うには食うが、自分で羊羹という四角い和菓子を買って、それを味わうといった気分には到底なれなかった。
それがどうも変わったらしい。『草枕』のなかの羊羹をたたえる箇所を何度も読み返しているうち、次第に羊羹が漱石と一体になった美しいものと思われ、かつて食わず嫌いだった四角い魔物の印象が徐々にほどけていき、今ではすっかり羊羹が好物になってしまっている。それもなるだけ、老舗の羊羹がいい。
『草枕』では羊羹のくだりが、まだある。老人が画工らに差し出した端渓の硯(すずり)の「鴝鵒眼」(くよくがん)を表す修辞で、以下の文の箇所だ。
《眼と地の相交わる所が、次第に色を取り替えて、いつ取り替えたか、殆どわが眼の欺かれたるを見出し得ぬ事である。形容して見ると紫色の蒸羊羹の奥に、隠元豆を、透いて見えるほどの深さに嵌め込んだようなものである》
(角川文庫版『草枕』より引用)
文庫版の注では「鴝鵒眼」について、《硯の表面に見える丸い斑紋》としている。
なるほど、そういう硯の画像をネットで調べて見てみた。硯の表面に大小の斑紋があったりする。…うーん、ちょっと不気味である。これが「鴝鵒眼」というものなのか。これが多いほど良いとのことらしいが、私には「鴝鵒眼」など、パンに生えたカビにしか見えない。
カビの大小で言えば、小さい方がいいに決まっている。しかし、このカビの繁殖にも似た「鴝鵒眼」は、大きい方が良いのだろう。私には何が良くて何が悪いのかさっぱり分からない。斑紋の色合いを、《紫色の蒸羊羹の奥に、隠元豆を…》とした漱石の屈託ない表現に、私は、『草枕』の収まるところに収まった理性の美意識を想起させた。しかも羊羹への敬虔なる追求を惜しまない姿勢に、いっそう感服した次第である。


コメント
≪…羊羹が漱石…≫で、こんな記事を見つける。
『陰翳礼讃』の次の文章を味わってみましょう。
かつて漱石先生は「草枕」の中で羊羹の色を讃美しておられたことがありましたが、あの色などはやはり瞑想的ではないでしょうか。玉のように半透明に曇った肌が、奥の方まで日の光を吸い取って夢見る如きほの明るさを含んでいる感じ、あの色合いの深さ、複雑さは、西洋の菓子には絶対に見られません。
♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪
数の菓子ペアノ公理ヒフミヨで