❖「《地平》のサウンド」とはいったい何か?
レヴォン・ヴィンセント(Levon Vincent)の音楽的表現は、誰しもが賛同できるハウス・ミュージックのcentrist(中道穏健派)に属しているかどうかはさておき、好みが分かれるところだが、彼のアルバムの中の、例えば「The Beginning」や「Launch Ramp To The Sky」などを聴いていると、まるで私は豚骨を与えられたドーベルマンのようにがつがつと興奮したかと思うと、途端にその興奮が収斂して、寝そべって大人しくなってしまうのであった。いったいこれはどうしたものか。
 |
| 【レヴォン・ヴィンセントのアルバムCD】 |
10代の頃までに培われた音楽的耳障りというものは、その生活密度が濃密なほど、大人になってリセットできるものではない。私の中学生時代の録音体験では、ぐいぐいと力強いゴスペル調のヴォーカルは、しっかりとしたコンプレッション処理を施さないと始末に負えないということを耳で学んだし、ばきばきとした快活で明るいクインシー・ジョーンズのアレンジでマイケル・ジャクソンの『Off The Wall』を大音量で聴いていた高校時代の耳の経験からすると、あのレヴォンの作り出すにゅるりと反復したサウンドは、どこか遠い、お伽の国の出来事/産物のように思えてしまう。
無論、それを否定するものではない。ローファイのたぐいとはまた少し意味が違うが、電源周りやケーブルの引き回しの感覚で言うなれば、レヴォンのサウンドは、いくばくかの電気的損失と負荷の微妙な関係の上で成立した、独特のナロー感がある。音源を重ね合わせる以前の段階で、既に出音が、ああいうサウンドになっているのだとすれば、少なくとも私の自宅におけるレコーディング・システムでは、あのサウンドはどうにもこうにも作り出せそうにないということを思った。
私は彼のサウンド&ミュージックを、半ば勝手に、「《地平》のサウンド」と呼ぶことにしている。言いかえれば、「大地のうねり」である。昔中学生の頃、CASIOのSK-1というサンプリング・シンセ(もどき!)で遊んだことがあったが、そんなノスタルジックなインストゥルメンタルに近い。今、若者が無邪気にiOSアプリのシンセで戯れているのを私が真に受け、iPhoneをアナログ・ミキサーにつなぎ、Pro Toolsで16bit/44.1kHzというフォーマットでかなり安直に録ったとしても、あの音に近づくことは、なかなかできない。
レヴォンの「《地平》のサウンド」の根本は、彼のパフォーマンスのうちの、心理的作用の道中にこそある。だからサウンドのスペックは二の次である。それこそが、彼の心の印象、世界観を表す。反復のリズムであろうと添え木的なパッドの和音であろうと、うねうね変化するフィルター&モジュレーション&ディレイさばきであろうと、彼の心の《地平》は一貫して平然さを保っている。厳密に言えば、平然さを保とうと必死に堪えているのが分かる。
 |
| 【サンレコ2017年12月号の「Berlin Calling」】 |
2015年に起きたパリ同時多発テロに関するレヴォンのあるメッセージによって、世界中のファンから痛烈なバッシングが相次いだ“事件”について、雑誌『Sound & Recording Magazine』2017年12月号の「Berlin Calling」(筆者Yuko Asanuma)でその概要が語られていた。非常に興味深い話である。レヴォンのFacebookページでのメッセージ、“もう自分の身は自分で守るしかない。みんな武器を持て。武装せよ”という趣旨の投稿は結果的に大炎上となった。失望と落胆が渦巻いたという。しかし今年の10月、彼は『For Paris』というアルバムを無料配信し、2年前の自身の投稿の謝罪と、新たな平和運動への呼びかけをおこなった。レヴォンはある意味、再起した。
彼の「《地平》のサウンド」を作り出す心の在処は、とてつもなくsensitiveでnaïveで危うい。もしかすると彼は将来挫折して、自身の音楽活動をやめてしまわないだろうか。そういう予兆が、彼のサウンドから感じられる。それでも彼が気づかせてくれた大事なことは、誰しもが共有しなければならない命題だ。政治的にも、音楽的なイデオロギーにおいても。思考と音楽の言語化をパブリックに提供しうる最も効果的なアプローチを、彼は模索しており、私たちはそれを追随しなければならない。独自のやり方で――。
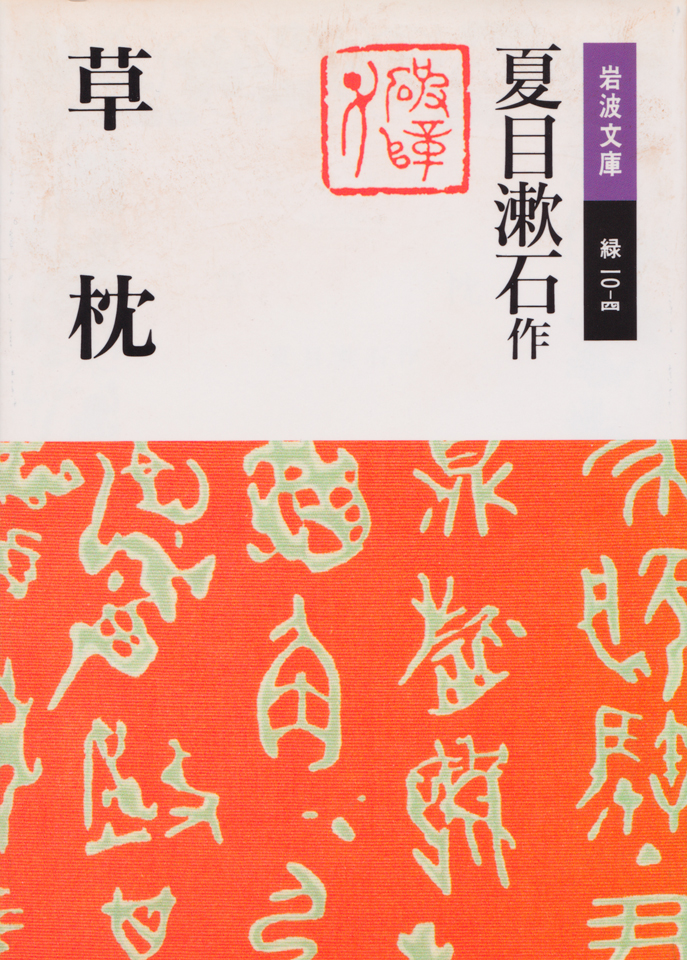

コメント