 |
| 【1986年刊の『NEW NUDE 3』】 |
作家でありセクシュアル・アートの評論家でもある、伴田良輔氏の様々な文筆作品に目を通す機会が多かった私は、その最初に出合ったショート・ショート作品「震える盆栽」の妖しげで奇怪なる感動が今でも忘れられない。それはもう、かれこれ27年も前のことになるのだった。
この「震える盆栽」については、当ブログ「『震える盆栽』を読んだ頃」(2011年2月)で書いた。いずれにしても27年前の“異形の出合い”がなければ、その後私はセクシュアル・アートへの造詣を深めることは無理であったろう。敢えてもう一度、この作品について深く掘り下げてみたくなった。あの時の、邂逅のエピソードからあらためて綴っていくことにする。
§
「震える盆栽」を初めて知った(初めて出合った)のは、90年代初め。私はその頃上野の専門学校に通っており、まだ20歳になったばかりの時である。
ある日、授業の合間に学校を抜け出て、入谷方面へと散歩に出掛けた。交差点近くの所に来て、小さな書店を見つけたのだった。暇つぶしにこれ幸い、とその店に駆け込んだのだけれど、今となっては、その場所も、店の名前もまったく憶えていない。――ちなみに後年、鬼子母神(真源寺)のある入谷におもむいて、この書店をしらみつぶしに探したことがあったが、見つからなかった。既に閉店していた可能性もある。
私は、ありとあらゆる理由を考えた末に、結局、あの書店はもともと狐なるものが経営していて、ある日忽然と消えてしまったのだ、と信じて已まない。そういえば店主は、細い目をしていたような――。
閑話休題。さて、その書店に入ったはいいが、真っ昼間で他のお客は誰も居なかったのだった。だから店内はしーんと静まりかえっていた。この狭い空間に、店主と私二人きり。何かUSENのBGMくらいかけておいて欲しい…。雰囲気としてはとても堪えられそうになかった。そう思ってしまったのは、なんとも若気の至りであった。
若気の至りほど感覚的に懐かしいものはない。今の私なら、そういう小さな商店に足を踏み入れて、場の悪い空気にさらされたとしても、何ら平気。何のためらいもなく居続けるに違いない。え、客は私ひとりですが、なにかそれが問題でも?――。店主に話しかけられようが何だろうが、ずっと居座り続けるに違いない。尤も、長い時間読みたくなるくらい面白い本がそこにあれば、の話だが。
年を取ると、次第に神経が図太くなるものなのである。若い頃はもっとセンシティヴで途端に羞恥心に駆られたりして――例えば街中にいてジーパンのファスナーが開いていたとしたら、たちまち顔を赤くしたものだが、今ならこう考えてしまう。そんなとこ、誰も見ちゃいないよ…。考え方が姑息というかずぼらになっていき、用意周到に立ち振る舞うことができるようになると、羞恥心の感覚が鈍くなるのだ。入った店に私ひとりしか居ないとなれば、もしかすると店主さんに、「ちょっと喉が渇いたのでお茶いただけますか」と図々しく厚かましく口を滑らせてしまいかねない。だからといって、年は取りたくない、とは決して思わないのである。
とにかくまだ若かった頃の私は、その書店の中で、私ひとりが恥ずかしげに店内を彷徨っていることに堪えられなくなって、〈早くこの店から出たい〉という衝動に駆られたわけである。いや逃げたい。何でもいいからなにか、一冊安い本を見つけて買って、早く出たかったのだ。さすがに何も買わずに立ち去る、という行為はできないなあと思いつつ、その時偶然手にしていたのが、伴田氏の『愛の千里眼』(河出書房新社)であった。
§
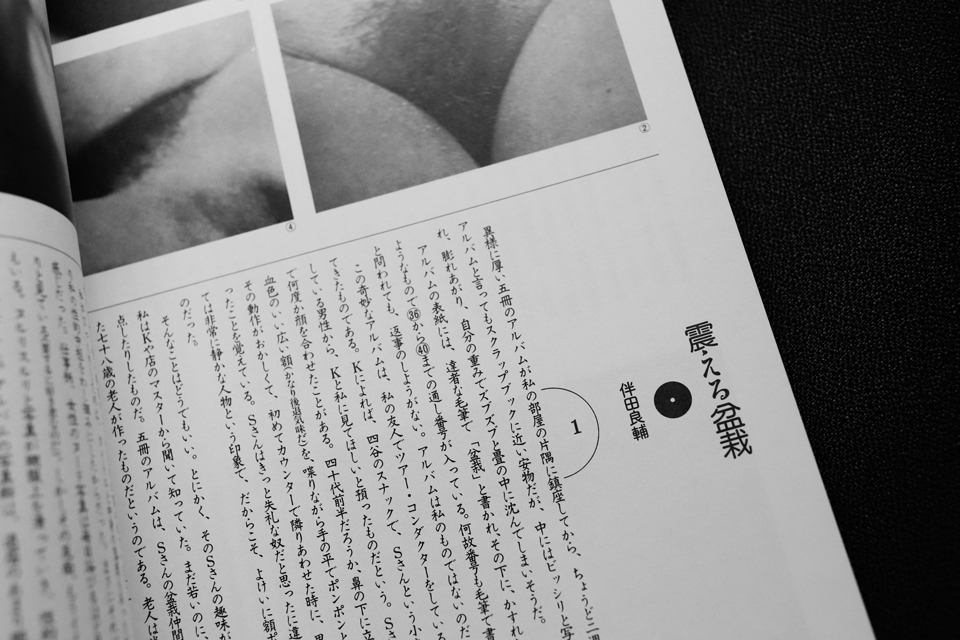 |
| 【『NEW NUDE 3』より伴田良輔著「震える盆栽」】 |
『愛の千里眼』は、なんともフェティッシュな書物であった。言うなればその本は、セクシュアル・フォトグラフィー&エッセイである。あるいは“エロティックにゅるにゅるサイエンス・フィクション・ショートショート”――と呟くこともできる。が、その『愛の千里眼』の本を手に持ち、ぱらぱらとページをめくっていた時、ふと、どす黒い写真を見たのである。
どす黒い写真の正体は、ずばり、女性のピュービック・ヘア(陰毛)のクローズアップであった。なんだこれは…! と、まさにこちらの体が震えて、驚きの声が漏れそうになったくらい、一瞬、私はひるんだのだけれど、およそその数秒後にはレジに向かい、会計を済ませ、電光石火のごとく店を出た。そのくせあんなに嫌がっていたこの書店に対し、思わず投げキッスをしてしまいたくなるほど有頂天になって、気持ち的にはスキップをしながらその場を立ち去ったのだった。
 |
| 【様々な“盆栽”写真】 |
――その挿絵的なピュービック・ヘアの写真こそ、「震える盆栽」の重要な謎記号なのであった。読めば、簡単な話である。
話の主人公の伴田氏は、ある知人を通じ、“盆栽写真の名人”と言われていた78歳の老人の、謎めく分厚いアルバムを計5冊引き取った。アルバムの表紙には「盆栽」と書かれていたから、てっきりそういうたぐいの写真アルバムかと思いきや、開いてみるとまったく違ったのである。そのアルバムは、なんと女性のピュービック・ヘアのクローズアップばかりを写したスクラップブックだったのだ。
老人の趣味の偏狂ぶりは凄まじかった。中身はどうやら、世界的に著名なフォトグラファーによるヌード写真の、そのごく一部分に過ぎないピュービック・ヘアのところだけを接写して撮ったものらしく、夥しい枚数の中には、ボケていたりブレていたりするものが多くあったという。伴田氏は、片っ端から接写撮りした大本の写真を突き止めるべく調べ尽くし、結局、それがマン・レイであるとか、エドワード・ウェストンであるとか、ヘルムート・ニュートンなどの写真であったことが分かった。
いったい何故老人は、このようなピュービック・ヘアばかりの写真を撮り続け、コレクションしたのだろうか。伴田氏の夢想的煩悶と幻惑の沙汰。そのケミカルな視点で描いた佳作小品の「震える盆栽」。これはフィクションなのか否かさえ分からない、伴田ワールドのかなり濃いめの読み物なのであった。
§
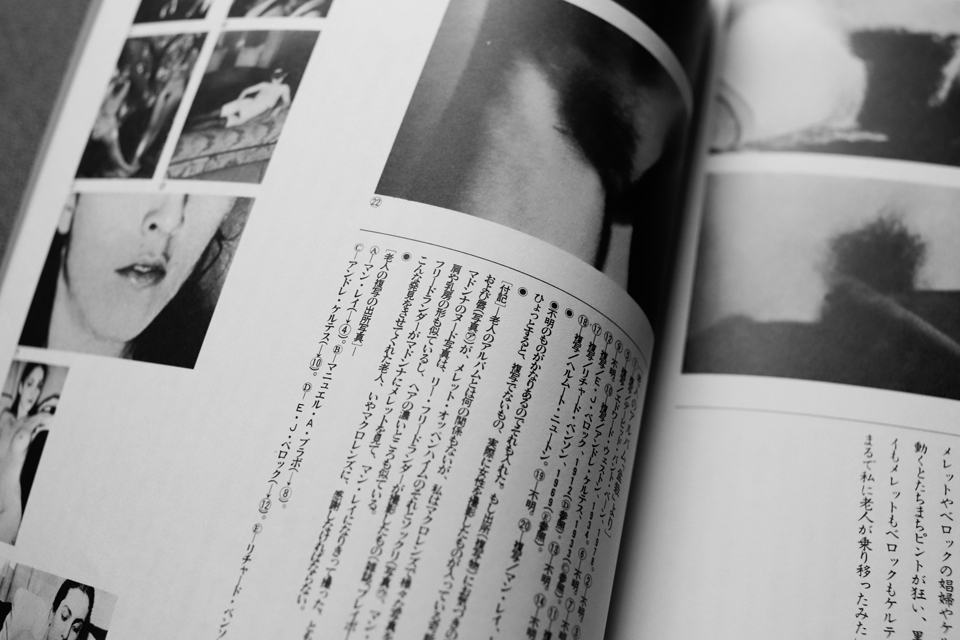 |
| 【注釈欄には伴田氏のかなり固執した解説も】 |
私は2011年に「『震える盆栽』を読んだ頃」を書いた。そこで「震える盆栽」が1986年7月号『カメラ毎日』の別冊版である『NEW NUDE 3』の所収であることを付け加えていた。その本についてはごく最近、幸いにして入手できたのである。
これまたそそられる本であった。『NEW NUDE 3』自体、とてつもなく濃厚かつ刺戟的なヌード写真集なのである。伴田良輔の「震える盆栽」は、中西昭雄、宮迫千鶴、鈴木志郎康、松山巌、草森紳一、伊藤俊治らの、その耽美と怪炎とアクの強いドグマ的な随筆に紛れて掲載されており、ここにおいても彼のショートショートは、鱗粉のごとき妖しさを充満させ、傑作として類を見ず勝ち誇っている。『NEW NUDE 3』での「震える盆栽」では、文庫本の方には無かったピュービック・ヘアのクローズアップが掲載されており、やはりそれらの写真のインパクトは斬新極まりなく、エロティシズムと人間の欲望を超越した文芸テクスト&アートのコラージュなのであった。
――その出合い。若気の至りと言えばその通り。あの頃、20歳そこそこだった私は、ヘア・ヌードそのものが物珍しく劇的であったから、これほど風変わりなエロ本、いやエロ小説があるものか、と『愛の千里眼』にすっかり感心してしまった。そのうちの「震える盆栽」においては、ピュービック・ヘアのクローズアップに夢中になった老人と伴田氏自身の、あまりの偏狂ぶりに腰が抜けそうになり、その衝撃は忘れられるものではない。こんな表現が不適切ではなく相応しいかどうか――言わばその時、若かった私の、セクシュアル・アートに対する感受性の《処女膜》が破られた瞬間だったのである。
§
 |
| 【見れば見るほどエロス的世界を超越していく“盆栽”】 |
狐達がどろんと煙を出して消え、持っていた紙幣の札束が、実は、枯れ葉の束であった――と分かる童話を思い出す。それって誰の、どんな話だった? 狐じゃなくて、狸だったっけ? などと頭の中の糸が絡まって答えが出ない。たとえ、思考する当人が半ば酩酊状態であったとしても、エピソードの本質部分というのは、現実のえぐみとして不変ではないか。その持っていた札束が、最初から本当に本物の札束であったかどうかは、もはや誰も分からないのである。
27年前に確かにあの本を買った書店は、後日、跡形もなく消えていた。私がいま手に持っている本『愛の千里眼』がいつ、どろんと煙を出して枯れ葉一つに化けるのか、冷静な心持ちでそれを受け止めてみようじゃないかと思っている自分自身がある。そうしてこの「震える盆栽」の話は、「そんな馬鹿げた作品がこの世にあるわけがない、君は狐につままれていたのだ」と言われてしまうかも知れない。現に、私の持ち出す話など、誰も信じなくなっている気がするのである。もうそろそろ鬼子母神様の境内で、入谷の朝顔市が始まる頃だ。


コメント