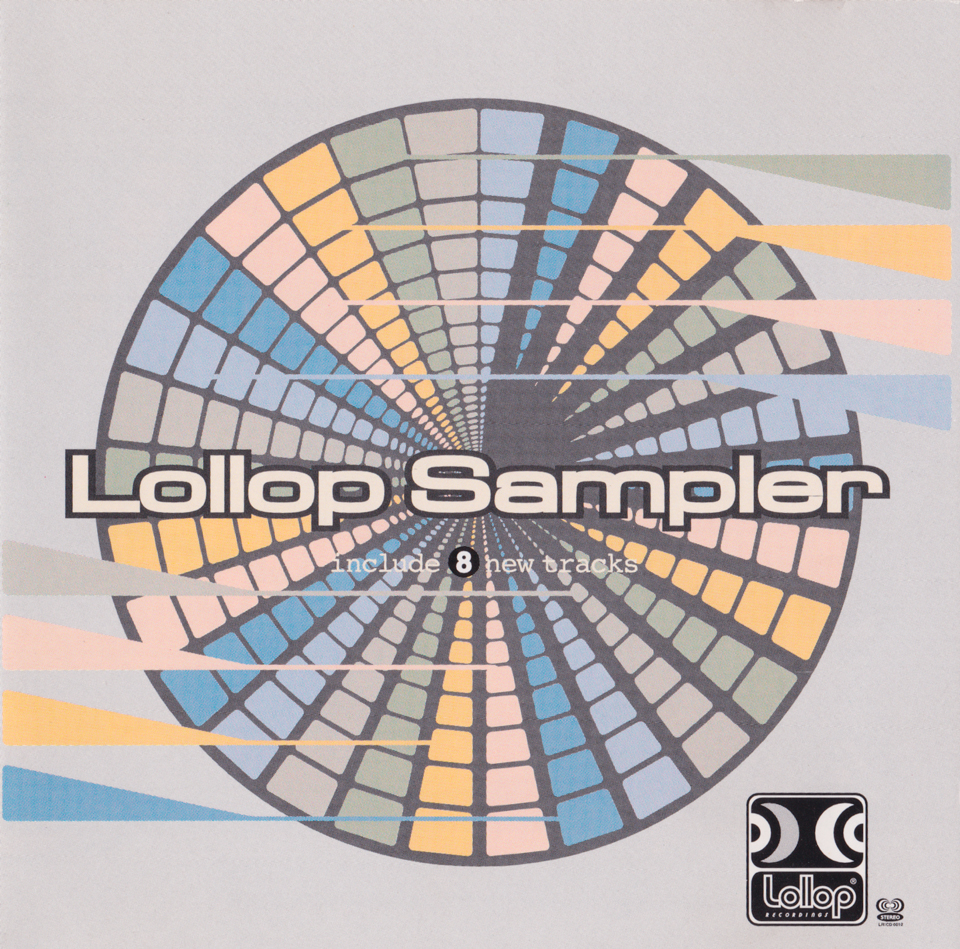 |
| 【コンピレーション・アルバム『Lollop Sampler』】 |
過ぎ去りし“90年代”における個人的なフェティシズムの小景として、スピリチュアル・ヴァイブスのユニット名で知られる竹村延和氏の音楽について、前回「90年代のフェティシズム―スピリチュアル・ヴァイブスとトリス」で取り上げた。あの頃、雑誌の誌面の各欄にぽつりぽつりと登場するスピリチュアル・ヴァイブス(Spiritual Vibes)並びに竹村氏の氏名がそこに躍るたび、私の心は捻れて複雑な思いに駆られたものだった。
それは、偏見とジェラシーと音楽的指向に絡まる怨念によって、本質的な“90年代”のミュージック・シーンの象徴でありながらも、私的に「見たくないもの、聴きたくないもの」といった負のレッテルを貼り付けたネガティブな記憶でもあった。今――あれから25年が経ち――それを俯瞰して眺めることができる。“90年代”の無垢なるものとして。さらに今、彼の音楽をじっくりと聴くことによって、あの頃の《心象》と《実像》とがにわかに甦り、20代であった私の様々な出来事が、懐かしく感じられるのである。
§
 |
| 【雑誌の中の『Lollop Sampler』解説】 |
竹村氏がチャイルズ・ビュー名義で参加されていた、1995年のコンピレーション・アルバムが、いま手元にある。『Lollop Sampler』だ。彼はこのアルバムに、7分20秒の「The Scenery Of S.H (Nadja’s taking mix)」という曲を提供している。これは彼独特の、ナチュラルな香りのする“菜食系ミュージック・オーガニゼーション”とも言うべきループ・サウンズであり、やはり、その香りがどこか懐かしいのだ。当時の月刊誌『Sound & Recording Magazine』(1995年10月号)では、小さなインフォメーション欄に、以下のような記事を掲載していた。
《スピリチュアル・ヴァイブスやソロ名義など、大阪を拠点に活動を続ける国内屈指の若手クリエイター竹村延和。そんな彼がオーガナイズするインディ・レーベル“ラロップ・レコード”の第1弾コンピレーション・アルバム『Lollop Sampler』(CD:LRCD-001/LP:LRLP-001~002)が発売された。ここに収録されているアーティストは、そのほとんどが今回ラロップに初参加というフレッシュな顔ぶれだ。ただDJ松岡成久、DJ木村タカシなど、アンダーグラウンドでは知られた実力派も参加しており、もちろん竹村自身も新ユニット、チャイルズ・ビューでハイ・クオリティなトラックを聴かせてくれる。このほかにもアルバム発売が待たれるリフレクションなどは素晴らしい内容なのでぜひ聴いてほしい》
(リットーミュージック『Sound & Recording Magazine』1995年10月号より引用)
ちょうどその頃私は、自身の演劇活動に限界を感じ、音楽活動に重点を置く希望を抱いていた。音源――音を鳴らすもの――仄かなる和音やエレピの音に対する強い欲求。先鋭なるシンセやサンプラーといったものが、自身の心象と有機的に結合し、音楽という形をコンポーズする可能性とその不思議な魅力。そのことに私は果てしない夢を描いていたのだった。ちょうど猫じゃらしを目の前にちらつかされて、心が揺れ動いていた20代半ばのことである――。
当時の『Lollop Sampler』における「The Scenery Of S.H (Nadja’s taking mix)」といった彼のサウンドを、私は〈見たくない、聴きたくない〉と思いながら、どこかでおそらく、その近似のサウンドを耳にしていたに違いなかった。そう、そうであった。あの頃、幾度となく訪れていた小劇場の、開演前の場内にて、数十分ものあいだ垂れ流されていたバックグラウンドの音楽――。まさにそのカオスの雲母に紛れて、彼の音楽が漂っていたはずである。そして私はこうしたサウンドを、〈まさに今、演劇が始まろうとしている暗がりの予兆〉=《予兆音》として受け取りながら、脳内の深奥に、ある種の抽象的かつ体系的なループ・サウンズとして記憶していったのであった。
§
“90年代”というとらえどころのない透明な時代が、私自身を創造した。だがしかし、その創造は、今もなお輪廻し続けている。うごめき続けている。ある年月においてところどころ句読点を打ちながらも廻転し、新たな展開に歯止めが利かなくなっているにもかかわらず、私は転がり続けているのだ。いったいどこへ向かおうとしているのか、その道筋は、自分でもよく分かっていない。
起点に戻って何かを取り戻すのか、いや、取り戻すのではなく何かに気づくだけなのかも知れない。が、その試みが、今の私を支えているようである。自らを「何ものか」にクリエイトしていった時代、それが私にとって“90年代”であり、竹村延和という一つの通過儀礼なのであった。この探求的な試みはまだまだ続く。

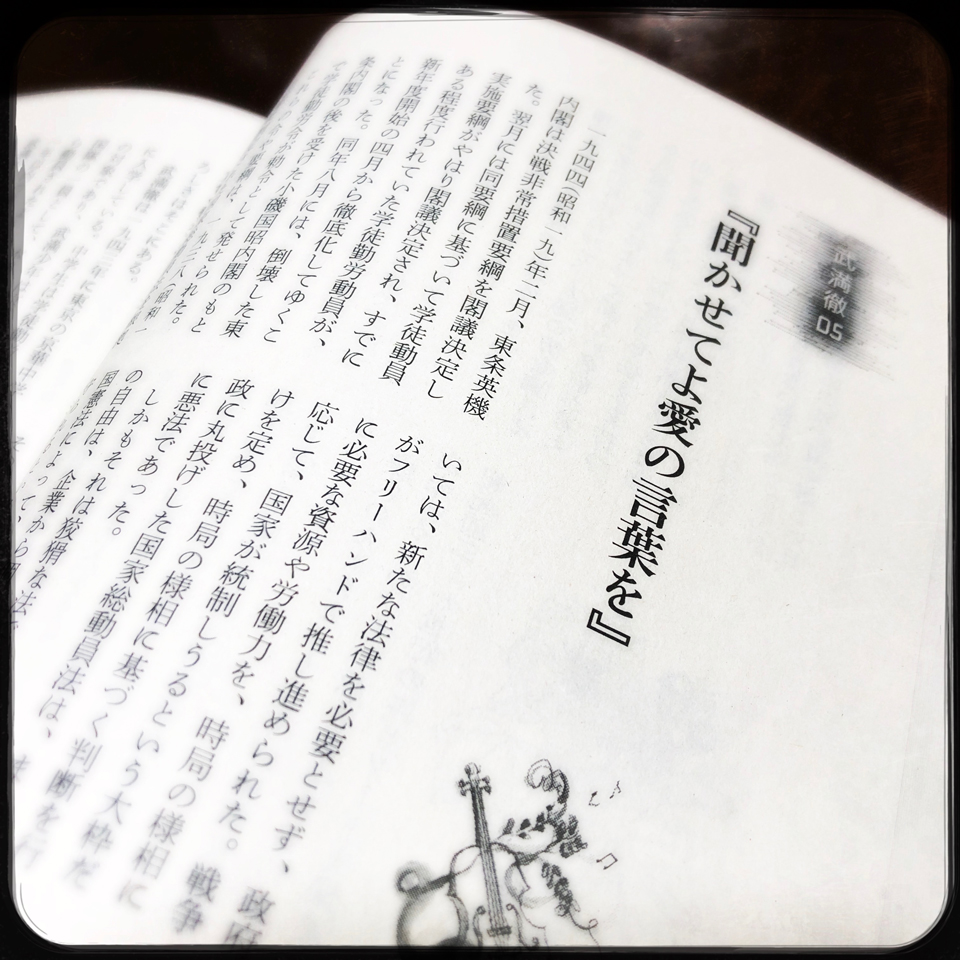
コメント