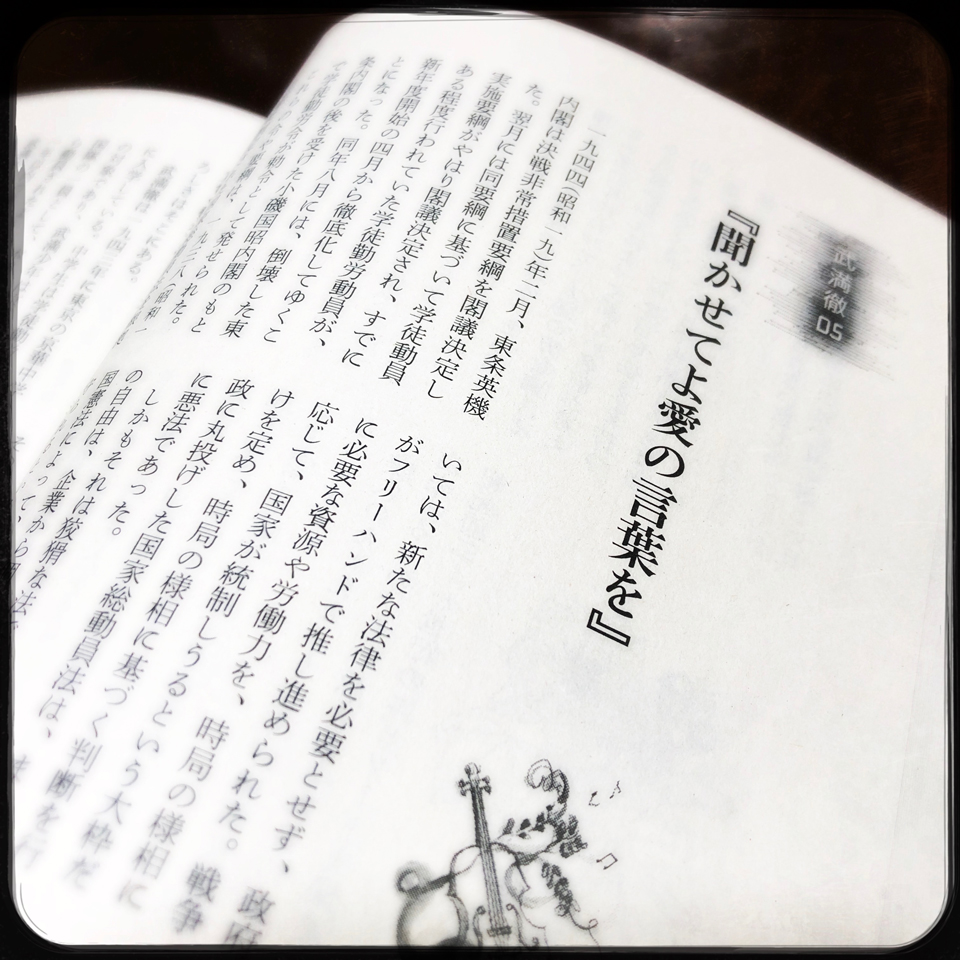 |
| 【片山杜秀著「『聞かせてよ愛の言葉を』」】 |
今年の夏、とある随筆を読んでいて、見落としがたい重要な文章を発見した。専門家や知識人であればそれは、とっくの昔の既成事実に過ぎないのだけれど、私は今頃になってその事実確認と修正のたぐいを余儀なくされた――。かつて筑摩書房の高校国語教科書に載っていた、私的に思い出深い随筆。武満徹著「暗い河の流れに」(『樹の鏡、草原の鏡』所収)に関すること。私がその随筆について当ブログに書いたのは、2年前の6月であった。
§
その時のブログ「武満徹―暗い河の流れに」で私は、武満氏が戦時中、旧制中学の勤労動員で駆り出されていた頃のある有名な話を書いた。むろんそれは、武満氏の随筆「暗い河の流れに」の挿話である。見習士官の一人が、武満少年ら学生達に音楽を聴かせてくれたというエピソードで、つまりその音楽は、戦時中における“敵性音楽”であって、フランスのシャンソンであった。歌っていたのは、アメリカ出身のジャズ歌手ジョセフィン・ベーカー(Josephine Baker)だったのだと、武満氏は「暗い河の流れ」の中で語っていた。
それがどうも、ジョセフィン・ベーカーではないらしい。
今夏、岩波書店のPR誌『図書』2019年8月号に掲載されていた思想史研究者の片山杜秀の随筆「『聞かせてよ愛の言葉を』」を読んで、私は初めて知ったのだった。片山氏ははっきりとそこに、あれはジョセフィン・ベーカーが歌った歌ではないことを、武満氏本人の言葉を借りて書いている。
《「ぼくは、『ジョセフィン・ベーカー、ジョセフィン・ベーカー』って言ってたんだけど、どうもジョセフィン・ベーカーじゃないらしいんだ、その中瀬さんに聞くと」》
(岩波書店『図書』2019年8月号片山杜秀著「聞かせてよ愛の言葉を」より引用)
片山氏の随筆によると、武満少年は、1943年に東京の京華中学に入学し、2年後の1945年の夏、“報国隊”という形で陸軍の糧秣廠(りょうまつしょう)に学徒勤労動員されたという。所は、埼玉の飯能である。糧秣廠では、飯能に食糧備蓄基地を建設していたらしい。それはそうと、武満氏の著書『音楽を呼びさますもの』(新潮社)所収の講演「私の受けた音楽教育」で彼は、基地に徴集され、来ていた見習士官が学生らに聴かせてくれたのは、シャンソンの「パルレ・モア・ダアムール」(聞かせてよ、愛のことば)であり、ジョセフィン・ベーカーが歌っていたのだと語っている。《それは私にとっては初めて知った、軍歌とはまるで違う別の、しかも甘美な音楽でありました》――。しかし後々、武満氏は、その記憶を覆すことになる。
音楽評論家の安芸光男を聴き手とした1990年のインタヴューで武満氏は、先記した「どうもジョセフィン・ベーカーじゃないらしいんだ」云々を口にしたのだった。当時の見習士官――中瀬さんと1980年代に再会し、あの曲はリュシエンヌ・ボワイエ(Lucienne Boyer)が歌ったレコードであることを、直接本人から聞いたのである。武満氏にとってもそれは、寝耳に水の事実ではなかったか。あるいはそうではなくて、戦後、何かしらどこかで、「パルレ・モア・ダアムール」はジョセフィン・ベーカーではなく、リュシエンヌ・ボワイエが歌っていることを、薄々知っていたのだろうか。
そうしたことは私自身、武満氏が自ら執筆した著作を片っ端から調べてみなければ分からないことなのだけれど、リュシエンヌ・ボワイエが歌う「パルレ・モア・ダアムール」(Parlez-Moi D’Amour、録音は1930年)をまず、聴いてみることにしたのだった。
§
聴き終わって、その歌と演奏の、あまりに《甘美な》心地良い響きと余韻に、身も心もとろけそうになった。聴けばおそらく皆、脱力するであろう愛の歌である。全身の力が抜け落ち、素朴な愛の抑揚に満たされた心はきっと、隣人を想い、恋人を想い、親しい家族を想うであろう。慎ましかった幸せなあの日のことを、想い出すに違いない。「パルレ・モア・ダアムール」とは、そういう気持ちが自然に湧き出てくる歌である。
おそらくあの時の武満少年の心も、同じだったはずだ――と私は思った。戦争なんて、なんと虚しいのだろう。争いをやめ、自由な日々を暮らしてみたい。好きな人のことを想い続けたい――。彼にとって強烈な印象として残った「パルレ・モア・ダアムール」が、ジョセフィン・ベーカーの歌だったと思い込んだのも、無理はない。しかしながら、こうして今聴くと、「パルレ・モア・ダアムール」は、リュシエンヌ・ボワイエ唯一無二の歌であることに気づかされる。高齢になって歌う姿の古い映像を、私は観た。それは録音した頃の若きリュシエンヌとは違う、研ぎ澄まされた「パルレ・モア・ダアムール」であった。
片山氏は随筆「『聞かせてよ愛の言葉を』」の中で、こう述べている。武満は歌手についての記憶は曖昧であったが、あの曲で並外れた衝撃を与えられたのは事実であろうと。
本来、フランス音楽のシャンソンが、“敵性音楽”であったかどうかは、ここでは問題ではない。外国の音楽すなわち西洋の文化を阻害し、純然たる日本精神を脅かすものはすべて排除するという戦時下の恐ろしい思想。我が皇国を尊ぶという国家の体制と、市民レベルにおける時世の、社会秩序を紊乱してはならぬという強迫観念。つまりファシズムの暗い空気こそが、その音楽を“敵性”と意識する感覚の、怖ろしさなのだ。
逆行する形で武満少年は、シャンソンの甘い響きを全身に浴び、ある種の官能を覚えた。そしてそこから、本当の自由とは何か、戦後の武満音楽が始まったのである。
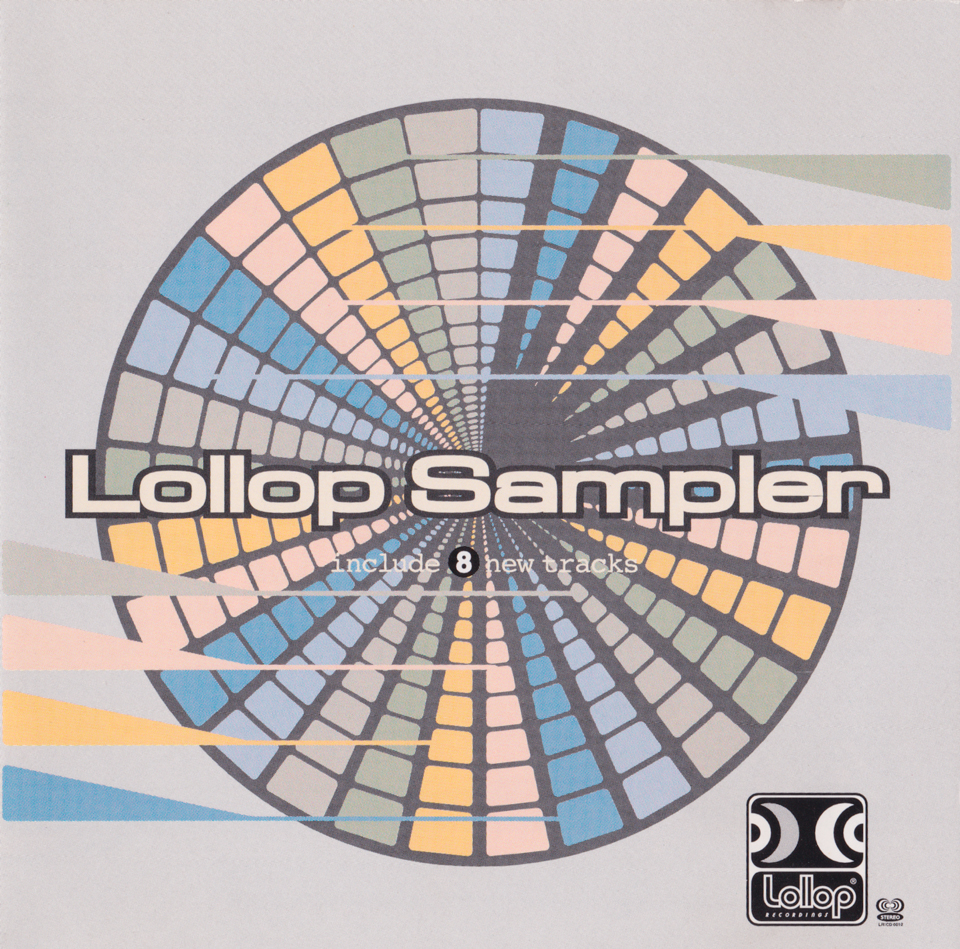

コメント