※以下は、拙著旧ホームページのテクスト再録([ウェブ茶房Utaro]2004年7月9日付「殉教―その映像と文体」より)。
三島由紀夫の作品に、『殉教』という短篇がある。昭和23年4月、「丹頂」に所収。三島は、この作品の自注に、〈詩人の殉教〉と書き加えている。この『殉教』は一体どのような作品だったのだろうか。
スパルタ式教育の名門校。その寄宿舎には、畠山という少年がいた。三島はこの少年を〈魔王〉と称している。畠山は、親の英才教育により体躯が美しく、発達がすこぶる良い。彼が所有する、ある〈面白い書物〉によって、もう一人の少年と因縁が生まれるのが、この作品の大きな局面である。
そのもう一人の少年は、亘理(わたり)といい、彼が畠山の持つ書物を盗んだことが、畠山を怒らせた原因だ。亘理は畠山と少しばかり毛色の違う美少年で、色白の脆弱な少年である。
「あいつはいじめられるとキリストみたいに空をじっと見上げるのだよ」
「そうするとあいつの鼻が少し上向きになるだろう。そこであいつの鼻の穴を僕はすっかり見てしまうんだ。あんまり丁寧に洟をかむので、あいつの鼻の穴は縁のところがうすぼんやり薔薇いろをしているよ」
(三島由紀夫著『殉教』より引用)
さて、畠山の持つ書物は、一体どのようなたぐいの本だったのか。畠山は、その本の装丁を自らこしらえ、毛筆で「プルターク英雄伝」と書いて本棚にしまっていた。この本を見ようと、宿舎の生徒は彼の自室に訪れ、その本を見せてくれるよう彼に嘆願するという。本の内容については、地の文で〈妙な色刷の複雑な断面図〉としか表現していない。
無論、その中身は英雄伝などではない。ある種の艶本的な裸体表現か、もしくは性教育的な生殖器の断面図だったのか。ともかく、彼の友人らは、その本を見ることで、何かを想起させ、興奮させた。
本を盗んだ亘理は、畠山にこっぴどく制裁を加えられる。畠山の自室に連行され、ベッドの上で二人は悶絶する。だが畠山は、その敵意をむき出した亘理に対して、恍惚とした欲情がわき、その肉欲の結露として、亘理の産毛だらけの唇に顔を押し当て、接吻をしてしまう。
宿舎では、畠山と亘理のいらぬ噂が飛び交う。魔王に従順な他者にしてみれば、亘理は「生意気だ」ということになる。校庭の大樹のある場所に亘理は連れられ、畠山のいる目の前で、その体を縄で樹に縛られる。
やがて、亘理の体を縛っていた縄は解かれ、縄は樹の高いところに縛り付けられる。そうして今度は、亘理をその大樹に吊り下げようというのである。しかし、ここのところは非常に曖昧な描写になっている。畠山とその従順な一味は、あまりの光景に恐ろしくなってその場を立ち去る。しばらくして戻ってみると、大樹にぶら下がった縄だけがあるという終わり方をする。亘理が本当に樹に吊り下げられたわけではなく、その間に亘理はどこかへ行ってしまった、と考えてよいのだろうか。
こうして『殉教』全体を見渡してみると、時代的な背景もあって、非常に抑圧された表現が多く、三島独特の――とくに女性を描いた他の作品と比べて――伸びやかさがなく、陰鬱な文体でピリオドを打っている。『殉教』は、ここに登場する少年たちの生々しい小悪魔的な「少年性」に不時着したまま、もう一方の――亘理への接吻のような――若く白濁とした「少年性」への突っ込みが欠けているように思えるのだが、どうだろうか。
ただし、その「少年性」への照射は、それがたとえ不十分な不時着であったとしても、照射としての感性と題材の的確さにおいては、やはり三島由紀夫の天性の表現力を賛辞せざるを得ない。三島の代表作『潮騒』は過去に何度も映画化(映像化)されていても、この『殉教』における「少年性」は、いまだ表現の源泉から閉ざされたままで、誰も手をつけようとはしていないのである。

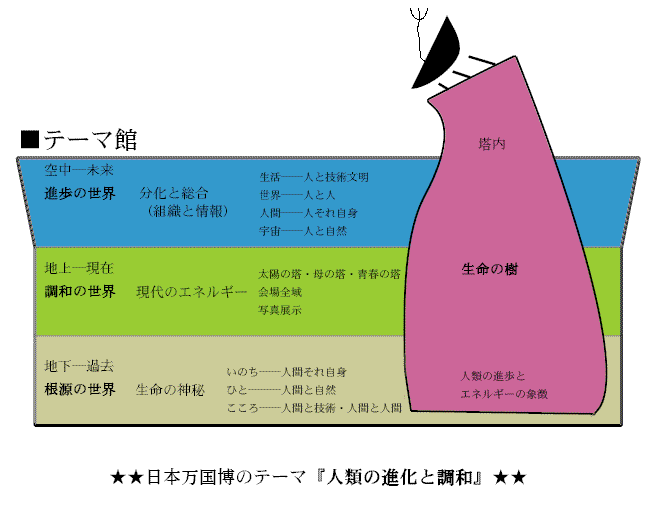

コメント