まず、小倉朗著「現代と音楽」の論考では、電子音楽及びミュージック・コンクレートについて以下のように触れられている。
《最近、電子音楽やミュジック・コンクレートが新聞やラジオに紹介されましたが、まるで新しい音楽が生れたと言わんばかりの騒ぎです。冗談ではない。出来たのは音楽を作る手段です。それも海のものとも山のものとも未だ判らぬ。判らぬうちからこのようなセンセーショナルな扱いをするのが、ジャーナリズムの好みでしよう。
尤も早速この手段を幾人かの作曲家が実験して、結果を持ちよつて先日音楽会を催した。そこで出掛た人達が果してどんな感慨を抱いて帰つたかは知らぬが、或るアブストラクトの画家が舌を巻いた。自分達が苦心惨憺していることを、これらの音楽はわけもなくやつてしまうと言う、その話を聞かされて、僕は甚だ面白く思つた》
また、伊奈一男の「楽壇の話題・記録・思潮【音楽界】」の欄では、もっと一般的な感覚に寄った形でそれらを紹介している。
《ミュージック・コンクレートと電子音楽の初の演奏会? が二月四日山葉ホールで行われた。作品の性質上、すべて過去において放送その他で発表されたものばかりだつたからこの場合、初めて会場で“行われた”という事実だけが貴重なのだろう。ところで会を開くについての宣言「既成の音楽は無内容な音によつて組立てられるようになつた。われわれは失われた音の生命を発見しよう…」に対して誰も何もいわなかつたのは何故だろう。伝統を破壊するという意味においては、論争をまき起した石原慎太郎の出現が与えた以上にショッキングなはずではないか。「あんなものは音楽ではない」と真正面から言い切れないことがすでに宣言のなかばを肯定せざるを得ない弱み――危機を感じているためといつてはいけないだろうか。もつともこの第一回の催し全体が、まだ新しきものの展示ですらもなく、宣言そのものをフエン、説明する程度のものであつたからかも知れないが》
こうして読んでみると、1956年当時では、まだ電子音楽やミュージック・コンクレートがより抽象的なものと位置づけられ、既成の音楽が“音楽”であるのに対し、前者はむしろ音楽ではなく“音覚”であるということに一般的には強い反撥があったかに思われる。当然ながら、電子音楽とミュージック・コンクレートの混同もあったであろうし、そうした一般的な誤解を含めた認知は、今日においてもあまり変わりないと思う。
さて、昭和31年の黛敏郎氏はいかなる芸術志向を持ち得ていたか。“現代芸術”を主題にした座談会形式の中で、それについて熱く語っている。音楽はもちろん、文学や映画に対する論考も冴え渡っており、明晰な芸術力で漲っていたことが分かる。やや私個人の主観になるが、彼の発言のうち、特に重要と思われた部分を以下に抜粋してみた。
座談会「現代芸術をめぐって」
出席者:洋画家・阿部展也/文芸評論家・原田義人/作曲家・黛敏郎/(司会)吉田秀和
《黛「文学が言葉から離れられないということは文学の強みでもあるが悲劇でもあると思う。いつでも思うんですが、日本に現代詩が育たないのも、言葉という存在があまりにも強力であり過ぎることに原因があるんじやないかしら。ハッキリ言つて日本の文学が現状のままでアグラをかいている状態がつづく限り、僕は文学に期待は出来ない。文字による人間の表現という枠から勇敢にトビ出さない限り、文学みたいにガンジガラメに縛りつけられているものから現代の息吹は出てこないんじやなかろうか」
黛「(一部略)音楽でも絵画でも、日本には昔からの伝統があつた。そこへ明治になつてから洋楽なり洋画なりが入つて来て、それらが今まで僕たちのもつていた音楽や美術に対する観念もテクニックも根本から引つくり返す様な全然次元の異つた考え方を植えつけた。僕に言わせれば、ここで文学だけがひとり取残されてしまつたのだ。現代文学というものは、いわば洋楽の位置に当るのじやないかと思う。カフカの手法をとるとかジョイスの意識の流れのような方法をマネルとか言つても、みんな手法としての借りものに過ぎず、そこに流れる内的な世界は依然として四畳半的ないわば洋楽の洗礼を受けない前の邦楽の世界なんじやないですか。せいぜい行つても和洋合奏までだな。オーケストラではないというわけだ」
黛「電子音楽がそうじやないかな。やはり阿部さんが今仰言られたことと関連してくることだと思うのです。つまりシェーンベルグに発しウェーベルンに受けつがれて、現代にまで至つている音楽の抽象化という問題から、必然的に出て来たのが電子音楽であつて、ここまで来る間には問題を徹底的に追究するために民族性とか人間性とかいうものと一応縁を切る位の覚悟が必要だつたわけです。そうしたところを通つて来てこそ、初めてインターナショナルな言語としての電子音楽が確立されることが出来た。これからはこのインターナショナルな言語を縦横に駆使して失われた人間性や民族性を新らしい形で抽象して行くという方向に向うと思うのです」
黛「ドイツ人の徹底した合理主義的な考えから生まれて来たのが電子音楽だけれどもこれをわれわれが使う場合に、あくまでもドイツ人的な発想に基いて使わなければならないという様な理屈は成り立たないと思うんです。東洋人には東洋人しか持つていない感覚があるし、思想もある。それらをただ単に純粋に東洋的な表現方法のみに頼つてやつていたのでは、チェレプニン楽派になつたりバルトークの引きうつしになつたりする危険が多分にあるわけで、僕たちはそれでは飽き足りない。表現の基盤になるテクニックは最も尖鋭な、最も完成されたインターナショナルな言語によつてこそ真の東洋人としての発言が自由に出来るわけで、今後僕たちに残されている課題はここにあるということです」》


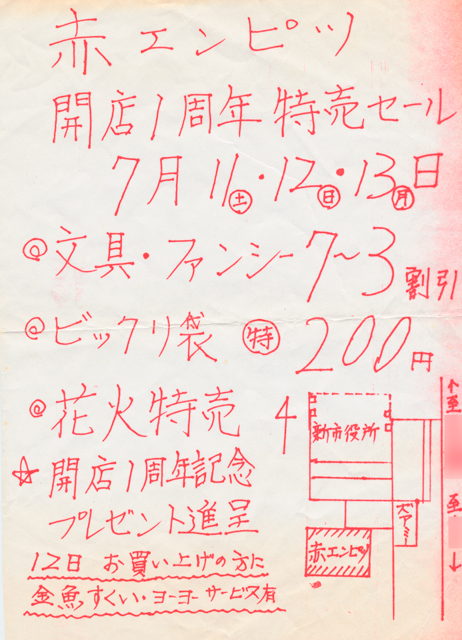
コメント