 |
| 【ジァンジァンの自主制作レコードと淡谷のり子さんの直筆】 |
渋谷ジァンジァンへの漠然とした憧れ、というものが10代だった頃の私の脳裏に刻み込まれていた。語弊があるかも知れないが、東京にはかつてそういう劇場が、方々にあった。10代の私はそれらをいちいち、憧れてみるのであった。
学生時代のある時期においては、ギター・クラフトの学校へ通う友人がいたために、敢えてお茶の水を避けていたのだが、もともと中学時代から馴染みのある池袋や渋谷の方の楽器店へ赴き、ケーブルを買ったり、新しいオーディオ機材を触ったりして、わざわざ遠い店舗へ足を運んでいた。確か渋谷の公園通りは、その楽器店のある付近であり、“渋谷ジァンジァン”というのをそこで意識したのではないかと思われる。
10代の私にとってそこはあまりにも大人の、大人すぎる劇場であった。なんとなく敷居が高かった。中学生の頃、日本橋の三越劇場で杉村春子さんや北村和夫さんの文学座公演を観るよりも、渋谷ジァンジァンは“大人”すぎて入り込む余地が無かった。
*
私は20代の後半になってその歌唱法を学ぶため、淡谷のり子さんの「別れのブルース」や「ラ・クンパルシータ」などをよく聴いた。淡谷先生の歌声は、最も小さな音量であっても輪郭がしっかりとしている。SP盤の古い音源では聴き取りにくいが、デジタル・マスターで聴いても淡谷先生の声は、テヌートの最後の切れ端が消滅するまで、研ぎ澄まされ且つ柔らかいのである。
ごく最近になって、『淡谷のり子ライブ』というレコード(自主制作盤)を繰り返し聴いた。1981年10月29日、渋谷ジァンジァンでの貴重なライブ音源である。ピアノ演奏は結城久さん。
残念ながら、高橋竹山の渋谷ジァンジァン・ライヴのレコード盤(当ブログ「津軽三味線」参照)のような極上の音質はそこにはなく、おそらくバジェットの都合か何かで機材やら人件費やらをかなり抑えられたのだろう、『淡谷のり子ライブ』はあまりいい録音ではない。
質の良いプリアンプを通ったとは言い難い、ピアノとヴォーカルへのマイクロフォン・アプローチ。結城さんのピアノの明るいパッションは波立たず、不明瞭に背後に押しやられており、淡谷先生のマイクロフォンも切れ味が悪く、ピアノとヴォーカルとのバランスはさらにジァンジァン特有のアンビエントによって濁ってしまっている。
それでも、淡谷先生の声は、研ぎ澄まされ柔らかい。それが何より素晴らしいし、驚くべきことだ。弘法筆を選ばず。
 |
| 【『淡谷のり子ライブ』レコード・ジャケット裏】 |
曲目のトップは五輪真弓さん作詩作曲の「恋人よ」。この曲は淡谷先生のフェイバリットだ。レコード盤ならではの、淡谷ヴォーカルのフルレンジが聴ける。「灰色のリズム&ブルース」もいいし、「アデュー」や「リリー・マルレーン」もいい。
いわゆるナイトクラブの、大人の男女の、拍手ではない。
これは私の勝手な聴感による。高橋竹山のライブ盤もそうであったが、渋谷ジァンジァンの観客は若いのだ。拍手の音がそれを表している。掌がまだ円熟していないから、調子が速くパチパチパチと音が硬い。これがナイトクラブになると、パチパチパチではなくパシパシパシとなる。少なからず酒に酔っている。男と女の数が均一。既に人生のわびさびを知ってしまった人達の、欲望に対する迷いと憂いとがあり、掌の筋肉がほぐれて音が甘い。それがナイトクラブの拍手の音。それに比べると、ジァンジァンの観客は総じて若いと言える。
淡谷先生のシャンソンは、その若い瞳とはち切れんばかりの若肌の熱気を感じながら(あるいはそれに嫉妬しながら)、さらに言えば若者の匂いを感じながら、独りの、老いていく女を演じたのであった。

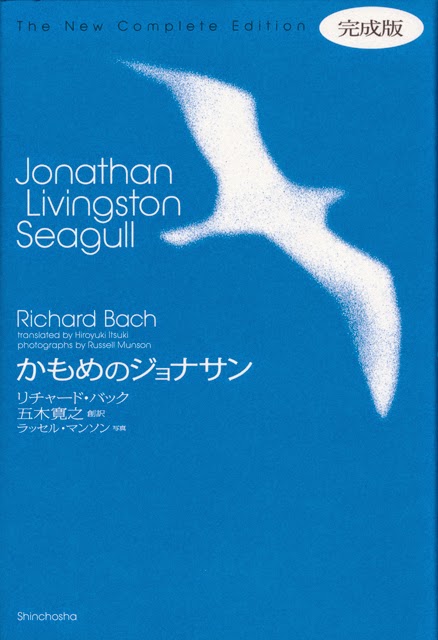
コメント