 |
| 【『洋酒天国』第31号】 |
師走に近づいた。周辺では比較的穏やかな日和が続いて、寒さはそれほどでもない。冬の本番はこれからのようである。
壽屋PR誌『洋酒天国』の第31号(洋酒天国社・昭和33年11月発行)。第31号はこの年の最後の号であるが、あまりクリスマス特集などと煽り立てておらず、その点ではいたって地味である。表紙自体も、すらりと美しいご婦人らが競馬場で遠方の競走馬を眺めていて、どこか気品がある。
この号のクリスマス関連と言えば、洋酒の豆知識「シャンパンいろいろ」、薩摩治郎八氏の「聖きこの夜」、SHOPPING GUIDEの「アベック・セット」ぐらいであろうか(トリスと赤玉の詰め合わせだとか、リップ・ポマードと口紅の詰め合わせだとかで、《密着度の強い「完全なる接吻」が楽しめます》と書いてあったりする)。
多少、師走ならではの物欲を仄めかしつつも、静かなホリデーを演出した大人のクリスマス、といった感じがする。
第31号の表紙の見返しには、豪華客船タイタニック号のカットがある。
そこには、牧逸馬氏の「運命のSOS」から引用した、酒にまつわる部分が添えられていた。
《酒場でウィスキー・ソーダをあおっている一団から、だれかが高く祝杯を差しあげて、
「何? 氷山だって! ありがたい。おい、給仕、ひとかけらぶっかいて来てくれ。この酒へ入れるんだ」
わあっと歓声が上がった。みなタイタニックを信じ切っていて、あんなことになろうとは一人として想像もしなかった》
(牧逸馬著「運命のSOS」より引用)
その直後の、未曾有の沈没事故をまったく予期しなかった船内の一瞬のジョークとも思える。参考までに「運命のSOS」の原文を少しばかり読んでみると、ウィスキー・ソーダは“ウイスキイ曹達”となっていて、古めかしい。牧氏(長谷川海太郎氏)は英国を旅した後、1929年頃から犯罪小説を書き始めたらしく、「運命のSOS」はその頃の小説のようだ。『洋酒天国』でこうしたジョークを取り上げると、まったく違ったジョークに感じられるから、面白い。
*
 |
| 【サントリーのウイスキー・ホワイト】 |
話は変わる。
安い国産のウイスキーで味がいちばん美味いのは、何と言っても角瓶だと思っているのだが、最近私は「サントリー・ウイスキー・ホワイト」を嗜んでいる。
サントリーの創業者、鳥井信治郎氏が1923年、京都の山崎に蒸留所を建て、必死に藻掻きながら国産第1号のウイスキーを完成させたのが、「白札」である。ピートが香しいこってりした本場のウイスキーに比べれば、やはりあっさりした味わいなのだが、これでもなかなか美味い。
先月、これの発売当時のラベルを復刻したものが限定販売されたらしいが、私はこれに運悪くなかなか出合えず、近々ようやく入手して楽しむつもりなのだ。ちなみに、この国産第1号のウイスキーが誕生したのは、1929年のことで、牧氏の小説の頃と重なる。こうして私は、昭和初期の酒と小説を“ダブル”で嗜むことにした。
あの「白札」が美味いと感じるのは、それだけのせいではない。
『洋酒天国』第31号には、「シュバンヌ氏のまむし酒」などというコラムがあって、これを読んでいるうちに気持ち悪くなり、やはり酒は壽屋がいいと思い直したからだ。
 |
| 【コラム「シュバンヌ氏のまむし酒」】 |
これはパリの居酒屋「風車」にて、まむし酒が密造されていて常連客が好んで呑むのだという話。密造だから、ボジョレーの樽の間に隠してあるとか。それだけ聞けば、まむし酒にしばし好奇心を抱いて、ちと呑んでみたいと思ったのだが、沖縄で呑んだことのあるハブ酒とは、少し違う。
何より見た目、瓶の中のまむしが、異様にでかい。これだけで気分を損なう。瓶の中のアルコールがレンズとなって、まむしの鱗を浮き上がらせて見える。非常に宜しくない。
しかもまむし酒は、“生きたまま”のまむしを瓶に詰めて、6ヵ月貯蔵するという。普通、半年経てば瓶の中のまむしは死ぬのだが、なかにはぴんぴんしたまむしがいて、出来上がった酒を呑もうと思った者が瓶の中でまだ生きていたまむしに噛まれて死んだ、ということがあるらしい。笑い話にもならない、寒気がする。
そうしてまむし酒は、見事にまむしの味が染み入っていて生臭いらしい。血の味もするという。まむしの生臭さとは一体どんなものなのか。こんなことは「シュバンヌ氏のまむし酒」にはちっとも書かれていないが、私は一気に好奇心が薄れてしまった。血の気も引いた。
そんな気持ちの悪い思いをしてまで、絶倫の精力をつけようとは思わない。酒は心地良く安らかに嗜むもの。ああ、「白札」に安堵するひととき――。

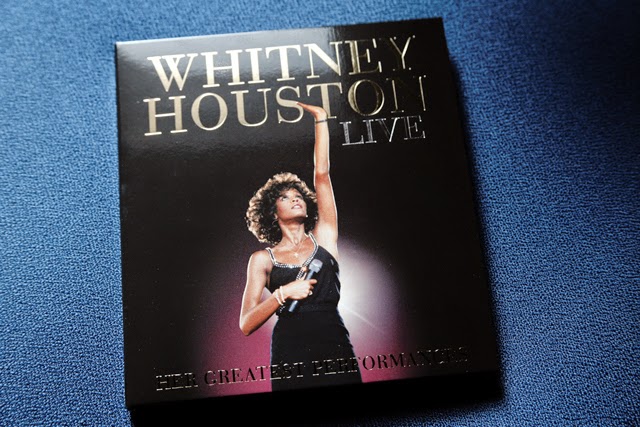
コメント