 |
| 【東博にて。『始皇帝と大兵馬俑』】 |
1月7日、“博物館に初もうで”に行った。私はほぼ毎年のように東京・上野公園の東京国立博物館を訪れる。
正月の特別公開である葛飾北斎の冨嶽三十六景(凱風快晴、山下白雨、神奈川沖浪裏)と狩野山雪の猿猴図は間近で観ることができた。だが長谷川等伯の松林図屏風は何故かスルーしてしまった。国宝の松林図は個人的にちょっとした思い入れがあったにもかかわらず(当ブログ「高瀬川」参照)。いずれにしてもこうした風光明媚な国宝を眺めることができたのは嬉しい。
年始は例年と比較して暖かかったように感じられた。この日も寒さで震えることなく上野公園を快活に散歩することができた。が、気がつけば、東博の年間パスポートが去年で切れていた。珍しく今回はチケット売り場に並んだ。
東博の正門から奥に位置する平成館までは、数百メートルあるだろうか。いつもこの時期は寒いので、足取り速く平成館へと向かうのだが、春を思わせる陽気でまずは館内散歩という気分になり、植え付けられた木々の種類やら成長やら方々見回しながら、たっぷり時間を使っての足取りであった。
*
 |
| 【東博の本館正面。平成館へは左側から奥へ向かう】 |
私にとって息を荒げずにはいられない待望の――昨年の秋から開催されていた――特別展『始皇帝と大兵馬俑』に訪れる。ホームページを見ると、昨年の12月の時点で入場者数は20万人を突破したとある。年が明けての観覧は正解だったかも知れない。午前、平成館へ向かう観覧者の多さはそれほどでもなかった。
特別展『始皇帝と大兵馬俑』。ここ最近の東博の特別展においては、最も東博フリークの関心が高まったテーマではなかったかと思われる。始皇帝と言えば秦の始皇帝。歴史の教科書でも度量衡や貨幣の統一、焚書坑儒、万里の長城の修築などが挙げられ、知らぬ者はいない。しかしながら私は、ユーラシア大陸東部の壮大な歴史と浪漫に、疎い。“始皇帝”と“兵馬俑”と聞いて連関せしめるイメージがごくごく限られている。つまり今回は分からないことだらけなのである。
ただし、“兵馬俑”の方は、わずかに連関というか微々たる空想が広がるものがあった。
高校時代に初めて買った漢和辞典に、“兵馬俑”の写真があった。これが私にとって初めての“兵馬俑”との出会いだったのだが、けっこうインパクトがあった。兵士の形をした埴輪的ものが、数千も埋まっていたという驚き。その一つ一つが、違う表情をしているという驚き。漢和辞典ってなるほど面白いなと一瞬思えたのを憶えている。
確か本の装幀が紺色のその漢和辞典は、どうやら旺文社の『漢和辞典』だったようだ。高校時代にそんな“兵馬俑”に出会い、国語の授業では難読と感じられた漢文の、『詩経』の「桃夭」だとか武帝の「秋風辞」だとかを筑摩の国語教科書でえらく習ったものの、ただただ難しくて苦痛で、身悶えしながらそれに耐える体力はまったくなく、ほとんどその時期は頭が空中分解していたに違いない。
そうして漢文の授業は陶潜(陶淵明)の「責子」の読解まで進み、教科書への鉛筆の書き込みが甚だしいのだけれど、『論語』だとか孟子だとか老子だとか漢文の奥深い授業には至っておらず、今となっては屈原の「漁父辞」くらいは予習復習すべきではなかったかと思う。これが私のいかんともし難い大陸に疎い根本原因なのではないかと、今更猛省する次第だ。
話を漢和辞典に蒸し返すが、そこで“兵馬俑”を知り、つまりは“俑”という漢字を覚えた。手持ちの『岩波 新漢語辞典』(第三版・岩波書店)で“俑”を引くと、
《ひとがた。死者の霊を慰めるために副葬した人形。「陶俑・兵馬俑」》
とある。そうした“兵馬俑”の実物を、私は東博で本当に観たのだ、ということになる。漢文の読解には決して到達しそうにないが、始皇帝の時代の大まかな変遷と浪漫主義的なものはなんとなく、胸に刻まれた感がある。
 |
| 【平成館玄関前】 |
陝西省の始皇帝の陵墓の兵馬俑発見が、まだ近年と言っていい、私が生まれた年の直後の1974年であるという事実も、浪漫を掻き立てる材料となっている。始皇帝の時代の遥か昔、殷王朝の時代の王墓にも、死者への供え物として青銅の武具や馬車が埋められたらしいが、そうしたものを《埋める》風習というか貴族文化が紀元前より継承されていたことに風雅が感じられる。
今回の特別展では、秦時代の2つの銅車馬(複製)を観ることができた。青銅であることを思わせない細工が施され、気品が漂う。それにしても埋蔵品としてのスケールがいちいち大きい。秦始皇帝陵博物院蔵の兵馬俑群は陶製で、ほぼ等身大だそうだが、陶製のせいか肉厚があり、等身大より少し大きめに感じられた。故に一体一体に漲る迫力があった。この兵馬俑の展示の仕方も工夫が為されていて、順路からのスロープ途中でまず全体を眺望し、スロープを降りてから間近で、兵馬俑を360度舐め回して鑑賞することができる。
東博の観覧から帰ってきて、司馬遷の『史記列伝』(岩波文庫)を少しばかりかじってみた。翻訳がとても端整で文体のリズムがある。これなら読み易く、春秋・戦国時代を知るよすがとなりそうだ。「孫子・呉起列伝」はある種、時代の生々しさの塊である。
特別展『始皇帝と大兵馬俑』を観て、まだまだ分からないことだらけでどうしようもないのだが、いわゆる秦の国のあたりの、農耕にとって肥沃な黄土地帯と黄河がもたらす水の恵みとが人民の活力を生み、想像を絶する巨大な文化となっていったのは、理解できる。
何よりも優先すべきインフラ、すなわち生活のための社会基盤の建設と整備はとても重要だ。そうしたものを疎かにする政治は、悉く腐敗し滅びる。想像すれば、蟠螭文鏡の鈍い照り返しが、それを現代に伝えてくれよう。
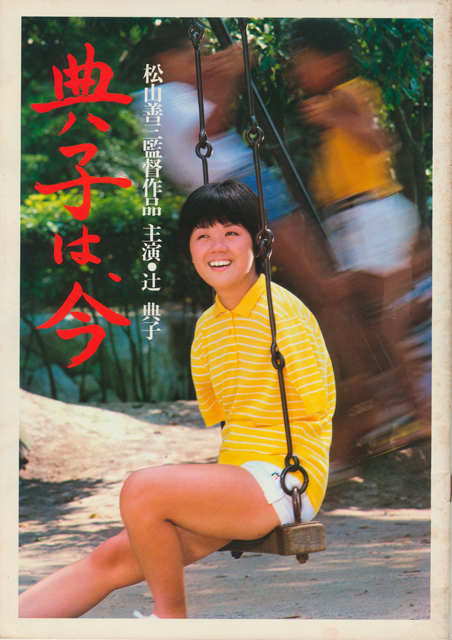

コメント