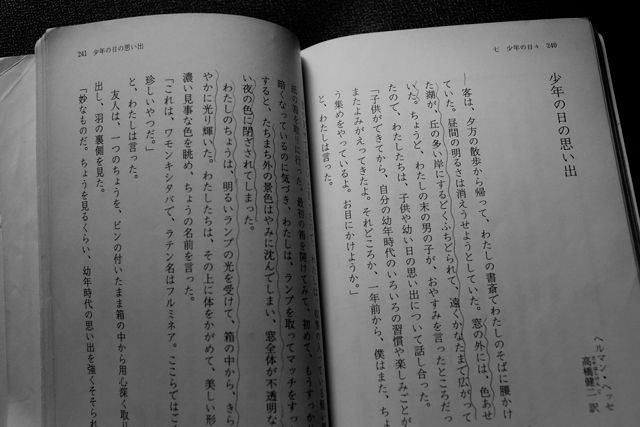 |
| 【ヘルマン・ヘッセ「少年の日の思い出」】 |
前回からの続き。私はいったいいつ大人になったか――。
その光村図書の中学国語教科書は全7章あって、第7章の標題は「少年の日々」となっている。第7章で取り上げられている課題作品は、井上靖の「赤い実」とヘルマン・ヘッセの「少年の日の思い出」だけだ。第7章の標題が掲げてある表紙には、次のような言葉が附されている。
《人はみな、少年や少女の「とき」をもつ。それはまるでみずみずしい果実のようだ。心の中で果実は永遠に光りつづける》
《人物の心情を読み味わい、作品の主題にせまる》
ヘルマン・ヘッセが1931年に改稿した「少年の日の思い出」(Jugendgedenken)は、もともと原題は“Das Nachtpfauenauge”であった。中公文庫の『教科書名短篇 少年時代』に収録されたヘルマン・ヘッセの「少年の日の思い出」では、原題“Das Nachtpfauenauge”とあり、初稿年である1911年の作品ということになっている。訳者は、光村図書の教科書及び『教科書名短篇 少年時代』いずれも高橋健二であり、底本は双方とも高橋健二訳『ヘルマン・ヘッセ全集』(新潮社)第二巻である。ちなみに『教科書名短篇 少年時代』によると、この作品の国語教科書への初採録は1947年だそうだ。
A子の教科書には、このヘッセの「少年の日の思い出」のページのあちらこちらに、彼女自身が授業で、あるいは予習復習の際に鉛筆書きしたと思われる傍線や波線の跡、段落番号の付記や特定の読みづらい言葉に注意を促す線などが書き込まれてあった。こうした教科書の痕跡を見れば、A子が直接、この作品に読み関わったことは明らかである。
翻って私は、中学1年当時――必ずしも教科書が光村図書でなかったとしても――「少年の日の思い出」を果たして読んだのであろうか。仮に私が学校の授業でこの作品と関わったとして、はっきりと今、その記憶がないということは、おそらくヘッセの作品に対する深い感動は当時、起こり得なかったのではないのか。そうだとすると、それはいったい何故なのか――。
中学1年の教科書の最後の章でこの作品を収録しているということは、教科書の監修、あるいは学習目的という観点において、何やら特別な意味を滲ませている。紛れもなく第7章の標題は「少年の日々」なのだから、その少年・少女の「とき」を振り返る、作者(井上靖とヘルマン・ヘッセ)の自己省察のたぐいの作品を選んで挙げていることは分かる。
しかし、これらを読む中学生らの受け取り方や感じ方は、明らかに別物で標題への関心は薄いと思われる。思春期の真っ只中にいる彼らにとって、愚直にもその只中をえぐり取ろうとする者はいないだろう。ここでの標題は、えらく無機質である。むしろ彼らが果敢に、意識的に挑もう乗り越えようとしている自己省察とは、少年・少女の「とき」を振り返るのではない、前へ向かって歩もうとする力に対し、大人として振る舞うことが過度に要求される日々の重圧、そしてその痛々しい心と身体の苛烈な葛藤なのであって、大きな暗闇を抱え始めた不安と反抗の悶えそのものなのだ。只中にいる彼らにとってその只中の体験すべてが、“みずみずしい果実”であろうとは、誰も感じないであろうし、渇いていない生傷を触るようなものに違いないのだから、感じたくもないであろう。
§
ヘッセの「少年の日の思い出」は、夕方の散歩から帰った「わたし」がその客人に、子供の頃の思い出を語り、収集した蝶の標本を見せるところから始まっている。
ワモンキシタバ(フルミネア)という蝶を見せられた客人は、かつての記憶が甦り、自分が子供の頃はこうした蝶を熱心に収集したものだと話し出す。そしてその思い出を、自ら汚してしまったと吐露する。この短篇作は、その客人によって語られる少年時代の追想録であり、彼の、蝶の収集にまつわる、およそ12歳の頃に経験したエーミールという少年とのいざこざに集約されていく。
少年時代の追想――「ぼく」として語られる――の中で、いくつかの蝶(蛾)の名前が挙げられていることにこの作品の深い情趣を感じる。10歳になった夏、初めてキアゲハに出会った話。先生の息子のエーミールにコムラサキを見せに行き、こっぴどく標本の仕方が悪いと指摘された屈辱の話。そして問題の、クジャクヤママユの顛末。
教科書の備考欄には、そのクジャクヤママユについて、《ドイツ語では、「夜のくじゃくの目」とよぶ大型の蛾》と記してあった。夜のくじゃくの目とはやや美麗な表現であるが、私などあまり昆虫が好きでない者がもし、この蛾を夜の街灯などでうごめいているのを発見したならば、思わず卒倒に近い恐怖を覚えるだろう。両羽にある4つの恐ろしい目の斑点は、文中にある鳥がおそれをなして手出しをやめる云々によって表現され、いたく共感できる。
だが「ぼく」は、そんなクジャクヤママユを特異にも欲しがったのだ。歴史家リビウス(Titus Livius)のなくなった本が発見されたと聞くよりも、エーミールがそのクジャクヤママユを“さなぎ”からかえした、という噂に興奮したのだ。そうしてエーミールが偶然その時留守であったという事情があれ、結果的には「ぼく」は、こっそり彼の家の部屋に忍び込んで、クジャクヤママユを持ち出そうとしてしまった。
ワモンキシタバを見せられた客人がそれを箱の中から取り出し、幼年の記憶が呼び覚まされた直後に、礼儀に反してすぐにそれを元に戻し、箱の蓋を閉じてしまったのは無理もない。過去のクジャクヤママユの顛末、もっと具体的に言えば、箱の中から標本を取り出す所作そのものが、トラウマのように心を動揺させ、あの時のことを思い出すのだろう。
それを持ち出そうとした「ぼく」はすぐに我に返り、エーミールの部屋に引き返して元の状態に戻そうとした。が、蝶の羽根は無残にも、ポケットの中でばらばらになってちぎれてしまっていた。クジャクヤママユの展翅(てんし)は元に戻らなかったのだ。
家に帰って母親に促されたその日の夜、ついに決心してエーミールに謝るため会いに行くのだけれど、思いのほかエーミールの態度は冷然としていて、少年達の間にわだかまりが残った。それから、遅く家に戻った「ぼく」は、自分の収集した蝶を一つ一つ押し潰してしまう――。エーミールの目の前で、決して過ちは償えないものだと気づいた「ぼく」はその時、初めて大人になったのである。
大人になること。それは、子供より偉くなることではないのだ。むしろ逆だ。純真さを一つ一つ喪い、悲しげなものに変貌を遂げていく、のだと私は思う。喪っていくものに、どう向き合えるのか。背を向け続けてしまうのか、あるいはひたむきに向き合うのか。その違いは、ある。
こうして今、私がヘッセに愛着を感じるのは、自らの、その葛藤の連続であったあの重苦しい思春期を、俯瞰して振り返ることができるようになったから、だけではない。それらが“みずみずしい果実”であったかどうか、それを虚像と捉えるか実像と捉えるか、振り返りざるを得ない。己は過ちの数々とどう向き合ってきたというのか――。クジャクヤママユの展翅が決して元に戻らなかったように、元に戻らないことへの、さらなる背負いの認識を顧みざるを得ないのである。
ヘッセはやはり、大人に愛されるべき作家であろう。あらためて「少年の日の思い出」を読む。もはや果実として熟された後の、少年の日々を振り返る独りの人間として。


コメント