 |
| 【ラフロイグの10年物】 |
とある英字新聞で、“like a dog with a bone”という慣用句を知った。根気強い、粘り強い、という意。その新聞では、ある映画を紹介していて、“like a dog with a bone”はその映画の中の台詞である。“fuck you around”などという慣用句も出てきて、日常会話の英語を習うには、映画は最適な教材であろうと思った。
イングランド北東部の町で暮らす主人公の男。彼が失業手当を受給するため行政を相手に孤軍奮闘するストーリー。私はひどくその映画に関心があった。英国の貧困や格差による労働問題が根底にあり、険しい現実の悲喜交々が描かれているようだ。ストーリーの背景となる町――イングランドのニューカッスル――がイギリスのどの当たりにあるのか、グーグル・マップで閲覧しているうち、その関心度は次第に高まっていった。
マップから、グラスゴーの地名が見えた。グラスゴー。確か村上春樹氏が、グラスゴー空港からアイラ島へわたり、大西洋に小さくこぢんまりと突き出たその島で、アイラのシングル・モルト・ウイスキー三昧を繰り広げた本があった。『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』(新潮文庫)である。スコットランドのアイラ島とアイルランドに旅し、各地のウイスキーにまつわる、短い読み物の、ウイスキー謳歌――。
私はそれを思いだしたついでに、まだ封を開けていないラフロイグの10年物をグラスに注いだ。強烈で癖になる「アイラの匂い」が嗅覚を刺戟する。そして一口、どろりとした琥珀色の液体を喉に流し込んだ。それが貧困とも格差とも、様々な問題を抱える英国とは無縁の、ケルト的超常現象と思える独特のシングル・モルトの味で、私たちは日頃これの、ブレンディッド・スコッチ・ウイスキーを飲んでいるのだと気づいた時には、その源流というか原風景を歩いたかのような錯覚に陥るのだった。
§
 |
| 【村上春樹著『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』】 |
村上春樹氏の『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』では、実に落ち着いた風情で豊かな言語を使い、我が極東から遙か遠い彼の地のシングル・モルト・ウイスキーを、入念に表現している。村上春樹流のウイスキー愛だ。一部を要約してみると、こういうことになる。
――ウイスキーにとって必要な原料は、大麦、おいしい水、ピート(泥炭)であり、これらはすべてアイラ島に具わっていて、それぞれのディスティラリー(蒸留所)では、個性的な「棲み分け」をしている。ディスティラリーにはそれぞれのレシピがあり、それがウイスキーの独特の個性となっている。
そのうちの一つ、ラフロイグ(Laphroaig)のディスティラリーは近代的で、フロア・モルティングの後の工程はすべてコンピューター制御されているという。だから他のディスティラリーとくらべると効率が良く、時代に照応したやり方で「伝統的な味」を守っている。こうしたことから、味を守るとは、必ずしも古いやり方を踏襲することではないようだ。
ラフロイグのウイスキーの味についても、春樹氏は、《アーネスト・ヘミングウェイの初期の作品に見られるような、切れ込みのある文体》だとか、《ジョニー・グリフィンの入ったセロニアス・モンクのカルテット》、15年物は《ジョン・コルトレーンの入ったセロニアス・モンクのカルテットに近い》といって、神妙かつ面白い表現で言い回している――。
私は、セロニアス・モンクがパトロンの女性キャサリーン・アニー・パノニカ・ロスチャイルド(通称ニカ夫人)のために作曲した1959年の名作、「パノニカ」(Pannonica)がとても好きだ。この曲をカヴァーした作品はプロ・アマとも無数にあって散見しているが、もはやモンクのオリジナルを聴いた後では、どれもこれも味が薄く平板で、酒の肴にもならない。
ニカ夫人の世話になったミュージシャンは他にもいるらしい。が、彼らとは決して恋人関係にならなかったのだという。ニカ夫人もミュージシャンも共にジャズを愛し、それ以上に恋人である必然がなかったからかも知れない。セロニアス・モンクが奏でる「パノニカ」の、その孤独なピアノの音色は、彼特有のごつごつとしたポリリズム的要素を多分に含んでいながら、ニカ夫人に手向けた愛情というべきもの、その想い出の一つ一つが音に喩えられている。それを聴くからこそ味わいがある。私としてはこの曲でさえ、ラフロイグのあの「アイラの匂い」と共鳴できると確信する。どこかラフロイグもセロニアス・モンクも、メルヘンティックな世界のモノと人に近いからではないだろうか。
普段の生活の中で、先述した映画のようなストーリーを目の当たりにしたり、そうした働くことの問題で友人が現実に苦しんでいたりするのを知るなかで、何か自分にできることはないかと、考えたりする。ほんの少し、それを実践したりもする。
我々は日々、常に束の間の「休息」を求めている。私にとってはその一つがウイスキーであったりする。幸福で僅かな「嗜み」であると思っている。――ウイスキーを飲み、読書をし、モンクを聴く――。生きているという当たり前の実感は、ウイスキーによって感覚的に発見させられ、その日々の苦しさが、どこかメルヘンの世界と行き来しているのではないかという思いすら芽生えてくる。
ウイスキーとは、鄭重な態度でヒトに人生を示してくる、不思議な飲み物である。だから私は、せめて、“like a dog with a bone”とつぶやきながら、生きていきたい。
追記:どうぞ、こちらも参考に→当ブログ「アイラ島憧憬―スコッチの源流」。

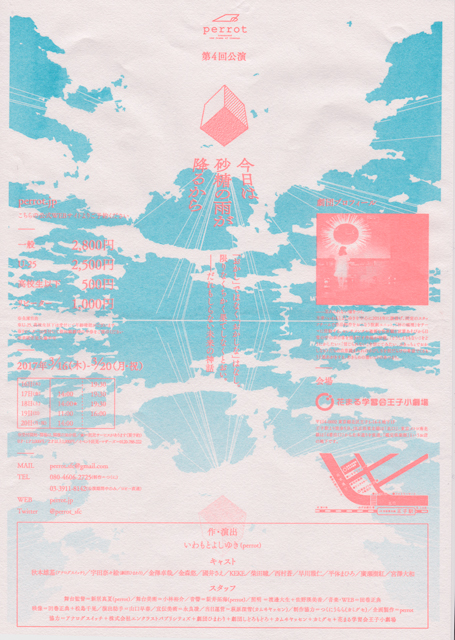
コメント