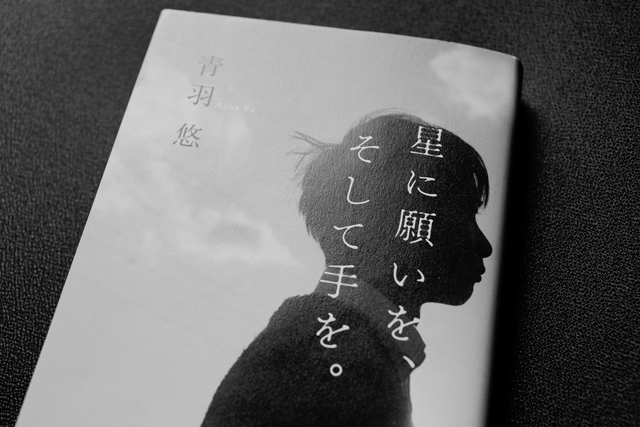 |
| 【青羽悠著『星に願いを、そして手を。』】 |
先月、ちょうど私の手元に、青羽悠著『星に願いを、そして手を。』(集英社)の分厚い単行本が届いた頃、集英社のPR誌『青春と読書』3月号にて、青羽悠と朝井リョウの対談が掲載されているのを知った。この同社編集部が企画した、ある意味において残酷な、また別の意味では「愚直」そのものにも思える生身の若者同士の対面は、まさしく新旧青春作家の“最年少”対決であり、そういう言葉がぽっと頭に浮かんだのは私だけではないだろう。
言うなればそれは、片方の朝井リョウの青春作家卒業の通過儀礼であった。第29回小説すばる新人賞を受賞した16歳(現役高校生)の青羽悠。そして第22回(2009年)の同賞を20歳で受賞した朝井リョウ(『桐島、部活やめるってよ』)は、2013年には戦後“最年少”で直木賞を受賞している(『何者』)。世の中においてこの“最年少”記録というのは、平素何事も飄々とした雰囲気の中で塗り替えられていくものだが、16歳の現役高校生による長編小説が、堂々と文学賞の栄冠を勝ち取ったのは快挙と言っていい。この大人達が担ぎ出す、文学界の“最年少”作家発掘アドバルーンは、業界の一つの慣例事として、終古変わらず続いていくに違いないのだ。
§
それはそれとして、青羽悠著『星に願いを、そして手を。』を読んだ。何故私はこれを買って読もうとしたのかについて、また、自分はこの小説に何を求めていたのか、それらの確固たる理由を言葉にできないまま、ほぼ1週間のうちに夢中になってこれを読んだ。
小説のモチーフは、とある町の、プラネタリウムを所有するしがない科学館である。学生時代にこの科学館の図書棟でよくたむろしていた男女4人が、時を経て20代半ばの夏、館長の死をきっかけに再び科学館に集まるのだが、そこで科学館がまもなく閉館されることを知る。若者達(この男女4人とさらに館長の孫の男子高校生と、そのクラスメイトの女子が加わる計6人)はそれぞれの思いを胸に秘めつつ、閉館までの一夏を全力で駆け抜けていく。
『星に願いを、そして手を。』の文体の特徴は、物事をとらえる一人称の主体が、たびたびそれぞれの登場人物に置き換わることである。例えば冒頭では、「私」の一人称で理奈という女子中学生が主体となり、次の第2節では「僕」の一人称に変わって、理奈の彼氏の祐人という男子中学生が主体となる。このようにして、物語の節ごとに一人称の主体が変わっていく。ちなみに、最後の章(第五章)の最終節(第8節)では、「俺」――館長の孫の直哉が主体となって閉じられている。
それぞれの登場人物に主体がその都度置き換わることの長所は、その主体の心と感覚によって物事を見渡す主観的性質にあるから、その都度文体の表現性が多彩になることだ。三人称の場合では、その文体の表現性が一つに統一される反面、その客観的主体が一主観の性質とほぼ同じ作用となってしまう恐れがある。
一人称の主体が置き換わることと、全体をとらえきることのできる三人称との違いは、前者では、主体と主体との間にできる心と感覚の隙間、主体と主体とがぶつかり合う思惟の矛盾感のようなものが醸し出されることにある。後者の三人称では、その隙間が生じず矛盾感も現出しないので、起こる万象と未来へ向かう時間軸すべてが際限なく見渡せてしまい、かえって文体としてのあざとさが残ってしまう。したがって、それぞれの主体の心と感覚から外れない程度に全体を見渡せる、この「一人称交代方式」は、特に一人が主人公として突出しない青春群像劇において、効果的に多彩な文体が味わえるはずなのだ。ただし、青羽悠の筆致がまだそこまでの多彩さに追いついていない面があるのは、やむを得ないだろう。
――彼ら若者達は、科学館にまつわるある謎を解こうと、一つの主題の筋道を自ら提示する。この謎が解ければ、自分達が抱えている“ある種の問題”も氷解するのではないかと予感だ。“ある種の問題”とは、誰しもが青年期で経験するであろう自らの「夢」(将来への具体的な希求)の衝突と疎外感、すなわちその「夢」と現実との間に生じる摩擦である。
祐人は、大好きな宇宙という「夢」を捨て、進学は文系を選び、町役場の観光課の公務員となった。理奈はもともと宇宙が好きで、大学は理学部へと進み、院生である。理奈からすれば、祐人は「夢」を「諦めた」人ということになり、それにこだわって、二人の関係にはぎくしゃくしたものが生じる。
他方、著者は、それを缶コーヒーの「苦み」に対する感覚でうまく表現している。「苦み」のある缶コーヒーを理奈はまだ飲めない。甘いミルクティーの方が断然好きだ。だが祐人は背伸びして、最も苦いブラック・コーヒーを飲んでみせる。
祐人は、その「苦み」のあるコーヒーの本当のふくよかな美味さなど、まだちっとも分かっていない。たとえそうであっても、大人になった自身への確認作業として(これはもう動物の本能なのだろう)、「苦み」のある不味い(と本当は感じている)缶コーヒーを我慢して飲み干し、てっぺんまで自己顕示してしまう。成長して大人になることへの寛容さがあるのとは裏腹に、若者というのは時に無茶をし、自らの羞恥や驕りを何かにごまかして対応するものなのだ。
§
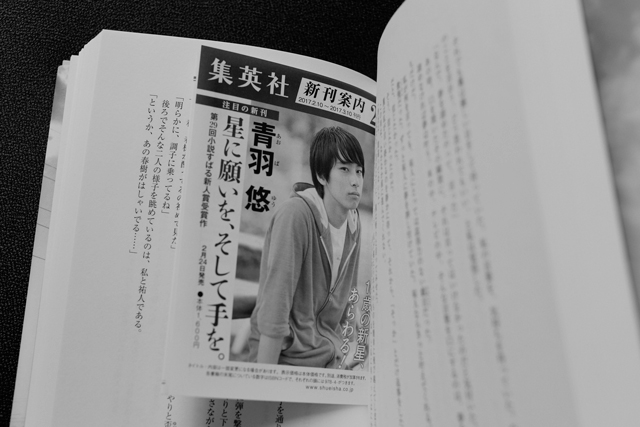 |
| 【本の中に挟まれた著者・青羽悠】 |
著者自身が宇宙が好きということもあって、この物語はたびたび夜空の星座を見上げ、星や宇宙について語る場面が多く、若者達の「夢」の問題と神秘的な宇宙への憧憬とが相俟って、若々しい躍動感の余韻が読後に牽引される。青羽悠は静かに健やかに、『星に願いを、そして手を。』で作家デビューした。
それにしても、この小説の最後の結び目が、実に自然で伸びやかなのだ。それは、彼の手のひらの「ぬくもり」を感じるかのように優しく、やわらかい。
このやわらかさが終始一貫して全体の文体を包み込んでいるとも言えるが、それが青羽自身の、(人生としてたった一度きりの16歳の)手のひらの「ぬくもり」であると分かれば、尚のこと、この長編の奥行きがさらに増して広がったような気がして、そのありがたさが骨身にしみる。
敢えて言う。これはとても大事なことなのだが、一読者である私が既に、著者の立場の青春時代をとうに超えてしまったところに佇立していて、その過ぎ去った青春時代という言葉にできない塊を、ある一人の作家の感覚を通じて如実に感じ取ることができるのは、幸福なことなのである。呼び覚まされた青春が、肉体を熱く掻き立てる。理屈ではないのである。若き日の成功の嬉しさだとか、失敗の涙の憂い、あるいは否応なく友人と訣別した悲しみのすべてを、私は日々、どこかに叩きつけたくなる。しかし、その溢れ出る感情を抑え、この書に人生の明暗を振り返ることができるのは、ありがたいことなのだ。
青羽悠の手のひらは、なんて優しく、やわらかいのだろう――。


コメント