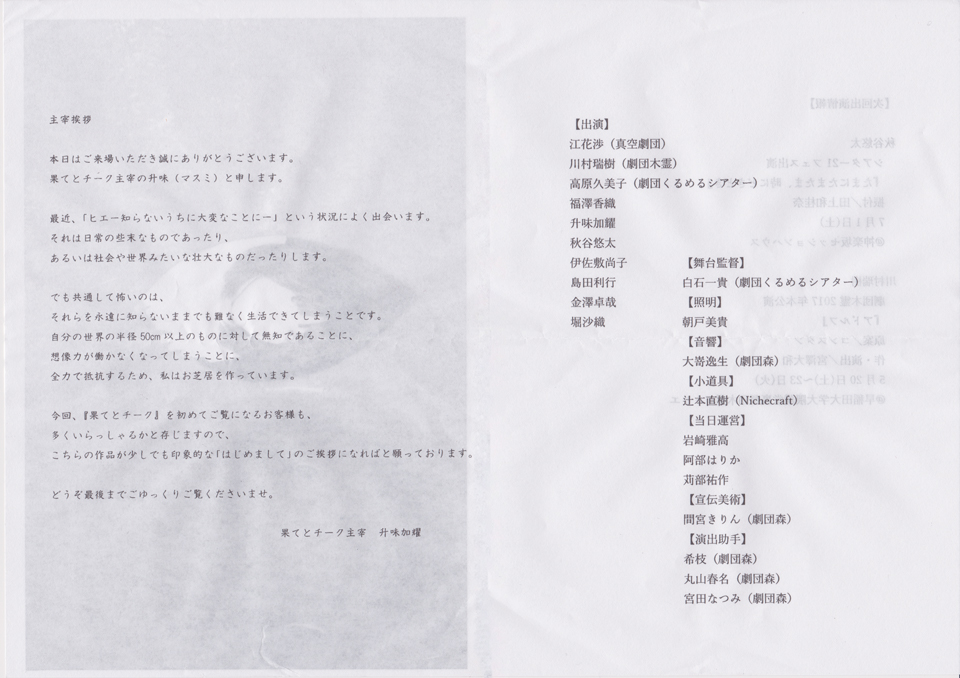 |
| 【「果てとチーク」升味加耀・主宰挨拶】 |
初夏を感じる気持ちの良い晴天であった昨日の午後。東京・王子の花まる学習会王子小劇場にて、升味加耀主宰・脚本・演出による「果てとチーク」第二回公演 『グーグス・ダーダ なになにもなになにもない NO nothing nothing nothing』を観た。出演は江花渉(真空劇団)、川村瑞樹(劇団木霊)、高原久美子(劇団くるめるシアター)、福澤香織、升味加耀、秋谷悠太、伊佐敷尚子、島田利行、金澤卓哉、堀紗織。
どうでもいいことだけれど、私はこの王子小劇場の“穴倉”感が好きである。ビルの雑踏の一角の、誰にも発見されないような一箇所に、まさしくぽっかりと、小さな穴が空いている。――私が子供だった頃、田舎町の商店街の一角に、地下に潜るかのような階段を降りて入口のある、地元では有名なオモチャ屋さんがあった。私はそのお店の、いくつかに分かれて陳列されていた、ガラスケースの中の“超合金ロボット”に眼を奪われたまま、立ち去ることができなかった。〈超合金ロボットが欲しい〉という強い欲望の夢心地。まるでそれは宝石のように輝いていた《モノ》と他愛ない《時間》との瞑想だったわけだが、まず“穴倉”に入るという行為が、もしかすると、そうした夢心地を誘発させる大きな理由だったのではないかと今、ふと思った。王子小劇場の地下階段もまた、子供心をより戻す、一つの装置に違いなかった。
§
 |
| 【王子小劇場入口付近の挨拶パネル】 |
『グーグス・ダーダ なになにもなになにもない NO nothing nothing nothing』。何が無いというのか、考えてみるとこのタイトルもなかなか面白い。ちなみに“グーグス・ダーダ”とは、ドイツ語の“Gugus dada!”。赤ん坊をあやす時の、“いないいない、ばあ!”だそうである。これまたちなみに(どうでもいいことだけれど…)、私が赤ん坊だった頃、親がこれをいくらやっても、私はムスッとしてなかなか笑わなかった、らしい。ふん、それがどうした、へん!ってな感じで――。
物語(あるいは世界観のようなもの)を大雑把にゆるく説明すると、こういうことになる。ここは広大な砂漠。そこには、国と国を分け隔てる「壁」があり、その「壁」と「壁」との間にある砂漠が、“私たちの国”。果たしてこの「壁」は、いったいいつできたというのだろう。仮国境の外にある“向こう側”、“あっち側”との軋轢によってテロ事件が巻き起こり、「わたし」(私達)と「あなた」(あの人達)の関係が狂わされていく――。
興味深いと思ったのは、この公演の開場時から、既にキャスト陣によるパフォーマンスが「始まっていた」ということだ。
劇場では、青いシートが敷かれたスペースを三方取り囲むようにして観客席が設置されており、既に「始まって」しまっている彼らのパフォーマンスを、まるで公演前のスクリーン・セーバーのように観察できた。青いシートに散乱されたオブジェと同様、彼らの存在もまたその世界の一つのシンボルであり、サインであり、マークであった。おしゃべりをする彼らのうちの一組。また別の一組は男女二人でゆっくりと静かなダンスを踊っている。向こうにいる一組も同じようにダンスをしていて、開演直前までゆるりとした時間が流れていく。青いシートのあちこちに設置された“街頭スピーカー”的オブジェ(スマートフォンを利用した小型スピーカー)から音や音楽が流れると、彼らの動きは停止し、やがて横向きに倒れて冬眠状態となる。こうして既に「始まっていた」パフォーマンスが、一定のサイクルで開演まで繰り返されるのだ。
開演して暗転後の演劇は、マルチプル方式の会話劇によって展開される。
マルチプル方式の演劇の特徴は、実際、王子小劇場でそうなっていたように、コの字に分散された観客席の座る位置によって、まったく「異なる光景」を見ることにあり、観客一人一人が「異なる光景」の主となる。
一つの会話劇が自分の座る席の近いところで展開されたとして、もう一つの会話劇が自分の席から遠く離れた「向こう」で同時に展開された場合、自分に近いところの会話劇ははっきりと目視追従できるが、遠い「向こう」での会話劇は奥の芝居、つまり背景的な意味となる。しかし、「向こう」にいる側の観客にとっては、その逆、つまり「こちら」で展開されている会話劇が背景的な意味となる仕組み。
一つの会話劇が自分の座る席の近いところで展開されたとして、もう一つの会話劇が自分の席から遠く離れた「向こう」で同時に展開された場合、自分に近いところの会話劇ははっきりと目視追従できるが、遠い「向こう」での会話劇は奥の芝居、つまり背景的な意味となる。しかし、「向こう」にいる側の観客にとっては、その逆、つまり「こちら」で展開されている会話劇が背景的な意味となる仕組み。
普段の我々の日常生活の物事は、このような現象に近い状況でのインプット&アウトプットの連続であり、マルチプル方式の演劇はそのリアリズムに沿ったものと言える。もちろんこのことを逆手にとって、観客が無理やり「向こう」の会話劇を聞き取り(離れていてかなり聴き取りづらいが)目視追従することも可能であり、こうした演劇の再現はしばし、円形もしくは円弧の形の劇場でおこなわれる。
 |
| 【王子小劇場の入口】 |
いずれにしても、各方面で同時に個別の演者の会話劇が進行する。したがって、おそらく観客の大半の視覚と聴覚なるものは、それぞれの会話劇をすべてとらえるのはきわめて「困難」であろう。また、王子小劇場ならではの、高い天井付近にあるキャット・ウォークでも会話劇が展開されるので、見るのも聞くのも「困難」さに輪をかけたに違いない。
しかし、だ。
これが実に面白いのである。敢えてこの演劇は、この「困難」がつきまとうマルチプル方式を採用し、ネット動画に飽き飽きしているであろう我々観客を、大いに刺戟して已まない。そう、映像系では絶対不可能な複層表現なのだ。展開される会話劇はどれもこれも日常的で瑣末かとも思えるが、複層的にそれが展開されるから、とても密度の濃い交差劇となる。時折、個別の会話劇と会話劇とがリンクし、新たな会話劇に結合発展する術などは、一筋縄ではとらえることのできないこの世界の時間的感覚を、より濃密な《気配》として表現した知恵である。これはまったく予測できない官能的な展開となって、演劇の奥深さを感じた。
§
ところで、私がこの『グーグス・ダーダ なになにもなになにもない NO nothing nothing nothing』で最初にインプットしたのは――確かにそうであろうと思われるのだけれど――チャールズ・チャップリンの声だ。あれはまだ第二次世界大戦が終わらない1940年、アメリカで公開された彼の映画で、チャップリンはナチス・ドイツのヒトラーを模した“独裁者”を演じ、クライマックスで大演説をおこなった。その時の声を聴いたのだ。それはとても激しく美しい、国民の平和と自由を希求する、崇高な演説であった。
この演劇に登場する人物達が、「血の通った人間」のようでありながら、そうであることを真に望み、故に藻掻き苦しみ、どこか暗く怯えた無機質な人々に見えてくるのは、開演前のパフォーマンスでさらけ出されたように、彼らが人間ではなくその世界のシンボルであり、サインであり、マークであることと一致する。
私が以前感銘を受けた、ベルリンのアーティストであるサシャ・ヴァルツの身体パフォーマンスも同様の表現指向があって、その共通点に驚きを隠せない。これは升味加耀主宰の「果てとチーク」の旗揚げ公演がベルリンであったことと関係するだろう。《気配》とは、まさに「死」のことである。
重い歴史を背負った民族の、離散と自決の瀬戸際で未来を模索する即座のきらめきが、赤ん坊へのあやし文句“Gugus dada!”(グーグス・ダーダ)に込められている。そこで笑い顔をいっさい見せなかった赤ん坊――私――の母は、その時どれほど心細かったであろうか。赤ん坊よ、大声で泣き、笑い給え。

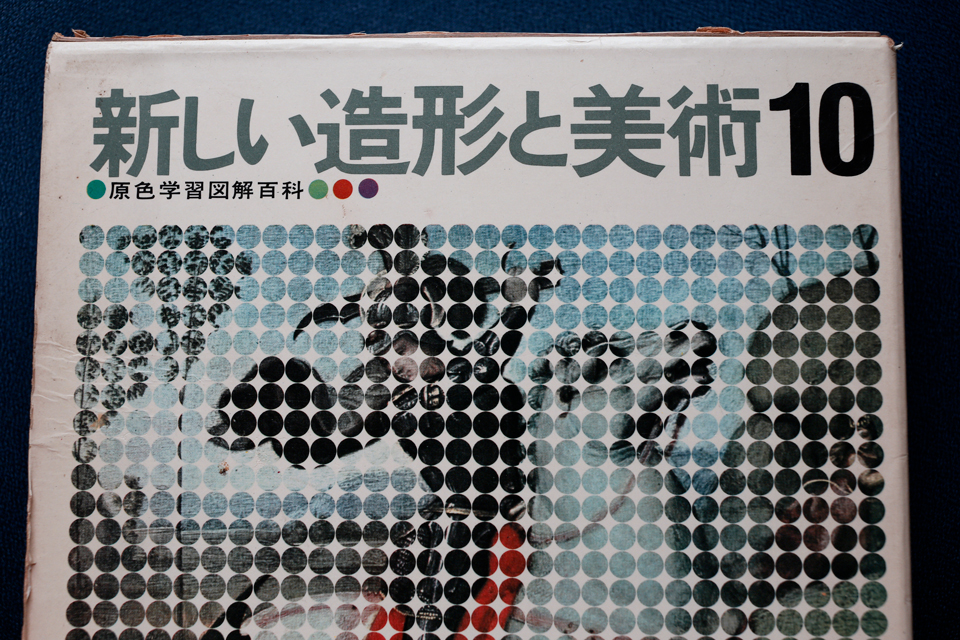
コメント