 |
| 【幼い頃聴いていた「アルルの女」収録のレコード】 |
レコードが奏でる物悲しいメロディが、突如として想い出の地の記憶へといざない、可憐な少女の面影を重ね合わせる。かつて聴いていた古ぼけたレコードの「アルルの女」は、見上げるその建物の5階の、あの「部屋」の物語でもあった――。
ジョルジュ・ビゼーの「カルメン」に続き、密やかな郷愁の記憶が甦ったのは、同じビゼーの「アルルの女」(L’Arlésienne)である。厳密に言うと、「アルルの女」の第2組曲第3曲の「メヌエット」(Menuet)であり、フルートのメロディが美しい有名な曲である。
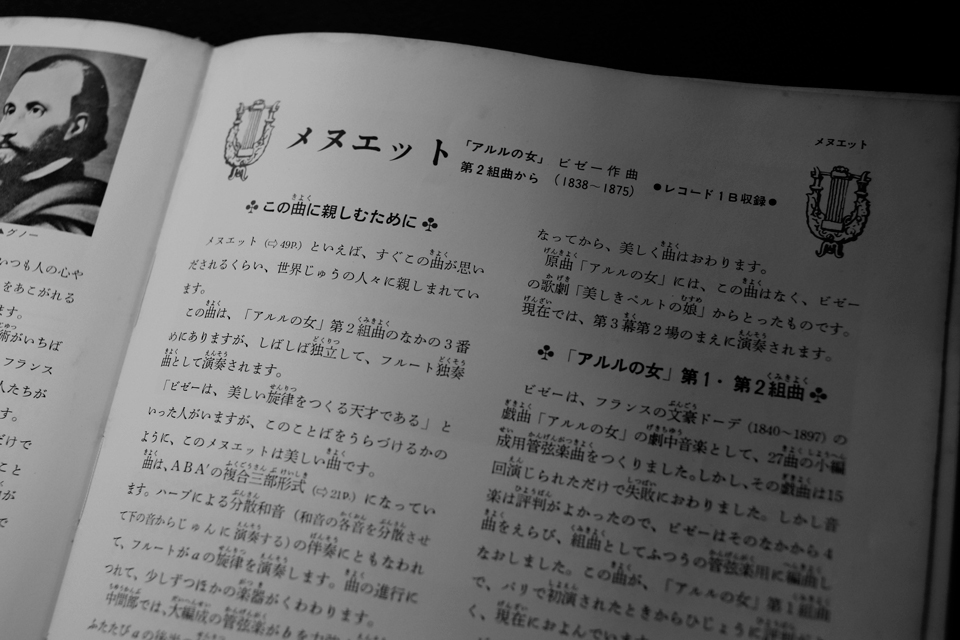 |
| 【『原色学習図解百科』第9巻のテクスト】 |
例によって幼少の頃、百科事典『原色学習図解百科』(1968年学研)の第9巻[楽しい音楽と鑑賞]によるクラシック・レコード集「名曲鑑賞レコード」(EP盤全6枚、全30曲)のうちの“アルル”のメヌエットを聴いた。日本フィルハーモニー交響楽団、渡辺暁雄指揮。
赤いレーベルのEPレコードをプレーヤーに載せ、その針のうごめきに眼を奪われる中、まさに密やかなフルートの音色に耳を傾け、心の些細な動揺を感じ取った平穏な日常の淡い香りは、夜の佇まいとして忘れられない記憶である。そうして矢も盾もたまらなくなって思いを馳せたのは、隣室に住む幼い少女のこと。仲良しだったその少女は、時折こちらの「部屋」に訪れてお飯事(クッキーを作るキッチンの玩具が素敵だった)をして遊んでいた。だが、私の一家がその集合住宅を去る前、彼女の一家もどこかの地へ引っ越してしまったのだった。実にあっけない幸せな月日ではあったものの、私はあの“アルル”のフルートのメロディと共に、今では写真でしか見ることのできない少女の円らな瞳を思い出す。あの「メヌエット」こそが、少女の「姿」の投影であったとさえ思えてならないのだ。
 |
| 【私の愛聴盤。マルケヴィチ指揮のビゼー集】 |
フランスの文豪、アルフォンス・ドーデの戯曲をもとに作曲された、ビゼーの「アルルの女」組曲。ドーデの戯曲のための付随音楽を、4曲の組曲にしたのが「アルルの女」第1組曲であり、ビゼーの死後あらためて編成されたのが第2組曲である。ドーデの戯曲がとても牧歌的で情愛に満ち、そして不憫な――フランスはプロヴァンスのアルルの地に現れた“アルルの女”に惚れてしまった豪農の息子フレデリの、悲劇と官能の――物語。幼かった私にとっては、そうした物語の背景などまるで分からなかったのだけれど、恋というべきもの、愛というべきものの《核心》は、少なからず感じ取れていたのかも知れない。
 |
| 【「アルル地方の風景」の写真】 |
当時のEPレコードによる「メヌエット」では、その後半部のオーケストラゼーションがやや迫力に欠け、ビゼーらしさが物足りないのだが、最近、コンセール・ラムルー管弦楽団でイーゴル・マルケヴィチ指揮による1959年12月にパリで録音された“アルル”、その「メヌエット」がとても優雅で気に入り、個人的には愛聴盤として親しんでいる。ビゼーのメロディアスな特徴と相まって、私は「カルメン」や「アルルの女」の官能的で烈しい部分がとても好きである。「カルメン」の前奏曲でもそうであったように、「アルルの女」第1組曲の前奏曲もまた、ビゼーらしい、熱情の度合いが高まった血と汗と涙が感じられる。第2組曲第4曲の「ファランドール」(Farandole)もしかり。そうした《生存》の根源的な旋律と和声の大動脈に、私はすっかり胸を打たれてしまうのだ。
私にとって「素朴な感傷」と言い得るあの頃の面影。そして“アルル”。本の中の「アルル地方の風景」の写真もまた、風情があって記憶の一つとなっている。まさに素朴なる永遠の感傷――。さて少女は、あの頃の密やかな日々を思い出すことが、あるのだろうか。
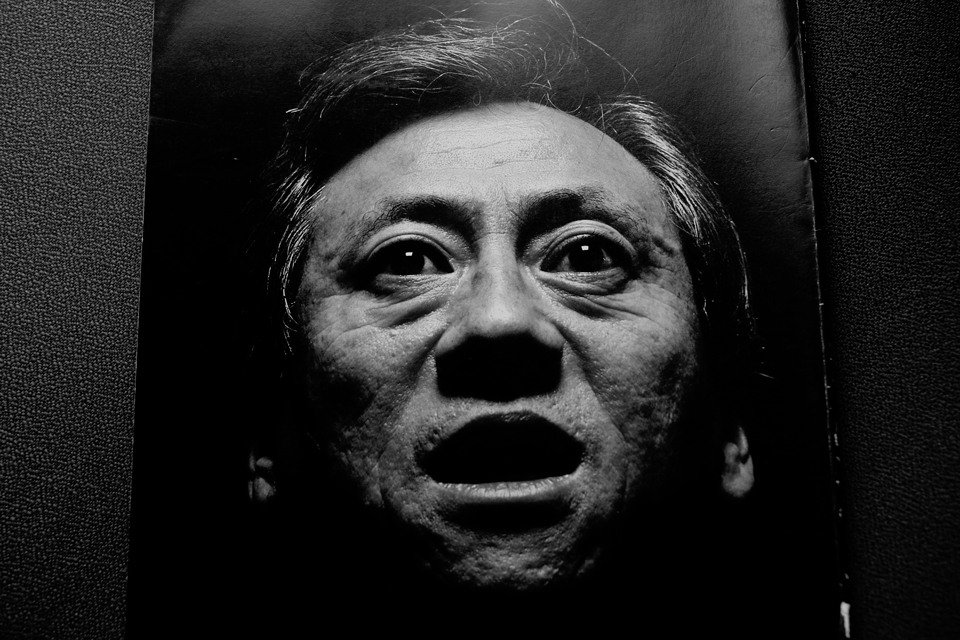

コメント