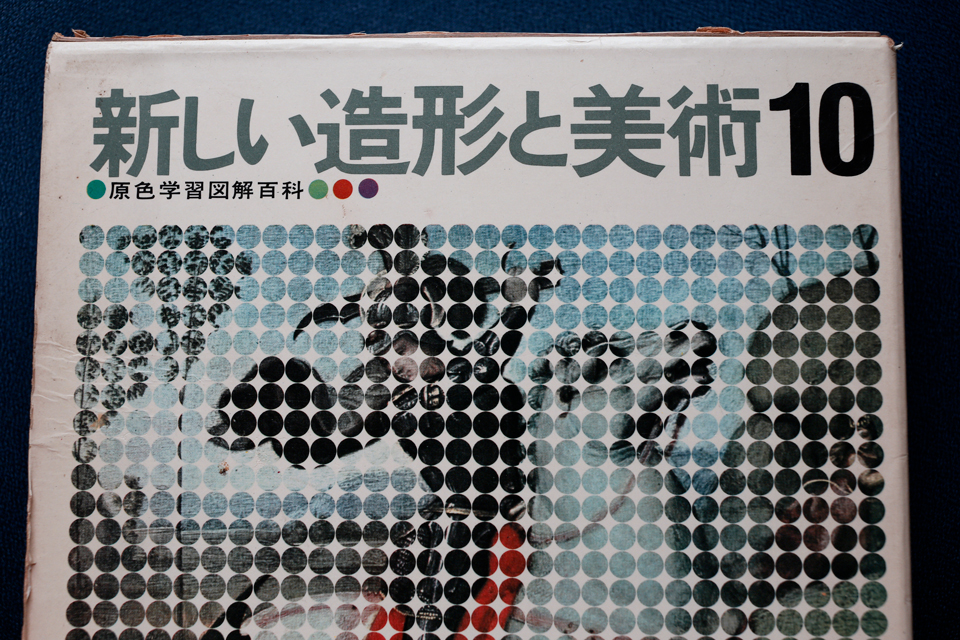 |
| 【『原色学習図解百科』第10巻「新しい造形と美術」】 |
幼児教育されているという感覚は、当の幼児にはなかった。そこに広がっていた「世界」は、視覚としての娯楽、聴覚としての豊かな娯楽であった。親から与えられたわけではなく、団地の家の中を徘徊し、片隅に設置された書棚の、何気なく美しいと思われた、ある「本」を手に取ったにすぎない。ただしそれは百科事典であった。「本」を読むというのではなく、その「世界」の閉じ込められた四角張った形状にまず関心があったのだ。
閉じられていた「本」を開き、パラパラと無数の紙が束ねられているのを美しいと思った。そこには文字と称するもの、そして鮮やかな色彩と記号の数々、さらにはシルクスクリーン印刷によって高精細な画や写真が鏤められていた。そうした無限の色彩と造形の「世界」に、私は――幼児でありながら――酔い心地を覚えた。
それは未知なる「世界」への出発であった。「私」という一個の人間の《現存》の始まり。モノとコトが交じり合う、果てしなき旅――。もはや、全人生のすべての起点とも言うべきこの時の原初体験から、私の中で生まれ出る「思考」は、宿命的に逃れることができなくなったのである。
§
 |
| 【色彩鮮やかな写真の数々】 |
その「本」=百科事典とは、1968年初版本の学研『原色学習図解百科』第10巻「新しい造形と美術」である。この時の原初の体験について、既に当ブログ「新しい造形と美術」で触れている。昭和40年代後半、私が生まれる以前より、『原色学習図解百科』の全10巻は家に有って、団地住まいにおいては片隅の書棚の、下から三段目にそれらは鎮座していた。幼児だった私にとって、最も手の届きやすい位置に、それらが置かれていたことになる。ちなみに、この百科事典の第9巻は、当ブログのトピックスで頻繁に登場させている「楽しい音楽と鑑賞」だ。
現在私が所有している全10巻は、その当時のものではなく、かなり後年に古書店で買い揃えたものである。もう50年近く経過した百科事典にしては、いまだなかなか状態が良い。しかし、当時家にあった『原色学習図解百科』は、発行からさほど年数が経っていないにもかかわらず、なんとなく痛みが激しかったように憶えている。それは私の想像の“上書き”による思い違いであろうか。初版発行から5年ほどしか経過していなかったはずだが、もしかするとそれらは、どこかの伝手によって中古のセットを手に入れたものだったのかも知れない。
 |
| 【衣裳スタイルに関するページも鮮やか】 |
こうして書いていくと、今以て私はこの古い百科事典に高い関心があり、しかもごく普通に愛読していることになるのだが、第10巻「新しい造形と美術」の存在は特別、かくも鮮烈であったと言っていい。
幼かったから、「新しい造形と美術」という本の主旨こそ理解し得なかっただろうが、そこに収められた無数のカラー写真や図解は、単純明快に私の視覚を大いに刺戟し、興味を駆り立ててくれた。先に述べた“未知なる「世界」への出発”とは、あながち誇張した言い回しでもなんでもない。まったく見たこともない(生まれて間もないのだから当たり前だが)モノやコトがそこに示されてあって、それがうごめく世界の一部であるとするならば、いったい全体この世界はナニモノなんだろうかという興味、好奇心。あるいは大いなる畏れと不安。漠とした気持ちでそんなことを感じつつページをめくっていき、いくつかのたいへん記憶に残る写真と図解に、私は出くわした。
§
「未来の住宅」という標題のページが、まずそれである。「21世紀における個人住宅の予想図」というイラストを、私はどれほど好んで何度も貪り眺めたか知れない。
それは、ある都市部の一角と思わしき未来型マンションもしくはコロニー型の個人住宅のイラストである。21世紀の住まいはこんなものだろうという未来予想図。これが実に奇想的で想像を刺戟した。
 |
| 【貪り眺めた「未来の住宅」のページ】 |
イラストを見てみよう。
左奥に見える住まいでは、家族がホーム・シアターを楽しんでいるのが分かる。70年代当時も8ミリフィルム映写機によるホーム・シアター的趣味は顕在しているが、空間としての趣が、ここでは未来志向でまるで違う。右奥の住まいを見ると、父親らしき人物がシャワーを浴び、隣の部屋で子供と母親らしき人物が音楽を聴きながら自動給水機システムでジュースを飲んでくつろいでいる。手前左の住居でも、同様の自動給水機システムで飲み物を用意し、その奥で男性がいわゆる電子頭脳=コンピューターで何やら勉強しているように見える。ロボットとボクシングを楽しんでいる若者が住んでいるのはその右隣の住居で、父親はテレビ画面で野球を観戦し、別の部屋で女性が電子楽器で曲を弾いている。また別の女性が個室のようなところでモニター画面を見ながら、テレビ電話を利用している。
テレビ電話なるもの。相手の顔をモニターで見ながら受話器を使って会話をしているが、テレビそのものにマイクロフォンを設置してあれば受話器などいらない――という発想は当時なかったのだろうか。また、話をするのにいちいち顔を映されては、スッピンで着衣が不格好な時に女性が困る、というのが定説になってビジネスモデル以外では不要論が根強い。
 |
| 【美しいステーショナリー】 |
が、それはともかくとして、テレビ電話的なものが1970年代において、どれほど夢物語なコミュニケーション・ツールであったか。私が子供時代、タレントの土居まさる氏が司会だった日曜昼帯のバラエティー番組「テレビ・ジョッキー」において、彼が視聴者に電話をかけるその電話機が、金色もしくは銀色の光沢で輝いていた“プッシュホン”であったのに対し、私はその電話機(という造形物)にどれほどの未来志向の憧れを感じ得ていたか。それを思うと、テレビ電話なるものに対する未来感覚は、さらにもっとえらく、想像もつかないほどの、研ぎ澄まされた憧憬であったのだ。
 |
| 【広告とタイポグラフィーによる造形美】 |
いずれにしてもあれから50年近く経て、これらの未来予想図は確かに、住宅の建築的な箇所はさておき、ほとんど実現してしまった(家庭でボクシングを楽しむという格闘意欲は、さすがに減衰)。むしろ今、さらに複雑で高度なネットワーク社会が成熟していることを考慮すると、この21世紀の未来予想図は単なる空想でも絵空事でもなく、真の意味での予想図であったことが頷ける。これらを遥かに凌ぐ「世界」に我々が今いるのだ、ということを思う時、あの幼児の頃の感動は、まさに“未知なる「世界」への出発”であった。
§
視覚によって耽美な酔いを覚えた「造形美術」とその百科事典の憧憬については、もっと踏み込んで書くべきなのだが、どこをどう書いても書き足りないような気がするのでここでやめておく。「造形」というのを辞書で調べてみた。「造形」(造型)とは、芸術作品としてのかたちをつくりあげること。「造形美術」は、目に見える形によって美を表現する芸術のこと。絵画、彫刻、建築など。「空間芸術」というのもこれに含まれるようである。以上の調べは三省堂の国語辞典の第七版に拠った。
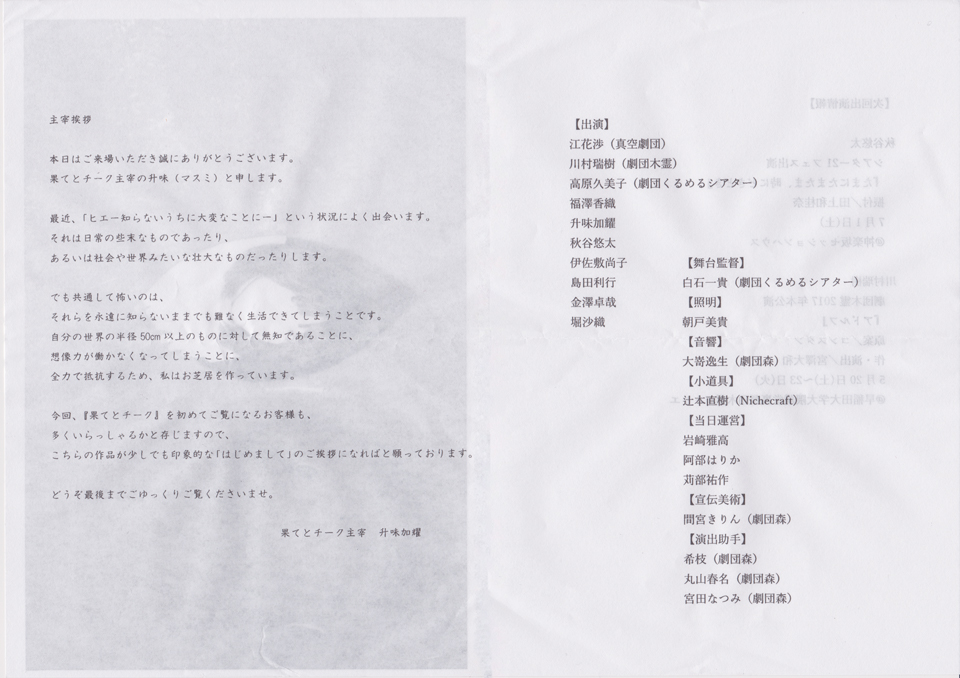

コメント