 |
| 【武満徹作曲・小澤征爾指揮「ノヴェンバー・ステップス」】 |
前稿に引き続き、武満徹の作品評と私の個人譚。
高校卒業後、幾年か過ぎ、その筑摩の国語教科書の武満徹著「暗い河の流れに」を読んでからというもの、「ノヴェンバー・ステップス」についてはやや関心があった。しかし私はまだその時、彼の映画音楽的な、いわゆる映画の映像進行に寄り添った形での音楽として、音楽家としての評価に傾き、彼の作品を避ける傾向があった。したがって「ノヴェンバー・ステップス」を“真に受けて”聴いたのは、今回が初めてのことであった。
私が今聴いているのは、1967年12月8日に録音(世界初録音)された小澤征爾指揮、トロント交響楽団による演奏のCDで、ハイレゾでリマスタリングされた高音質でクリアなサウンドの「ノヴェンバー・ステップス」である。この曲は同年11月、ニューヨーク・フィルの創立125周年を記念した委嘱作品として初演され、作曲者である武満徹監修のもと、翌月カナダ・トロントのマッセイ・ホールにてレコーディングされたものと思われる(CD封入のブックレットの最終頁には、その時の録音スタジオ写真――武満及び小澤の神妙な表情と態度が写った――が掲載されている)。ちなみに、トロントはカナダの南東部、アメリカのニューヨーク州と国境を隔てたオンタリオ湖の北西部にある。
§
彼の生涯に遺した作品歴が明らかとなっている今となっては、それが実に“武満らしい”と分かるオーケストラによる金属的なひしめき、弦楽の不穏な和声の合間を縫うようにして、「ノヴェンバー・ステップス」では邦楽の琵琶(演奏者・鶴田錦史)と尺八(演奏者・横山勝也)が全体の21分間弱のうち大半をしめて独奏される。これらの邦楽器の存在が少なくともニューヨークの初演やトロントでのレコーディングでまことに“好奇な”評価を得た大きな理由であったと、私は思う。
レコーディングにおける音像では、尺八が右チャンネルに定位し、琵琶が左チャンネルに定位。ほんの幾度か、これらの独奏に覆い被さるようにして左右に広がったオーケストラのアンサンブルが加わるのだが、それもごく限られた尺のことで、この曲のほとんどの印象は、邦楽の琵琶と尺八の響きで形成されると言っても過言ではない。
琵琶と尺八による独奏で私がインスピレーションを得たのは、東海道四谷怪談などといったいわゆる怪談物の独演会で奏でられる、奇々怪々でおどろおどろしい響きである。
先月だったか、私はある古いテレビ映画の二代目中村鴈治郎演じる“死神”(三遊亭圓朝の古典落語が原作)を観た。怪談の起承転結を劇的に引き立てているのは、まさに音としての琵琶と尺八以外にあらず、と実感したばかりであったし、その後「ノヴェンバー・ステップス」を聴くと、突然怪談物の講談が挿入されるのかと思ったくらいに、私いや日本人なら誰しもが琵琶と尺八の演奏でそれを直感するであろう。これを聴いてホラー系の音楽だと評されることも、致し方ない面がある。
たとえそうであっても、それだけで済ますことのできない武満独特の、音の響きの推移というものがある。
そもそも現代音楽の巨匠、あるいは巨人と謳われる武満徹の作曲すなわちオーケストレーションは、西洋のオペラやワルツ、ハンガリー舞曲、あるいはセレナーデ、さらにはドビュッシーの印象派といわれる系統のリズミカルかつ和声の荘重な趣、とはまったく異にし、言わば「《腐蝕》の時間変遷」を思わせる音楽なのである。
仮にそこに1個の「蜜柑」があるとする。先に連ねた西洋の音楽というのは、いかにその「蜜柑」が美しく味わい深いものであるかを形式的にこまめにモンタージュして音楽的に表現したものであり、その美しく甘酸っぱく芳醇な「蜜柑」の一瞬一瞬の「生きた」躍動感を、切り取って貼り合わせたものである。翻って武満の音楽は、そういうものではない。
「蜜柑」がいかに変容して《腐蝕》していくか――。「蜜柑」の表面の色合いが変色し、黒ずみ、やがてカビが生え、腐って腐臭を漂わせていく様子を時系列で追って示す音楽。人間が決して生理的に快楽と感じ得ない世界の実存の、そのリアルさをオーバーラップさせた音楽。しかも人間には怖い物見たさというのがあって、このリアルな直視感を否定したり取り除くことはできない。「ノヴェンバー・ステップス」というタイトルは、“11月の階梯”とは裏腹に、私にとっては皮肉にも、11の段階を経験して《腐蝕》していく「世界」のモノゴトの、すべてを表現し得たモニュメントに思えてならないのである。
§
琵琶と尺八が抱えて表現する音というのは、その一つの旋律を表すのに、比較的長い尺(まさしくこれをdecay timeという)が必要であることを、「ノヴェンバー・ステップス」は物語っている。オーケストラの金管も木管も弦楽も、一つのセンテンスでこれだけ長い尺が進行してしまうと、作曲上、協奏として手に負えなくなる。その音の冗長な減衰の印象によって、聴感上、記憶からアタックの明るさを失ってしまうのだ。
これらの楽器の違いは、音色とその演奏技法の違いによるものではなく、むしろ必要な旋律の長さやセンテンスの長さの違いを抱えた、まったく異なる時空間の響きなのである。琵琶や尺八が一つのセンテンスを放つと、その音を反射する空間の音場がありありと分かるほどで、この反射音そのものまでが琵琶や尺八の実音形成なのである。そうなるとやはり、オーケストラが奏でる浪漫派のオーナメントとは無縁の別世界と言えるだろう。
武満徹が《腐蝕》の世界を示すために「ノヴェンバー・ステップス」を作曲したかどうかについて、それは事後共犯的な解釈となるので明らかにすることは不可能だ。しかし、日本人が琵琶や尺八を聴いてホラーを想像する規定の概念には、平安後期あたりからたびたび古典で登場する、死世界と現世界とを往来するような物語や伝説の数々でも分かるように、生きたものが死後へと向かうある種の様式美があるからで、それは宗教的な趣と言うよりはむしろ、もっと純粋な自然観に近い、東洋独特の、生きものへの霊性的な感受であろうかと思われる。
私は武満の音楽のすべてを、一言で「《腐蝕》信仰の音楽」(もっとモダンに言い換えれば《腐蝕》フェチシズムの音楽)ととらえていいと考えている。
したがって「《腐蝕》の時間変遷」を形式として表した彼の音楽は、優越感を満たす蘇生のためにハイレゾでリマスタリングするよりも、当時の素材のまま、もしくはその経年劣化で磁気が剥落し、烏合のノイズによって変質してしまった状態の方のが、いっそう彼らしく、その音楽のなんたるかを指し示しているのではないかと、思う。「ノヴェンバー・ステップス」は腐りのステップと向き合った作品である。
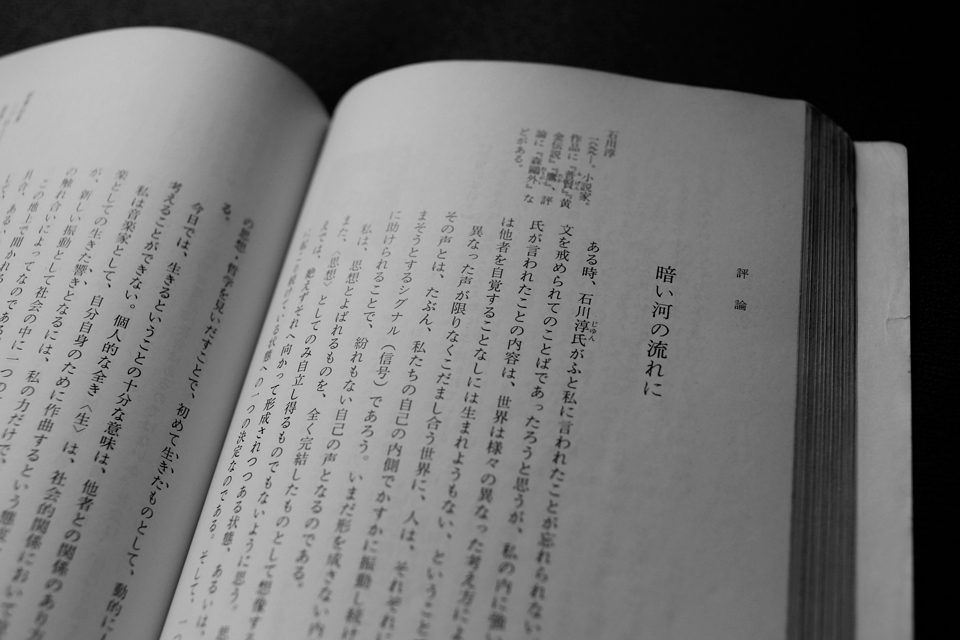
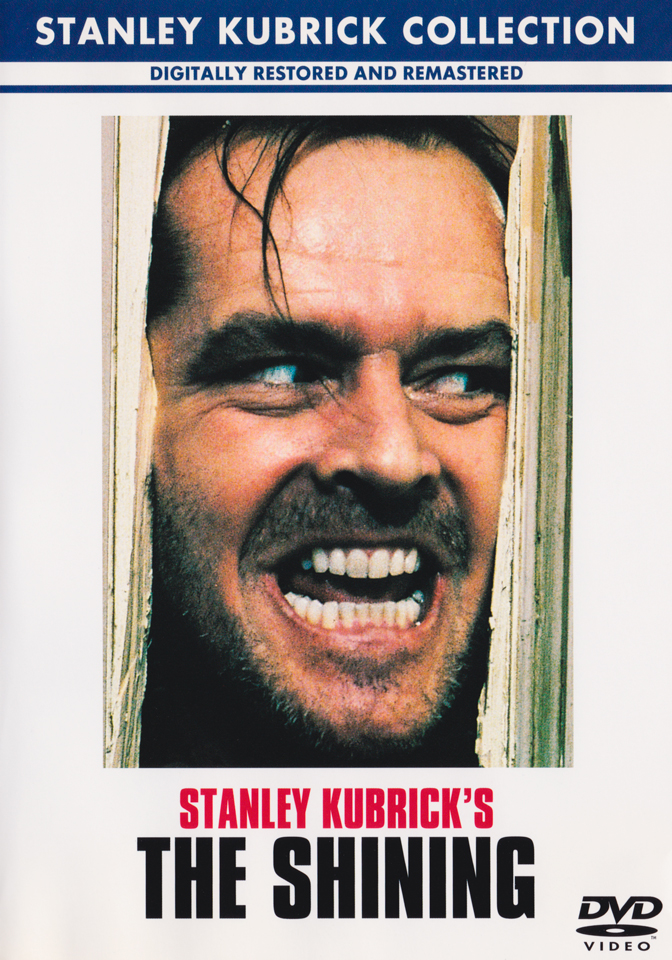
コメント