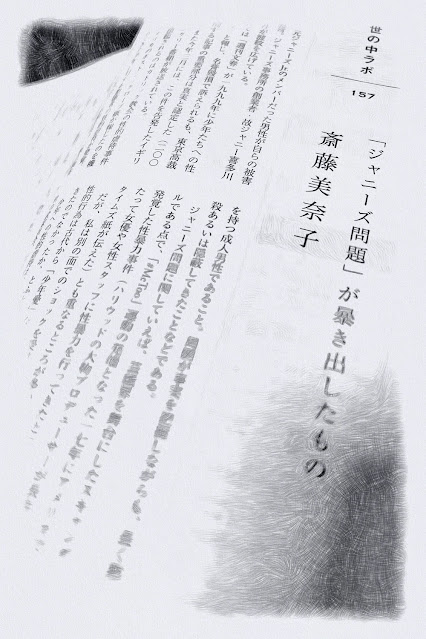 |
| 【斎藤美奈子氏の「『ジャニーズ問題』が暴き出したもの」】 |
前回からの続き。
日本古来より蔓延っている性的指向の一つとして、「少年愛」というのがある。「少年愛」とは、年上の男性もしくは女性が、年下の若年の男子に愛情を抱く性癖である。これと同じ類の性的指向として、「少女愛」というのがある。が、女性が抱く「少年愛」と「少女愛」に関しては、ここではいっさいふれない。
ジャニー喜多川氏の性的指向が、主に「少年愛」に偏っていた面があることから、ここでは男性が少年に抱く形での「少年愛」にかぎって言及していく。
ところで私を幼くして映画狂に導いてくれた映画『犬神家の一族』(1976年公開/監督:市川崑)のストーリーの中で、「衆道の契り」(しゅどうのちぎり)という言葉が出てくる。
この言葉は、登場人物である探偵の金田一耕助(演じたのは石坂浩二)が発したものだが、事件の重要人物である犬神佐兵衛翁が少年だった頃、彼を生存から救ってくれた那須神社の神官・野々宮大弐が寵愛し、この二人の関係は、「衆道の契り」で結ばれていたというのだった。
すぐに次いで金田一が「男色関係」と補足したので、まだ4歳だった私は、ごくありふれた男女の関係とは少し違うことには勘付いたが、それ以上のことはよくわからなかった。むろん後年、「男色関係」がどういう関係であるかを一般論的に理解したのだけれど、「衆道の契り」の方はなかなか生々しい言葉であり、これを小学生くらいまでに通暁するには至らなかった思い出がある。
ただしこの映画では、“絶世の美人”である野々宮珠世(演じたのは島田陽子)の美的世界で括ったため、イメージとして犬神佐兵衛翁の少年時代が美少年であったことや、おそらく青沼静馬や犬神佐清も同様にしてたぐいまれな美青年であったことへの関心は、演出上、市川崑監督の美的な感覚からは疎外されてしまったのだけれど、唯一、佐清を演じたあおい輝彦氏の美青年性だけは、おおむね映像の中で担保された感があった。
つまりもともと、憎々しく血なまぐさい復讐劇である『犬神家の一族』(原作は横溝正史)は、一族における古今の美女美男によって華麗な世界を描かねばならなかったと私は感じており、映画の中でざっくりとしか「衆道の契り」が描かれていなかったことは、その世界観からして不足な欠落を思わざるを得なかったのである。
衆道の契り
いま私は今稿の中で、ジャニー喜多川氏の根源的な罪悪となっている部分の、性的指向「少年愛」について語ろうとしている。
「少年愛」について考えようとした時、私は『犬神家の一族』の「衆道の契り」を思い出し、また皮肉なことに、あの映画に出演した元初代ジャニーズのあおい輝彦氏が、全く見事なくらいに、犬神佐兵衛翁の怨念に駆られた母・松子を心から愛する美男の役を演じ、罪をかぶって涙ぐむのである。「衆道の契り」からくる怨念がいかに恐ろしいものであるかを、映画ではなく自らの経験を滲ませていた――のではなかったかと、私は新たな想像をしてしまうのである。これは実に皮肉なことではないか。
いま呼び起こされている喜多川氏の性加害の問題の根源は、「少年愛」すなわち「衆道の契り」の罪悪のことであって、おそらく喜多川氏本人は、昭和6年生まれの“昭和1ケタ”世代であることから、観念上、いや共同生活の中の実像として、「衆道の契り」が男子間で「ありふれたもの」であった体験をしてきたのではなかったか――。何はともあれ、この「衆道の契り」について調べる必要があった。
まず「衆道」とは、若衆道の略で、これはつまり男色(男性の同性愛)を指し、若道(じゃくどう)ともいう。ちなみに若衆は若い男、若者、青年の意で、江戸時代においては元服前の少年を指す。
少年俳優の称あるいは男色を売った少年のことを陰間(かげま)ともいった。歌舞伎では、美少年の役柄を「若衆方」という。狭義においては、身分差のある同性愛を指したり、紅顔の美少年を愛する意であったりするが、実際のところは、さほどそこまで厳密なものではなかったであろう。
これに「契り」を付け足すと、情が通じた仲ということになり、肉体的に交わったことを指す。すなわち「衆道の契り」を「結ぶ」とは、男性の同性愛者で肉体的な関係(性的接触もしくは肛門性交)があったという意である。
聖職者における性犯罪
こうした「衆道の契り」に関して思考を巡らしていた時、ちょうど斎藤美奈子氏の「『ジャニーズ問題』が暴き出したもの」(筑摩書房PR誌『ちくま』6月号No.627)を読むことができた。『ちくま』の誌面においても、もはやジャニー喜多川氏の性加害問題が噴出し始めたことになる。斎藤氏がその中で、「少年愛」の文化史的側面についてふれていたので、これも参照しておこうと思う。
斎藤氏は、まず冒頭で「ジャニーズ問題」の概略について述べている。
1999年に週刊誌『週刊文春』が喜多川氏のセクハラ(少年たちへの性的虐待)を報道。この記事が当事者から名誉毀損で訴えられ、裁判になった。東京高裁は記事の核心部分を真実と認定。2004年に判決確定。今年の3月にイギリスBBCのドキュメンタリー番組が放送されたことにもふれている。
斎藤氏はその後の文面で、聖職者による性的虐待について述べ、フランスのカトリック教会では過去70年に及んで、約3,000人の神父たちが累計21万人の子どもたちに性的虐待をおこなっていた旨を挙げ、「ジャニーズ問題」との共通点として、被害者の多くが未成年の少年であり、加害者が圧倒的に権力を持った成人男性であること、事実は黙秘され、総体的に黙殺または隠蔽されてきたことなどを挙げた。
ただ斎藤氏は、仮説として、少年に対する性的行為は「少年愛」といった名目で容認され美化されてきたのではなかったか――と問うている。これはどういうことか。
つまりそういった年上の男性が少年に対して、性愛観念及び性的行為(性犯罪を含む)に及ぶといったようなことが、中世近世の武家社会や伝統的な宗教、軍隊、男子校の寄宿舎、スポーツの世界等々で蔓延っていたではないかとする仮説であり、むしろ、少年へのこれらの事実性に対する謙虚な歴史的文化的注釈である。こと性的行為に関して、斎藤氏曰く、《少女だけでなく少年も被害者になり得ることを、私たちはきちんと認識してこなかったのではあるまいか》と――。
少年愛という美学
ここで斎藤氏は、なんと稲垣足穂の『少年愛の美学』を引っ張り出してくる。
しかし――この本をちょっとばかり読んでみると、その内容に関して躊躇せざるを得なかった。
冒頭の「はしがき」では、いきなりこんな話か――とたまげたほど、ラブレー(François Rabelais)のガルガンチュア(Gargantua)に通ずる話に富み、スカトロだのお尻拭いだの、座薬だの、痔だの、浣腸器だのといった話が出てきて、《「VでもPでもなくて、A相手が面白いのだな」とひとりごちた》と語られ、語弊を恐れずにいえば、おおむね、少年のヒップ論の話ばかり出てくるのであった。
そうはいいつつも、幸か不幸かどういうわけだか、私の書棚には、以前装幀がユニークだという理由で買い求めた仏版『GARGANTUA E PANTAGRUEL』全3冊を所有している。これを読んだことはない。
斎藤氏はざっくばらんにこの稲垣氏の『少年愛の美学』のことを、《大部分は臀部ないしは「A(アヌス感覚)」に対する偏愛的な考察で、それ自体は趣味の範囲だし、同性愛を賞揚している点では意味もあろう》と述べた。
とはいえ、斎藤氏は、稲垣氏がフロイトの弁「教師や監督者の中に小児を性的に誘惑する者が非常に多いのは、その好機会が与えられているという理由だけによって説明される」という《ある境位に恵まれない限り、何とも手の打ち様のないものである》としたいいっぷりに対し、《いい気なものである》と非難糾弾している点は見逃せない。
男性の権力者が、教え子の男児を性的ターゲットとして狙いやすいのは、一般的に男性が女児を狙うよりも、はるかにその情景が見極めづらくわかりにくい、見えにくい、ということと同時に、権力者が庇護されるべきであろうという権威的対象者への敬う通念あるいは先入観があるからだろう。しかし、そうしたところで男性が男子に対する性犯罪がおこなわれている可能性が高いのである。
そのほか斎藤氏は、丹尾安典著『男色の景色』や井伏鱒二の『雞肋集』などから、男同士の上下関係の場で起きた男色の実録話にふれ、「硬派」な武士的男色と文弱の美少年などの少年同士の同性愛についてそれぞれ述べ、対等のプラトニックな性愛というのと、支配被支配の関係における同意のない強引な性的交渉とは一線を画したものとして、この手の話が十把一絡げに同性愛者を糾弾するようなことがないよう配慮した文脈となっていた。
§
斎藤氏が最後に述べたのは、2017年施行の刑法改正の、男性への強制性交罪(※正しくは強制性交等罪であるが、2023年の改正で名称は「不同意性交等罪」と変わった)についてである。もと女性への強姦=強姦罪が、なんと110年ぶりに改正され、男性の口腔及び肛門への陰茎挿入も対象となった。男性が男性に対する同意のない強制的な性交が、これまで半ば「放置」されてきたことへの言及だ。
ところで、ジャニーズ事務所(現SMILE-UP.)の会社としてのその後の対応やその他諸々の報道内容に関しては、時々刻々とアップデートされていくので、ここではそれらを説明することをあえて避けた。
「少年愛」に絡んだ性的虐待の問題が、これほど大きくクローズアップされたことはないだろう。
しかし、歴史的にみて、「少年愛」や「衆道の契り」といった習俗的側面が根底にあったにせよ、一個人である喜多川氏の性的加害の事実は免れるものではなく、断固として否定されるべきであり、被害者の救済策が直ちに必要であることは明白である。当然ながら、ジャニーズ事務所(現SMILE-UP.)の問題としてだけではなく、古今の習俗性から鑑みて、学校や塾、スポーツクラブ、障がい者施設、病院、刑務所、あるいは家庭といったところでのこの手の児童虐待がおこなわれていないかどうか、総点検すべきであろうと思われる。
以上をもってとりあえず、3回にわたって綴った「かつてジャニーズはメディアの寵児だった」を脱稿する。また大きな進展があった際には、ふたたびこのタイトルが浮上することを宣告しておきたい。
〈4〉に続く。


コメント