約半年ぶりになる当ブログの不定期シリーズ「お茶とサブ・カルチャーのアーティクル」。前回は今年の5月。mas氏が2001年に訪れた上高地への旅行記であった。今回はmas氏の「中国茶のオルタナティブ」から。それも恐縮ながら、「お茶とサブ・カルチャーのアーティクル〈五〉」の“復習編”なるもの。初心に戻って中国茶を飲み、茶の精神論について雑学的に語っていきたい。
ちなみにmas氏に関しては、当ブログ「お茶とサブ・カルチャーのアーティクル〈一〉」をご参照いただき、「中国茶のオルタナティブ」は彼が2000年から2001年にかけて、ネットのホームページで更新していたコラムのことであり、私が当時、そのコラムを読んで中国茶についての深い造詣をつまみ取り、なおかつmas氏の“クラシック・カメラ愛”を初めとする数々のサブカルに私淑したことを敢えて冒頭で述べておく。
残念なことに、mas氏の「中国茶のオルタナティブ」のホームページは、とうの昔に削除されてしまっており、現在、ネット上にそれにあたるミラーサイトは存在しないものと思われる。
残念なことに、mas氏の「中国茶のオルタナティブ」のホームページは、とうの昔に削除されてしまっており、現在、ネット上にそれにあたるミラーサイトは存在しないものと思われる。
§
〈五〉で紹介した、「中国茶のオルタナティブ」のその六。「『茶』をどのように発音するか。誤読の歴史。」。その復習のため、もう一度ここに全文を掲載しておく。
《中国では、チャー、インドではチャイ、日本では、チャ/サ、イギリスでは、ティーTea、フランスではテThe、ブラジルではシャーcha。
もちろん、いずれも語源は同じ、中国人が「茶」を発音した音。
しかし、発音した中国人はどこの地方で、何世紀だったのか? その音をアルファベット表記した者の母国語は? そして、そのアルファベット表記をさらに違う母国語を持つ者が読み、その音をアルファベット表記したらどうなったのか? そんな誤読の歴史の中で似てるけど違う表記/発音が生まれた。
そして、飲み方についてもしかり。ミルクを入れてみたり、バターを入れてみたり、石臼で挽いてみたり、焙煎してみたり、そんな誤読の歴史の中で茶であることは変わりのないのに様々なスタイルが生まれた。
初めてミルクティーを作った人なんかはかなり変人だったと思う。それとも、すごく猫舌で手元にあった冷えた牛乳を入れてみたとか、そんなもんだったのかな。あ、あれはチャイの変形版か。インドだと水より牛乳か。。。
そういえば、香港あたりのファミレスふう大衆食堂に入ると、コーヒーと紅茶のハーフ・アンド・ハーフとか、レモンコーヒーとか、そういうおもしろ飲み物があるね。あのチャレンジ精神は素晴らしいと思う。あと、韓国のコッピ( あえてコッピ、Coffeeね) はインスタントコーヒー粉末を麦茶で割ったりするんでしょ? それにインドのコーヒーはやはりインスタントコーヒーをチャイで割ったものなんでしょ? ある意味、フレイバー・ティーと言えないこともない。おもしろいね》
(mas氏「中国茶のオルタナティブ」より引用)
そもそもmas氏の日本語の文体が、どことなく不安げで調子がゆらいでおり、なにか日本列島ではない別の大陸の人であったり、別の風土のそれを感じてしまうのは、私のうがった見方であろうか。これについて探るのはまだ時期尚早として、“奇妙な謎”のまま残しておくことにする。そのことはともかく、彼はここで、「茶」の発音について言及しているのだが、それについて私は〈五〉で、英語のteaに関して述べた。
近頃、パソコンやスマホの翻訳アプリでは、外国語を訳して表示してくれるだけではなく、それが人工知能と言えるものなのかどうか知らないが、訳した言葉を音声で発音してくれたりするので、とても便利で有り難い。
実際に翻訳アプリを使って、「茶」を中国語で発音させてみると、まさしくmas氏が述べているようにチャーであり、ヒンディー語ではチャイであり、英国ではティー、フランスではルテ(ルチ)、ポルトガル語ではシャーなのである。さらに面白がって遊んでみると、アルバニア語ではチャーイ、エストニア語ではベー、カタルーニャ語ではテー。クロアチア語ではチャーイ、タミル語ではティーレイ、ベトナム語ではチャーア。ポーランド語ではヘルバータ、ラトビア語ではテーヤ、ロシア語ではチャーイ――と、日本語の“チャ”(Cha=茶)とはことごとく違って発音される。
少々興奮気味になった。気分を落ち着かせるべく、中国茶を飲むことにした。用意したのは、「白芽奇蘭」(はくがきらん)であった。
「白芽奇蘭」は福建省の平和県の青茶で、「ランの香りがする」という半発酵茶である。気分を落ち着かせる――という意味合いにおいては、日本茶でも充分そういう効能があるが、「香りを愉しむ」という副産物的悦楽が、中国茶にはのべつ幕無しに――ある。これは世界のどんな種類のお茶が束にかかっても、中国茶のそれにはかなわない。
ところで「白芽奇蘭」は、清代の乾隆年間(1736年~1796年)につくられた茶である――というようなことが、中国茶に詳しい本の工藤佳治・俞向紅編『中国茶図鑑』(文春新書)で書かれてある。《芳醇で馥郁としてボディのある味》という表現も。実際に私が飲んでみると、確かにランの花の馥郁とした香りがしたし、〈これぞまさに中国四千年の味!〉――と軽はずみで意味不明な表現を思わず口に出してしまいそうになるのだけれど、ここはひとつ落ち着いてみよう。
茶の伝播の歴史については、岡倉覚三(岡倉天心)著『茶の本』(岩波文庫)に拠るが、16世紀末にオランダ人が東洋における灌木の葉から飲料がつくられることを報じた、とあり、1610年にオランダの東インド会社の船が西欧に初めて茶を輸入した、ということになっている。この流れはフランス、ロシアへと続き、1650年には英国にも茶が伝わる。つまりオランダのゼーイから始まって、フランスでのルテとなり、ロシアのチャーイとなって茶の飲料は世界中で歓迎されたわけだが、「白芽奇蘭」はそれよりもずっと後の新興茶ということになる。言うなれば、モダンな発想のもとに生まれた青茶――ということになるのかも知れない。
茶の伝播の歴史については、岡倉覚三(岡倉天心)著『茶の本』(岩波文庫)に拠るが、16世紀末にオランダ人が東洋における灌木の葉から飲料がつくられることを報じた、とあり、1610年にオランダの東インド会社の船が西欧に初めて茶を輸入した、ということになっている。この流れはフランス、ロシアへと続き、1650年には英国にも茶が伝わる。つまりオランダのゼーイから始まって、フランスでのルテとなり、ロシアのチャーイとなって茶の飲料は世界中で歓迎されたわけだが、「白芽奇蘭」はそれよりもずっと後の新興茶ということになる。言うなれば、モダンな発想のもとに生まれた青茶――ということになるのかも知れない。
ところで、mas氏はさらに、茶にミルクを入れたり、バターを入れたり、石臼で挽いてみたりといった茶のアレンジメントのrevolution、あるいはtransformation、あるいはvariation――といったことにも言及していて興味深い。
最近、自販機の炭酸飲料などの商品を眺めても分かるように、ハーフ・アンド・ハーフの商品が増えているように思える。日本には多様な外国人がいる――という側面からしても、もともと日本人の感覚には無かったような、異なる国々の“テイスト文化”の影響(需要)があって、飲料系におけるハーフ・アンド・ハーフの(供給の)勢いが止まらない、ということはもしかすると言えるのではないか。
しかしながら、mas氏はそれを「誤読の歴史」と受け止めている点で、冷静さを失ってはいない。要するに、茶の世界的な波及の背景には、そうした“誤読”(misreading)という広い意味での「必要悪」が混在し、発展してきた――という解釈のようである。
しかしながら、mas氏はそれを「誤読の歴史」と受け止めている点で、冷静さを失ってはいない。要するに、茶の世界的な波及の背景には、そうした“誤読”(misreading)という広い意味での「必要悪」が混在し、発展してきた――という解釈のようである。
文化的な「必要悪」を断つのではなく、あくまで“誤読”の範疇として受け流し、あるいはそれを許容し、その文化なり歴史なりを未来永劫に拡張していく観念。その術――すなわち人類の、ある意味においてつっけんどんな、「包容力のある精神」を、今一度現代にあてはめて甦らせることは可能かどうか、様々な事案の文化的・政治的・外交的失敗の中から、炙り出してみなければならないのではないだろうか。
そうしてよくよく我々現代人は、膨大なる《過去》を振り返り、あらゆる面で相互に省みなければならないのではないか、と思うのである。“誤読”に寛容でない文化や伝統なるものは、たかだが数十年で廃れる。寿命が尽きるのが早い。その反射の精神論が、茶の歴史における経済功利と優雅の普遍性を示している。茶は決して古いものではなく、まったく新しい精神論であり、新しい悦楽なのだ。だから私はそこに惹かれつつ、茶を飲む。〈十〉に続く。
そうしてよくよく我々現代人は、膨大なる《過去》を振り返り、あらゆる面で相互に省みなければならないのではないか、と思うのである。“誤読”に寛容でない文化や伝統なるものは、たかだが数十年で廃れる。寿命が尽きるのが早い。その反射の精神論が、茶の歴史における経済功利と優雅の普遍性を示している。茶は決して古いものではなく、まったく新しい精神論であり、新しい悦楽なのだ。だから私はそこに惹かれつつ、茶を飲む。〈十〉に続く。

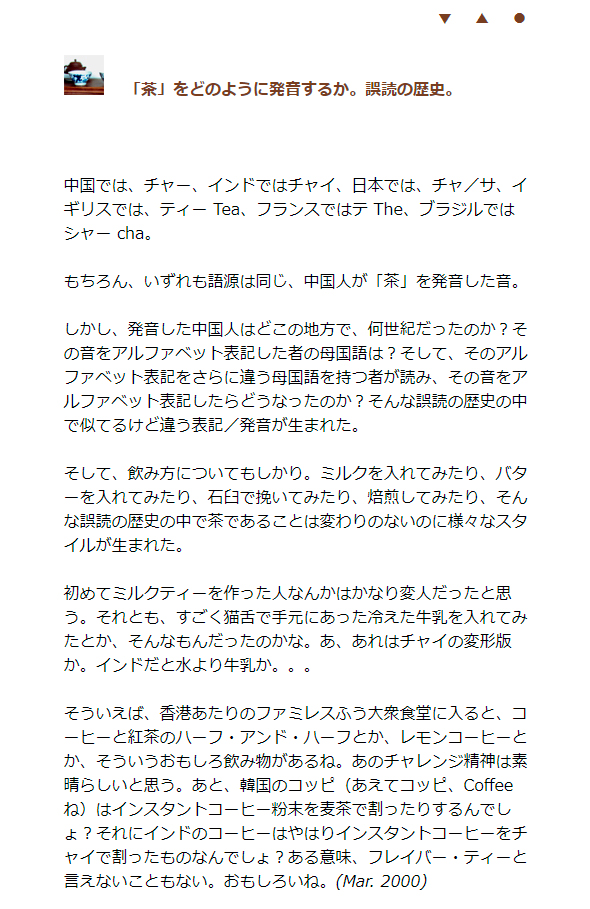

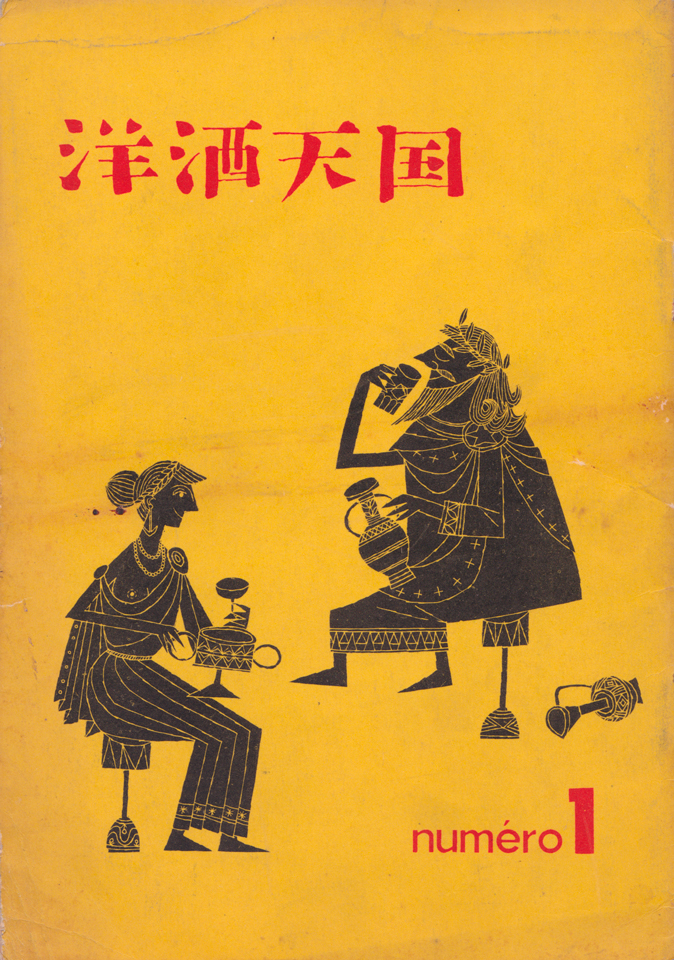

コメント