 |
| 【世界最古の蒸留所が誇るアイリッシュ・ウイスキー「キルベガン」】 |
朝日新聞が毎月第1日曜日に発行する特別紙面[朝日新聞グローブ](GLOBE)のNo.245は、興味深いウイスキー特集だった。その紙面のトップページにあった写真に、思わず私は眼を奪われたのだ。それは、ウイスキー・グラスに注がれた琥珀色の液体が、揚々たる深い海と化し、そこに突き出た南極大陸の氷山を思わせる氷の塊の、なんとも美しい風景――。
この世に存在する桃源郷とは、そのようなものなのだろうか。写真の下に、それとなく村上春樹氏の言葉が添えられていた。《あらゆる酒の中ではウィスキーのオン・ザ・ロックが視覚的にいちばん美しい》(『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド(上)』新潮文庫)。
私はしたたかにこのウイスキー特集を読んでから、ジェイムズ・ジョイス(James Joyce)の本を開いた。ウイスキーのオン・ザ・ロックがこの世で最も美しい酒の姿であるとするならば、ジョイスの小説は、男にとっても女にとっても、破廉恥で最も穢らわしい毛皮をはいだ自己の内面の姿を、目の前の鏡の中に見出す瞬間を与えてくれるものであり、その傍らに寄り添うウイスキーは、みすぼらしい本当の《私自身》と“親しい友”でいてくれる、最良の飲み物なのである。
ゆえに私は、心からウイスキーを愛している。
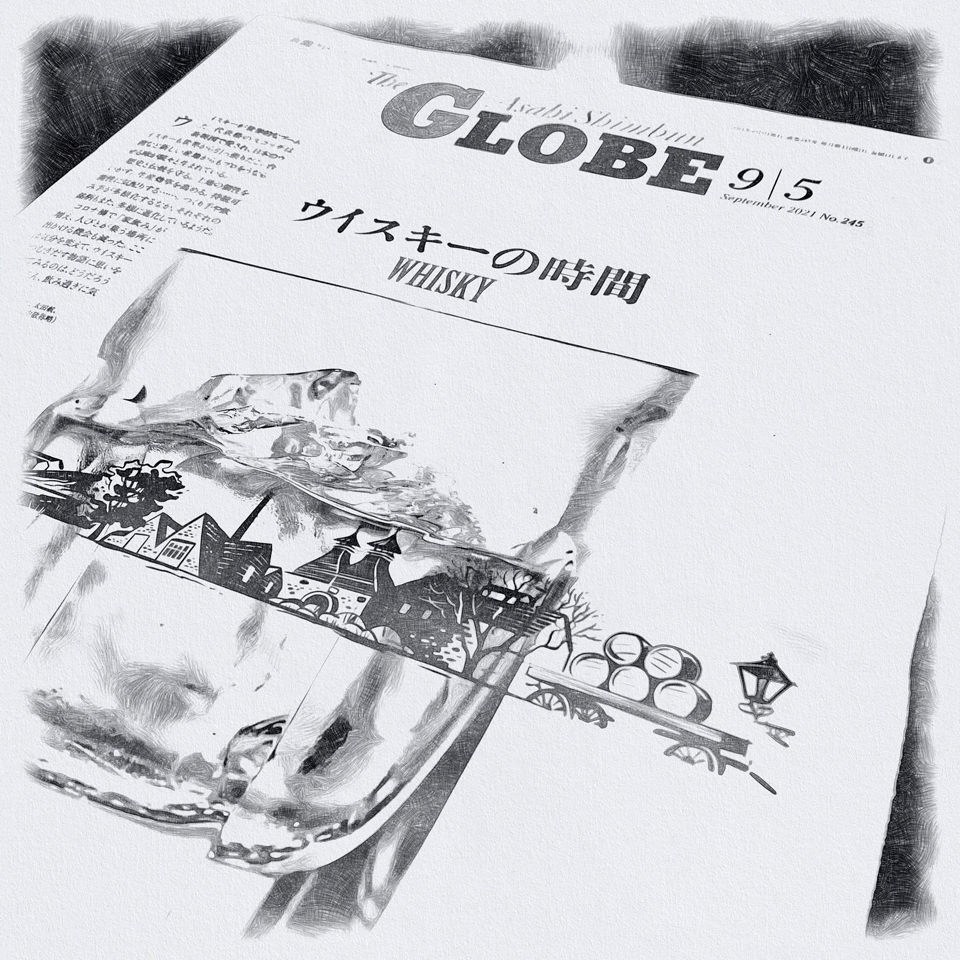 |
| 【[朝日新聞グローブ]No.245「ウイスキーの時間」】 |
GLOBEの「ウイスキーの時間」
特別紙面のウイスキー特集のメインテーマは、「ウイスキーの時間」。コロナ禍で「家飲み」が増えたという。どの国においても、家族や友人知人と共にバーやレストランなどで酒を飲み交わす機会が減ったというわけだ。そんなご時世でも尚、ウイスキーは世界的なブームだそうである。むしろビールやワインとは違い、ウイスキーはもともと孤独を愛する人々が嗜む酒の代名詞であったから、「家飲み」の需要が底上げしたのかも知れない。
とは言いつつも、ウイスキーは近頃、ハイボールという飲み方でもたいへん愛されてきているから、女性が好んで“軽くウイスキーを飲む”という機会が増えているせいなのだろう。
紙面全体の内容を大雑把に要約すれば、スコッチの生まれ故郷以外の国でも――勿論日本も含まれる――新しいウイスキーが次々と誕生しているという。
ここでいう新しいウイスキーとは、伝統的な技法を重んじた“正統派”と呼んでいい新興ウイスキー、もう一方では、いわゆる異種の、新たな製造技法によって効率良く生産されているウイスキー。どちらにしても、愛飲家のみならず若い人たちにもウイスキーが好まれるようになってきて、確たる「ウイスキーの時間」は、この21世紀の時代に意外なほど、おおぶりの豊饒と変革期をもたらしている――と言っても過言ではないのではないか。
伝統と革新という話でいうと、スコットランドでも次々と新しいディスティラリー(蒸留所)が生まれているようだ。
エディンバラとイングランドとの境にある村に2018年、ボーダーズ蒸留所が開業した。朝日新聞グローブの記者の取材記事で、経営者ジョン・フォーダイス氏が試飲をさせてくれた旨の話を読んだのである。《舌に焼けつくようなアルコールの刺激》を感じた、と記者は述べる。華やかな香りはあったという。
このディスティラリーのスコッチは3年ほど寝かされており、スコッチを名乗れる段階にきているようだが、まだ若干“若い”――ということなのだろう。納得できる味に仕上がっているかどうか、現場の酒職人は気が抜けない。
ボーダーズの経営に関しては、ITを駆使したフィンテック・サービスによって、市場への安定的な供給による経営活動を維持しているという。スコットランドでは、140近くディスティラリーが存在し、ここのところ新しいディスティラリーの開設や閉鎖されていた所の復活が相次いでいるらしい。
やはりそれだけ、世界的にウイスキー狂の、とりわけスコッチの需要が高まってきているせいなのだろう。ウイスキーとは何ぞや? スコッチとはいったいどんなウイスキーなのか? といった価値ある情報がインターネットで交錯している現代の日常生活において、ある意味、スコッチの価値がようやく広まった、あるいは最盛期を迎えたと言っていいのかも知れない。
ラボ・ウイスキーとアイラ似の国産ウイスキー
さらに「ウイスキーの時間」を読んでいく。
異種すなわち革新のウイスキーの話題では、“ラボ・ウイスキー”と称される、熟成にかかる時間を大幅に短縮したインスタント・ウイスキーが紹介されていた。もし、高級ウイスキーの味と香りがインスタント・ウイスキーで再現できるとなったら、どうであろうか。
サンフランシスコの企業Endless Westの共同創業者でCEOのアレック・リーはまだ若く30代。ハイテクを駆使し、熟成の時間を短縮した生産効率性の高いウイスキーを開発した。「Glyph」という銘柄のウイスキーの第1弾「85H」が、2018年に発売されている。
「Glyph」の製法は、天然の植物や果物そして酵母から、熟成後のウイスキーと同じ成分を抽出して混ぜ合わせるのだという。本来なら年単位で熟成するウイスキーの味を、たった1日でつくりだすのだとか。
このラボ的な製法により、熟成工程を経ないから、樽木材の消費もなく経済的で、必要な水の量や農地の広さも伝統的な製法の10分の1で済むのだという。現在のところ、味や香りの評価は意見が分かれるところではあるが、世界的にウイスキー全般が、とりわけ熟成に時間のかかる高級ウイスキーが枯渇し高騰する現状を見ても、将来こうしたインスタント・ウイスキーの需要は大いに高まるはずだ。むしろ高級ウイスキーの安定的な供給の付与に、インスタント・ウイスキーが市場で貢献できる未来はやってくるのではないかと思われる。
日本の北海道の厚岸町には、地産地消の製法で新しいウイスキー造りを始めたディスティラリーがある。2016年に製造を開始した、厚岸蒸留所である。今年の5月に発売された同蒸留所のシングルモルト・ウイスキー「芒種」は、1万本がすぐに売り切れたという。
環境はアイラ島(当ブログ「アイラ島憧憬―スコッチの源流」参照)によく似ているとのこと。夏は涼しく湿度が高く、ピート(泥炭)も取れるという。本場アイラのモルト・ウイスキーを日本でつくりたかったと、蒸留所を所有する堅展実業の樋田恵一社長は語っている。原料となる大麦は厚岸産、水はホマカイ川、ピートは別寒辺牛湿原の周辺のもの。樽の原料のミズナラも地元産だ。
こうした北海道の原野で、アイラ・ウイスキーによく似た、親しみを感じさせるクラフト・ウイスキーができるとは、驚きである。ウイスキーの製造には、たいへん長い時間と労力と、そして莫大な資金が必要である。質のよい酒は、世界中の愛飲家の目にとまり、味覚を唸らせ、評価される。しかし、そうした「良い」と評価される酒の品質を保つには、製造の試行錯誤や経済状況における苦難の荒波を覚悟しなければならないだろう。ウイスキーづくりは必ずしも効率性の高い商品とはならないゆえに、いかに品質を保ち、持続可能なシステムの構築ができるかが鍵となる。そういう意味で、私は厚岸蒸留所の志に敬意を表し、今後もこのディスティラリーのウイスキーを刮目していきたいと思っている。
ウイスキーと共にジョイスの小説を
さみしいと思える夜を迎えたら、グラスに注いだワン・フィンガーのウイスキーを味わうがいい。アイリッシュが最適だ。そうしてグラスを片手に、今宵はジョイスを読むのだと――決め込むのである。
「KILBEGGAN」(キルベガン)は実に柔らかく、優しい。
1757年創業で“世界最古の蒸留所”として知られるキルベガン・ディスティラリーは、アイルランドの首都ダブリンから西へ70kmほどのウェストミーズ、キルベガンにある。できうるなら、ぜひともGoogleマップを使って、このディスティラリーあたりの、のどかな田舎風景を堪能していただきたい。
アイリッシュ・ウイスキーのうち、特にブレンデッドは、スコッチよりマイルドな味わいを感じられるものが多い。したがって、普段さほどウイスキーに飲み慣れていない者は、アイリッシュを嗜むといいだろう。その場合、「JEMSON」(ジェムソン)や「TULLAMORE DEW」(タラモアデュー)をお薦めする。
「KILBEGGAN」も比較的、ウイスキー特有の刺激が軽少で柔らかい方だ。口から喉を通り抜けるあいだにわずかなアイリッシュらしい柔らかさを感じた後、胃の中にすうっと消えてゆく。スコッチのようなじわじわとした刺激(これをかつて男性的と称した)が少なく感じられ、ケンタッキー・バーボンのようなアメリカ人らしいがっつりとした甘味も少ない。しかしそれでいて、何かしらの存在感を味覚に示しているのだから、それはまさにケルト的な実存――という他はない。ともかくウイスキーとは、銘柄の持つ価値以上に哲学的であり、神秘的であり、その神秘主義者の好む酒として、気負わず奥が深いものなのだ。
さて、ジョイスを読む――。
がっつりと『フィネガンズ・ウェイク』などを読む必要はない。私がアイリッシュ・ウイスキーにちなんで読み耽ったのは、柳瀬尚紀訳の『ダブリナーズ』(新潮文庫)の「小さな雲」(“A Little Cloud”)であった。
妻子ある30代の男リトル・チャンドラーは、ダブリン市内の(グラッタン橋を渡った先の)コーレスのバーで、馴染み深い若き青年イグネイシャス・ガラハーと8年ぶりの再会を果たす。ガラハーはロンドンに行って新聞記者となり、出世して休暇のために束の間、ダブリンに帰ってきたのだった。
リトル・チャンドラーは会う直前に密かに、自分には文学的いや詩人としての才能があるのではないかと想像をめぐらせ、その才能をガラハーの力を借りて売り込めば、人生が華開けるのではないかと夢見ていた。そうして彼らは酒場で会い――全く当然のことながら――酒を飲み交わす。言うまでもなくそれは、ウイスキーである。さらに言えばそれは、アイリッシュに違いない。ウイスキーと言えばここでは、アイリッシュ・ウイスキーに決まっているのである。
リトル・チャンドラーはガラハーの話――すなわちロンドンでのお気楽な出世話――に興奮し、夜の遊びの話題にも率先して耳を傾け、聞き惚れていた。しかし、ふと気がつけば、ガラハーは抜け殻のような、以前のガラハーではないように思えてきた。やがて明らかに、リトル・チャンドラーは、かつて善き友人であったガラハーに失望に似た気持ちを抱くのだった。
チャンドラーが自宅に戻ると、家庭内の苦々しい喧噪が待っていた。妻は機嫌が悪く、自分に対する態度も決して良くない。チャンドラーが買って帰るのを忘れた物を買いに、妻は外へ出かける。チャンドラーは気弱な思いに耽る。なぜ自分はこの女と結婚してしまったのだろうかと――。そうして野心に浸りたく、バイロンの詩を読み出す。読めば読むほどに、自分の出世もほとんど潰えた気がしてくる。バイロンの憂鬱は自分への憂鬱さだ。
そのうち、赤ん坊が泣き出す。思わず苛立って、赤ん坊を怒鳴りつける。さらに赤ん坊が激しく泣きじゃくる最中、妻が帰ってくる。その様子に驚く――。
なんなの? …この子になにをしたのよ?…
リトル・チャンドラーはそうした自身のうだつが上がらない生活に、あるいはもっと、自身の宿命のようなものの退屈さに、嫌気がさした――挙げ句、そののたうち回っている憂鬱な自分に対しても、後悔の念を抱く。根深いカトリックへの敬虔と質素さに阻まれていながら、それに諍おうとしている自己の態度にも反吐が出るのだった。
ここにジョイスの小説の庶民的でありつつ、その庶民感情を揺さぶる文学的萌芽が内在していて、私はすこぶる好きなのだ。ダブリンはジョイスの映し鏡であり、そのダブリンは田舎の中の都会であるという、その田舎的なものから脱却したいという人々の憧れと憂いとを、忠実に、静かな力強さをもって表現し、まさにそれこそがアイルランド人であるという明晰さがジョイスには感じられる。
古代ヨーロッパの深奥を冷徹に見つめ、それを諧謔に仕立て、現代文学に身を置いた偉業。若き頃のジョイスは親しみ深い街ダブリンを、《多くの人間が都会だと思っている半身不随もしくは中風》とまで述べている。そんなダブリンの人々を描こうとしたこの短篇小説集である『ダブリナーズ』には、見事に憎々しいまでに、市民の屈託ある苦悩と哀しみがにじみ出ていて、温かみが感じられる。
とろんとした気分でウイスキーの琥珀色を眺めていれば、ジョイスの世界がたちまち理解できるだろう。迷うことはない。そこにウイスキーがあるのなら、飲めばいい。


コメント