 |
| 【梅田晴夫著『ひまつぶしの本 無我夢中に楽しむ法』】 |
個人的にこれは、長年の夢であった。若輩の20代の時分に、この3つの作品を頭に刻み込んで制覇しよう――などと思いついたものの、ほとんど手を付けられずにいた(当ブログ「ヘチマコロンから思い出すこと」参照)。余談になるが、個人的に関心があったにもかかわらず、手を付けられずにいた映画は他にもある。佐野史郎さん主演の石井輝男監督の『つげ義春ワールド ゲンセンカン主人』である。
鈴木清順監督の三部作について書き連ねる前に、かの時代(1912年~26年の大正時代のあたり)の日本人の文化やセクシュアリティ、風俗について、ある程度知識が必要ではないか――という考えで、そうしたことに関連した文献を調べ始めた。ところがこれが困ったことに、大正期の一般大衆の文化やセクシュアリティに関する書物等は、全く茫々たる湖沼(あるいは内海)と化しており、原書自体が存在していることも多々あって、いったいどこから手を付ければいいのか、逆にペンを書き進めることができずに、窮地に立たされてしまったわけである。
「ペンを書き進めることができず」という言い方は、調べのメモに限った話であって、半ば比喩である。ドラフト以降は「文字を打ち込むことができず」というのが正しい表現になる。
そんなことはともかく、いわゆる「大正浪漫」(これは「大正ロマン」としてもいいし、「大正ロマネスク」と言い換えてもかまわない)に括られる、大正期のセクシュアリティと風俗に関しては、その様態なり様式なりを、江戸東京学の観点で鋭角的に絞らざるを得なくなった。しかも「大正浪漫」という観念の通奏低音は、現代にいたるまでその仔細が伸びていて、枚挙に暇がない。
昭和の戦後から今日の令和にいたっても、その和洋折衷の文化的素地が、気づかぬところで社会的な影響を及ぼしていることがあり、あらためて驚かされる。その一種の現象が、近年においては、大正期を描いた吾峠呼世晴の『鬼滅の刃』ブームとしてにじみ出ている。
近年――という括りを解いてしまえば、幼児や子ども向けのお菓子のパッケージに、その「大正浪漫」の文化が面々と受け継がれていることに気づくだろう。江崎グリコのあの“ゴールインのポーズ”は、創業者の江崎利一氏が子ども達の健康促進を考え、“文化的滋養菓子”としてキャラメルを考案し、そのパッケージとしてたいへん有名である。また、森永製菓のミルクキャラメルは、創業明治32年当時はバラ売りで、大正期になって今とおおむね変わらないパッケージになっている。言うなれば大正期における大正デモクラシーは、子ども文化のファンタジアであったのだ。
現代の日本人にとっても、「大正浪漫」的文化は、古い概念として駆逐されることなくすんなりと受け入れられる観念的世界となっており、むしろやはりそれは、面々と続いているロマンティシズムの通奏低音なのである。
大正期の江戸文化
ここでは大正期おける、日本人のセクシュアリティと風俗の話に絞りたい。
セクシュアリティに係る知識の源の多くは、明治以降とくに大正期から昭和初期にかけての浅草六区の娯楽街の繁栄などから、落語の世界のそれに起因していると推察できる。上方落語については調べが及んでいないから、ここではその言及を避ける。
江戸期のセクシュアリティの通奏低音をひきずって、それが大正期前後において浅草が発信源となっていることは、踏まえておく必要がある。そうした江戸の文化的潮流が西洋の文化と濃厚に混ざり合ってできたのが、「大正浪漫」であり「大正ロマンチシズム」である。私はあくまで、江戸東京学の観点に絞って述べている。
オフェル・シャガン氏の『わらう春画』(朝日新書)を読むと、歌川国貞や河鍋暁斎などの春画から垣間見られる江戸期の風俗が、いかに豊かで容易ならざるものであったかが分かる。すなわち、婚姻にかかわる風習や制度が今の時代よりもはるかに封建的であったがゆえに、郭(くるわ、遊郭)の存在が溶け込んだ「性文化の進捗」が、意外なほど聡明かつ多様であからさまに悉知されていたし、これにおいては、現代人にとっての“性の風刺画”と見えなくもない側面である。
このようなことから、“大正浪漫”を知るうえで、和洋折衷あるいは和漢洋才の片側半分――江戸期の世俗や風習――が、大正モダニズムに大きな役割(=民本主義の帰着点)を果たしていたことは、踏まえておかなければならないだろう。
江戸の性文化について語り出すと、全くきりがない。
その方面の話は、良きにつけ悪しきにつけ、実に豊かで興味深いものだ。とても字数が足りなくなってしまいそうで、はて、どうしたものか――と思っていた矢先、脚本家・フランス文学の翻訳家・随筆家で知られる梅田晴夫氏の名著『ひまつぶしの本 無我夢中に楽しむ法』(KKベストセラーズ/1974年初版)に出くわしたのだった。この本に、「ポルノ・クロスワード」と題されたクロスワードパズルが掲載されていて、〈これ幸い、一石二鳥だ〉と膝を打った次第である。
 |
| 【梅田氏の「ポルノ・クロスワード」を参考にして作成】 |
梅田晴夫のポルノ・クロスワード
《クロスワードは古くからヨーロッパやアメリカの紳士たちに愛好され、その結果クロスワードに熱中のあまり、夫人への奉仕がおろそかになって物議をかもすようなことも多くなり、切手蒐集とクロスワード・パズルは西欧の人妻たちの“敵”とさえ言われるようになっている。そのために“切手寡婦”、“クロスワード寡婦”というような言葉まで出来ているほどなのである。
わが国でもクロスワードはある程度さかんであるといえるが、欧米のそれの人気にくらべれば、月とスッポンとでもいうほかはない》
(梅田晴夫著『ひまつぶしの本 無我夢中に楽しむ法』より引用)
クロスワードパズルについて、梅田氏はそう語る。
寡婦(かふ)とは、女やもめ――つまり夫をうしなった未亡人を指す言葉であるが、“クロスワード寡婦”と言った場合、「夫をうしなった未亡人」がクロスワードに夢中になるのではなくて、「夫がクロスワードパズルに熱中する」あまり、妻の相手をせず、ほとんど寡婦同然の家庭状況に陥ったその「御婦人」を意味している。不憫というのか、実に切ない流行語ではある。
ちなみに、スタンリー・ドーネン監督の映画『シャレード』を観ると、ヨーロッパ人は切手蒐集が好きなのだなというのがよく分かる。あの映画に、切手市のシーンが出てくる。もし、クロスワードもこれと同じだとするならば、やはり日本の人気とは月とスッポン――ということになるだろう。そうして梅田氏は、「ポルノ・クロスワード」を作成した経緯について以下のように述べている。
《文豪には洋の東西を問わず、若き日または老後に書かれた、いわゆる“秘稿”というものが多く、その多くはやはり“春文”だといわれている。
永井荷風作と信じられている『四畳半襖の下張り』などの場合でも、それはやがて文豪の死後に遺され世人の目を瞠らせることを計算に入れて、ひそかに精魂こめて執筆された名作であって、たとえそれが永井荷風の作ではないとしても、これはやはり“文豪級”の才能の持主の書いたものにまちがいない。そこで平素の訓練としてのポルノ・クロスワードを試みて、自分の性的語彙を豊富にしておいたらどうであろうか》
(梅田晴夫著『ひまつぶしの本 無我夢中に楽しむ法』より引用)
『四畳半襖の下張り』は、今でも永井荷風の作として、はっきりと伝えられている。金阜山人の手記あるいは作という立て付けになっているのは、これが“秘稿”であるがゆえである。しかし今ここで、『四畳半襖の下張り』の話を進めるわけにはいかない。
なんといってもクロスワードパズルである。梅田氏はそれを、「ポルノ・クロスワード」と称している。が、決して中味は下品なポルノではないのだ。江戸期のセクシュアリティと近代以降に扱われている性用語における、言わば和漢洋才の由緒正しい性用語集(語録)となっており、誤解を招く恐れがあるから、むしろこれは「性のクロスワードパズル」と称した方がいいだろう。したがって、私はこれをそう呼ぶことにしている。
言うなれば、鈴木清順監督の映画=“(大正)浪漫三部作”を心底堪能するための予備知識として、このクロスワードパズルを解き、これを取っ掛かりにしてその方面の教養を深めていく――というのがいい。これをこのまま、古本の中に閉じ込めておくのは勿体ない。そう思ったので、私はこれを模写して作図してみたわけである。ぜひ関心のある方は、「性のクロスワードパズル」に挑戦していただきたい。
尚、解答は、敢えてどこにも記さないことにする。それはちょっといじわるだ、困ると思うかも知れないが、いまどきネット検索で調べるのは容易いし、むしろ正解を求めるべく、じっくりと頭を抱えて取っ組み合うのがいいではないか――と思うのだ。言葉からしたたるそのエッセンスを掻き集め、時間をかけて集成していくことも大事である。そういう方針なので、なにとぞお許し願いたい。
四十八手は相撲用語だった?
性用語の空欄を埋めるクロスワードパズルとしては、梅田氏の提示した「性のクロスワードパズル」は、たいへん難易度が高い。
ちょっと分かりづらいワードもあるので、一箇所ヒントを申し上げてみる。タテのカギの2の、「ショートではない」とは、いったいなんのことか――。
この場合のショートというのは、つまり「休憩」のことで、転じてロング=宿泊のことを平易な言い方で何と言うか――というクイズなのである。男女の色めくサービス営業の料金体系に関連したクロスワードということになろうか。
ところで「四十八手」というのは、ここではむろん、性交体位のそれを指していることは言うまでもない。ただしもともとは、相撲の勝負を決める手の48種だったということを知っている人は、果たしてどれだけいるだろうか。四十八は縁起のいい定数で、江戸期によく汎用されたらしい。もともとである相撲の方の「四十八手」は一般的には忘れられ、性交体位の「四十八手」はその言葉として知っているという人の方が、圧倒的に多いのではないか。もはやこのワードの旗手は、そちらの色めいた世界に占有されつつある。
江戸期の性用語に関しては、永井義男著『江戸の性語辞典』(朝日新書)が詳しい。
永井氏は「四十八手」の48種そのものについて、あくまで俗説で、どの体位が含まれるのかは諸説あって明らかではないと述べている。しかしながら、性交体位の「四十八手」とやらを相撲のそれに倣って最初に開発したのは、どうやら江戸期の浮世絵師・菱川師宣らしい。あの「見返り美人図」の肉筆画を描いた名匠である。
これがまた、難儀を要するのであった。永井氏が言うように、「四十八手」はあまりに諸説ありすぎた。ありすぎて、このクロスワードの解答となっているワードが、「四十八手」に出てこないものもある。江戸期の性交体位は四十八手にとどまらず、ということの傍証なのだが、こうなると、専らそういう関連の文献に頼らざるを得ない始末である。
あまりの奥深さに、私は思わず感心してしまった。「性のクロスワードパズル」を解くのに、ヤワなネット検索だけでは太刀打ちできないワードが含まれていて、面白い。存分に好奇心を掻き立たせてくれる。
いずれにしても、これぞまさしく「大正浪漫」的な、和漢洋才のセクシュアリティを多分に示していて、その時代――大正期――の通念を理解するにも、まことに都合がいいクロスワードパズルである。へたに御託を並べて性文化を語るより、このクロスワードパズル一つで、その方面の教養を身につけることができるのではないかと思われる。むろん、多少の労力と時間は惜しむべきではない。
性の文化は、歴史的に裾野が広く、またさぐるのに手強く、難解であるがゆえに、この道においても、険しく、終着点がない。しかしながら、鈴木清順監督の映画を観るには、じゅうぶんな素養となるだろう。
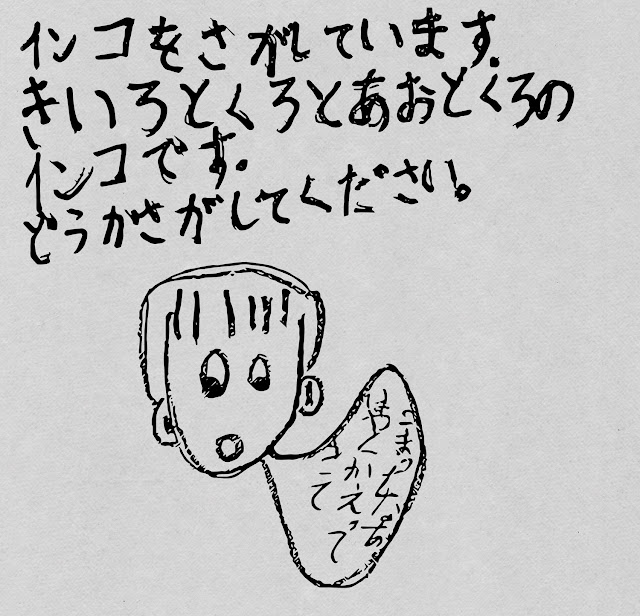

コメント