 |
| 【貴重な雲右衛門の写真がその本に掲載されていた】 |
前稿「地縛霊 恐怖の心霊写真集」で触れた『地縛霊 恐怖の心霊写真集』の著者である心霊研究家・中岡俊哉氏――。私は中岡氏を以前から、敬愛の念を込めて、“先生”と勝手に称している。
中岡先生の略歴の中で、際立って目立つのが、桃中軒雲右衛門(とうちゅうけんくもえもん)の名である。雲右衛門は、中岡先生の祖父にあたる。私は今、この明治・大正期の天才浪曲師・桃中軒雲右衛門について、お粗末ながら少しばかり触れておきたいと思っている。
浪曲とは浪花節のこと
その前に、浪曲について簡単に触れておく。
『広辞苑』で「浪曲」をひけば、浪花節(なにわぶし)の異称というふうに出ていて、盛んになったのは明治以後、桃中軒雲右衛門の功が大きいと、雲右衛門の名がはっきりとそこに出ている。
実際のところ、私はこれまで、心霊研究家あるいは超常現象研究家という肩書きをもつ、稀にみる稼業の中岡先生と、浪曲師であった祖父・桃中軒雲右衛門とを結びつける線が、思惟的な連想の中で全く希薄であった。中岡先生の骨太な顔立ちとドスの効いた低い声は、私の脳裏から離れることはなかったけれど、今となっては、雲右衛門を知るにあたり、明治人らしい努力家の才気に溢れ、かつ反骨的な気概に満ちた魂の片鱗が、どこか先生にも窺える――とさえ思うようになったのだった。
浪曲(浪花節)は、義理人情を主眼とし、三味線に合わせて節を付けたり、啖呵を切ったりする通俗的な語り・口上の、古い時代からある遊芸の一つである。もともとの祭文語りやちょぼくれ、ちょんがれ、浮かれ節などという遊芸が明治以降に盛んになり、東京において「浪花節」という名で確立する。のちにこれは、浪曲という言い方にもなった。
浪曲に関してわかりやすいところを拾うとなれば、昭和期の浪曲師、二代目広沢虎造が的確であろう。彼の得意とする演目「清水次郎長」は、彼の知名度を上げ全盛を誇った。幸いにして今、虎造のレコード音声は多くディスク化されており、容易に聴くことができる。浪花節とは何ぞやを大まかに知るには、適当な音源資料かと思われる。
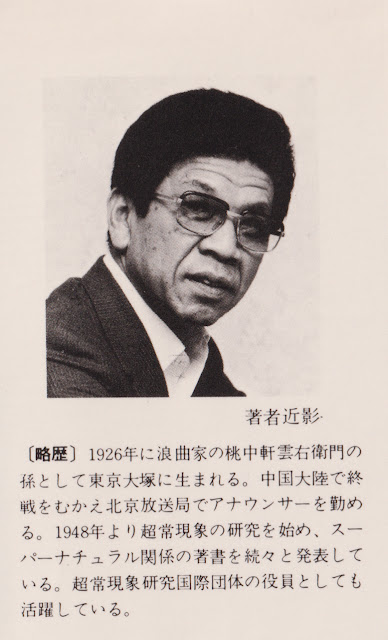 |
| 【『地縛霊 恐怖の心霊写真集』より中岡俊哉先生の略歴】 |
中岡氏の略歴にクモエモン
話を少し戻す。
数ある中岡先生の著書の中から、威風堂々とした略歴を一つ選んで喧伝するならば、以下の文面が相応しい。ここに厳然と、雲右衛門の名が刻まれている。
《1926年に浪曲家の桃中軒雲右衛門の孫として東京の大塚に生まれる。馬賊を志して中国大陸に渡る。終戦後は北京放送局に勤務。以来25年にわたり超常現象の研究を続け、ESP関係の著書を続々と世に問う。日本超能力研究会を主催している》
(中岡俊哉編著『続 恐怖の心霊写真集』より引用)
桃中軒雲右衛門の孫――。
中岡先生はかつて、小学館入門百科シリーズの『ふしぎ人間 エスパー入門』(1974年刊)など、自身の研究分野であるオカルト系に沿った本を、子ども向けに編修し、多く執筆していた。例えば、同シリーズの『空飛ぶ円盤と宇宙人』(1975年刊)の略歴は、実にシンプルなもので、以下の通りである。
《1926年、東京の大塚に生まれる。超能力研究家。著書には『エスパー入門』(小学館)ほか、多数がある》
(中岡俊哉著/小学館入門百科シリーズ42『空飛ぶ円盤と宇宙人』より引用)
子ども向けの本ではどういうわけだか、“桃中軒雲右衛門の孫”という部分が、意図的にごっそりと抜け落ちている。
むろん、私は、小学生の頃から、“恐怖の心霊写真集”シリーズを貪り読んでいたので、中岡先生が浪曲家の孫である――ということは、頭の片隅にあった。しかし、頭の片隅にあったというだけで、それ以上に関心は及ばず、クモエモンがドラえもんと違ってどういう人物なのか――など、知る由もなかった。
私の周囲の大人たちに、心霊研究家の中岡先生に関心を持つ者がいなかった――ということが遠因で、浪曲師の雲右衛門を知る機会を失っていたという言い方もできる。
今にして想像すれば、あの80年代ポップ・カルチャーの最先端の渦中に、先生の祖父にあたる浪曲師某に関心を抱き、どんな人物であったかを子どもの時分に知ることができていたならば――ああ、漫談でテレビによく出てくる玉川スミさんのお父さんは、クモエモンのお弟子さん(桃中軒雲工)だったんだ――ということが理解できたであろう。
江戸あるいは明治以後の遊芸の名残は、私が子どもの目線で見ていた昭和時代にも多く受け継がれており、玉川スミさんもまた、幼少の頃に雲右衛門の影響を多分に受けた、気骨ある女性浪曲師(浪曲はスミさんの多芸のうちの一つ)であったのである。
森鷗外の「余興」
鷗外の掌編に、「余興」(1915年)というのがある。文中、辟邪軒秋水(へきじゃけんしゅうすい)という浪曲師が登場する。この秋水なる男は、桃中軒雲右衛門がモデルということになっている。私はこの鷗外の掌編を、新潮文庫の『阿部一族・舞姫』で読んだ。
ある男が柳橋の亀清(料亭・亀清楼かと思われる)におもむき、同郷人の懇親会に寄り合う。鼠頭魚(きす)というあだ名の年増芸者が知り合いで、鼠頭魚が男に声をかける。「お暑うございますことね」。
懇親会の幹事である畑少将が企てた“余興”が、別室でおこなわれると知った男は、やがてその部屋に案内される。その座敷には既に、秋水が居座って宴会客を待っていた。
男は事前に、雑誌などを見て秋水なる浪曲師の風貌をよく知っていた。《芝居で見る由井正雪のように、長い髪を肩まで垂れて、黒紋附の著物》姿――。おもむいた部屋で座っている秋水を見た男は、こう表している。《顔は極て白く、脣は極て赤い。どうも薄化粧をしているらしい。それと並んで絞の湯帷子を著た、五十歳位に見える婆あさんが三味線を抱えて控えている》。
浪花節(浪曲)の演目は、「赤穂義士討入」。この出し物は異様に長く、義士が吉良の首を取るまでにえらく時間を要した。聴き慣れぬ漢語や詩の調子が耳障りと感じられ、三味線の枯れた音が猛烈な雑音としか聞こえぬ男は、何度も座を立とうと心が揺れ動くのだが、先輩に敬意を払う気持ちでそれをぐっと抑えつけた。そうしてこれを聴いている畑少将など同郷人一同は――否応なく男自身も含めてであるが――その秋水の告別の詞に、歓喜をもって拍手するのだった。
ところでこの掌編は、小説的な体裁としての要領を得たか得なかったか、もやっとしたまま、あっけなく、がくりと文章が閉じられている。閉じられる直前のエピソードを要約しておく。
余興を見終わった男は廊下で、鼠頭魚とすれ違う。「大変ね」と声をかけられる。その足で宴会の部屋に戻り、酒を飲もうとすると、猪口を差し出す若い芸者が、「面白かったでしょう」と男に言う。
《大人が小児に物を言うような口吻である。美しい目は軽悔、憐憫、嘲罵、翻弄と云うような、あらゆる感情を湛えて、異様に赫いている。
私は覚えず猪口を持った手を引っ込めた。私の自尊心が余り甚だしく傷けられたので、私の手は殆ど反射的にこの女の持った徳利を避けたのである》
(新潮文庫/森鷗外著『阿部一族・舞姫』「余興」より引用)
実に巧妙な心理眼的掌編で、鷗外の刺々しい私心が垣間見られると言えなくもない。
浪花節は当時、とくに文壇からは、ひどく嫌悪された。大衆には大受けの遊芸稼業も、知識人からは冷たくあしらわれたのである。
とどのつまり、文中では辟邪軒秋水としているが、実際の桃中軒雲右衛門の、下層社会から気炎を上げるような芸風に対し、鷗外の感情も熱を帯びて燃えさかり、なにをこの男――と、少なくとも一昼夜程度は、激情したかと想像できる。
それは鷗外にとって耳障り、猛烈な雑音と感じられ、浪花節の非難という身を震わせざるを得ない心中だったに違いない。しかしその感情は一気に冷めていき、冷静さを取り戻していったかと思われる。しかるに燃え尽きた激情の灰なるものは、自己への「憂い」そのものであった。
鷗外はさすがにそうであっても、一般知識人の浪花節に対する冷ややかな眼差しは、なかなかどうして冷ややかなままである。
文中の秋水には、「武士道の鼓吹者」「浪界の泰斗」という実際の雲右衛門と同じ肩書を呈している。浪花節など、ああいったものに情を揺さぶられる大衆や、贔屓の女客が多いことは、憤懣しごく。なにが義理と人情か。言うなればそうした感情は、富国強兵の時代にあやかった人気者――浪界の花形・雲右衛門――への、苦味のある男性社会の嫉妬心であった。
 |
| 【岡本和明著『俺の喉は一声千両 天才浪曲師・桃中軒雲右衛門』】 |
桃中軒雲右衛門
中岡先生の、あの略歴に記される“雲右衛門の孫”という文言が、いかに大きなものであったか、もはや遅かりし私個人の気づきであったと思わざるを得ない。
しかし、断じて述べるが、桃中軒雲右衛門という男は、決して明治の知識人から侮蔑されるべき軽薄な男ではなかった。このことは強調しておく。この大人物の複雑な実体像を突き止めるには、いくつか資料を照らし合わせなければならなかったのだが、あまりに大きな海原の、荒れ狂うような生涯でもあるので、ここではほんのわずかな事柄に触れる程度に、とどめておく。
桃中軒雲右衛門について、平凡社の『世界大百科事典』(1966年初版)をひくと、書き出しにこうある。
《明治時代の浪曲家。本名岡本峰吉。茨城県結城在に生まれた》
峰吉は峯吉と記されることもあり、また厳密な出生地に関しては、訂正が必要であろうか。
岡本和明著『俺の喉は一声千両 天才浪曲師・桃中軒雲右衛門』(新潮社)を読むと、《明治六年上州高崎に生る》という文言が含まれた、明治35年のとある新聞記事が引用されていたり、“上州生まれ”とある大正期の『九州日日』の新聞記事などもあって、彼の出生地は、今の群馬県の高崎であったかのような印象を受ける。しかし、確たる出生地の記録というわけでもなさそうで、このあたりのことはいまだ判然としない。
生まれた年は、明治6年(1873年)と定まっている。
父は、祭文語りで、地方をドサ回りする吉川繁吉という名である。峰吉は、9歳頃に父から浪花節を習い、三味線弾きの母・ツルから三味線を習った。これら両親の教示が、のちの雲右衛門としての芸事の礎となった。やがて父の名を継ぎ、繁吉と改め、30歳の頃に関西や九州を回って浪花節を磨き、桃中軒雲右衛門と名乗るようになる。
さらに『世界大百科事典』には、こうある。
《1906年(明治39)初冬、東京本郷座で興行し、一躍満都の人気を博し、さらに12年には東京歌舞伎座にて単独興行をおこなって、いわゆる桃中軒雲右衛門節を確立した。長髪紋服で特色ある雄健荘重な節調を駆使し、内容も武士道の鼓吹、普及向上につとめ、それまで、いやしい市井演芸にすぎなかった浪曲の格式を向上させた功績は大きい。しかし晩年は不遇のうちに肺結核を病んで没した》
(平凡社『世界大百科事典』1966年初版より引用)
没したのは大正5年(1916年)で、享年四十四。鷗外の「余興」が雑誌『アルス』で初出となった翌年ということになる。
大事なことなので触れておくが、先に記した本『俺の喉は一声千両 天才浪曲師・桃中軒雲右衛門』の著者・岡本氏は、演芸研究家であり、なんと中岡俊哉先生のご子息なのである。つまり、岡本氏からすれば、雲右衛門は、曾祖父にあたる。
『俺の喉は一声千両 天才浪曲師・桃中軒雲右衛門』は、時代読み物という形式になっている。ただ、浪花節誕生の肝を語る時、雲右衛門が育った「芝新網町」(今の港区浜松町付近)とことさらつながりがあることを強調している点で、そのほかの伝記本とは少し異質である。
「芝新網町」は当時、下谷万年町や四谷鮫河橋とならんで東京の三大“貧民窟”といわれた細民街で、言うなればスラムである。父親の繁吉が死んだ後、峰吉たち一家はそこでじりじりと息を殺して暮らしていたという。いわゆる“最下層”の暮らしをしていた彼らに対しての差別や偏見は、その時代において相当なものであったかと思われる。
反骨の精神で、雲右衛門は、浪花節の偏見を取っ払い、格式を向上させた。その偉業はとてつもなく大きい。
雲右衛門節が、海軍軍人の伊東祐享元帥の目にとまり、そしてついに、皇族の有栖川宮妃殿下の目前で浪花節披露をやり遂げるにいたる。その時の演目は、雲右衛門が磨きに磨いた「義士伝」であった。
赤穂浪士の忠臣蔵事件などを綴ったこの「義士伝」は、孫文の支援者として知られる宮崎滔天が明治35年、ひょんな経緯で雲右衛門の弟子となったことがきっかけとなって、その基礎となる資料『元禄快挙録』(明治40年)を書いた九州日報の福本日南、そして政治団体・玄洋社の社員で新聞記者の末松節らとともに“改良創作”したものである。
九州地方を回った雲右衛門の活況を、新聞がセンセーショナルに喧伝し、彼の名が広く知られるようになったのは、滔天のアイデアによるメディア戦略であった。雲右衛門の「義士伝」は、独創性の高い演目であり、共同作業で元のそれをつくり直して、「武士道鼓吹」の雲右衛門としてその名を轟かせるにいたった。
彼の遊芸稼人としての浪花節は、ジャーナリストや大物政治家、そして皇族にまで浸透し、一世を風靡したのである。この「一世を風靡する」という遊芸的稼業こそが、まさに心霊研究家という肩書きをふるった、中岡先生の得意中の得意とした部分ではなかったか。芸は孫に受け継がれたのである。
追記:桃中軒雲右衛門の貴重な肉声レコードが聴ける動画↓を配信中!


コメント