 |
| 【大江健三郎著『「伝える言葉」プラス』(朝日新聞社)】 |
作家・大江健三郎氏が3月3日に亡くなった――。14日付の朝日新聞朝刊では、「大江文学 戦後精神と歩む」という見出しで、大江氏の来歴や評伝などが掲載された(筆者・吉村千彰)。「民主主義・反戦 問い続け 未来へ」という小見出しでも頷けるように、氏が歩んできた文学的こころざしの高みが偲ばれる。
まことに私的で恐縮ながらも、かつて私が好きだった彼の著作のうちの一つから、“戦後派”といわれた彼の文学的精神を読み解いていきたいと思う。
エラボレーションの極み
大江健三郎著『「伝える言葉」プラス』(朝日新聞社/2006年初版)は、2004年以降、朝日新聞朝刊で月一連載されていた「伝える言葉」の随筆を収録した単行本であり、まだ30代半ばだった私が、手探り状態のインターネット時代をどうとらえ、生き抜くかの遠視的旗標となった随筆集であった(装幀画は舟越桂)。
この本に(というか連載の一つに)、「晩年の読書のために」という稿がある。大江氏はその頃既に、《もう先の見えている自分》と括り、自身の“晩年”という観念を強く抱いて執筆していたことがわかる。ただし、多少の〈若い者に負けてたまるか〉という気負いの部分の謙遜が、含まれていたかと思われる。
私が“大江文学”というものを直視し、初めて彼の書き物に対して個人的な雑感を抱いたのは、まことに恥ずかしながら、20代を過ぎただいぶ後のことだった。
一言でいって、“大江文学”とはたいへん「難解」な、その彼の執筆する「巧妙なる構文」を読み解くのに苦労した――という点で、一筋縄ではいかぬ慎重さを覚えたのは忘れもしない。
これについては、勝手な解釈として、彼がフランス語で思考した論理的な構文を、日本語にそのまま置き換えているせいだ――と思っているのだけれど、いずれにせよ、そうしたことから、今でも彼の書き物を読む私側の癖――すなわち読解に神経を尖らせる難儀な作業――は、かえって私自身の「あらゆる書き物に対する読解力」が鍛えられたというか、よい経験になったと自負している。
実際、「晩年の読書のために」においても、そこにはいくつかの論旨が複雑に絡んでいて、「難解」といえば「難解」なのである。いまここで、一つの段落を例に取り出し、それを掻い摘まんで説明するとするならば、こういうことになる。
以下の文章(「晩年の読書のために」の冒頭の、3行で括られた段落)をまず読んでみてほしい。
《大きい地震に備える、ということを考えたのが始まりでしたが、もう先の見えている自分の、本の読み方自体を整理する、という進み行きとなって、書庫とそこからはみ出しているものを片付ける仕事に三年かかりました》
(大江健三郎著『「伝える言葉」プラス』「晩年の読書のために」より引用)
ここでの論旨は、書庫の外にはみ出している――すなわち書棚に収まっていない、無数の本を片付ける作業が、3年かかったという箇所であるかと思われる。
けれども、読み人がその論旨を理解するのに、書庫を整理するのに三年かかったという意味の文章が出てくる段落の最後まで読み通さなければならないため、その間の1行なり2行なり(①大きい地震に備えるということ、②先の見えている自分の読み方を整理する進行具合のこと)を、いったん脳内の別の、いわばレジスタ的な記憶装置に置いておかなければならず、最終的に前後の文章の組み合わせから論旨を理解するのに、少しばかり――あるいはその数十秒を超えて――時間を要する、つまり骨が折れるのであった。これが彼の構文の特徴であり、「難解」ととらえられてしまう根本原因となっている。
こういった調子で、全体の数段落を読み解いていくとなると、短い随筆であっても、それはもう、“大江文学”とはこれいかに――。喩えるならば、噛み応えのあるスルメイカを、いつまでも口の中で噛んでしまっていて、いっこうに喉の下に落とすことができない――のによく似ていると思えるのだった。
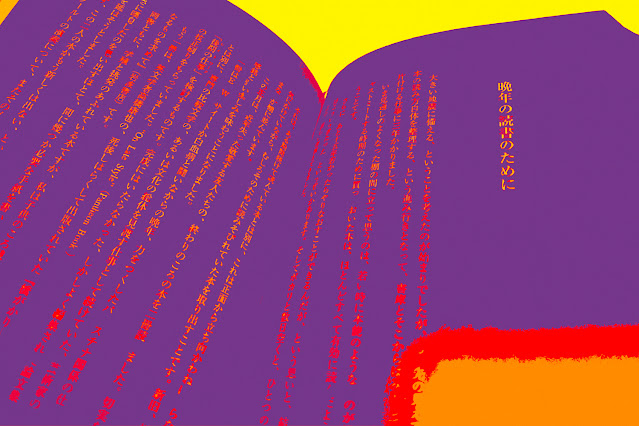 |
| 【大江氏の随筆「晩年の読書のために」】 |
2つの「晩年」
話を大いに煩わしてしまった。
「晩年の読書のために」の稿で大江氏は、ある2つの本から、通念として抱かれるであろう「晩年」――という言葉の意義を示唆している。一つは、エドワード・ワデイ・サイード(Edward Wadie Said)の“On Late Style”=『晩年のスタイル』。方々の芸術家の、“Late Works”=「後期の仕事」を「検討」するもので、これは未完の作(大橋洋一訳/岩波書店)だ。もう一つは、翻訳家で知られる高橋康也の『橋がかり――演劇的なるものを求めて』(岩波書店)。
実は私は、『橋がかり――演劇的なるものを求めて』の本がたいへん気に入ってしまった。なぜなら、高橋氏が能やシェイクスピア、あるいはベケットといった演劇の戯曲を、ふくよかな知性で瑞々しく見事に解題しているからだ。
演劇は、ある物語(神話、寓話、伝承、生活空間の映し絵など)を、人間的な経緯や営みをもって、主義主張を、人間の滑稽な皮肉といったことを、大衆にドラマティックに知らしめる独創的表現の装置である。まさにこれを、ドラマツルギーの妙味ということができる。
舞台上の演者が、形式的に仮構のモノローグやダイアローグを演じ、音や光の現象における技術(視聴する者にとっては全くの魔術に思えるかもしれない)を駆使しながら、荘厳な世界を創り上げることができるリアリスティックなお伽の空間。それが演劇と呼ばれ、台本とか戯曲の設計図を読み解いたり解釈を加えたりすることは、演者にとっても演出家にとっても、あるいは演劇の鑑賞者にとっても、謎めいた魔群の創出の在処を知る探検譚のようであるかと思われる。
高橋氏はその一端を、戯曲の翻訳という形で担ってきた仕事人である。『橋がかり――演劇的なるものを求めて』を読むことで、こちら側の読者も、演劇と高橋氏自身とその向こうにある作り手との橋がかりとなるであろう。
大江氏はこの2つの本を紹介した後、こう述べている。
《二人とも、迫っている終わりの時をあきらかに意識して、生涯の仕事の頂点をきざみ出そうとしています》。
さらにサイードがベートーヴェンの後期作品を綴ったのに意義を重ねて、《異様なほどの精気にみちていますが、技術にも論旨にも、エラボレーションを重ねた上での、優美な軽みがあります》とも述べてつなげていた。
大江氏はこれらの本を読んだ時、彼らは「もういない」のだと、半ば打ちのめされたような心持ちだった。
そしてこんなことを意識した。《世界的な水準の学者による専門の徹底した展開》――。自分はそういった学問の道を、中途半端にしてしまったという反省である。彼らは自ら推し進めた学問を、「後期の仕事」の中で満ち足りた成果を残した、という羨む気持ちがあったのだろうか。
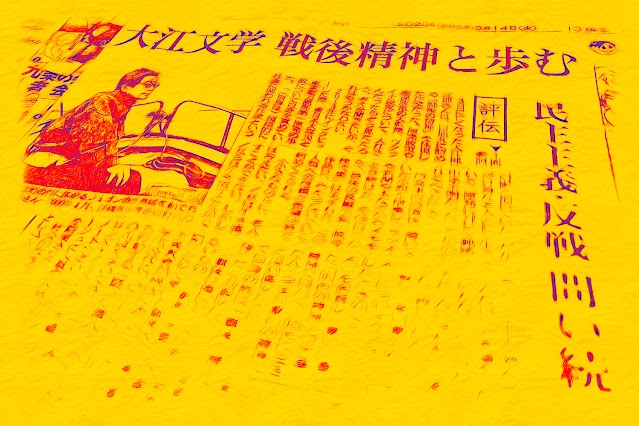 |
| 【2023年3月14日付朝日新聞朝刊「大江文学 戦後精神と歩む」】 |
§
若き青年作家であった大江氏が、日本の敗戦という歴史的事実と向き合い、その心理的あるいは物理的頽廃の混乱期から、凄まじく矛盾に満ちた“戦後史”について綴った、2つの社会派ルポルタージュ――『ヒロシマ・ノート』(1965年)と『沖縄ノート』(1970年)を私は忘れない。
いうなれば、読み人に「民主主義とは何か」の必定の信念を刻み込んだ、稀にみる二作品であったと私は感じている。しかし、彼はあまりに多産の作家であったため、あれらのルポルタージュを根本から否定する者にとっては、都合よく取り扱わずに楔を打ち込む――村上春樹と大江健三郎という戦後作家の“二刀流”として――という安直な手段を通じて、履き違えた“戦後派”をうえつけるものとなった感は否めないだろう。むろん、真に大江文学を通暁する読み人は、この私の見解を一掃し、冷笑していただいてもかまわない。
先の新聞記事において、大江氏の「戦後の精神」に関して、「明治の精神」を対象化する文面があった。大江氏は漱石の「こころ」を再読し、《漱石の書いた「明治の精神」は天皇の精神ではなく、明治に生きた人々つまり漱石の精神だと思い直した》と記している。彼は《自身の核は「戦後の精神」だと力説した》という。
大江氏はやがて、自身の心中で已むにやまれず、「晩年」という個人的イデオロギーに立ち向かった。そして、サイードや高橋氏のような「後期の仕事」の本の読者ともなった。
そのことで、「晩年」というもののかたちは、人々にとって精神的荒廃のそれではなく、綠豊かな広葉樹に似たものとして、平和的な解決を模索する伸びやかな樹木、そのゆったりとした落ち着いた構えそのものとして、残された私たちに知恵を与えてくれたのである。「晩年」というキーワードこそ、大江氏の文学的精神の真骨頂なのだと、私は思うことにしている。
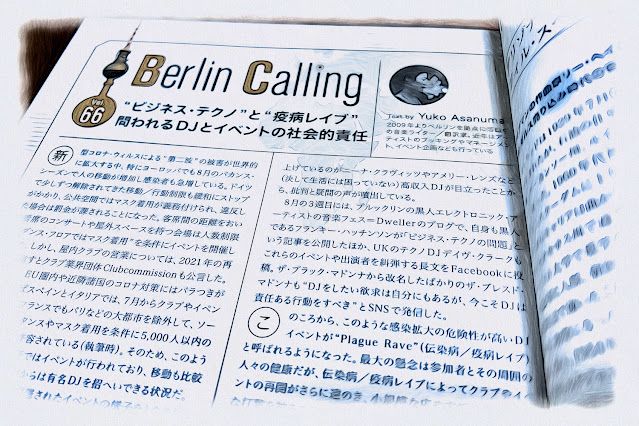

コメント