今年の春頃、どういうわけだか私の周辺の知り合いの中で、チロルチョコブームが起きた。こんなチロルもある! ほら、ストロベリーのチロル、これ生クリーム入りのミルクチロルだって!
3センチほどの四角錐台形のチロルは、実に可愛らしくて誰からも好かれる。封を開け、口に頬張れば、あっという間にチョコが溶け、口いっぱいにそれぞれの味が広がる。そんな楽しさに火がついて、いい歳をした大人の連中である私の知り合いたちは、こぞって珍しいチロルチョコを買ってくるようになり、その度に私は、いろいろな種類のチロルと出逢うことができ、この春、ほぼ毎日のようにチロルを食してきたわけである。名付けてチロル愛。
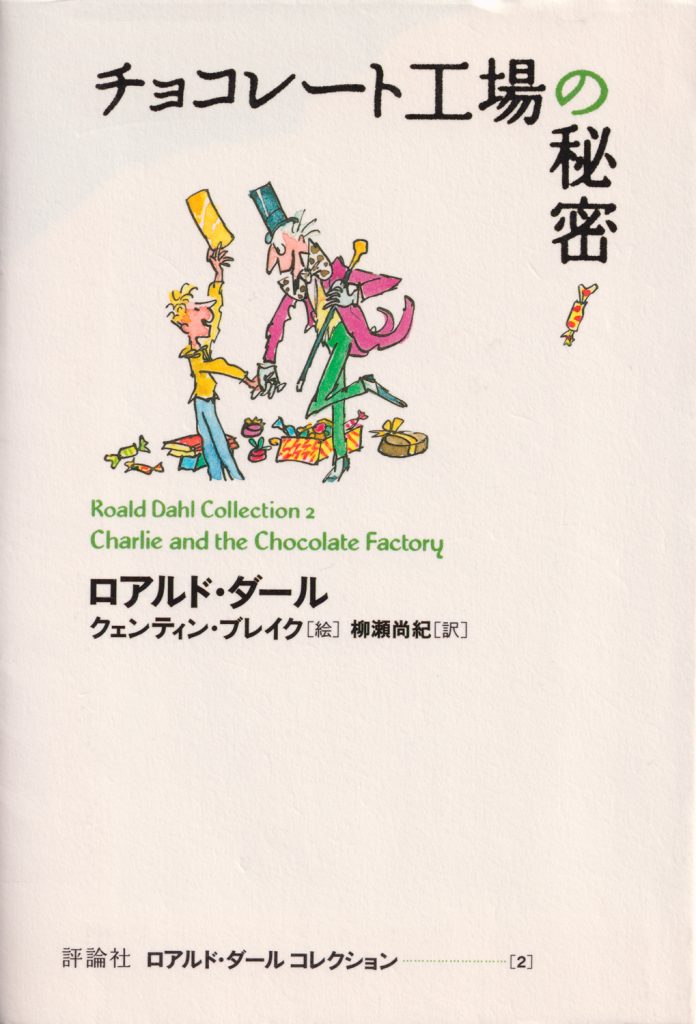
読書感想文を書く
前後の脈略を含めて話をすっ飛ばすけれど、私はこの夏、ロアルド・ダール(Roald Dahl)の『チョコレート工場の秘密』(評論社/柳瀬尚紀訳)の“読書感想文”を書こうと思った。タイトルは、「『チョコレート工場の秘密』を読んで」…。
高校時代に武者小路実篤の『友情』の感想を作文にしたり、専門学校時代にはウェイン・W.ダイアーの『もっと大きく、自分の人生!』(知的生きかた文庫)の感想文を書かされたりしたものだが、普段こうしてブログでなにかの作品の批評を書くのとは違って、それら、“読書感想文”という清楚な響きの括り付けで本を読んだ感想を作文にしたら、ある種のノスタルジックな文体が引き出せるのではないか――などと考えたりして、ちょっと興奮したのは事実である。
ではなにゆえに、私は『チョコレート工場の秘密』の“読書感想文”を書こうと思ったのか――。
きっかけはこうである。
実は今年の春、いやもう初夏であったろうか、そうした季節が移りゆく頃に、ひろひろさんという方のブログに出合った。ひろひろさんは、20代男性のブロガーだ。
彼のnote.comのいくつもの投稿の中で、ひときわ輝いていたのが、「映画『ウォンカ』が、今よりもうちょっと楽しみになる話。」だった。私はこれを読んで、どっぷりはまり、彼が生み出す文体の虜になってしまった。
だってだってそれは、チョコレートの映画の話題だったから?
いや、そうではない。たしかに、チロルチョコへの関心が個人的に高まっていたせいも、多少ある。『チョコレート工場の秘密』は、ウォンカのチョコレートの話ではあったけれど…。
ちなみにウォンカというのは、原作を映画化した、2005年公開のジョニー・デップ主演の『チャーリーとチョコレート工場』(Charlie and the Chocolate Factory)に登場する、チョコレート工場の工場長、ウィリー・ウォンカのことである。
ひろひろさんが書いている話は、厳密にいうと、ウォンカのチョコレートの話――ではない。今年12月公開予定の映画『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』(Wonka)に出演する、ティモシー・シャラメ(Timothée Chalamet)に関する話題なのだ。
とりあえずティモシー・シャラメのことはおいておく。
あのジョニー・デップが出演した映画『チャーリーとチョコレート工場』の原作の、『チョコレート工場の秘密』(Charlie and the Chocolate Factory)の作者であるロアルド・ダールの名が、私の記憶の中でうっすらと、〈以前どこかで見たような…〉と明滅したのが、ひろひろさんのnoteに関心を抱いた理由なのだが、はじめはどうもそれを思い出すことができなかった。
私はジョニー・デップのあの映画を、その時まだ観ていない。ならば、ロアルド・ダールの名を知るわけがないではないか――。はて、ロアルド・ダール、はて、ロアルド・ダール。
悶々としてわかりかねていた時、ふとしたことがきっかけで、その答えが見つかったのだ。自分のブログを検索してわかったのである。以前、『洋酒天国』の本で、彼の著作を知っていたのだ、と。
イギリスの小説家ダールは、短篇小説作家――と、私は以前、認識した。彼はもと英国の空軍パイロットで、その時の従軍経験が様々な題材となり、アメリカに駐在していた際、作家としての基礎を足らしめたという略歴からの云々。私が彼の作品で最初に知ったのは、「味」(Taste)であり、訳者は田村隆一氏。いま手元に、それを所収したハヤカワ文庫の『あなたに似た人』(Someone Like You/1953年)がある。
1964年の作品『チョコレート工場の秘密』は、ダールの膨大な著作のうち、児童小説という括り付けで構わないはずである。児童文学を好む固定的な読書家からは、ダールは児童小説の作家という印象を強く受けるに違いない。
しかし、先の「味」などの短篇作を読み、『チョコレート工場の秘密』を読むと、それが単なる児童小説ではないことに気づく。彼は『チョコレート工場の秘密』を子どもたちのためだけに書いたのではない、別の目的も潜んでいたのではないかという疑念が生じてくるのだが、悪態をつく子どもらの登場と対比して善良な子、善良な大人の登場といった手法は、彼の児童小説の多くに貫かれた信義的なものであり、まだ私はこの時、ダールの著作全体からのそうした作風や信義的な執筆作法について、理解が及んでいなかったことを付け加えておきたい。


『チョコレート工場の秘密』の6ペンス銀貨
以下、柳瀬尚紀氏の翻訳による登場人物名及び名称等で書いていく。
ダールの『チョコレート工場の秘密』では、少年チャーリー・バケツの父方の祖父のジョウじいちゃん(Grandpa Joe)がこっそりとチャーリーに、お金を与えて、それでチョコレートを買ってくるよう促す場面がある。
ジョウじいちゃんは枕の下から革製の財布を出し、それを開いて逆さにする。すると財布から、6ペンス銀貨が落っこちるのである。ジョウじいちゃん曰く、「わしのへそくりさ」。
祖父から受け取ったこの6ペンス銀貨で、チャーリーは、板チョコの“ワンカのナッツ風ぼりぼりびっくり”を買ってくる。ここからこのあとの展開を書いてしまうと、本を読んでいない人の面白みが半減してしまうので、この先は割愛したい。
チャーリーの一家は小説の冒頭にも記されているように、町のはずれの小さな木造の家に住んでいて、父方と母方のおじいちゃんおばあちゃんを含め、7人で生活している。裕福ではなく、たいへん貧しい。冬は凍りつくような冷たい風が床を吹きぬけ、すさまじい。
チャーリーの父親のバケツ氏は、歯みがき工場で働いているが、稼ぎは少ない。家族の食事についての記述がある。朝はマーガリンをつけたパン、昼はゆでジャガイモとゆでキャベツ、夜はキャベツの煮汁といったぐあいで、どうやら毎日同じ献立らしい。ただし、日曜日だけは特別で、おかわりができるのだ。
育ち盛りのチャーリーにとっては、とても足りない貧しい食事である。そんな彼の好物は、チョコレートだ。学校へ行く途中で、店のガラス窓に積み上げられた板チョコを立ち止まって眺める。よだれが出てくるほど――。時に子どもたちが自分のポケットからチョコレートを取り出して食べたりするのを、チャーリーは眺めるだけだった。
唯一、彼の誕生日には、家族がその日のために貯めたお金で、小さな板チョコを買ってくれて、お祝いしてくれる。その板チョコをチャーリーは大事にし、木箱にしまい込んでから、何日も「見つめる」だけで楽しむ。そして何日かして、包み紙を少しめくり、ほんの少しだけかじる。《とろりとした甘い味が舌にひろがれば、もうそれでじゅうぶん》。
チャーリー少年にとって最高の幸せな瞬間とは、甘くて美味しいチョコレートを眺め続け、本当に食べたくなった時にほんの少しだけかじる瞬間――なのであった。
ジョウじいちゃんが渡してくれた6ペンス銀貨の価値を、いまの日本円に換算したらいくら? といったような話は、ここではほとんど意味がない。
6ペンス銀貨は英国の庶民的な硬貨だったから、日本の100円玉や50円玉くらいに考えておけばいいのだが、ジョウじいちゃんの「わしのへそくりさ」の意味合いは、それ相当のひもじい思いを超えた先の、一人の孫のためにできうる限りの援助、いや愛情であったことを私は述べたい。
6ペンス銀貨の実物を手にとってみると、本当に小さいもので、日本の1円玉くらいの大きさ(直径2センチ)でしかない。この内緒の「へそくり」の銀貨で、チャーリーは誕生日以外に板チョコをもう一つ買ってくることができ、彼、そしてジョウじいちゃんは幸せな気分を味わえたに違いないのである。
さらなる6ペンス銀貨の秘密
私の――チロル愛などと称して、もらったチロルを無遠慮にいくつも口に頬張るなど、チャーリーから見れば、ドン引きの行為、しかも本当のひもじさすら知らない私は、“痛い人間”にしか見えないであろう。大の大人が、そんなことをしてていいのですか、と天から冷めた声が聞こえてきそうで、穴があったら入りたい。
ダールが、『チョコレート工場の秘密』の物語でチャーリー一家、ひいては少年チャーリーをどんな幸福の世界に導いたか――。それは単に、ハッピーエンドだとか大団円だとかという童話的「筋」の閉め方の話ではない。むろん、ダールの児童小説を、そういう小説として読むことは大いに構わないのだ。子ども向けのエンタメ小説と括って、大人が子どもたちに「夢」を買い与えることも、決して悪いことではない。
しかし結局、私がこの本でいちばん心を揺さぶられたのは、先のジョウじいちゃんとチャーリーのやりとりの場面であり、6ペンス銀貨のほんとうの意味での重みなのであった。
6ペンス銀貨に関しては、マザーグース(Mother Goose)の「6ペンスの唄」(Sing a song of sixpence)がよく知られ、またマザーグースの幸せを呼ぶ詩の中に、“Sing a song of sixpence”(靴の中に6ペンス銀貨を)とあることから、庶民的な6ペンス銀貨は「幸福のコイン」として、結婚式の花嫁の靴にこれを入れておくと、その夫婦は永遠にお金に困ることがない、というような言い伝えがあったりする。ジョウじいちゃんとチャーリーのやりとりが、これにあやかっていると考えるのは間違いだろうか。
小さな子どもであれば、おそらく誰しも憧れて已まないチョコレートは、体がとろけるくらいに「甘くて美味しい」ごちそうなのだと思う。ダールは決して、児童小説だからといって、天からじゃんじゃんチョコレートを降らせ、子どもたちにそれを与えて幸せにしてあげようという物語にはしなかった。あくまで、善人の大人が子どもを愛すればこそ、彼らのために苦心して手に入れる象徴として、小説の前半部分でチョコレートという存在は描かれている。これはきわめて寓話的な、作家ダールの領分の核心といっていい。
文明社会における資本主義というものが、どのような構造を持ち、人々のあいだでどのような醜美の生活に満ち溢れているか、そして何より「最も大事なもの」を手に入れるためには、己の何かを犠牲にしたり、愛する人のために何かを喪失せざるを得ない過酷な状況における刹那も、彼は熟慮し見抜いた上で小説を書いている。実に英国人らしいふるまいとして――。
彼の代表作でもある短編「南から来た男」(Man from the South/1948年)は、寒気がするほど恐ろしい、人間の冷淡さや執念深さや哀切の集積として描かれ、それが彼の作風の「いわんとする領分」であり、『チョコレート工場の秘密』においてもそれぞれの子どもたちの個性の中ににじみ出ている。人間の本性の真贋を、もし児童小説を通じて読者の子どもたちに見抜かせるというような啓蒙主義的なものがあるならば、ダールのそれは最もふさわしい、徹底した本ということになる。ただし、それはあまり表立っては見えてこない。
ぱくりと口に頬張るチョコレートの味は、「甘くて美味しい」がゆえに、この世の資本主義の欺瞞と富の不均衡の俗悪さに、読者は感づく。とはいえ、『チョコレート工場の秘密』の文学的な面白さは、このことの示唆以外にもたっぷりと充満しているから、よりよい児童小説の一つとして、理屈抜きにこの本をおすすめする。私のプロフの【興味あること】の中に、“ロアルド・ダール”を付け加えておきたい。
以上、これが私の、この夏に課した読書感想文である。どうか赤点はお許し願いたい。

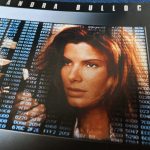
コメント