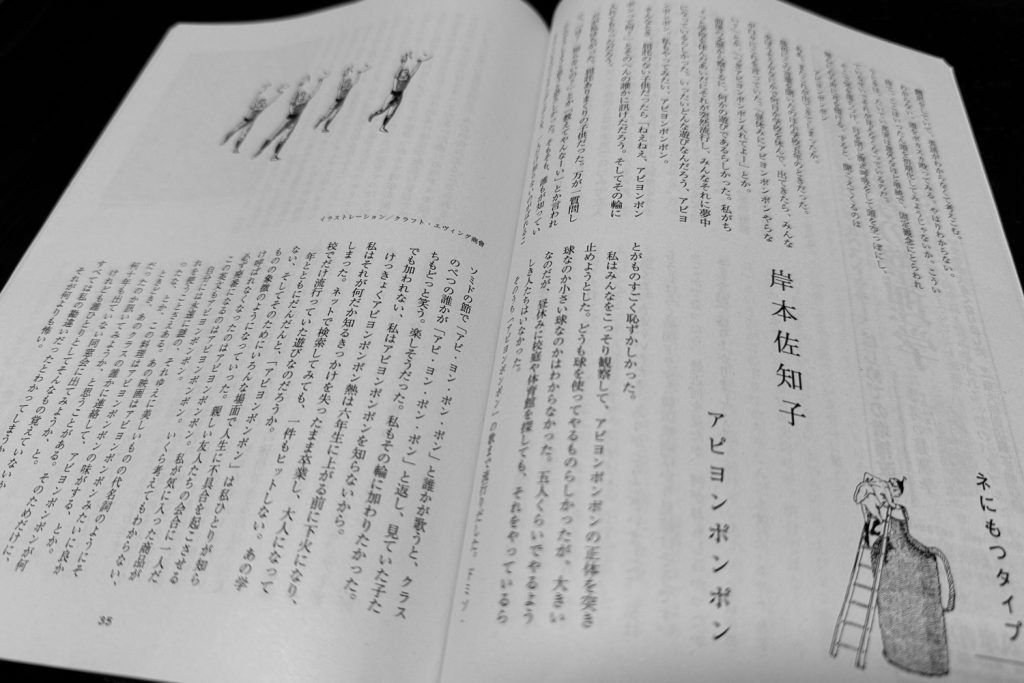
これを書かずにいると、夜も眠れなくなる――と思ったので、書いておくことにする。
翻訳家でエッセイストの岸本佐知子さんが、筑摩書房のPR誌『ちくま』で「ネにもつタイプ」を連載している。その9月号(No.642)に、「アピヨンポンポン」という奇妙なタイトルをつけている。
岸本さんといえば、ジョン・アーヴィング(John Irving)の『サーカスの息子』(“A Son of the Circus”)の翻訳などで知られるだろう。アーヴィングで思い起こすこととして、私はここ最近読み続けている新潮文庫のヘミングウェイの短編集を逐一読み終えるたびに、本のカバーの折り返しのところに記された“新潮文庫のアメリカ文学”のリストに目をやる癖がついてしまったのだが、その先頭に記されているのがアーヴィングだ。
『ガープの世界』(“The World According to Garp”)と『ホテル・ニューハンプシャー』(“The Hotel New Hampshire”)の上下巻がリストに記されている。こうして書いていると、『ホテル・ニューハンプシャー』の映画が観たくなるし、『サイダーハウス・ルール』(“The Cider House Rules”)を映画化したトビー・マグワイア(Tobey Maguire)主演のそれも、やはり観たくなってくる。しかし今は、それを語る時――ではない。
アピヨンポンポンの謎
クラフト・エヴィング商會(吉田篤弘、吉田浩美)のイラストの“アピヨンポンポン”が、私の網膜に焼きつけられて、不思議な感覚に陥った。
小学校の夏休み期間に何のためか忘れたが登校日があった。嫌々ながら登校した朝、全体朝礼で校庭に集合し、レコードの演奏で「ラジオ体操の歌」を歌った。そのあと、ラジオ体操をさせられたわけだが、「ラジオ体操第二」が、こんなようなポーズをさせたのではなかったか。
学校というところの全体で何かを行う際の、気恥ずかしさを誘発させるものとは、いったい何か。それは、不器用で不格好な私たちが、誰のためだかわからない不器用で不格好な一日のために繰り出す束の間のユーモアのようなもので、そのユーモアのぞんざいな輝きに、思わず堪えられなくなるのである。
ともかくそれを読んで、私はアピヨンポンポンがなんだかよくわからなかった。岸本さんも、アピヨンポンポンがわからなかった。エッセイの内容を要約すると、だいたいこういうことだ。
――仕事で翻訳がわからなくなる。英語がわからない。気を落ち着かせて、目を閉じて腹式呼吸をする。
ふう。
すると、頭の中で聞こえてくるのは、アピヨンポンポンだった。《ああ。またこれが出てきてしまったか》。
岸本さんは小学5年生の時にしばらく学校を休んだことがあった。久しぶりに学校に行くと、みんながそれを口走っていた。アピヨンポンポン。
どうやらそれは、5人位でやる“ボール遊び”らしかった。だが、それがなんだかわからない。アピヨンポンポンで遊んでいるところを見てみたいと思ったが、昼休みにそれをやっている子たちはいなかった。
アピヨンポンポンの歌も流行りだした。
アピ・ヨン・ポン・ポン♪と歌うと、誰かがアピ・ヨン・ポン・ポン♫と返す。なんだか楽しそうだったが、岸本さんはそれを知らないから、尚のこと加われなかった。
そのうち、アピヨンポンポンの遊びは下火になった。大人になっても結局、それがどんな遊びなのかわからなかった。岸本さんはこう述べる。《年とともにだんだんと、「アピヨンポンポン」は私ひとりが知らない、そしてそのためにいろんな場面で人生に不具合を起こさせるものの象徴のようになっていった》。ちょっと悲しいアピヨンポンポンである。
とどのつまり、子どもたちが遊んでいたアピヨンポンポンとは、いったいなんだったのか。
インターネットでもアピヨンポンポンの意味は出てこない。いろいろ調べて、一つの仮説を組み立ててみたのだけれど、全く自信がない。これから述べることは、私個人の一考察として受け流してもらってかまわないが、他の説を考えうるだけの余地がなかったことも事実である。
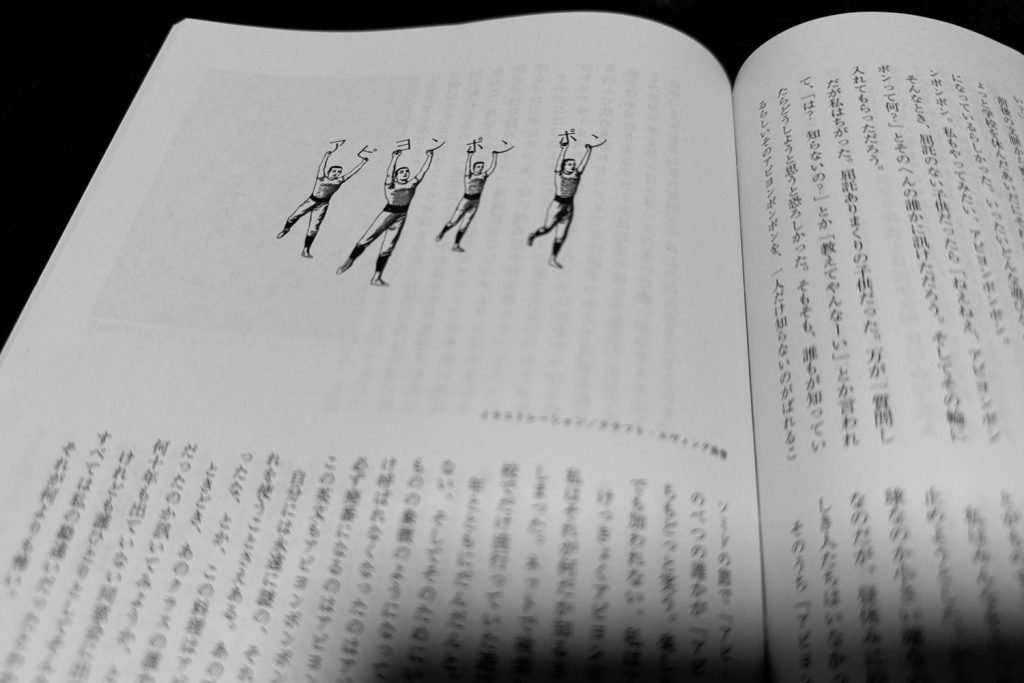
アピヨンポンポンはポピーのこと?
岸本さんは1960年生まれで横浜出身。東京の世田谷区で学校生活を送ったようで、当の岸本さんを含め、その学校の子どもたちは恵まれた知育環境にあったと想像できる。上級の5年生であれば、耳に入った言葉で遊び心をくすぐられることもあったと考えて良さそうだ。
こんな架空の物語はどうか。
お茶目でかしこい女の子・ナツコちゃんが放課後、ある地区のグラウンドでサッカーの試合を見たのだった。
「あ、外国人のオジサンたちがサッカーやってる!」
ナツコちゃんは、なんだか赤いものがうごめいてるのを見つけた。
その日は11月11日のリメンバランス・デー(Remembrance Day=第一次世界大戦の終戦記念日)に近い日で、サッカーをやってる外国人の人たちはみんな胸に、赤いポピーのワッペンをつけていた。「あのオジサンたち、どうして赤い花のワッペンを胸につけてるんだろう」。
リメンバランス・デーでポピーの花のマークをシンボルとするのが、英国やその他の国々で風習になっていた。第一次世界大戦で亡くなった軍人を追悼することから始まったのだが、単に“平和への祈り”という意味も込められている。
ナツコちゃんはちょっとせっかちで、お父さんがそんなふうに説明してくれた話をしっかり聞かず、とにかくあの赤いのはポピーの花だということだけは理解した。
えらいお父さんにも教養がある。ポピーといってもあれはヒナゲシのことだよ。英語でコーン・ポピー(Corn poppy)というんだ。他にもね、ポピーには種類があって、毒のあるポピーはオピウム・ポピー(Opium poppy)といって、これは勝手に栽培したりしちゃいけない花なんだ。毒があって危険だからね。
ナツコちゃんはうんうん頷くだけで、胸に赤いポピーをつけてサッカーをしてた外国人のオジサンたちの姿だけがとても印象に残ったのだった。
次の日、ナツコちゃんは友達にその話をしたくてしたくてたまらなかった。休み時間に興奮して話しだした。
「ねえ、きいて、昨日ね、学校から帰ったらね、カッコいい背の高い外国人のオジサンたちがね、えーと、なんていったっけ、えーと、ポ、ポ、えーとね、ポ、ポー、じゃなくて、あー、あ? あ、そうそう、アピヨーンポンピーやってたの!」
アピヨーンポンピー?
「え? ちょっとちがったかな? なんだっけ、えーと、あのね、アピヨーンパン? ポン? ピー? 違う違う、ピンポンパンのおねえさんじゃないよね、えーとね、外国人の、あ、そうそう、アピヨンポンポン!」
アピヨンポンポン!!!!
みんなが驚いたのである。まさか、お茶目なナツコちゃんの口から、アピヨンポンポンなんて途方もない、聞いたこともない言葉が出てくるなんて。
なんじゃいそりゃ?
その後、くどくどとナツコちゃんは説明して、ようやくみんなが理解してくれた。それね、サッカーのことね。はい、サッカーです。
その日からナツコちゃんのクラスでは、サッカーのことを面白がってアピヨンポンポンというようになり、5人でやるミニサッカーがたちまち流行りだしたのである。岸本さんは、そんな時に学校に復帰したのだった。アピヨンポンポンを知らないのは、岸本さんだけであった。
§
ということで、調べに調べまくって結局まさか、アピヨンポンポンがオピウム・ポピーであるとは私自身もまだ半信半疑なのである。岸本さん、アピヨンポンポンはですね、ポピーのことでして、つまり、リメンバランス・デーにちなんでやってたサッカーのことなんですよ、きっかけは――。うーん、どうも、そうはっきりいいきれないので甚だ困る。
誤解を招かないように、これだけは断っておきたいのだけれど、アピヨンポンポンはオピウム・ポピーを指しているが、リメンバランス・デーのシンボルはあくまでコーン・ポピー(ヒナゲシ)だということ。子どもどうしの言葉遊びだから混同してしまっているのは已むを得ず、ということを踏まえたうえで、ちょっと、オピウム・ポピーのことについて真面目にふれておきたい。

ケシとアヘンについての補遺
ポピーはケシ(罌粟)のこと。狭義ではヒナゲシを指すと、三省堂の『新明解国語辞典』(第八版)ではそう記している。それ以外のことについては何もふれていない。
毒性のあるケシをアヘンケシともいう。これがオピウム・ポピーである。麻薬成分のアヘン及びモルヒネが抽出できるケシ。
些か不謹慎に思えるかもしれないが、私がアヘンケシのことを初めて知ったのは、ずばり幼少期で、映画『犬神家の一族』を観たためであった。登場人物の犬神佐兵衛の悪徳な手練手管によって戦中期、軍部とのあいだで極秘裏にケシを栽培していた――という驚くべきことが明らかになる場面が出てくるのだ。
植松黎著『カラー図説 毒草の誘惑―美しいスズランにも毒がある』(講談社+α文庫)には、アヘンケシとモルヒネに関する記述がある。
《ケシの麻薬成分は、花びらが落ちたあとにできる、「ケシ坊主」と呼ばれるさく果(実)から滴りでる汁の中にふくまれているアヘンであって、人類が文明を築いた紀元前3000年以上前から現在にいたるまで、ずっと「眠り」と「癒し」をもたらしつづけている》。デオスコリデスの薬学の著『マテリア・メディカ』によると、アヘンは少量では痛みを和らげ、眠りを誘う。過量摂取では昏睡状態に陥り、死にいたる。とはいえ、この汁から抽出されるモルヒネは、鎮静作用をもつため、鎮静剤として医療に欠かせない薬品である。
アヘンの採れるケシは、ソムニフェルム種である。花が開いてのち、さく果(実)ができる。それは《ニワトリの卵ほどもある果実》だという。《アヘンの汁液は、ふつう表皮から内側約2ミリぐらいの間にしかなく、内部はびっしりと種がつまっている。もし刃先が種にまで達すると、ケシは生命を失い二度とふたたび汁液を出さなくなる。死んだ実をふたつに割ってみると、白い種が茶色く変色していた》。
ジャン・コクトー(Jean Cocteau)の『阿片―或る解毒治療の日記―』(堀口大學訳/角川文庫)には、彼が解毒治療中に想起したと思われる、アヘンの奇妙なる効果について綴った記述に遭遇でき、ひときわ文体が壮麗で果敢でさえある。こんな記述だ。
《肉欲の復活(これは解毒の、最初に現はれる判然した徴候だが)は、嚔と、欠伸と、洟と、涙とを伴つて現はれる。また他の徴候としては、向ひの家の鶏舎の鶏のむれと、鐵葉の屋根上を、背中で両腕を組み合わせたやうな恰好で、行きつ戻りつしてゐる鳩のむれとが、五月蝿くつて仕方がなかつたのが、七日目、牡鶏の歌が、僕には気持ちがよかつた。僕はこのノオトを朝の六時から七時の間に書いてゐる。阿片をやってゐる間は十一時までは、何にも分らない》
1930年に出版されたこのコクトーの本は、ソムニフェルムのさく果から滴り落ちる白い液のように、物静かで、厳格に、沈みゆく魂の恩寵ともいえる照応を示唆していて、感動的だ。療養院の看護婦曰く、「禁断状態の八日目に、ものを書いたりなさる患者さんは、あなたが初めてです」。
阿片から遠ざかつた結果として生ずる精神的覚醒のきざしは、男には生理学的に現はれるが、女には風儀的な現象として現はれる。阿片は男の心臓(こころ)は眠らせないが性を眠らせる。女の場合には彼女の性を醒めさせ心臓(こころ)を眠らせる。阿片を遠ざけて十八日目、女はやさしくなり、泣き虫になる。だから、解毒治療する療養院にあつては、婦人患者は悉く医員に惚れてゐるやうな様子をしてゐる。
ジャン・コクトー著『阿片―或る解毒治療の日記―』より引用
追記:赤塚不二夫先生の漫画『天才バカボン』に登場するキャラで、「アピヨーン星人」というのがあるらしい。確たる証拠はないが、これもまたアピヨンポンポンの可能性がある。



コメント