三島由紀夫の「ドルジェル伯の舞踏会」などというのは、表層的にはラディゲに対する詰問責めという形で、幻の中で彼との密会を描き、夭折した若者への主観的作家的欲望を満たそうという企図になっている。その決して穏やかとは言い切れない主観的作家的欲望に、読む側が引き込まれ、同時に中途で呼吸困難に陥り、作者の欲望とはかけ離れた部分でこの一幕を垣間見ようとするが、ついにその全体像が見えぬまま幻は消えていく構図である。
この短篇を知るきっかけとなった短篇集『裸体と衣裳』を先日手にしたのは偶然でも何でもなく、私が20歳の頃(1990年代初め)に三島文学に興味を持って『仮面の告白』や『音楽』『金閣寺』などを貪り読み、今になって読み忘れていた『裸体と衣裳』を読み始めたに過ぎない。実際、その中の三島自身の日記は特に意味はないにせよ、結果的に「ドルジェル伯の舞踏会」が引っかかってきたのである。
さて、三島由紀夫が書いた短篇「ドルジェル伯の舞踏会」ではなく、原作のラディゲの『ドルジェル伯の舞踏会』の方も堪能した。こちらは恋愛小説でありながら、作者曰く「最も淫らな貞潔」が主題である。
8月某日、ラディゲの『ドルジェル伯の舞踏会』読了。最後に登場人物達の破綻があるのかと思いきや、そんなものは何もなく、夫人とドルジェル伯の平常を取り戻そうとする会話で終わっている。とても小説の末尾という感じではないから、この小説は未完成なのか、意図的に最後の原稿を抜き去ったか、ラディゲ自身が時代の良識に合わせて削除してしまったか、いずれかであろうと思われる。個人的には、3番目の事由が濃厚なのではないかと思うのだが、表題の”舞踏会”がそこにあることはどうやら確信的だ。
三島由紀夫の「ドルジェル伯の舞踏会」は決して佳作小品といったたぐいの稿ではない。かといってラディゲの表題に対する説明でもなく、ある意味独善的な、三島本人の観念的現代語訳のダイアローグである。
ダイアローグにおいて、その彼の観念的現代語訳は、ほとんど意味を持たない。普遍的な観念ではなく、見るものに通ずる世俗的なトピックスではないからだ。ラディゲそのものが、日本人の現代文学にほとんど影響を与えていないせいもある。いや、仮に影響を与えた作家だとしても、ドルジェル伯夫人の貞潔云々を書いたラディゲと三島の観念的対話を、一体誰が見たいと思うのか。
大きく転じて、坂東玉三郎が監督した短篇『外科室』(泉鏡花原作)は、まさしくドルジェル伯夫人の貞潔云々を描いている。手術室の冷たい質感、夫人の透明な胸と腹、そしてきらりと光るメス。夫人の葛藤か諦念かの心情を、それらの映像的視覚と対照させ、泉鏡花の情念の世界を描き出そうとした。しかし後半の、晴天下の躑躅公園を歩く夫人と青年を描いてしまったために、前半の冷たい《青》のイメージが壊れ、映画としても台無しになっている。
その点、三島の「ドルジェル伯の舞踏会」は、完璧である。窓の外が炎に包まれ、映像に緊迫感と強烈なテンポが生まれる。静謐の《青》と緊迫感の《赤》とのコントラストにより、ラディゲ作品としても三島作品としても共有できるものがあるのだ。

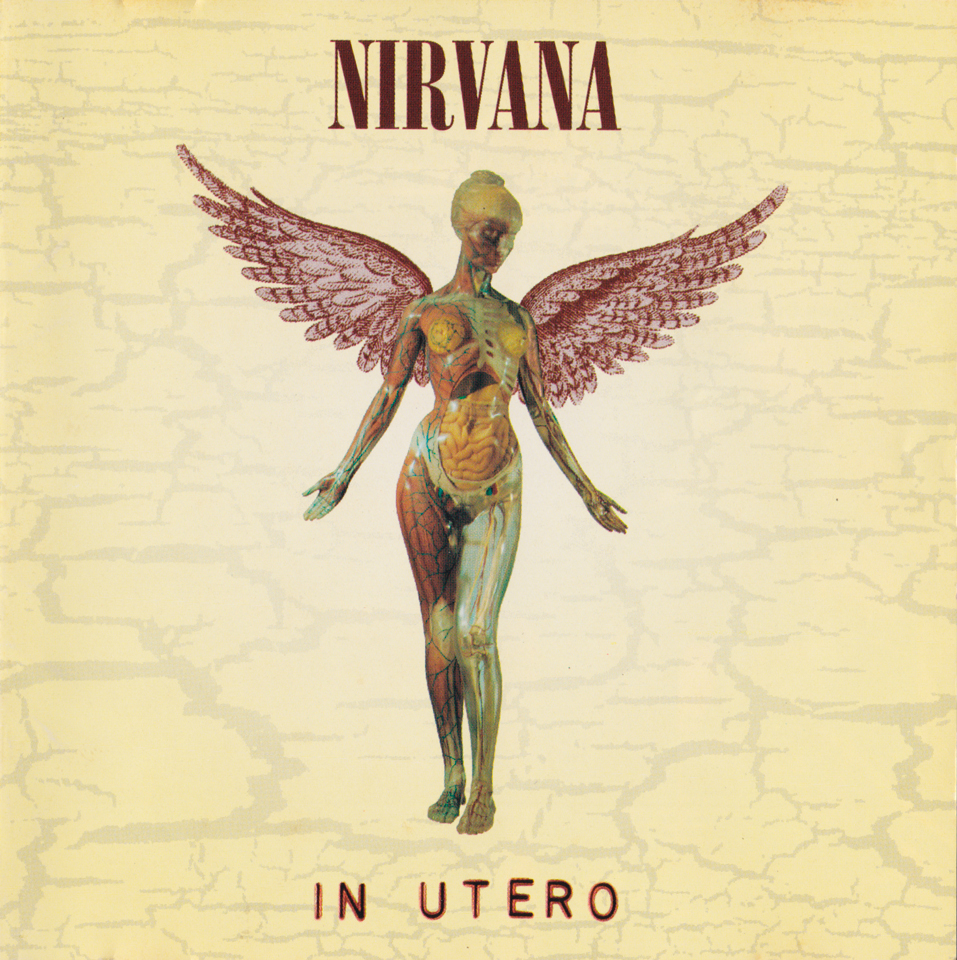

コメント