当ブログ「再び『愛蘭土紀行』」でも触れた、ポール・マッカートニーの「Pipes Of Peace」という曲について。
その前にもう一度、ケルト的な気分を味わうため、アイルランド民謡の「The Last Rose of Summer」を聴いてみた。明治17年、里見義がこれに日本語詞を付けて「庭の千草」とした。
――司馬さんの一行は現地の人にこの「庭の千草」を歌って聴かせるのだが、その店でこれからバグパイプ名人の演奏に陶酔しようとする現地の酒飲み人らには、何のことか分からぬ様子。何故「The Last Rose of Summer」を日本語で歌うの?といった困惑した感じ。
明治期に遙々アイルランドの民謡が入ってきて日本の愛される唱歌の一つとなったことを、司馬さんは説明したかったのだろうが、そのちょっとした国際交流的な気遣いは、歌の理解を前にして少しばかり及ばなかった――。
「庭の千草」のように、原題の“夏の最後のバラ”が庭の千草、あるいは菊の花、白菊に置き換わっても、ケルト的な悲しい調べは、曲に溶け込んだまま残っている。比喩は変われど本質的な部分は不変であるという、歌としての最たる善例だと思うが、私個人としては、やはりこういう歌を若い学生時代に学んでおきたかったと悔やむ。
同じような例では、コンヴァース作曲の「What a Friend we Have in Jesus」(日本では杉谷代水作詞の「星の界」)が挙げられるが、これらは単に意味もなく日本語詞を付けているのではない。原曲の中に含まれている深い意味を汲み取って、それなりに掘り下げていることがよく分かる。音楽教育の上で、それが和物か洋物かといったような十把一絡げの価値判断の植え付けは、かえって原曲の純粋な歌の意味を読解することができなくなってしまうから、日本人はもっと原曲への自然な愛着をもった方がいい。
*
 |
| 【PAUL McCARTNEY『PIPES OF PEACE』(UK盤)】 |
ということで、話題を「Pipes Of Peace」に転ずる。
私自身、ポール・マッカートニーのアルバム『PIPES OF PEACE』が本当の意味での“白地”のジャケットであることを、いつ知ったのだろうか。
1987年に発売された『All The Best!』でそれを聴いて以来(高校生の時)、この分かり易いタイトルのメッセージが世界平和に向かっていることには気づいていたものの、それがアイルランド民謡「The Last Rose of Summer」と同じ底辺を持つことを知るには、そこからかなり年月が経ってからのことだ。やがてこのアルバムの白っぽさが、とても美しい画であることに気づかされる。
あの白いジャケットに関しては、アルバム『PIPES OF PEACE』に記されているクレジットを引用しておく。
《Cover photo by Linda McCartney
‘Chair and Pipe’ by Vincent Van Gogh
reporiduced by permission of the
Trustees of the National Gallery,London.
‘Van Gogh’s Chair’, chrome sculpture
by Clive Barker 1966》
(ポール・マッカートニー/アルバム『PIPES OF PEACE』クレジットより引用)
 |
| 【エリック・スチュアートとマッカートニーが写ったフォト】 |
白い背景にクローム製の椅子。その上には美しく輝く銀色のパイプと刻み煙草(?)。
「ゴッホの椅子」がモチーフとなったこのジャケットの写真には、巨大にデフォルメされた金属製のパイプ、さらに南米の民族楽器サンポーニャやインディアン・ピース・パイプが見える。実はジャケットの背面は、気の利いたジョークとなっているのだが、インディアン・ピース・パイプを望遠鏡に見立てて三脚を据え置いて、巨大な金属製パイプを跨いでいるのだ。マッカートニーはそれで何を見ようとしていたのだろうか。
1982年にアルバム『TUG OF WAR』が発売され、その時の面子(プロデューサーはジョージ・マーティン、エンジニアはジェフ・エメリック、ミュージシャンはスタンリー・クラーク、スティーヴ・ガッド、アンディ・マッケイ、エリック・スチュアート)がそのまま引き継がれた形の低予算アルバムと酷評されたのが、翌年発売のこの『PIPES OF PEACE』だ。その通り、シングルの「Pipes Of Peace」とマイケル・ジャクソンとのデュエットで話題となった「Say Say Say」以外、他のアルバム曲はまったくぱっとしない。
ところがどうして、私はこのアルバムのジャケットとシングル「Pipes Of Peace」が好きである。「Pipes Of Peace」は、誠にアレンジが込み入っていて飽きることがない。ずばり、マッカートニーが“トップギアを入れた”メッセージ性の強い曲となっている。
イントロからの数小節にかけてのピアノのリフ、コシの利いたベースとの絡み、少年合唱隊の掛け合い、バグパイプのアクセントの強いリズム。そしてジョージ・マーティン的アレンジの交響。それはまるで「Live And Let Die」を彷彿とさせるが、全体を通じたシンコペーションの変化が、この曲の肝である。
『All The Best!』が出た時、ポール好きの友人とCDの貸し借りが始まって、なかなかそのCDが返ってこず、「Pipes Of Peace」が聴けなくてストレスが溜まった。その後の流れとしては、マッカートニーにあやかってベースギターを友人から購入するのだが、これもやがて人手に渡ってしまう。高校時代のそのあたりの思い出は、マッカートニーと「Pipes Of Peace」がどうしても絡んでくる。
いま、私の所有するターンテーブルもかなり与太ってきてしまっている。ピッチが怪しいのは以前からだが、ポールの歌声が妙に間延びしして少し可笑しい。間延びした「Pipes Of Peace」もなかなか乙で、これはこれで味わい深い。
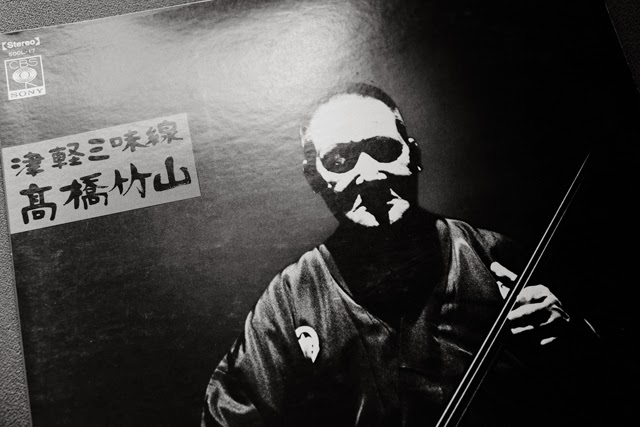

コメント