一纏めに、私が学生時代(小学校から専門学校まで)に書いた、学校提出作文としての読書感想文について記憶をたどってみた。
《友情というものは言葉で表わすものは何もない。つまり体しかそれは知らない。解答は自分で出すしかない。目に見えるものは嘘しかない》
小学校での、夏休みの宿題として提出を要求される読書感想文にはそれなりに風情があった。――夏休みの期間中、学校指定の本(文部省推奨の、感想作文の課題となる本)が、児童を通じて各人に手渡されるリレー配達方式――。
まず夏休み直前に先生から本を受け取った最初の児童は、それを読み終えたら、名簿順に次の児童の家に行って本を渡す。登校日であれば学校で渡してもよい。こうして本を渡された児童は、一両日中にそれを読んで(大抵は持参している間に作文を書き)次の児童の家に行かねばならない。名簿順だから、例えば“ワタナベ”君などの場合は夏休みが終わる直前に手渡されてしまうことがある。締切に追われつつ早急に作文を書かなければならなくなる。“ワタナベ”君は可哀想だが、なんとなく一丁前の作家風情である。
ともかく、名簿順というのは理不尽と言えば理不尽なのだが、本を買わされず無償で貸し出しされて本が読めるので、本が届けられた時はワクワクしたものだ。
*
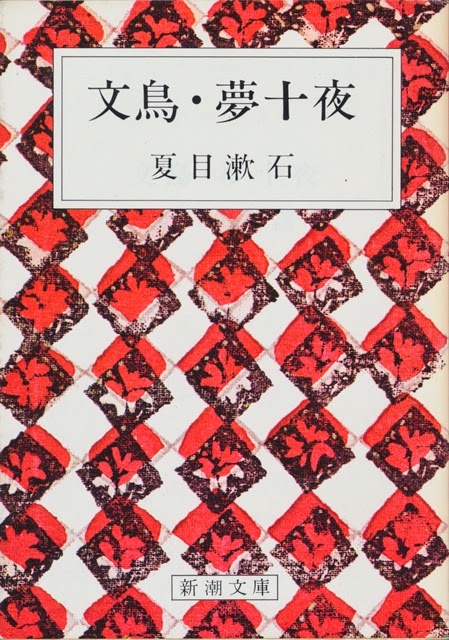 |
| 【新潮文庫版『文鳥・夢十夜』(三十二刷)】 |
翻って、高校時代の読書感想文宿題の話。小学生の時のような締切に追われる他人を笑ってはいられなくなった。この手の宿題がいちばん身体に悪い。汗が噴き出てくる。
憶えているのは、高校2年か3年であったか、芥川龍之介の『羅生門』が宿題に出された時。私はまるっきり芥川龍之介の文体に馴染めず、この短篇小説の面白さがどこにあるのかまったく分からなかった。したがって、自分で書いた作文の内容もおそらくちんぷんかんぷんなものであったと思われ、それがトラウマになってしまい、ごく近年まで彼の小説や文集に目を通すことができなかった。
“読書”という観点で少し大袈裟に述べれば、私の生涯で最初に沸点に到達したのが、夏目漱石であった。気持ち的に芥川の場合とまったく正反対である。
高校3年、友人が新潮文庫版の『こころ』を買ったのを知って、私も真似をしてそれを買った――。長年、このあたりの記憶を自ら勘違いしていて、夏休みの宿題で『こころ』(原題『こゝろ』)の感想作文を書き、先生に提出したらやがて“C”という低ランクの評価を付けられて作文が戻され、至急その書き直しを求められた、と思っていた。
しかし実際は違った。それは『こころ』ではなかった。武者小路実篤の『友情』(角川文庫版)であった。その当時私が付けていた個人日記の中に、書き直しした自作感想文の文章の引用があったのだ。これによってそれが『友情』に対する感想文であったことが分かった。
《友情というものは言葉で表わすものは何もない。つまり体しかそれは知らない。解答は自分で出すしかない。目に見えるものは嘘しかない》
漱石の『こころ』は高校の国語教科書で読み、それから友人の真似をして新潮文庫版を買った。感想文の課題には選ばなかったが、読んだことは読んだ。もしあの時、『こころ』を読んで作文を提出し、それの評価が低かったならば、私は漱石に対してもトラウマになったのだろうか。そう考えると、馬鹿馬鹿しくも恐ろしい。
ともかくその時から新潮文庫版を通じて、漱石本を読み始めていく。『文鳥・夢十夜』『彼岸過迄』『門』『それから』『硝子戸の中』。『こころ』の文庫本には、陣内孝則さんが演じた「とーちゃんも、夏、読んだ」の“新潮文庫の100冊”広告帯が掛かっていた。漱石への思いはさらに膨れ上がり、全集や初版復刻版で読むようにもなった。
それにしても、新潮文庫版は忘れがたい。高校時代の思い出が次々に湧いてくる。その後いくら本を買って読み耽ったとしても、そんなふうにその本に自己の生活臭が纏わり付くことはない。漱石―新潮文庫ならではの思い出である。


コメント