中村屋サロンと中村彝についての本題に入る前に、新宿東口界隈についての個人的な思い出を記しておく。
中学生の頃――それは昭和60年前後――「トーキョー」と言ったら私の中で「シンジュク」であった。新宿がトレンドであった。というくらい、あの頃は何かしらの機会に新宿駅を訪れ、東口界隈をよく歩き回った。
私の中で、東京への憧れは、新宿への憧れと同義であった。
専ら地下のプロムナードを歩き回ってから地上に出、アルタの巨大な街頭ビジョンを見上げつつ、紀伊國屋書店で立ち読みしたり、マルイへ入ったり、あの頃盛んだった新宿コマ劇場での演歌歌手の公演を観たりしたこともあった。そう言えば、スピルバーグ監督の映画『カラーパープル』(原作はアリス・ウォーカーの同名作)を観たのも、確か歌舞伎町の新宿ミラノ座だったし、シアターアプルや紀伊國屋ホールは演劇少年であった私には憧れの劇場だったのだ。
中学高校と演劇仲間が入れ替わる。それでも尚、演劇に関する情報収集の場は、常に紀伊國屋書店であった。話が前後するが、中村屋サロン美術館を訪れた直後、私にとって懐かしい紀伊國屋書店にも足を運んだ。
ここは昔と何も変わっていない。ただし東京においての“変わらない”というのは一過性のもので、次に訪れたらまったく変わっていたということがよくある。たまたま私が“変わらなかった”現状を見ただけに過ぎず、あまりこの場合の肯定は意味をもたない。
紀伊國屋書店(新宿本店)にあったあの頃の熱気は、なんとなく薄れた感がなくもない。
芸術・演劇関連の本が並べられたスペースの、必ずしも群がっているとは言えない程度の、内省的な熱気を帯びた人だかり。あの頃、演劇の本を読むには紀伊國屋書店に行くのが最適と思われ、よく演劇関連のスペースに立ち寄った。
演劇や戯曲関連の売り場には、若手の演劇人がしばし立ち読みしていることもあり、その雰囲気がいかにも演劇人らしさを醸し出していて空間的に味わい深かった。紀伊國屋ホールで様々な公演のチラシを貪るのもよくやった。一つの公演を観終わると、持って帰るチラシの束の分厚さに驚くのである。ともかく、書店の雰囲気は大幅に変わり、いまその種の文化的気勢はどこにも感じられない。
*
 |
| 【新宿中村屋ビルのパネル】 |
今年の1月、私は新宿区立中村彝アトリエ記念館を訪れて、中村彝と鶴田吾郎のエロシェンコ肖像画の複製を観た(当ブログ「下落合のアトリエ」参照)。
今回、中村屋サロン美術館(新宿中村屋ビル3階)を訪れ、中村屋所蔵の鶴田吾郎の「盲目のエロシェンコ」(1920年)を間近で観ることができた。かつて中村屋サロンに集った芸術家たちの作品が、貴重にも展示されており、その中に中村彝の、相馬俊子を描いた画があって、私の胸は本物を観る悦びでときめいた。
その一つが、「小女」である。
彝は1913年から14年にかけて、おそらく猛獣となって俊子を追いかけ、彼女の像を描きまくった。「小女」は1914年の作品だが、前年に描かれた作品と比べて、どことなく俊子の表情が子どもっぽくあどけない。俊子の乳房を露わにした前年の「婦人像」や「少女」「少女裸像」の方が遥かに大人びていて、画家とモデルとの関係性において少し客体的に思える。
ところが翌年の「小女」はまったく違い、彝の恋心が既に完膚なきほどに焼き尽くされて、俊子の肉体の細部に至るまで怨念が込められている。したがってその俊子の両腕の描写の肉感は、尋常ではない。
創作活動におけるサロンというのは、物理的空間として必要不可欠であろう。今で言うSNSだけでは、まったく事足りないものである。
それは芸術への意識開化の場であり、研究錬磨の場であり、人脈の場であったりするが、それぞれに含みをもたらし、仮想空間ではおよそ経験し得ないプラスアルファを有する。サロンは主宰者の懇意によって成立する。
中村屋の相馬夫妻は中村彝の面倒を見、その中村彝は俊子に出会った。彝と俊子の恋慕の関係は後に瓦解するのだが、彝は俊子像で多様な美の結晶を遺すことができた。
都市空間の時代が違うとは言え、かつてこの場所に多彩な芸術家が集ったサロンがあったとは、なかなか想像し得ないことだ。しかしそこに彝が居て俊子が居て、ということを想像する時、芸術作品の発端と出発の奇妙さはなんとなく理解できる。街の隅々にいたる人と人との交流の中から、作品は生まれ出てくる。新宿はそういうサロンの巣窟であったのかも知れない。
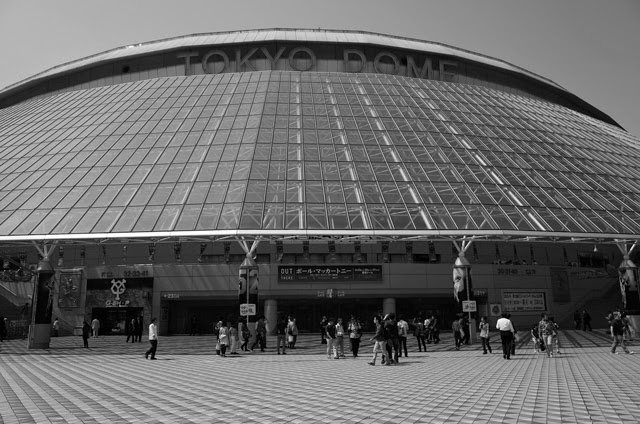

コメント