 |
| 【昭和40年頃の国鉄古河駅(写真集より)】 |
夏休み近し――という巷の風情に少しばかり煽られて、子供の頃に読んだ児童文学をいまおもむろに手にしたりする。そうして不思議とその頃の思い出の風景が蘇り、手元の本を閉じたまま夢想したりする。あっけなく時間が過ぎ、淡い体験にいざなわれた白昼夢のような気分にもなる。
ふと、私の住んでいる町の、昔の駅の姿を思い出した。子供の頃の記憶が蘇る。昭和40年代当時のその駅舎は、木造モルタル建築で古く、なんとなく悪臭が漂う感じの、田舎の小さな駅舎であった。
その古い駅舎――当時の国鉄古河駅は、東北本線で唯一茨城県内の駅であり、東京は上野駅から、北は栃木県の宇都宮、黒磯方面へと向かう中途にある。今年、古河駅は明治18年の開通から130年を迎え、「古河駅130年とまちのすがた」と題された企画展がこの夏休み期間中に市内の歴史博物館にて催される。この駅を利用してきた市民にとっては、とても興味深い企画展である。
ここに掲載した写真2点は、古河市の写真集『こが 半世紀―古河市制50周年記念誌―』(2000年発行)によるものだが、昭和40年代の頃の駅舎はまさにこんな感じであった。
乗車券――その頃は“切符”と呼んでいた――は当時、ほとんど窓口を介して駅員に口頭で降車駅を告げ、代金を支払って受け取る仕組みだった。駅ホームへの入場券のみは、古びた粗末な自動販売機で購入できた。私が小学生だった昭和59年には、高架化に伴って駅舎が新築され、もちろん今、その古い駅舎の面影はまったくない。
*
 |
| 【同じく昭和40年代の古河駅東口(写真集より)】 |
昭和59年のおそらく前の年。私が小学5年生だったかの頃。
学校で必要な文具を買いに、3つ先の駅ビル内の書店へ行こうという話になって、私を含めた男子2名と女子2名が放課後、駅で待ち合わせをするということになった、「子供ながらの事件」の思い出がある。
何せその頃、学区外に子供だけで行ってはいけないという校則があった。駅は学区外にあり、その駅で待ち合わせて3つ先の駅まで電車に乗る、ということがいかに子供にとって大冒険であったか。
ところがいくら待っても、女子1名が駅にやって来ないのである。事件はしごく簡単な様相である。焦るのである。
夕方5時までに買い物を済ませて戻ってこようよ、と示し合わせていたものだから、なおさら出発時間が遅れることに苛立ちがつのった。しかし、いくら待ってもその子は駅に現れない。
ケータイのない時代。
公衆電話で連絡をと思ったが、あいにくその時その女子の家の電話番号を知らなかった。だから連絡の取りようがなかった。約束を平気でやぶる女子ではなかったので、何か理由があるのだろうと察したが、時間だけはどんどん過ぎてゆく。
おそらく考えられるのは、親に電車に乗ることがばれたのだろうということだった。学校帰りに自転車で学区外を越えて駅に行き、電車に乗るなどとんでもない。女子の親だから当然行くな、と言われたに違いなかった。
諦めムードが漂った。仕方なく3人は、3人だけで行こうということになった。このまま帰る気には到底ならなかった。この冒険はなんとしても完遂したいと思った。
既に買っておいた切符を握りしめ、おそるおそる駅員の立っている改札に向かった。駅員はカチカチと改札鋏を鳴らしており、あの黒い制服を着た駅員のいる改札を子供だけで通過することは、とても勇気のいることだった。
3人が改札口へ向かうその瞬間、女子が高い声を上げてあることを呟いた。伝言板。そうだ、伝言板だ。伝言板があった。
その駅舎の待合場には、チョーク――当時は子どもたちの間で“白墨”とは言わなかった――で書き込むことのできる小さな黒板が据え置かれていた。そこに伝言を書いておけば、もし後から女子がやってきたとしても、それを見て我々が先に電車に乗ったことが分かるはずだ。
伝言板には、大人の誰かの書き込みが複数あって、書けるスペースが限られてしまって、これからあまり目立つようには書けなかった。が、女子が小さな字で○○ちゃんへと名前を書き、先に行ったことを伝える文言を書き加えた。これで大丈夫、と安堵した。
――3人は改札口を通って1番線で電車が来るのを待ち、やがて入ってきた電車におそるおそる乗り込んだ。そして3つ先の駅へと向かった。乗ってから15分くらいで3つ先の駅に着き、その駅ビルの書店で目的の買い物をした。目新しいものがいっぱい売られている駅ビルだった。欲しかった文具もその駅ビルの書店でないと買えなかったのだ。
再び電車に乗って古河駅に帰ってきた時は、とうに5時を過ぎていた。しかしなんだか、駅で解散するのは名残惜しいように思われた。自分たち3人だけの小さな旅。明日はまた学校で会える。けれども薄明かりの夕暮れ、このまま駅で佇んでいたい、ずっと来る人来る人の姿を眺めていたいと、私は思った。何かそれは、涙が込み上げてくる悲しみのようにも感じられた――。
私はそんな駅舎の、窮屈な待合場にある古ぼけたガラスケースに飾られた、名産品の展示物を見るのが好きだった。
そこに白い繭が数個飾られていた。繭である。繭は埃を被っていて虫が食ったような穴も空いていた。その繭の穴をじっと見ているのが好きだった。古河は製糸業が盛んな町で、かつては重要な地場産業だったらしい。
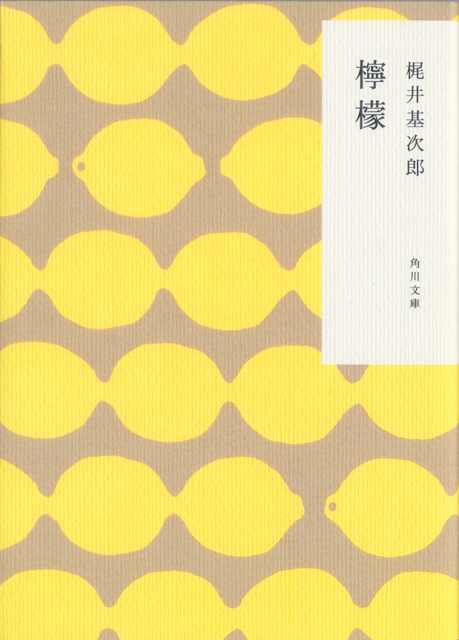

コメント