 |
| 【映画『典子は、今』のパンフレット】 |
小学校の頃に一度だけ観た映画が懐かしくなり、たまらなくなってその映画を――なんと34年ぶりに――鑑賞することができた。松山善三監督の『典子は、今』である。
私が入手したビデオテープ版にあった解説文が最もこの映画を理解するのに適当かと思われるので、以下、まずそれを引用しておく。
《昭和37年1月、辻典子は両腕が退化したサリドマイド児として誕生した。この映画は、彼女の出世から競争率26倍という難関を突破して市役所への就職を果した典子の姿を、本人自らが主人公を演じるというドキュメント手法で描かれている。
「足」を「手」に換えて、ミシン針に糸を通し、器用に櫛を持つ姿は、人間の真の「勇気」と真の「努力」の何たるかを感じさせてやまない。身障者への「哀歌」ではなく、むしろ大らかな「人間讃歌」として公開当時多くの人々に熱い感動を投げかけた》
昭和56年(1981年)キネマ東京製作、東宝配給、松山善三監督『典子は、今』。主演は辻典子、渡辺美佐子、長門裕之。映画の公開年から探ると、私がこの映画を観たのは、小学3年生ということになる。
朧気な記憶がどうも歯痒い。かろうじて記憶しているのは、この映画全体の漠然とした印象と、最初にこの映画を知ったきっかけとなった、学校の教室での淡い残影である。
私が教室の机に座っていると、映画のフライヤーか招待券あるいは優待券か何かが一人一人に配られた。そこで『典子は、今』というタイトルが頭にインプットされた。まだこの時点では、どういう内容の映画であるか知らない。
おそらくその直後の担任先生の話によって、これは文部省推薦の映画ですよということが強調されたのだと思われる。まだ内容を知らない私は、〈この映画は文部省が推薦なのだから絶対観なければいけない〉とある種の観念を抱いたのを憶えている(※映画のパンフレットのデータによれば厳密には、文部省特選、総理府後援、厚生省推薦である)。やがて先生の説明で障害者の映画なのだと知ると、私は次第に興味本位でこの映画を観てみたいと思うようになった。
さてそうして、私が『典子は、今』をどこかで観たのには違いないが、どこでどのようにして観たかについての記憶は、ほとんど途切れてしまっている。
フィルムの部分的なシーンの印象は薄らとあるのだが、果たしてどこで観たかの記憶が思い出せない。地元の映画館だったのか、公民館だったのか、どこか別の場所での小学生のための特別上映だったのか。
*
34年ぶりに、『典子は、今』を観た。そうであった。私はあの時、この映画で初めて“サリドマイド”という言葉を覚えたのだ。辞書を引けば“サリドマイド”はこのように記されている。
《サリドマイド thalidmide 1958年に旧西ドイツで開発された睡眠薬の一種。妊娠初期に服用すると胎児にアザラシ肢症などの障害が生じることが判明し、61年製剤・使用が禁止された》
(三省堂『大辞林』第三版より引用)
映画に登場するまだ十代だった辻典子さんの上着は、腕が通されていないから両腕の部分がぶらんぶらんとしている。映画の主役は実は典子さんの足である。
普段、歩くため以外に使わない足は、顔と同じ高さにそれがあるのは不自然な体勢となる。そもそも足がそこまで上がらず、筋を痛めて身体が後ろに倒れてしまいそうだ。
しかし彼女の足は、実によく動く。柔らかくこまやかだ。食事では足で箸を持ち、習字や勉強のための筆記では足で筆を持ち、ミシンでは足で糸を通す。顔を洗うのも足を使う。ジャガイモを切るのも足。マンドリンを弾くのも足。すべて足。足。足。この映画は足の映画である。
このことで観ている私の感覚はだんだん麻痺してくる。手も足も同じに思えてくる。少なくとも典子さんは器用すぎるくらいに器用に、平然と、何事もなく当たり前に、足で生活する。違和感が消え失せ、彼女がサリドマイド児で両腕が無いということが、観ているうちにどこかに吹っ飛んでどうでもよくなっていく。彼女の仕事先の役所での窓口応対など、足を使った書類の“足さばき”は、圧倒されるというよりうっとりと見惚れるほどであり、あんな器用な足があったらどんなに便利だろうとつい思ってしまう。
しかしながら彼女が(映画の中の典子さんが)、胸の内の果断な挑戦で、自分一人で熊本から広島へ旅することを決行した時、ありとあらゆる困難に直面する。
駅から電車を乗り継ぐという行程において、あれほど器用だった足がまったく封じられて使えず、切符を買うのにも他人に頼らなければならなくなる。車内で弁当を買うにも、財布を取り出すのにも他人に頼らなければならず、自分がそれを食うことさえも、他人に頼って口まで運んでもらわなければならなかった。
健気だった典子さんは、一人旅に断固反対する母親に向かって何度も「わたし、やってみる!」と言い放ち、旅に出た。それは痛快な場面ではあったが、彼女は旅をしてみて、未知なる世界に放り込まれて初めて分かった。
「やってみる」のは自分本位で、本当は親切な誰かが「やってくれている」のだと。
このことは観ている側もショックであった。典子さんが足を使って生活することが実に器用で平然としたものであると信じられた世界が、あっけなく壊された瞬間である。外野へ出れば、器用だった足は封じ込められてしまう。歩行し、身体を支えるためだけの足となる。両腕が無いという弱者の典子さんが浮き彫りになる。典子さんはひたすらお願いします、お願いしますと人々に頭を下げて手伝ってもらうしかなかった。
『典子は、今』という映画は、足の映画であるということと同時に、人間はその能力のために生きるのではないということを分からせてくれる。
人間は誰しも生涯、何かしら学び続けて生きていく。典子さんの場合は、手が使えないから足を使うということを必然的に学んだ。何より自分が生きるために。
だがそれも、一つの始まりだったのだ。学んだ能力の器用さとは裏腹に、生きるとは他者との共存であり共有であって、助けを求める方も求められた方も、共存共有される《生きる》ことの喜びに向かって、身体と心を結び合わせる。別の言い方をすれば、手をつなぐということ。それを幸せという。相互の身体と心とが結び合わせられなければ、幸せにはなれない。
だからこそ幸せのために、我々は知恵を学ぶ。典子さんは自分の足の器用さ以上に、そのなにものかを学んだ、ということになる。まさに「人間讃歌」だ。
映画の最後、典子さんが海に飛び込んで懸命に泳ぐ。不器用で挑戦を恐れているのは観ている私の方であり、まるで彼女が海に暮らす魚のように見えた。
人魚ではなく魚女――辻典子さん。私にとって『典子は、今』は懐かしく、そして新しい映画になった。
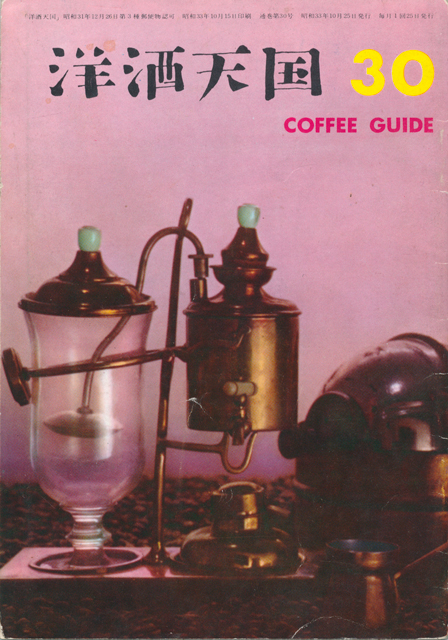

コメント